Blue Lagoon(高中正義)が減七でない理由とルーマニアン・メジャー・スケールの関係 [楽理]
機能和声を標榜する場合であるならば、主和音がディミニッシュとなる状況というのは短和音が一時的に半音変位したりというオルタレーションの状況を先ず考える必要があり、「トニック・ディミニッシュ」という状況を機能和声の方から照らし合わせるのは危険な事であると私は考えるのでありますが、現代のジャズ/ポピュラー音楽に於てはドミナント7thコードを「Ⅴ」としてだけではなく「Ⅰ」として聴く事もある様に、ディミニッシュ・コードをトニックとして聴くという状況も確かにあります。とはいえその世界観を、カデンツ(終止)を標榜する機能和声社会と同一視してしまってはいけないので、その辺りは区別し乍らディミニッシュ・コードという物を視野に入れておく必要があるという物です。
ひとたび3度音程堆積構造へと還元すればこそ、トリスタン和音とてハーフ・ディミニッシュ・コードへ還元する事は可能です。とはいえジャン゠ジャック・ナティエが33人の大家によるトリスタン和音の解釈を33人33様の例として取り上げている様に、トリスタン和音を一元的に、しかもハーフ・ディミニッシュ・コードとして見立てる事は非常に危険である訳ですが、トリスタン和音出現以降、和音体系は大きく変容したのも事実であり、ディミニッシュという世界観も結果的にはそうした多様な世界観を拡大させる事の助力となっている事も確かなのであります。
例えば、ホ音 [e] 音を根音とする減七の和音を形成してみましょう。和音構成音は下から [e・g・b・des] を形成する事となります。つまり、英名表記をすれば「E・G・B♭・D♭」という事になりまして、[des=D♭] は決して [cis=C♯] ではないのであります。
異名同音(=エンハーモニック)というのは、ギターのフレットやピアノの鍵盤上から見れば「物理的」には同じ所にある音であるという事をも意味しているので、音楽への配慮の足らない人からすれば《異名同音という実際があるのだから、音をどのように呼ぼうとも構わない》と考えてしまうのは誤りです。
それは、異名同音を「己の呼びたい方の音」として考えてしまう事が危険であるという意味でもあるので、7番目の音である「D♭」の異名同音は「C♯」なのであるも、決して7番目が6番目に置き換わる物ではないという事なので音度の捉え方を己の都合よく解釈してしまってはいけないのです。
前振りが長くなってしまいましたが、高中正義の名曲「Blue Lagoon」での曲冒頭に於けるコードは、ホ長調主和音が変位した和音であり(※ここの文は、《謬見として広く知られる事となってしまっている「Edim7およびEdim」という減七和音は”あたかも”ホ長調主和音が変位した和音の様に見せますが》という含意に過ぎず、次の過去のブログ記事を参照されたし)、根音を掛留させたままEメジャー7thとの2コード進行となっている物で、過去にも取り上げた事がありますが今回は譜例でも例示するという訳です(先のリンク先のPDF版はコチラ)。
(2019年10月20日加筆)

扨て、その「Blue Lagoon」冒頭のコードこそがキモなのでありますが、配慮に乏しい解釈として広く周知されてしまっている謬見となっているのも「Blue Lagoon」の悲哀なる側面でもありまして、その謬見たるや、冒頭のコードを「Edim7」(または、四和音でありながら七度音を明示しない不文律的表記としての「Edim」)という風に誤って充てられてしまっているという所が酷い誤りなのであります。こうしたコード理論方面を熟知している者ならば少しだけ考えを及ばせればそれが誤りである事は理解できる筈であるのに、コード表記にばかり躍起になってしまい、楽曲を構成している線的な部分を蔑ろにしている事で、和音構成音と、それに随伴するフレーズがコード表記のそれとアヴェイラブル・モード・スケールのどちらから照らし合わせても飽和してしまうという矛盾を晒す事に気付かないという状況を露呈しているのですから滑稽であります。
結論を言えば、「Edim7」と誤解されてしまうそれを正しく表すならば「Em6(♭5)」こそが正しい表記となります。とはいえ、マイナー6thフラッテッド5thのコード表記という物はおそらく馴染みの薄い表記であり、このコード表記を別のシーンできちんと取り扱っているのは濱瀬元彦著『チャーリー・パーカーの技法』位でしか見かけない物であります。換言すれば、濱瀬元彦のコード解釈のそれが如何にして音楽的に慮った解説なのかがあらためて能く判るという事でもありますが、他のシーンでは配慮の浅いコード表記嵌当が見受けられるという所が嘆かわしい側面でもあるという訳です。
では何故、「Blue Lagoon」のそれを「Edim7」と判断してはならないのか!? という事を詳らかに語る事としましょう。それでは、下記リンクのYouTube譜例動画を確認してもらう事に。
この譜例動画の弱起小節を除いた3小節目のメロトロンのパートを見て下さい。4拍目に [dis=D♯] 音が現れております。この小節でのコードは「Em6(♭5)」であるという事も同時に念頭に置いていただきたいと思います。
仮にこの箇所でのコードが「Edim7」であった場合、そのコード表記が示す通り [e] から数えた7番目の音は [des=D♭] である筈ですから、7番目のD♭とオクターヴ上の [e] の音との間には充填されるべき音が有る筈がないのです。なぜならばヘプタトニックを基とするのは歴然とした状況である為、コード表記がいくら「Edim」として七度音を明示化していない状況としてもアンサンブル上では間違いなく「D♭」音がある状況であるにも拘らず、コード表記の不十分さに胡座をかいて [dis] をガメついてしまったら、その時点でヘプタトニック・スケールではなく8音音階としてのモードを想起する事と同様の矛盾を晒す事になってしまいます。
正しく「Em6(♭5)」とやれば、その表記こそが決して当該和音の構成音としてではないアヴェイラブル・モード・スケールとしての姿から類推される「7番目の音」という状況をメロトロン・パートが [dis=D♯] 音であるという風に正しく活用される状況を生ずる為、矛盾した世界観の解釈の為に8音音階をモード想起する必要など全く無く大手を振って「Em6(♭5)」上で [dis=D♯] 音を使う事が理論的な側面からも正しく整合性の採れた活用となる訳なのであります。
つまり、減七和音という誤ったコード表記を正当化する為に、D♯音をストリングスが用いた途端に8音音階(オクタトニック)となるモード・スケールを想起する様に曲解するのは莫迦げた発想なのであり、「Em6(♭5)」と正しくやれば本来なら問題の無い事なのです。
加えて、仮にもコード表記「Edim」がディミニッシュ・トライアドと強弁した場合(伴奏にはD♭音が無いと考えて)、その場合モード想起としては「D♭」と「D♯」を共存できるのではなかろうか!? と考える人がおられるかもしれませんが、「D♭」を使った時点で、本来ならコードの伴奏として有るべき音に気付くはずですし、それに併存させて同度由来の変化音として「D♯」を想起するというのは、やはり同度由来の派生音を併存させる必要がある以上はヘプタトニックのモード想起が出来ない事を意味するのです。
扨て、「Em6(♭5)」を想起するとなると、モード想起は次に示す物になります。
※ディミニッシュ系となるコード・ヴォイシングのヴァリエーションは、シャイエの『音楽分析』にも触れられている様に、リンク先の例を参照。
このスケールは、Aルーマニアン・メジャー・スケールの5番目のモード・スケールという事になります。ルーマニアン・メジャー・スケールというのは聞き慣れないヘプタトニック・スケールかもしれませんが、リディアン・ドミナント7thスケールの第2音が半音下がった物として考える事が出来ます。「この様なモード、どうやって使うんだ!?」と疑問を抱く方もおられるかもしれません。用法的には長調に於けるサブドミナント・マイナーの使い方に似る所があると考えると容易です。無論、E音から見たⅣ度上の和音はマイナーになるのではなく、Aルーマニアン・メジャーでのA音上のダイアトニック・コードはAメジャー系になるのでありますが、その辺りを解説する事としましょう。
サブドミナント・マイナーの特徴的な用法としては、ドミナントを経由せずにトニックへの帰結感を柔和に齎す所にあります。ドミナントを経由せずに、という所が肝心なのですが、サブドミナント・マイナーの用法というのは実質、サブドミナントに進行時に於て下属調同主調の音脈、つまりは和声二元論的にマイナーの世界観を「プラガル」な状況として見立てる事で、下属調同主調の世界へとモーダル・インターチェンジを介す事で、実際には部分転調を生じているのです。サブドミナント・マイナーと変じた瞬間、その平行長調とは原調との調域が二全音/四全音調域同士での部分転調という事になるので、ハ長調が原調だった場合、「F△」へ進んで同主調音脈「Fm」となるのですが、この場合下属調同主調=Fmの平行長調=A♭という事となり、原調との調域と照らし合わせれば、その関係性があらためてお判りになるかと思います。
つまり、Eメジャーというホ長調に於て通常のサブドミナント=Aメジャーがサブドミナント・マイナーではなくAルーマニアン・メジャーに移旋したと考えると良いのです。それは、リディアン・ドミナント7thの第2音を半音下げたのと同様の音列なので、実質的にはメロディック・マイナー・モードの一部を変じている状況になるので、全体としては「マイナー感」が生まれる訳です。明示的なサブドミナント・マイナーとは異なるのでありますが、マイナー感に酷似するモードであるので音楽的な揺さぶりが大きくかかる事になるのです。ある意味では手垢のつきまくったサブドミナント・マイナーよりも使い道があるのかもしれません。それをさらりとやってのける高中正義の感性と、本曲の目指す世界観のそれにはあらためて称賛すべきでありましょう。
尚、譜例動画についてあらためて付言しておきますが、9小節目で表される「Esus4」は便宜的な表記であります。正確に表すならばギター・パートのヴォイシングを勘案すれば「Eadd4」でも良いと思います。場合によっては「E△7」を引きずったままのシーンも考えられる為、完全四度音を付与する「E△7add4」を用いたり、或いはその類型として「E△7sus4」と表記されるコードの用例も視野に入れる事が可能となります。
リック・ビアト流の表記をするならば、氏はadd4を「sus4/3」とも表記します。これは七度音の無い状況でありますが、氏の『THE BEATO BOOK』では「メジャー7th sus4」も漏れなく記載されているので、add4系統のコードを選択して表記しても良かったのでは無いのか!? と疑問を抱かれる方もおられるかと思います。とはいえ今回私が敢えてsus4表記にとどめた理由は次の通りです。
メジャー7th sus4というコードの構成音というのは、三全音を包含するので機能和声的な側面から見つめると「Ⅴ7omit5 on Ⅰ」という状況を喚起し易くなります。無論、メジャー7th sus4コードを充てる時には、そうした調的状況に負けじとする響きをモーダルに薫らせる為に用いる事が肝要なのでありますが、先述の通り「Blue Lagoon」は、
Aルーマニアン・メジャーの第5モード
↓
Eメジャー
という状況を固守したいが為に、ホ調での「Ⅴ度」となるドミナント感を極力忌避する必要があり、その上でメジャー7th sus4が喚起し易くなってしまうドミナント感をコード表記の上からも避けたというのが私の狙いであり、故に単に「sus4」表記で逃げたとも言えます。ただ、原曲当該箇所で [dis=D♯] 音は含まれないので、「Eadd4」という表記でも問題無いのですが、時代背景を勘案した上で当時ならsus4というコード解釈であろうという事も勘案した上での判断で「Esus4」という表記を充てました。
唯、コード表記の方を絶対視する癖の有る方はなるべくそうした癖を排除していただき、五線の中の音を重視していただきたいとあらためて思うところです。
2019年10月20日加筆分
Facebookからのアクセスから辿ると、日置寿士氏という方から本記事に対する論駁を受けましたが、私はこうした論駁は歓迎する立場と共に、私の本記事の欠点を挙げらている点にはあらためて感謝したいと思います。
彼の語る通り私自身もっと多義的な解釈で論ずるべきであったかもしれません。字数の面と今後のブログで語りたい(公にはしていない)目論見があって不十分な点があったかと思いますがその辺はあらためてお詫び申し上げます。
確かに、減七和音の構成音が短三度等音程構造である以上は少なくとも4種の調域を列挙した上で減七の同義音程和音であるマイナー6th(♭5)を呈示すれば確かにもっと多義的に例示する事ができたかもしれません。可能性ももっと拡大する訳ですからそれらをもっと呈示しても良かったであろうと思います。
然し乍ら私は、ルーマニアン・メジャーのモードの可能性を押し出す為にひとつの見立てを立てただけに過ぎず、一義的に調域を判定しているという意図はなかったのでその点だけは留意していただきたいと思います。
いずれにせよ「Em6(♭5)」というコードが他調の「Ⅳ」度由来という点だけを絞って、それが一義的解釈として捉えられてしまったのでありましょうが、私のスタンスとしては日置氏の想起する調域の判定も受け入れますし、どの様にモーダルに穿った見方をした所で、調性や協和の大義とも言える彼の表現する所の「啓蒙主義的」という点に音楽の調的な世界観が収斂する様に力が働くという含意も踏まえた上で深く首肯する所です。
とはいえ、ある楽曲の構造が完全な無調とは異なるも、半音階的全音階の世界を標榜する際に希薄化するドミナント感の楽曲の現実というものを私は本ブログで近いうちに取り上げる予定であるところに加え、本記事に於てはドミナントをなるべく経由せずに「Ⅰ」と「Ⅳ」での循環という構造を先ずは語っておきたかったので、私は「Em6(♭5)」というコードが他調の「Ⅳ」という事を最初に挙げていたのです。無論、この部分だけを読んでしまった場合、私が多義的かつ広範に亘って解釈しているとは思いつかないかもしれませんが、ある程度私のブログを通読しておられる方ならば私の本記事が、断定している様に一元的に語っていそうな事に疑問を抱かれるかもしれません。その辺りは誤解のなきようご理解のほどを。
また、「Ⅳ」に拘る私の個人的な理由として挙げておきたいのは、上方倍音列に下属音は登場しないからこそ取り上げたいのであります。こうした点を語る為に、私は前置きの様な感じで本記事を書いていたのであり、その後のフローラ・プリムの「I'm Coming For Your Love」の記事でも論じていたのです。
2019年12月7日加筆分
Facebookにて日置寿士氏から再度論駁されている様ではありますが、彼の謬見が甚だしいので取り敢えずは私の方から「正当」なソースを提示しようかと思います。
私の本記事の底意にあるものは、プラガルな世界観および民族的なものも含んだモーダルな世界観という物が協和感に強く基づく音楽観を恣意的に見る必要があるという点で、多くの場合西洋音楽の基礎のそれとは異なる大義で傾聴する必要がある物です。故に「同義音程」という恣意的に見る状況が生ずるのですが、その辺りを例示しておく事にします。これ以外にも彼は縷々述べておりますが、冒頭から斯様な断章取義に陥っているので応える必要はないでしょう。彼の論述の一部と私の例示するそれらを比較した上でどちらが正しいかご判断下さいませ。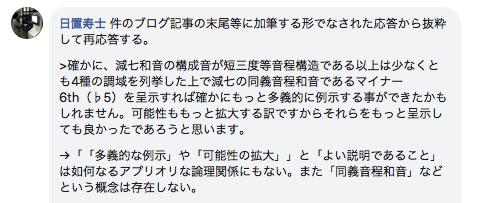
シャイエ/シャラン『音楽の総理論』65頁から この辺りを知らずに音楽を語ろうなど、モグリも好い所だと思いますけれども。まあ、もう少しマトモに音楽を学んで欲しいと思わんばかりです。
この辺りを知らずに音楽を語ろうなど、モグリも好い所だと思いますけれども。まあ、もう少しマトモに音楽を学んで欲しいと思わんばかりです。
なにゆえ「恣意的」かつ「同義的」という状況が生ずるのか!? それは、西洋音楽が「恣意的」に避けて来た通俗的な線運びは乞丐(ジプシー、ロマ、ボヘミアンなど)社会を想起させてしまうから避けられてきたのであり、その線運びとやらの正体は「増二度」です。
増二度音程は恣意的に短三度にも聴こえるのであり、ヘプタトニックをオクタトニックのように音階の材料音を増やす恣意的な粉飾の物として使える素材へと変容した訳でありますが、フリギア終止がプラガルである様に、フリギアのⅤ度をムシカ・フィクタとして用いない禁則はそのままに、フリギアのⅤ度がムシカ・フィクタさせる事で生ずる上行導音をジプシー音階の導音および増四度として用いる方便と、フリギア調の多様な変容がアンダルシア進行として醸成されていった事で、斥けていた世界観が西洋音楽界隈でも用いられる様になったのが音楽観の恣意的な傾聴による物です。これが判らなければ終生音楽を正視していて下さい。
A・イーグルフィールド・ハル著『近代和聲学の説明と應用』(改題:『近代和聲の説明と應用』)にて述べられるEx.180の例は’Generator’と称される物で短属九の上声部を異名同音で読み替える事に依る多方面の調域への「着地」と、減七を形成する上声部とは別の短三度等音程として根音が跳躍する音脈を例示する物です。
譜例から読み取らねばならない事は、(コンビネーション・オブ・)ディミニッシュト・スケールという8音音階(オクタトニック・スケール)が発生する根拠です。
例えば、オクターヴという完全八度音程の一方を「増四度」で分割した時、その転回となる陰影分割は「減五度」となるのは明白です。それらの音程は、音階数はそれぞれ4音のテトラコルドと5音のペンタコルドでありますが、1つの音を共有している為オクターヴは8つの階名で満たされる状態ではありますが、これはヘプタトニックから成立してオクターヴ累乗しているに過ぎません。つまりオクタトニック・スケールというのは実際にはオクターヴを9つの音階で割譲しない事には生じない事となります。
全音階的社会が拡大するのは概して関係調への近親性を利用して可動的臨時変化音を材料音として新たに増やして持ち込む事で得られる音楽観であります。即ち、全音階が半音階を目指すにはその第一歩としてヘプタトニック(7音)から少なくとも1つの材料音として増える社会を目指す事が先決となります。そこで「(コンビネーション・オブ・)ディミニッシュト・スケール」の成り立ちをあらためて考えるという訳です。
扨て、通俗的であった筈の世俗音楽での「増二度」音程ですが、増二度の転回すなわち陰影分割が「減七度」となるのも亦音楽社会の宿命の様な物でありましょう。この「減七度」というのは「みなし減七度」として同義音程としての恣意的な見方として「長六度」をあてがうと、途端に音楽社会を「恣意的」に見る事が可能になります。
その恣意的状況は扨措き、まずは「減七度」という状況が発生する音楽的状況からどのような「応用」が生まれたのかをひとたび確認する事にしましょう。
扨て、減七度を生ずる三度堆積の和音を表す事にしましょう。つまり減七の和音という4音の和音構成音となるコードを例示すれば良いのですが、ハルは譜例の様にまずは「G♯dim7」を示します。減七の和音は、その全音階的に三度下方(※カウンター・パラレル)にある音が省略された物とも用いられるので、「G♯dim7」という和音は「E7(♭9)」という短属九の根音省略形として見られる事が多い物です。
とはいえ、音楽の歴史はこうした状況から更に拡大していったのであり、短属九の根音省略となる上声部が「短三度等音程」構造という事を好い事に、根音もそれに乗じて「短三度等音程」を累積していくと、「G♯dim7」の和音構成音 [gis・h・d・f] とは全く異なる [e・g・b・cis (des)] を生ずる事になります。それが譜例の1〜4で示される物なのです。上声部の4音となる和音構成音とは異なる下声部での4音の双方を併存させる事でディミニッシュト・スケールという半音階社会への拡大する第一歩となる恣意的な音楽的状況のひとつの側面を生んだと言える訳です。
扨て、今度は上声部に備わる和音の側を同義音程和音として恣意的に見ていく事としましょう。下声部に生ずるバスは先の例1〜4と同じ音脈であります。5の例は1の例と全く同様ではありますが、5の場合は和音の側を一義的に「G♯dim7」とばかりに見ずに「Bdim7」「Ddim7」「Fdim7」という風に見る事も可能なのです。
同様にして6の例は「Bdim7」として見立てると同時に「Ddim7」「Fdim7」「A♭dim7」という風にも和音を見立てる事が可能な状況ですが、下声部に [g] を採らせているという状況に於て上声部を「A♭dim7」と見立てた時、上声部での [as] から見た七度音は実質的には [geses] であるので、下声部が [g] を採るという事は自ずと複調を一層喚起している状況である訳です。七度音由来の音度が2つ併存している以上、複調の喚起がより強まる状況であるという訳です。高中正義の「Blue Lagoon」はコレに近しく、減七をマイナー6th(♭5)と読み変える事で初めて、その複調および通常の最も靡き易い世界観である1番のしがらみから脱する状況を見据えつつモーダルかつ民族的なモードを使用する状況が整った恣意的な実態となる訳です。それが7〜8番の例と繋がる訳です。
100年以上前から、ハルが呈示するディミニッシュの世界観からの複調の例には同義音程和音の恣意的な転義が見られるにも関わらず同義音程和音の概念など無いとする無知蒙昧な指摘には笑止千万であります。
ひとたび3度音程堆積構造へと還元すればこそ、トリスタン和音とてハーフ・ディミニッシュ・コードへ還元する事は可能です。とはいえジャン゠ジャック・ナティエが33人の大家によるトリスタン和音の解釈を33人33様の例として取り上げている様に、トリスタン和音を一元的に、しかもハーフ・ディミニッシュ・コードとして見立てる事は非常に危険である訳ですが、トリスタン和音出現以降、和音体系は大きく変容したのも事実であり、ディミニッシュという世界観も結果的にはそうした多様な世界観を拡大させる事の助力となっている事も確かなのであります。
例えば、ホ音 [e] 音を根音とする減七の和音を形成してみましょう。和音構成音は下から [e・g・b・des] を形成する事となります。つまり、英名表記をすれば「E・G・B♭・D♭」という事になりまして、[des=D♭] は決して [cis=C♯] ではないのであります。
異名同音(=エンハーモニック)というのは、ギターのフレットやピアノの鍵盤上から見れば「物理的」には同じ所にある音であるという事をも意味しているので、音楽への配慮の足らない人からすれば《異名同音という実際があるのだから、音をどのように呼ぼうとも構わない》と考えてしまうのは誤りです。
それは、異名同音を「己の呼びたい方の音」として考えてしまう事が危険であるという意味でもあるので、7番目の音である「D♭」の異名同音は「C♯」なのであるも、決して7番目が6番目に置き換わる物ではないという事なので音度の捉え方を己の都合よく解釈してしまってはいけないのです。
前振りが長くなってしまいましたが、高中正義の名曲「Blue Lagoon」での曲冒頭に於けるコードは、ホ長調主和音が変位した和音であり(※ここの文は、《謬見として広く知られる事となってしまっている「Edim7およびEdim」という減七和音は”あたかも”ホ長調主和音が変位した和音の様に見せますが》という含意に過ぎず、次の過去のブログ記事を参照されたし)、根音を掛留させたままEメジャー7thとの2コード進行となっている物で、過去にも取り上げた事がありますが今回は譜例でも例示するという訳です(先のリンク先のPDF版はコチラ)。
(2019年10月20日加筆)

扨て、その「Blue Lagoon」冒頭のコードこそがキモなのでありますが、配慮に乏しい解釈として広く周知されてしまっている謬見となっているのも「Blue Lagoon」の悲哀なる側面でもありまして、その謬見たるや、冒頭のコードを「Edim7」(または、四和音でありながら七度音を明示しない不文律的表記としての「Edim」)という風に誤って充てられてしまっているという所が酷い誤りなのであります。こうしたコード理論方面を熟知している者ならば少しだけ考えを及ばせればそれが誤りである事は理解できる筈であるのに、コード表記にばかり躍起になってしまい、楽曲を構成している線的な部分を蔑ろにしている事で、和音構成音と、それに随伴するフレーズがコード表記のそれとアヴェイラブル・モード・スケールのどちらから照らし合わせても飽和してしまうという矛盾を晒す事に気付かないという状況を露呈しているのですから滑稽であります。
結論を言えば、「Edim7」と誤解されてしまうそれを正しく表すならば「Em6(♭5)」こそが正しい表記となります。とはいえ、マイナー6thフラッテッド5thのコード表記という物はおそらく馴染みの薄い表記であり、このコード表記を別のシーンできちんと取り扱っているのは濱瀬元彦著『チャーリー・パーカーの技法』位でしか見かけない物であります。換言すれば、濱瀬元彦のコード解釈のそれが如何にして音楽的に慮った解説なのかがあらためて能く判るという事でもありますが、他のシーンでは配慮の浅いコード表記嵌当が見受けられるという所が嘆かわしい側面でもあるという訳です。
では何故、「Blue Lagoon」のそれを「Edim7」と判断してはならないのか!? という事を詳らかに語る事としましょう。それでは、下記リンクのYouTube譜例動画を確認してもらう事に。
この譜例動画の弱起小節を除いた3小節目のメロトロンのパートを見て下さい。4拍目に [dis=D♯] 音が現れております。この小節でのコードは「Em6(♭5)」であるという事も同時に念頭に置いていただきたいと思います。
仮にこの箇所でのコードが「Edim7」であった場合、そのコード表記が示す通り [e] から数えた7番目の音は [des=D♭] である筈ですから、7番目のD♭とオクターヴ上の [e] の音との間には充填されるべき音が有る筈がないのです。なぜならばヘプタトニックを基とするのは歴然とした状況である為、コード表記がいくら「Edim」として七度音を明示化していない状況としてもアンサンブル上では間違いなく「D♭」音がある状況であるにも拘らず、コード表記の不十分さに胡座をかいて [dis] をガメついてしまったら、その時点でヘプタトニック・スケールではなく8音音階としてのモードを想起する事と同様の矛盾を晒す事になってしまいます。
正しく「Em6(♭5)」とやれば、その表記こそが決して当該和音の構成音としてではないアヴェイラブル・モード・スケールとしての姿から類推される「7番目の音」という状況をメロトロン・パートが [dis=D♯] 音であるという風に正しく活用される状況を生ずる為、矛盾した世界観の解釈の為に8音音階をモード想起する必要など全く無く大手を振って「Em6(♭5)」上で [dis=D♯] 音を使う事が理論的な側面からも正しく整合性の採れた活用となる訳なのであります。
つまり、減七和音という誤ったコード表記を正当化する為に、D♯音をストリングスが用いた途端に8音音階(オクタトニック)となるモード・スケールを想起する様に曲解するのは莫迦げた発想なのであり、「Em6(♭5)」と正しくやれば本来なら問題の無い事なのです。
加えて、仮にもコード表記「Edim」がディミニッシュ・トライアドと強弁した場合(伴奏にはD♭音が無いと考えて)、その場合モード想起としては「D♭」と「D♯」を共存できるのではなかろうか!? と考える人がおられるかもしれませんが、「D♭」を使った時点で、本来ならコードの伴奏として有るべき音に気付くはずですし、それに併存させて同度由来の変化音として「D♯」を想起するというのは、やはり同度由来の派生音を併存させる必要がある以上はヘプタトニックのモード想起が出来ない事を意味するのです。
扨て、「Em6(♭5)」を想起するとなると、モード想起は次に示す物になります。
※ディミニッシュ系となるコード・ヴォイシングのヴァリエーションは、シャイエの『音楽分析』にも触れられている様に、リンク先の例を参照。
このスケールは、Aルーマニアン・メジャー・スケールの5番目のモード・スケールという事になります。ルーマニアン・メジャー・スケールというのは聞き慣れないヘプタトニック・スケールかもしれませんが、リディアン・ドミナント7thスケールの第2音が半音下がった物として考える事が出来ます。「この様なモード、どうやって使うんだ!?」と疑問を抱く方もおられるかもしれません。用法的には長調に於けるサブドミナント・マイナーの使い方に似る所があると考えると容易です。無論、E音から見たⅣ度上の和音はマイナーになるのではなく、Aルーマニアン・メジャーでのA音上のダイアトニック・コードはAメジャー系になるのでありますが、その辺りを解説する事としましょう。
サブドミナント・マイナーの特徴的な用法としては、ドミナントを経由せずにトニックへの帰結感を柔和に齎す所にあります。ドミナントを経由せずに、という所が肝心なのですが、サブドミナント・マイナーの用法というのは実質、サブドミナントに進行時に於て下属調同主調の音脈、つまりは和声二元論的にマイナーの世界観を「プラガル」な状況として見立てる事で、下属調同主調の世界へとモーダル・インターチェンジを介す事で、実際には部分転調を生じているのです。サブドミナント・マイナーと変じた瞬間、その平行長調とは原調との調域が二全音/四全音調域同士での部分転調という事になるので、ハ長調が原調だった場合、「F△」へ進んで同主調音脈「Fm」となるのですが、この場合下属調同主調=Fmの平行長調=A♭という事となり、原調との調域と照らし合わせれば、その関係性があらためてお判りになるかと思います。
つまり、Eメジャーというホ長調に於て通常のサブドミナント=Aメジャーがサブドミナント・マイナーではなくAルーマニアン・メジャーに移旋したと考えると良いのです。それは、リディアン・ドミナント7thの第2音を半音下げたのと同様の音列なので、実質的にはメロディック・マイナー・モードの一部を変じている状況になるので、全体としては「マイナー感」が生まれる訳です。明示的なサブドミナント・マイナーとは異なるのでありますが、マイナー感に酷似するモードであるので音楽的な揺さぶりが大きくかかる事になるのです。ある意味では手垢のつきまくったサブドミナント・マイナーよりも使い道があるのかもしれません。それをさらりとやってのける高中正義の感性と、本曲の目指す世界観のそれにはあらためて称賛すべきでありましょう。
尚、譜例動画についてあらためて付言しておきますが、9小節目で表される「Esus4」は便宜的な表記であります。正確に表すならばギター・パートのヴォイシングを勘案すれば「Eadd4」でも良いと思います。場合によっては「E△7」を引きずったままのシーンも考えられる為、完全四度音を付与する「E△7add4」を用いたり、或いはその類型として「E△7sus4」と表記されるコードの用例も視野に入れる事が可能となります。
リック・ビアト流の表記をするならば、氏はadd4を「sus4/3」とも表記します。これは七度音の無い状況でありますが、氏の『THE BEATO BOOK』では「メジャー7th sus4」も漏れなく記載されているので、add4系統のコードを選択して表記しても良かったのでは無いのか!? と疑問を抱かれる方もおられるかと思います。とはいえ今回私が敢えてsus4表記にとどめた理由は次の通りです。
メジャー7th sus4というコードの構成音というのは、三全音を包含するので機能和声的な側面から見つめると「Ⅴ7omit5 on Ⅰ」という状況を喚起し易くなります。無論、メジャー7th sus4コードを充てる時には、そうした調的状況に負けじとする響きをモーダルに薫らせる為に用いる事が肝要なのでありますが、先述の通り「Blue Lagoon」は、
Aルーマニアン・メジャーの第5モード
↓
Eメジャー
という状況を固守したいが為に、ホ調での「Ⅴ度」となるドミナント感を極力忌避する必要があり、その上でメジャー7th sus4が喚起し易くなってしまうドミナント感をコード表記の上からも避けたというのが私の狙いであり、故に単に「sus4」表記で逃げたとも言えます。ただ、原曲当該箇所で [dis=D♯] 音は含まれないので、「Eadd4」という表記でも問題無いのですが、時代背景を勘案した上で当時ならsus4というコード解釈であろうという事も勘案した上での判断で「Esus4」という表記を充てました。
唯、コード表記の方を絶対視する癖の有る方はなるべくそうした癖を排除していただき、五線の中の音を重視していただきたいとあらためて思うところです。
2019年10月20日加筆分
Facebookからのアクセスから辿ると、日置寿士氏という方から本記事に対する論駁を受けましたが、私はこうした論駁は歓迎する立場と共に、私の本記事の欠点を挙げらている点にはあらためて感謝したいと思います。
彼の語る通り私自身もっと多義的な解釈で論ずるべきであったかもしれません。字数の面と今後のブログで語りたい(公にはしていない)目論見があって不十分な点があったかと思いますがその辺はあらためてお詫び申し上げます。
確かに、減七和音の構成音が短三度等音程構造である以上は少なくとも4種の調域を列挙した上で減七の同義音程和音であるマイナー6th(♭5)を呈示すれば確かにもっと多義的に例示する事ができたかもしれません。可能性ももっと拡大する訳ですからそれらをもっと呈示しても良かったであろうと思います。
然し乍ら私は、ルーマニアン・メジャーのモードの可能性を押し出す為にひとつの見立てを立てただけに過ぎず、一義的に調域を判定しているという意図はなかったのでその点だけは留意していただきたいと思います。
いずれにせよ「Em6(♭5)」というコードが他調の「Ⅳ」度由来という点だけを絞って、それが一義的解釈として捉えられてしまったのでありましょうが、私のスタンスとしては日置氏の想起する調域の判定も受け入れますし、どの様にモーダルに穿った見方をした所で、調性や協和の大義とも言える彼の表現する所の「啓蒙主義的」という点に音楽の調的な世界観が収斂する様に力が働くという含意も踏まえた上で深く首肯する所です。
とはいえ、ある楽曲の構造が完全な無調とは異なるも、半音階的全音階の世界を標榜する際に希薄化するドミナント感の楽曲の現実というものを私は本ブログで近いうちに取り上げる予定であるところに加え、本記事に於てはドミナントをなるべく経由せずに「Ⅰ」と「Ⅳ」での循環という構造を先ずは語っておきたかったので、私は「Em6(♭5)」というコードが他調の「Ⅳ」という事を最初に挙げていたのです。無論、この部分だけを読んでしまった場合、私が多義的かつ広範に亘って解釈しているとは思いつかないかもしれませんが、ある程度私のブログを通読しておられる方ならば私の本記事が、断定している様に一元的に語っていそうな事に疑問を抱かれるかもしれません。その辺りは誤解のなきようご理解のほどを。
また、「Ⅳ」に拘る私の個人的な理由として挙げておきたいのは、上方倍音列に下属音は登場しないからこそ取り上げたいのであります。こうした点を語る為に、私は前置きの様な感じで本記事を書いていたのであり、その後のフローラ・プリムの「I'm Coming For Your Love」の記事でも論じていたのです。
2019年12月7日加筆分
Facebookにて日置寿士氏から再度論駁されている様ではありますが、彼の謬見が甚だしいので取り敢えずは私の方から「正当」なソースを提示しようかと思います。
私の本記事の底意にあるものは、プラガルな世界観および民族的なものも含んだモーダルな世界観という物が協和感に強く基づく音楽観を恣意的に見る必要があるという点で、多くの場合西洋音楽の基礎のそれとは異なる大義で傾聴する必要がある物です。故に「同義音程」という恣意的に見る状況が生ずるのですが、その辺りを例示しておく事にします。これ以外にも彼は縷々述べておりますが、冒頭から斯様な断章取義に陥っているので応える必要はないでしょう。彼の論述の一部と私の例示するそれらを比較した上でどちらが正しいかご判断下さいませ。
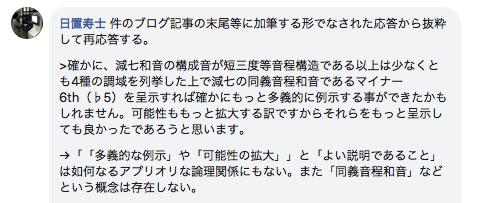
シャイエ/シャラン『音楽の総理論』65頁から

なにゆえ「恣意的」かつ「同義的」という状況が生ずるのか!? それは、西洋音楽が「恣意的」に避けて来た通俗的な線運びは乞丐(ジプシー、ロマ、ボヘミアンなど)社会を想起させてしまうから避けられてきたのであり、その線運びとやらの正体は「増二度」です。
増二度音程は恣意的に短三度にも聴こえるのであり、ヘプタトニックをオクタトニックのように音階の材料音を増やす恣意的な粉飾の物として使える素材へと変容した訳でありますが、フリギア終止がプラガルである様に、フリギアのⅤ度をムシカ・フィクタとして用いない禁則はそのままに、フリギアのⅤ度がムシカ・フィクタさせる事で生ずる上行導音をジプシー音階の導音および増四度として用いる方便と、フリギア調の多様な変容がアンダルシア進行として醸成されていった事で、斥けていた世界観が西洋音楽界隈でも用いられる様になったのが音楽観の恣意的な傾聴による物です。これが判らなければ終生音楽を正視していて下さい。
A・イーグルフィールド・ハル著『近代和聲学の説明と應用』(改題:『近代和聲の説明と應用』)にて述べられるEx.180の例は’Generator’と称される物で短属九の上声部を異名同音で読み替える事に依る多方面の調域への「着地」と、減七を形成する上声部とは別の短三度等音程として根音が跳躍する音脈を例示する物です。
譜例から読み取らねばならない事は、(コンビネーション・オブ・)ディミニッシュト・スケールという8音音階(オクタトニック・スケール)が発生する根拠です。
例えば、オクターヴという完全八度音程の一方を「増四度」で分割した時、その転回となる陰影分割は「減五度」となるのは明白です。それらの音程は、音階数はそれぞれ4音のテトラコルドと5音のペンタコルドでありますが、1つの音を共有している為オクターヴは8つの階名で満たされる状態ではありますが、これはヘプタトニックから成立してオクターヴ累乗しているに過ぎません。つまりオクタトニック・スケールというのは実際にはオクターヴを9つの音階で割譲しない事には生じない事となります。
全音階的社会が拡大するのは概して関係調への近親性を利用して可動的臨時変化音を材料音として新たに増やして持ち込む事で得られる音楽観であります。即ち、全音階が半音階を目指すにはその第一歩としてヘプタトニック(7音)から少なくとも1つの材料音として増える社会を目指す事が先決となります。そこで「(コンビネーション・オブ・)ディミニッシュト・スケール」の成り立ちをあらためて考えるという訳です。
扨て、通俗的であった筈の世俗音楽での「増二度」音程ですが、増二度の転回すなわち陰影分割が「減七度」となるのも亦音楽社会の宿命の様な物でありましょう。この「減七度」というのは「みなし減七度」として同義音程としての恣意的な見方として「長六度」をあてがうと、途端に音楽社会を「恣意的」に見る事が可能になります。
その恣意的状況は扨措き、まずは「減七度」という状況が発生する音楽的状況からどのような「応用」が生まれたのかをひとたび確認する事にしましょう。
扨て、減七度を生ずる三度堆積の和音を表す事にしましょう。つまり減七の和音という4音の和音構成音となるコードを例示すれば良いのですが、ハルは譜例の様にまずは「G♯dim7」を示します。減七の和音は、その全音階的に三度下方(※カウンター・パラレル)にある音が省略された物とも用いられるので、「G♯dim7」という和音は「E7(♭9)」という短属九の根音省略形として見られる事が多い物です。
とはいえ、音楽の歴史はこうした状況から更に拡大していったのであり、短属九の根音省略となる上声部が「短三度等音程」構造という事を好い事に、根音もそれに乗じて「短三度等音程」を累積していくと、「G♯dim7」の和音構成音 [gis・h・d・f] とは全く異なる [e・g・b・cis (des)] を生ずる事になります。それが譜例の1〜4で示される物なのです。上声部の4音となる和音構成音とは異なる下声部での4音の双方を併存させる事でディミニッシュト・スケールという半音階社会への拡大する第一歩となる恣意的な音楽的状況のひとつの側面を生んだと言える訳です。
扨て、今度は上声部に備わる和音の側を同義音程和音として恣意的に見ていく事としましょう。下声部に生ずるバスは先の例1〜4と同じ音脈であります。5の例は1の例と全く同様ではありますが、5の場合は和音の側を一義的に「G♯dim7」とばかりに見ずに「Bdim7」「Ddim7」「Fdim7」という風に見る事も可能なのです。
同様にして6の例は「Bdim7」として見立てると同時に「Ddim7」「Fdim7」「A♭dim7」という風にも和音を見立てる事が可能な状況ですが、下声部に [g] を採らせているという状況に於て上声部を「A♭dim7」と見立てた時、上声部での [as] から見た七度音は実質的には [geses] であるので、下声部が [g] を採るという事は自ずと複調を一層喚起している状況である訳です。七度音由来の音度が2つ併存している以上、複調の喚起がより強まる状況であるという訳です。高中正義の「Blue Lagoon」はコレに近しく、減七をマイナー6th(♭5)と読み変える事で初めて、その複調および通常の最も靡き易い世界観である1番のしがらみから脱する状況を見据えつつモーダルかつ民族的なモードを使用する状況が整った恣意的な実態となる訳です。それが7〜8番の例と繋がる訳です。
100年以上前から、ハルが呈示するディミニッシュの世界観からの複調の例には同義音程和音の恣意的な転義が見られるにも関わらず同義音程和音の概念など無いとする無知蒙昧な指摘には笑止千万であります。
2019-09-08 06:00

.jpg)



