マイク・マイニエリに学ぶ投影法(6) [楽理]
扨て、マイク・マイニエリにどれほど多くの事を学ぶ事が出来たでありましょうか!? こうした用法を知らなかった人が目からウロコが落ちるかの様にしてジャズのアプローチの多様さを今一度再確認してもらいたいものであります。
パーシケッティ著・水野久一郎訳『20世紀の和声法』での投影法という訳語は非常に判り易いものですし、シャルル・ケクラン著・清水脩訳『和声の変遷』第三章〈九の和音、十一の和音、十三の和音〉、ヴァンサン・ダンディ著・池内友次郎訳『作曲法講義第一巻』第六章〈下部共鳴〉をひとたび目を通せば、濱瀬元彦著『ブルー・ノートと調性』での5.1〈sus4の導入〉および6.4〈IIm7→V7の導入〉が意味する事など途端に繙く事が出来る訳です。私は濱瀬の著書を手に取る前に幸いにも先の著書の理解が前提にあった為と、私自身ベースを奏する為か非常に『ブルー・ノートと調性』は判り易かったものでしたが、多くの人には不思議と『ブルー・ノートと調性』というのは理解しづらい本だと認知されているのが実情です。それには濱瀬側のスタンスにも問題が無いとはいえません。彼は文中に参考とする書物を記すものの、注釈を付け加えたり参考文献の為の解説頁を割いたりはしません。おそらく大半の読者は濱瀬のスタンスが冷酷であるかの様に描写を伴わせる事でしょう。しかし、前提智識があると途端に氏のその言葉が仄めかしている楽理的背景が読み手の脳裡に幾つも浮かび、その脳裡に浮かんだそれが後押しをして完全に歩調を合わせるので実に読みやすいのであります。私は希有なタイプなんだろうか!?(笑)と思うこともありますが、前提智識の有無から読み手を選別するタイプの物であるとはいえ、どんな教科書であろうと答は其処に載っているという事実を読み手はいつしか忘却の彼方に葬り去っていないだろうか!? という事を痛切に感じ取り乍ら省みる必要性があるかと思います。同じ本を読んでいるのに理解が全く異なるのは今も昔も変わりはありませんが、答が書いてあるにも拘らず判らないのなら、何を問うても無駄ではないのか!? それを読み取れぬ事を補強しなくてはならないという事を知る事が先ず先決なのではないのか!? と思うことしきりです。
殊濱瀬元彦や菊地成孔関連になると相当なアレルギーを起こしている輩がいる為か、アマゾンの『ブルー・ノートと調性』の読者レビューなどでは最たる物ですが、デューク本郷などと名乗る馬鹿者は、己が理解に到達しきれない苛立ちを自己にぶつける事が出来ないが故に喧〈かまびす〉しく断罪している訳ですね。ああいう馬鹿は先のパーシケッティ、ケクラン、ダンディの著書を読んでいないのかと思わせる事しきりです。
無論、下方倍音列に於いてはジャック・シャイエ著・藤田幸雄、若桑毅共訳『音楽分析』では、それが多くの全音階的社会礼賛者にとっては大いに首肯したくなる判り易い言葉で下方倍音列を断罪してはおりますわ。而してどれほど読者がシャイエの自己矛盾をも読み取っているのか!? というと私の経験から言えば極々僅かであります。これにはアントワーヌ・ゴレアが十二音技法を礼賛するがあまり(ゴレアはシュトックハウゼンを手引きした人でもありますが、ケルン派と呼ばれるそれに最も注目すべき人物はウェルナー・マイヤー=エップラーであります)エドモン・コステールもやはりゴレアのそれに依拠してヒンデミットのそれを断罪する)、ヒンデミットの音程根音を断罪するそれと非常に似た側面を持ったものでして、それらに共通しているのは下方倍音列の是非は扨置き、結合差音の物理現象を全く視野に入れていない事に起因する自家撞着であります。下方倍音列と結合差音は全く別物です。
処が思弁的な側面に陥っている輩というのは、判り易い言説に依拠して脆弱な智識は「壓」を感じるそれに身を手向けるのであります。智力が脆弱である所に腑に落ち易い物とは得てして真を拏攫せぬ物であります。まあ、判り易さと伝え易さは同一ではなく、欲求が減退する事がなければ必ずしも判り易く伝える必要は無いのです。伝える力の維持と欲求の減退さえ防ぐ事ができれば、真に到達する事を教えるに際して必ずしも咀嚼する必要は無いのであります。処が大半の人間というのは咀嚼力が低下しております。噛む力というのもまさしく現代人の衰えている部分ではありまして、お判りとは思いますが茲での「咀嚼力」は「理解力」の意味ですのでお間違いの無いように。
扨て、今一度ジャック・シャイエの『音楽分析』について言及しておきますが、この著書は全体的に非常に深く首肯し得る名著の一つであり、音楽書として大いに参考すべき点の多い物ですが、第6章〈非自然的協和音、総論〉にて述べている短三度協和音の指摘に関する事で、結合差音の存在を全く無視して了って私感を述べている處があるため、茲にて断罪されるリーマンやエッティンゲンの下方倍音列の件をまともに受け止めてしまうと、それ以外のシャイエの堅実なまでの実直性に心を奪われ読み手は判断を誤りかねないので注意が必要なのです。
シャイエの指摘も尤もで、確かに短和音を組成する音程比(5:6:8)が倍音列に生ずるのは上方倍音列にある物の、長和音の音程比の様に倍音の根幹に短和音の音程比は備わっているものではなく、倍音列の一部の抜萃であるに過ぎない様にして枝葉を付けるかの様に存在しているのが実際です。故に短和音の持つ音程比を単に倍音列の帰依を同等に扱うのは甚だ疑問があるという論点こそは間違いではないものの、正論でもないのです。
何故かと言うと、結合差音を考慮に入れた場合「ミッシング・ファンダメンタル」と知られる現象を避けて通る事ができません。つまり、倍音列を例えば一様に各部分音を正弦波で「第1〜6次倍音」を同時に鳴らしたとして、茲から基音を鳴らすのをやめても、人間の耳は基音が在るかの様に聴こえるという現象。つまり、倍音の合致を元にして音を補完する現象やら、特定の倍音を制御する事で和音の平行進行にていつまでもピッチの上昇感を得る「無限音階」という現象もある通り、それらは基幹とする倍音を逸したりする事で得られる現象であり、特に基音を無くしても他の倍音列が聴覚を補完するという現象を目の当たりにすれば、短和音の音程比が倍音列の基音に根差している事など無関係であり、単に長和音を構成する音程比との「優位性」が短和音の場合は下位に置かれるという強度で語れば良いものを、シャイエは下方倍音列にレッテルを貼ってしまい自家撞着を語ってしまうのであります。
その論述の先には、著書刊行当初ではまだまだ新しい理論であったであろう、本人もそれの正当性についてはまだまだ懐疑的であるというギリシャのディミトリ・レヴィディスの新説である〈潜在倍音〉を取り上げて、此方を暗に支持しているのであります。
レヴィディスの言わんとする〈潜在倍音〉というのはつまり、上方倍音列の基音がc音にあるとしたら完全五度下方つまりf音を基音とする潜在的倍音列を視野に入れると、潜在倍音中に生ずる第七倍音がより低次に元の倍音列のe音より低い処に生ずる為、これが短三度を呼び込む脈だとする理論を取り上げている訳です。
シャイエが此の点に依拠する理由として推察するしかありませんが、基本的に協和性で以て語ろうとしているのが前提であるので、五度音程の共鳴体つまり完全五度音程を繰り返す五度圏にて長音階が成立しており、主音から完全五度下方にf音が存する所から完全五度累積を始める事でその累積は長音階のシステムを呼び込むのであるから、その潜在倍音という見渡しは理に適っているという所に依拠するものだというのは、大完全音列「シュステーマ・テレイオン」を生んだ歴史とも合致する為であるのは明白でありますが、実は現今社会では長三度も短三度も「不完全協和音程」なのであり、協和の優位度が違うだけなのであります。但し、短三度が協和度の最果てであるとは到底思えず、短三度よりもより不協和の要素の強い音程は微分音空間にはある筈ですが、第七倍音が齎す「自然七度」の音程は短七度よりも1単位六分音≒33セント程低く、これを転回させた場合広い二度音程になるのは言う迄もありません。短三度に近しくなる広くなってしまった二度音程に、「真正な短三度」とは異なる情緒を見付けた時、その「狭い三度」は短三度よりもビートが無いにも拘らず不協和となってしまいます(現今社会では既に気付いています)。
実践では応用しなかったものの、ブゾーニは三分音を用いて113種の調性を理論的に求め、アロイス・ハーバは自著『新和声法』にて三分音はおろか五分音組織も説明しております。
然も長三度とて純正三度と平均律とでは地位は安定的な物でもありません。その大きな違いはフリアン・カリジョの提唱した16分音の1単位微分音よりも広い為、純正長三度と平均律の長三度の間に収まる十二分音を微分音等分平均律の一つの最果てとして見立てる人も居るのであります。
そうした微分音的微小音程に拘泥するのが現実であるため、自然的に発生し得る短三度の帰依するのは、協和的な五度音程の累乗由来ではなく、不協和的な完全四度音程の累積から生じる短三度由来として、つまり完全四度螺旋で見れば短三度の出来が「不完全協和」ではなく「不完全不協和」に括られて然るべきだと私個人は感じております。こうした見渡しで短三度を鑑みると、オクターヴの繰り返しの無い直線平均律法(螺旋音律)やらその後の微分音空間での微小音程の取り扱いでの三度との整合性が取れるものであるが故の括りだと私は信じてやみません。つまり、シャイエが触れていないのは結合差音の存在と四度音程累積による短三度の出来であり(五度音程累積として協和性としての世界で短三度を推量している)の部分であるため、五度累積の側だけから観測するのは五度螺旋がヘプタトニック組織を超える時にはシントニック・コンマの半分の音程は既にズレが生じている訳なので、三度の時には敏感であった微分音的微小音程に、五度音程には頓着せずに四度累積も考慮に入れていないのは矛盾しているというのが私の指摘なのであります。
こうした理論に「ピアノ的発想」を以てして語ってしまうと、完全音程はいつも揺ぎない、それこそ微動だにしない指針としていつも働いてしまうのでありますが、これこそが陥穽に嵌ってしまいかねないモノでもあり、通常螺旋構造を求めているにも拘らずその螺旋構造にて外れてしまった音程を常にリアルタイムに修正しているのが人間の「音感」の素晴しさなのであり、修正した事に気付かず、修正した筈の微小音程に無頓着になってしまうのは体系とピアノ的音律に依って均されて疏外されてしまった音楽観の成れの果てだと私は常々感じております。故にこうした所をいつしか無視して完全音程以外の音程の情緒と協和性を求めるのは私はナンセンスな事だと思います。現実に、ビートを起こさぬ不協和な音程など沢山ある訳ですから。
シャイエの論述はオルガンの器楽音の組成もそれとなく語っている訳ですから、オルガンの部分音に対して明確に触れればよもやミッシング・ファンダメンタルを知らない訳がなく、結合差音ですら態と無視している様にしか思えません。パイプ・オルガン研究としてポツダム大のマルクス・アーベル等のグループが逆相同期の観測を成功させております。これについては2014年集英社新書にて刊行された蔵本由紀著『非線形科学 同期する世界』について詳述されておりまして、平均場近似を語る意味でも非常に重要な事であり、逆相を「半オクターヴ」として捉えた時の非直線形な視野からオクターヴを見るという、そうした均齊と呼べる「均衡状態」は、不協和の世界に於いて看過する事は決してできない実例であるのです。ですから、単に協和的社会の枠組みだけで推量するのは陥穽に嵌るのであり危険な事なのであります。
脆弱な知識しか有していなければ、強い牽引性を持つ全音階的&調性社会の枠組みからの後押しは非常に強固な信頼を以て後押ししてくれる事でしょう。極言すれば、脆弱な知識しか有しないものは、己の理解し易い根拠があればどんな物でも鬼に金棒だと思い込んでしまうのであります。シャイエのそれは全体的に非常に良い音楽書でありますが、先の点だけは疑念の目を向けざるを得ない論述であるのは言う迄もありません。
理解のし易さという点で「教え」という物が理解者にとって常に勝者であるとするならば、誰もが総じて産まれた時から敗者であったのが一所懸命正しい智慧を付けるに努めても何故勝者になれぬのか? 智慧とは身に付いた時に勝者になれるのではなく伝承・伝播させた時に始めて贏ち得る物なのです。身に付いた時は一人前にすぎません。つまり、己の矮小な心の中で収まっているだけの知恵とやらは智慧でないのです。己に身に付いていない物を伝えられる訳もない。伝えるつもりなど毛頭無ければそれは自己愛の為に智力を掻き集めようとしているだけの事で、単なる収集家の心理と変わりありません。
シャイエですらオルガンの音の組成を論述しておき乍らミッシング・ファンダメンタルの実例を忘却の彼方に葬り去ってしまうくらいなのに、どこぞの素養の薄い者がそうしたジレンマに気付く事ができるわけがありません。オルガンに準拠した管弦楽法の楽器編成に応用したのは何を隠そうラヴェルじゃありませんか。オルガンを組成している部分音が結果的に「平行」を伴う事を応用した編成法の一つではありませんか。
処が全音階的な枠組みである調性社会での厳しい仕来りは平行を禁則扱いする事です。つまり完全八度と完全五度の音程聯続はその音程自体が他の並進行および反進行よりも際立つから回避する訳で、茲を遵守するがあまりにいつしか重畳しい和音体系には及び腰になっておりますし、半音階的音脈など和声感の熟達に甘い状況に陥っているのが殆どのケースでありましょう。彼等はそこまで禁則に従順であるものの、十二度音程に依る対位法は習熟に達しているのだろうか!? と疑問を呈する左近治であります(笑)。
ジャズという世界は和音の重畳しい響きが前提です。能く云われる所の「硬い響き」です。処がジャズに於てもその重要な和音体系が汎く人口に膾炙し、コード表記体系がポピュラー音楽にも浸透する様になった頃は、和音進行に明確な四度進行になるかのような「勾配」付けという素振りは少なくなって来て、それに準じてポピュラー音楽界でも勾配の少ない和音進行が見られる様になってきたという変遷を辿っているのですが、つまり大局的に見れば調性感も稀薄になりつつあるという事を示唆していると云えるのでしょう。
例えばツーファイヴ進行が稀釈化した場合、それまでのツーファイヴ進行がIIm7 -> V7という「動的」であったものが「IIm7/V」若しくは「IV/V」という分数コード(又はonコード)という「静的」な物に置換して事足りる様になった物を「稀釈化」と呼んでいるのであり、和音進行という名の「勾配」は曖昧模糊なのであります。
では、私が和音進行に於いて「勾配」と態々呼んでいる事をきちんと理解をされている人はどれほど居られるでしょうか?和音進行に於ける「勾配」が意味する物は、先行する和音の和音外音に対して次の和音がその和音外音を使う様にして音脈が埋まる状況の事を「勾配」と呼んでいる訳です。つまり、G7がC△に進行するという状況に於ける全音階的見渡しに依るG7にとっての和音外音は「a、c、e」の脈です。これらに音が埋まれば勾配が付く訳です。a音はこの場合考慮にいれずともc音とe音への勾配は「半音」であるため、全音という勾配よりも強く傾斜が掛っている状況なのです。この強い半音の傾斜が全音階(=ダイアトニック)なシステムで生じている「2つの半音音程」を巧みに使っている事になり、弾みがとても強く付いている事になり、解決感を得るという事になるのです。
つまり、全音階的な進行感を得る「和音進行」というのは、先行する和音の和音外音の隙間を埋める為に後続の和音がその音脈を使うという事を意味するのです。処が和音が重畳しくなり、仮に全音階の総和音状態であるならば和音外音というのは調性を跳越する事になります。全音階の総和音状態というのは和音の動的な動きを止めてしまおうとはしないのです。総和音でなくとも重畳しい和音構成というのは全音階以外の音脈を求めて「平行」の欲求が現われるのが常なのです。ですから、和音進行が稀薄なモーダルな状況および単一の和音一発の状況というのは、和声的には重畳しいアンサンブルがなくとも、そうした総和音もしくは重畳しい和音の状況と非常に似通っている、という事を語って来たのであります。
今一度念頭に置いてもらいたいのはラヴェルのボレロです。100何十回もあの様な移旋を繰り返すモチーフの聯続、都度生じる移旋による奇を衒う調性を逸脱する音脈のそれをどれほど断罪すべきでしょうか!? 断罪等お門違いも甚だしい行為でありましょう。そのラヴェルが「クープランの墓」に於いてやはりマイナー・メジャー9thとも呼ぶに相応しい短和音の5度音を基準にした等比音程の和音の使用が見られる様に、よもや1世紀近い昔の人の音使いすら断罪してしまわなければならない程ジャズというのは狭い調性社会の仕来りに均されてしまう様になったのか!?と悲痛にすら思えてしまう訳ですね。
sus4コード(あくまでも四度音が後続和音の長三度に戻らない体系での四度和音としての)を巧く取り扱えない者も、概して投影法を知らないが故の事だったりします。
パーシケッティは自著『20世紀の和声法』にて、完全四度累積の四度和音の五声体までも協和音として取り扱い、六声体以上のそれを不協和音と括っております。完全四度の4回の重畳は既に短三度と長二度を生むのですが、和音の性格は転回させて単音程に凝集させてしまう事ではなく、音程そのものが性格を表わすという記述を最も注目する点であるのです。ハービー・ハンコックの作品『処女航海』等それなら実に深く首肯したくなる物ですね。『処女航海』はどこに解決しますかね!?エンハーモニック・トランスフォーメーションすら内在させてモーダルに跳越しますね。エンハーモニック・トランスフォーメーションを以てしないと解決先の進行の跳躍を説明するのは難しいでしょうが、エンハーモニック・トランスフォーメーションを示唆せずにモーダルな状況で解決させてはいても、自身のソロの音脈として投影法やエンハーモニック・トランスフォーメーションに依る音を脈にすれば多様なソロを展開させる事ができるでしょう。
リディアン・クロマティック・コンセプトを提唱したジョージ・ラッセルは、先にも語ったディミトリ・レヴィディスやらにもヒントを得ていて思い付いた見渡しなのでしょうが、何もリディアンを絶対的指針として基準を置く必要は全くないのであります。寧ろ、投影法では何処に共通音としての短和音・長和音があるか!?という事を見抜くのが大事であり、長和音よりも短和音の方が誘引材料として用い易いのは、短和音の構造そのものが5th音を中心とした構造として働くからであり、そこに長和音との鏡像の形が対称として現われる為、投影法に依る対称形と合致し強化されて使い易くなるからです。ですから、ジョージ・ラッセルの云うリディアン・トニックなど、ある基準となるモードから見た時のスケール・ディグリーなど色んな見渡しから音組織を俯瞰する能力を養った方が凡ゆる面で対応できるため、リディアン・クロマティック・コンセプトに頼ってしまう事がどれほど馬鹿げているかという事も同時に判る訳です。全音階的な音使いに辟易して半音階的揺さぶりの欲しい連中が、偶々リディアン・クロマティック・コンセプトに遭遇して半音階的な音脈を使う事に役立てる事が可能だとしても、それはリディアン・クロマティック・コンセプトが齎してくれた物ではなく、投影法の一部の音脈に過ぎないのです。北極点に探検に行くのに南下して地球をほぼ一周して北極点に辿り着くのがリディアン・クロマティック・コンセプトの様なものでして、以前にも横浜駅西口と東口を行き交うのに態々タクシー使う様なモンだと、リディアン・クロマティック・コンセプトを会得する事はそれに近い事だと罵倒したものでしたが、リディアン・クロマティック・コンセプトに対する非難は今も私は変わりありません。これに依拠する者の白痴加減が手に取る様に判るのが滑稽でしかありません。
とはいえ茲でリディアン・クロマティック・コンセプトについて茲であらためて述べる価値など無いのでありますが、ジョージ・ラッセルはもとよりシャイエの下方倍音列の断罪の論述にある通り、それを根拠にしてしまう類の素養に薄弱な者にあらためて感じ取ってもらう必要があるのは、今回のマイク・マイニエリのプレイが器楽的なハーモニーとして断罪し得るものであるか否かという事をあらためて自身の音楽的感性で感じ取ってもらいたいと思わんばかり。こうした音使いを体得できないのであらば、先述のケクラン、パーシケッティ、ダンディの音楽書の内容など何一つ理解出来ない事を実感して欲しいとあらためて思います。体得すら出来ておらぬ方面を思弁で語るなとあらためて言いたい所です。
そういう訳で今一度、マイク・マイニエリのアプローチを耳にしてもらいたいと思うのです。
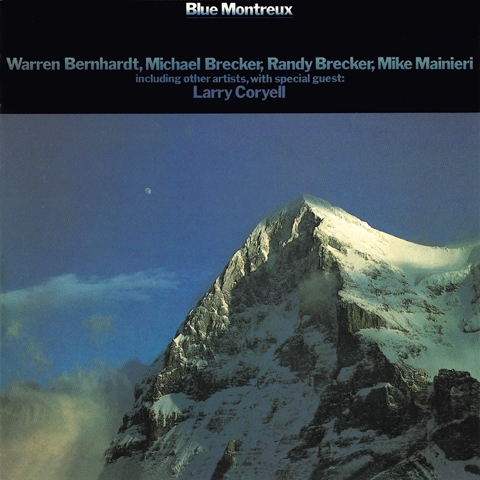
パーシケッティ著・水野久一郎訳『20世紀の和声法』での投影法という訳語は非常に判り易いものですし、シャルル・ケクラン著・清水脩訳『和声の変遷』第三章〈九の和音、十一の和音、十三の和音〉、ヴァンサン・ダンディ著・池内友次郎訳『作曲法講義第一巻』第六章〈下部共鳴〉をひとたび目を通せば、濱瀬元彦著『ブルー・ノートと調性』での5.1〈sus4の導入〉および6.4〈IIm7→V7の導入〉が意味する事など途端に繙く事が出来る訳です。私は濱瀬の著書を手に取る前に幸いにも先の著書の理解が前提にあった為と、私自身ベースを奏する為か非常に『ブルー・ノートと調性』は判り易かったものでしたが、多くの人には不思議と『ブルー・ノートと調性』というのは理解しづらい本だと認知されているのが実情です。それには濱瀬側のスタンスにも問題が無いとはいえません。彼は文中に参考とする書物を記すものの、注釈を付け加えたり参考文献の為の解説頁を割いたりはしません。おそらく大半の読者は濱瀬のスタンスが冷酷であるかの様に描写を伴わせる事でしょう。しかし、前提智識があると途端に氏のその言葉が仄めかしている楽理的背景が読み手の脳裡に幾つも浮かび、その脳裡に浮かんだそれが後押しをして完全に歩調を合わせるので実に読みやすいのであります。私は希有なタイプなんだろうか!?(笑)と思うこともありますが、前提智識の有無から読み手を選別するタイプの物であるとはいえ、どんな教科書であろうと答は其処に載っているという事実を読み手はいつしか忘却の彼方に葬り去っていないだろうか!? という事を痛切に感じ取り乍ら省みる必要性があるかと思います。同じ本を読んでいるのに理解が全く異なるのは今も昔も変わりはありませんが、答が書いてあるにも拘らず判らないのなら、何を問うても無駄ではないのか!? それを読み取れぬ事を補強しなくてはならないという事を知る事が先ず先決なのではないのか!? と思うことしきりです。
殊濱瀬元彦や菊地成孔関連になると相当なアレルギーを起こしている輩がいる為か、アマゾンの『ブルー・ノートと調性』の読者レビューなどでは最たる物ですが、デューク本郷などと名乗る馬鹿者は、己が理解に到達しきれない苛立ちを自己にぶつける事が出来ないが故に喧〈かまびす〉しく断罪している訳ですね。ああいう馬鹿は先のパーシケッティ、ケクラン、ダンディの著書を読んでいないのかと思わせる事しきりです。
無論、下方倍音列に於いてはジャック・シャイエ著・藤田幸雄、若桑毅共訳『音楽分析』では、それが多くの全音階的社会礼賛者にとっては大いに首肯したくなる判り易い言葉で下方倍音列を断罪してはおりますわ。而してどれほど読者がシャイエの自己矛盾をも読み取っているのか!? というと私の経験から言えば極々僅かであります。これにはアントワーヌ・ゴレアが十二音技法を礼賛するがあまり(ゴレアはシュトックハウゼンを手引きした人でもありますが、ケルン派と呼ばれるそれに最も注目すべき人物はウェルナー・マイヤー=エップラーであります)エドモン・コステールもやはりゴレアのそれに依拠してヒンデミットのそれを断罪する)、ヒンデミットの音程根音を断罪するそれと非常に似た側面を持ったものでして、それらに共通しているのは下方倍音列の是非は扨置き、結合差音の物理現象を全く視野に入れていない事に起因する自家撞着であります。下方倍音列と結合差音は全く別物です。
処が思弁的な側面に陥っている輩というのは、判り易い言説に依拠して脆弱な智識は「壓」を感じるそれに身を手向けるのであります。智力が脆弱である所に腑に落ち易い物とは得てして真を拏攫せぬ物であります。まあ、判り易さと伝え易さは同一ではなく、欲求が減退する事がなければ必ずしも判り易く伝える必要は無いのです。伝える力の維持と欲求の減退さえ防ぐ事ができれば、真に到達する事を教えるに際して必ずしも咀嚼する必要は無いのであります。処が大半の人間というのは咀嚼力が低下しております。噛む力というのもまさしく現代人の衰えている部分ではありまして、お判りとは思いますが茲での「咀嚼力」は「理解力」の意味ですのでお間違いの無いように。
扨て、今一度ジャック・シャイエの『音楽分析』について言及しておきますが、この著書は全体的に非常に深く首肯し得る名著の一つであり、音楽書として大いに参考すべき点の多い物ですが、第6章〈非自然的協和音、総論〉にて述べている短三度協和音の指摘に関する事で、結合差音の存在を全く無視して了って私感を述べている處があるため、茲にて断罪されるリーマンやエッティンゲンの下方倍音列の件をまともに受け止めてしまうと、それ以外のシャイエの堅実なまでの実直性に心を奪われ読み手は判断を誤りかねないので注意が必要なのです。
シャイエの指摘も尤もで、確かに短和音を組成する音程比(5:6:8)が倍音列に生ずるのは上方倍音列にある物の、長和音の音程比の様に倍音の根幹に短和音の音程比は備わっているものではなく、倍音列の一部の抜萃であるに過ぎない様にして枝葉を付けるかの様に存在しているのが実際です。故に短和音の持つ音程比を単に倍音列の帰依を同等に扱うのは甚だ疑問があるという論点こそは間違いではないものの、正論でもないのです。
何故かと言うと、結合差音を考慮に入れた場合「ミッシング・ファンダメンタル」と知られる現象を避けて通る事ができません。つまり、倍音列を例えば一様に各部分音を正弦波で「第1〜6次倍音」を同時に鳴らしたとして、茲から基音を鳴らすのをやめても、人間の耳は基音が在るかの様に聴こえるという現象。つまり、倍音の合致を元にして音を補完する現象やら、特定の倍音を制御する事で和音の平行進行にていつまでもピッチの上昇感を得る「無限音階」という現象もある通り、それらは基幹とする倍音を逸したりする事で得られる現象であり、特に基音を無くしても他の倍音列が聴覚を補完するという現象を目の当たりにすれば、短和音の音程比が倍音列の基音に根差している事など無関係であり、単に長和音を構成する音程比との「優位性」が短和音の場合は下位に置かれるという強度で語れば良いものを、シャイエは下方倍音列にレッテルを貼ってしまい自家撞着を語ってしまうのであります。
その論述の先には、著書刊行当初ではまだまだ新しい理論であったであろう、本人もそれの正当性についてはまだまだ懐疑的であるというギリシャのディミトリ・レヴィディスの新説である〈潜在倍音〉を取り上げて、此方を暗に支持しているのであります。
レヴィディスの言わんとする〈潜在倍音〉というのはつまり、上方倍音列の基音がc音にあるとしたら完全五度下方つまりf音を基音とする潜在的倍音列を視野に入れると、潜在倍音中に生ずる第七倍音がより低次に元の倍音列のe音より低い処に生ずる為、これが短三度を呼び込む脈だとする理論を取り上げている訳です。
シャイエが此の点に依拠する理由として推察するしかありませんが、基本的に協和性で以て語ろうとしているのが前提であるので、五度音程の共鳴体つまり完全五度音程を繰り返す五度圏にて長音階が成立しており、主音から完全五度下方にf音が存する所から完全五度累積を始める事でその累積は長音階のシステムを呼び込むのであるから、その潜在倍音という見渡しは理に適っているという所に依拠するものだというのは、大完全音列「シュステーマ・テレイオン」を生んだ歴史とも合致する為であるのは明白でありますが、実は現今社会では長三度も短三度も「不完全協和音程」なのであり、協和の優位度が違うだけなのであります。但し、短三度が協和度の最果てであるとは到底思えず、短三度よりもより不協和の要素の強い音程は微分音空間にはある筈ですが、第七倍音が齎す「自然七度」の音程は短七度よりも1単位六分音≒33セント程低く、これを転回させた場合広い二度音程になるのは言う迄もありません。短三度に近しくなる広くなってしまった二度音程に、「真正な短三度」とは異なる情緒を見付けた時、その「狭い三度」は短三度よりもビートが無いにも拘らず不協和となってしまいます(現今社会では既に気付いています)。
実践では応用しなかったものの、ブゾーニは三分音を用いて113種の調性を理論的に求め、アロイス・ハーバは自著『新和声法』にて三分音はおろか五分音組織も説明しております。
然も長三度とて純正三度と平均律とでは地位は安定的な物でもありません。その大きな違いはフリアン・カリジョの提唱した16分音の1単位微分音よりも広い為、純正長三度と平均律の長三度の間に収まる十二分音を微分音等分平均律の一つの最果てとして見立てる人も居るのであります。
そうした微分音的微小音程に拘泥するのが現実であるため、自然的に発生し得る短三度の帰依するのは、協和的な五度音程の累乗由来ではなく、不協和的な完全四度音程の累積から生じる短三度由来として、つまり完全四度螺旋で見れば短三度の出来が「不完全協和」ではなく「不完全不協和」に括られて然るべきだと私個人は感じております。こうした見渡しで短三度を鑑みると、オクターヴの繰り返しの無い直線平均律法(螺旋音律)やらその後の微分音空間での微小音程の取り扱いでの三度との整合性が取れるものであるが故の括りだと私は信じてやみません。つまり、シャイエが触れていないのは結合差音の存在と四度音程累積による短三度の出来であり(五度音程累積として協和性としての世界で短三度を推量している)の部分であるため、五度累積の側だけから観測するのは五度螺旋がヘプタトニック組織を超える時にはシントニック・コンマの半分の音程は既にズレが生じている訳なので、三度の時には敏感であった微分音的微小音程に、五度音程には頓着せずに四度累積も考慮に入れていないのは矛盾しているというのが私の指摘なのであります。
こうした理論に「ピアノ的発想」を以てして語ってしまうと、完全音程はいつも揺ぎない、それこそ微動だにしない指針としていつも働いてしまうのでありますが、これこそが陥穽に嵌ってしまいかねないモノでもあり、通常螺旋構造を求めているにも拘らずその螺旋構造にて外れてしまった音程を常にリアルタイムに修正しているのが人間の「音感」の素晴しさなのであり、修正した事に気付かず、修正した筈の微小音程に無頓着になってしまうのは体系とピアノ的音律に依って均されて疏外されてしまった音楽観の成れの果てだと私は常々感じております。故にこうした所をいつしか無視して完全音程以外の音程の情緒と協和性を求めるのは私はナンセンスな事だと思います。現実に、ビートを起こさぬ不協和な音程など沢山ある訳ですから。
シャイエの論述はオルガンの器楽音の組成もそれとなく語っている訳ですから、オルガンの部分音に対して明確に触れればよもやミッシング・ファンダメンタルを知らない訳がなく、結合差音ですら態と無視している様にしか思えません。パイプ・オルガン研究としてポツダム大のマルクス・アーベル等のグループが逆相同期の観測を成功させております。これについては2014年集英社新書にて刊行された蔵本由紀著『非線形科学 同期する世界』について詳述されておりまして、平均場近似を語る意味でも非常に重要な事であり、逆相を「半オクターヴ」として捉えた時の非直線形な視野からオクターヴを見るという、そうした均齊と呼べる「均衡状態」は、不協和の世界に於いて看過する事は決してできない実例であるのです。ですから、単に協和的社会の枠組みだけで推量するのは陥穽に嵌るのであり危険な事なのであります。
脆弱な知識しか有していなければ、強い牽引性を持つ全音階的&調性社会の枠組みからの後押しは非常に強固な信頼を以て後押ししてくれる事でしょう。極言すれば、脆弱な知識しか有しないものは、己の理解し易い根拠があればどんな物でも鬼に金棒だと思い込んでしまうのであります。シャイエのそれは全体的に非常に良い音楽書でありますが、先の点だけは疑念の目を向けざるを得ない論述であるのは言う迄もありません。
理解のし易さという点で「教え」という物が理解者にとって常に勝者であるとするならば、誰もが総じて産まれた時から敗者であったのが一所懸命正しい智慧を付けるに努めても何故勝者になれぬのか? 智慧とは身に付いた時に勝者になれるのではなく伝承・伝播させた時に始めて贏ち得る物なのです。身に付いた時は一人前にすぎません。つまり、己の矮小な心の中で収まっているだけの知恵とやらは智慧でないのです。己に身に付いていない物を伝えられる訳もない。伝えるつもりなど毛頭無ければそれは自己愛の為に智力を掻き集めようとしているだけの事で、単なる収集家の心理と変わりありません。
シャイエですらオルガンの音の組成を論述しておき乍らミッシング・ファンダメンタルの実例を忘却の彼方に葬り去ってしまうくらいなのに、どこぞの素養の薄い者がそうしたジレンマに気付く事ができるわけがありません。オルガンに準拠した管弦楽法の楽器編成に応用したのは何を隠そうラヴェルじゃありませんか。オルガンを組成している部分音が結果的に「平行」を伴う事を応用した編成法の一つではありませんか。
処が全音階的な枠組みである調性社会での厳しい仕来りは平行を禁則扱いする事です。つまり完全八度と完全五度の音程聯続はその音程自体が他の並進行および反進行よりも際立つから回避する訳で、茲を遵守するがあまりにいつしか重畳しい和音体系には及び腰になっておりますし、半音階的音脈など和声感の熟達に甘い状況に陥っているのが殆どのケースでありましょう。彼等はそこまで禁則に従順であるものの、十二度音程に依る対位法は習熟に達しているのだろうか!? と疑問を呈する左近治であります(笑)。
ジャズという世界は和音の重畳しい響きが前提です。能く云われる所の「硬い響き」です。処がジャズに於てもその重要な和音体系が汎く人口に膾炙し、コード表記体系がポピュラー音楽にも浸透する様になった頃は、和音進行に明確な四度進行になるかのような「勾配」付けという素振りは少なくなって来て、それに準じてポピュラー音楽界でも勾配の少ない和音進行が見られる様になってきたという変遷を辿っているのですが、つまり大局的に見れば調性感も稀薄になりつつあるという事を示唆していると云えるのでしょう。
例えばツーファイヴ進行が稀釈化した場合、それまでのツーファイヴ進行がIIm7 -> V7という「動的」であったものが「IIm7/V」若しくは「IV/V」という分数コード(又はonコード)という「静的」な物に置換して事足りる様になった物を「稀釈化」と呼んでいるのであり、和音進行という名の「勾配」は曖昧模糊なのであります。
では、私が和音進行に於いて「勾配」と態々呼んでいる事をきちんと理解をされている人はどれほど居られるでしょうか?和音進行に於ける「勾配」が意味する物は、先行する和音の和音外音に対して次の和音がその和音外音を使う様にして音脈が埋まる状況の事を「勾配」と呼んでいる訳です。つまり、G7がC△に進行するという状況に於ける全音階的見渡しに依るG7にとっての和音外音は「a、c、e」の脈です。これらに音が埋まれば勾配が付く訳です。a音はこの場合考慮にいれずともc音とe音への勾配は「半音」であるため、全音という勾配よりも強く傾斜が掛っている状況なのです。この強い半音の傾斜が全音階(=ダイアトニック)なシステムで生じている「2つの半音音程」を巧みに使っている事になり、弾みがとても強く付いている事になり、解決感を得るという事になるのです。
つまり、全音階的な進行感を得る「和音進行」というのは、先行する和音の和音外音の隙間を埋める為に後続の和音がその音脈を使うという事を意味するのです。処が和音が重畳しくなり、仮に全音階の総和音状態であるならば和音外音というのは調性を跳越する事になります。全音階の総和音状態というのは和音の動的な動きを止めてしまおうとはしないのです。総和音でなくとも重畳しい和音構成というのは全音階以外の音脈を求めて「平行」の欲求が現われるのが常なのです。ですから、和音進行が稀薄なモーダルな状況および単一の和音一発の状況というのは、和声的には重畳しいアンサンブルがなくとも、そうした総和音もしくは重畳しい和音の状況と非常に似通っている、という事を語って来たのであります。
今一度念頭に置いてもらいたいのはラヴェルのボレロです。100何十回もあの様な移旋を繰り返すモチーフの聯続、都度生じる移旋による奇を衒う調性を逸脱する音脈のそれをどれほど断罪すべきでしょうか!? 断罪等お門違いも甚だしい行為でありましょう。そのラヴェルが「クープランの墓」に於いてやはりマイナー・メジャー9thとも呼ぶに相応しい短和音の5度音を基準にした等比音程の和音の使用が見られる様に、よもや1世紀近い昔の人の音使いすら断罪してしまわなければならない程ジャズというのは狭い調性社会の仕来りに均されてしまう様になったのか!?と悲痛にすら思えてしまう訳ですね。
sus4コード(あくまでも四度音が後続和音の長三度に戻らない体系での四度和音としての)を巧く取り扱えない者も、概して投影法を知らないが故の事だったりします。
パーシケッティは自著『20世紀の和声法』にて、完全四度累積の四度和音の五声体までも協和音として取り扱い、六声体以上のそれを不協和音と括っております。完全四度の4回の重畳は既に短三度と長二度を生むのですが、和音の性格は転回させて単音程に凝集させてしまう事ではなく、音程そのものが性格を表わすという記述を最も注目する点であるのです。ハービー・ハンコックの作品『処女航海』等それなら実に深く首肯したくなる物ですね。『処女航海』はどこに解決しますかね!?エンハーモニック・トランスフォーメーションすら内在させてモーダルに跳越しますね。エンハーモニック・トランスフォーメーションを以てしないと解決先の進行の跳躍を説明するのは難しいでしょうが、エンハーモニック・トランスフォーメーションを示唆せずにモーダルな状況で解決させてはいても、自身のソロの音脈として投影法やエンハーモニック・トランスフォーメーションに依る音を脈にすれば多様なソロを展開させる事ができるでしょう。
リディアン・クロマティック・コンセプトを提唱したジョージ・ラッセルは、先にも語ったディミトリ・レヴィディスやらにもヒントを得ていて思い付いた見渡しなのでしょうが、何もリディアンを絶対的指針として基準を置く必要は全くないのであります。寧ろ、投影法では何処に共通音としての短和音・長和音があるか!?という事を見抜くのが大事であり、長和音よりも短和音の方が誘引材料として用い易いのは、短和音の構造そのものが5th音を中心とした構造として働くからであり、そこに長和音との鏡像の形が対称として現われる為、投影法に依る対称形と合致し強化されて使い易くなるからです。ですから、ジョージ・ラッセルの云うリディアン・トニックなど、ある基準となるモードから見た時のスケール・ディグリーなど色んな見渡しから音組織を俯瞰する能力を養った方が凡ゆる面で対応できるため、リディアン・クロマティック・コンセプトに頼ってしまう事がどれほど馬鹿げているかという事も同時に判る訳です。全音階的な音使いに辟易して半音階的揺さぶりの欲しい連中が、偶々リディアン・クロマティック・コンセプトに遭遇して半音階的な音脈を使う事に役立てる事が可能だとしても、それはリディアン・クロマティック・コンセプトが齎してくれた物ではなく、投影法の一部の音脈に過ぎないのです。北極点に探検に行くのに南下して地球をほぼ一周して北極点に辿り着くのがリディアン・クロマティック・コンセプトの様なものでして、以前にも横浜駅西口と東口を行き交うのに態々タクシー使う様なモンだと、リディアン・クロマティック・コンセプトを会得する事はそれに近い事だと罵倒したものでしたが、リディアン・クロマティック・コンセプトに対する非難は今も私は変わりありません。これに依拠する者の白痴加減が手に取る様に判るのが滑稽でしかありません。
とはいえ茲でリディアン・クロマティック・コンセプトについて茲であらためて述べる価値など無いのでありますが、ジョージ・ラッセルはもとよりシャイエの下方倍音列の断罪の論述にある通り、それを根拠にしてしまう類の素養に薄弱な者にあらためて感じ取ってもらう必要があるのは、今回のマイク・マイニエリのプレイが器楽的なハーモニーとして断罪し得るものであるか否かという事をあらためて自身の音楽的感性で感じ取ってもらいたいと思わんばかり。こうした音使いを体得できないのであらば、先述のケクラン、パーシケッティ、ダンディの音楽書の内容など何一つ理解出来ない事を実感して欲しいとあらためて思います。体得すら出来ておらぬ方面を思弁で語るなとあらためて言いたい所です。
そういう訳で今一度、マイク・マイニエリのアプローチを耳にしてもらいたいと思うのです。
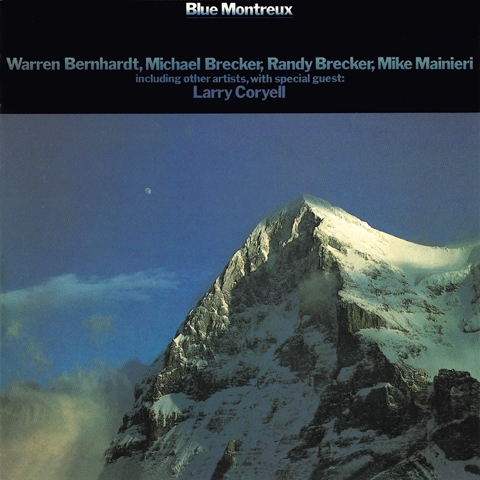
2014-10-09 23:40



