マイケル・ブレッカーの四分音運指について [楽理]
茲の所アリスタ・オールスターズの「Rocks」の話題を語っていたこともあり、折角の機会なので今回は記事タイトル通り、故マイケル・ブレッカーがクォーター・トーン(四分音)の運指を用いていると思われる例を語る事に。
前述の通り、アリスタ・オールスターズのアルバム『Blue Montreux 1』収録の「Rocks」でのマイク・マイニエリに依る投影法を扱ったばかりでもあり折角の機会なので、投影法の実例をもっと突き詰める前に先のアルバム「ブルー・モントルー」収録の他の曲にも語る価値が十二分にあるので、そうした意図でマイケル・ブレッカーの四分音の取り扱いを語る訳です。
サキソフォンを奏する事など無い門外漢の私がサキソフォンを語るのも烏滸がましいのでありますが、それならば一寸だけベース周りの事でも語ってみましょうか!?(笑)
 そういえば前回のサンプルで用いたチャップマン・スティックの音は、アルバム通りの音を企図したものではなく、実はキング・クリムゾンのアルバム『Discipline』収録の同名曲「Discipline」の音を模して作った音ですが、まあ、食いついてもらいたいのはそうした点ばかりではなく、アルバム「ブルー・モントルー」収録の他の作品という事で、これは今秋(2014年)に亦再発される予定だそうで、それもあってのレコメンドなのですね。とはいえ再発で「ブルー・モントルー 2」が予定されているのかどうかは現時点では不明ですが、孰れにせよ非常に高次な部分を堪能できるアルバムですので、ライヴ・アルバムとは雖もマスト・アイテムのひとつですので、ジェントル・ジャイアントに喩えるならば『Playing The Fool』の様な価値があるものだと思っていただければコレ幸いです(笑)。
そういえば前回のサンプルで用いたチャップマン・スティックの音は、アルバム通りの音を企図したものではなく、実はキング・クリムゾンのアルバム『Discipline』収録の同名曲「Discipline」の音を模して作った音ですが、まあ、食いついてもらいたいのはそうした点ばかりではなく、アルバム「ブルー・モントルー」収録の他の作品という事で、これは今秋(2014年)に亦再発される予定だそうで、それもあってのレコメンドなのですね。とはいえ再発で「ブルー・モントルー 2」が予定されているのかどうかは現時点では不明ですが、孰れにせよ非常に高次な部分を堪能できるアルバムですので、ライヴ・アルバムとは雖もマスト・アイテムのひとつですので、ジェントル・ジャイアントに喩えるならば『Playing The Fool』の様な価値があるものだと思っていただければコレ幸いです(笑)。
 扨て、故マイケル・ブレッカーの四分音の取り扱いについて漸く語りますが、その顕著な曲に「I'm Sorry」という曲があります。本曲は先のアルバム「ブルー・モントルー」の演奏バージョンはもとより、スタジオ・オリジナル・ヴァージョンであるマイク・マイニエリのソロ・アルバム『Love Play』収録の「I'm Sorry」もやはり四分音の運指を一部に使っているので、先ずはそのオリジナル・ヴァージョンでの方から当該個所を語る事にしましょう。
扨て、故マイケル・ブレッカーの四分音の取り扱いについて漸く語りますが、その顕著な曲に「I'm Sorry」という曲があります。本曲は先のアルバム「ブルー・モントルー」の演奏バージョンはもとより、スタジオ・オリジナル・ヴァージョンであるマイク・マイニエリのソロ・アルバム『Love Play』収録の「I'm Sorry」もやはり四分音の運指を一部に使っているので、先ずはそのオリジナル・ヴァージョンでの方から当該個所を語る事にしましょう。
オリジナル・アルバムで言うところのCDタイム0:28〜の部分、コードは「D7(♭13)」の部分にてマイケル・ブレッカーはCより1単位四分音高い「high C」からc音へ下行(アンブシュアもしくは四分音運指)させる部分がありますね。決してcis(=C#)として聴いてはならない音なのですが、お判りでしょうか!?
(※当該コードのルートから見た中立七度=Neutral seventhで、自然七度のSeptimal seventh および Harmonic seventh とは異なる)
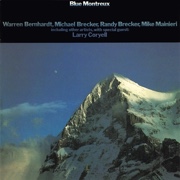 アルバム『ブルー・モントルー』側の方だとCDタイム0:26〜の所で同じくコード(此方はオルタード・テンションの♭9thを附与)「D7(♭9、♭13)」の部分にて顕著に使っている様であります。
アルバム『ブルー・モントルー』側の方だとCDタイム0:26〜の所で同じくコード(此方はオルタード・テンションの♭9thを附与)「D7(♭9、♭13)」の部分にて顕著に使っている様であります。
音を聴けばそれが四分音だというのは明確に判ります。つまり微分音的に誇張させた音から元にピッチを戻しているのではなく、明確な四分音運指を伴わせての1単位四分音高い「high C」の音を出してc音へポルタメントさせている訳ですね。
私がまだ微分音に不慣れな時というのは、どことなくそれを自分の記憶の中で「cis音」として歪めてしまっておりましたが、フレッテッド・ベースから弾き始めた私がベースを弾き始めて4年程してからフレットレスを弾く様になってからはこの差異が如実に実感できる様になった物です。半音階のそれでもどことなく釈然としない実感はあったものの身の回りに微分音を明確にする楽器が無いと確信を持てなかったという背景もありましたが、この時、半音階に均されてしまう危険性を痛切に感じ取ったモノでありましたし、フレットレス・ベースを手にする様になる事を機に、それまでジャコ・パストリアスの「トレイシーの肖像」で生ずる11次倍音のそれも、脳内で増四度と置換して聴いてしまう様な感覚が薄まり微分音の感覚が強化された事を実感するのでありました。慣れれば慣れるほど強化するのは凡ゆるシーンで実感した物です。

サキソフォンの四分音運指というのは実際には個体や製造モデルに依っても変化する様なのですが、ロチェスター大学のJ・W・ポールソンの"Quarter-tone Production on the Saxophone"ではセルマーのマークVIモデルにて、次の様な運指にて先のマイケル・ブレッカーの当該音が鳴るとの事で、それを示したのが次のex.1であります。
御存知の通りテナー・サキソフォンは移調楽器(=B♭)であるため、表記上は1オクターヴ+長二度高く記譜されるのでありまして、ですから譜例の様に、調号無しのハ長調では恰もd音より1単位四分音高い(異名同音はe音より3単位四分音低い)音として記譜され、実音は譜例の通り、c音より1単位四分音高い音(異名同音はd音より3単位四分音低い)として示しているのであります。
マイケル・ブレッカーが四分音そのものを使用する事に驚いた事はもとより、「D7(♭13)」というコードでの基底和音であるドミナント7th上の短七度と長七度の間にある中立音程にてその音脈を使うという事に、当時私は最も驚いた事だったのであります。なにしろ、こうした微分音的可動性を伴う音は3度で使う物だと盲信していたので、非常に驚いたものです。
然し乍らブルー・ノートの出現の歴史を鑑みれば七度の可動性をこの様に使っているのは非常に理に適っている事でありまして、短七度音よりも1単位6分音ほど低い自然七度の音を使っている訳でもありません。但し、コードの体系に頭デッカチになってしまっていると「D7」という基底和音上にて和音構成音の短七度よりも僅かに高い「high C」音を奏しても問題は無いのか!?という疑問を抱く人があるかと思いますが、実はこれも亦大変理に適っている事なのであります。
ドミナント7thコードというのは、和音構成音として生ずる長三度音と短七度が平均律にて600セントというトリトヌス=三全音を生ずる訳ですが、マイケル・ブレッカーが短七度と長七度の間の中立音程を使ったという事はトリトヌスが650セントに誇張されたと看做した状況でもある訳です。これはアロイス・ハーバの『新和声法』での四分音社会での取り扱いにて、24四分音階を650セントずつ円環にして「過大増四度圏」を創出させた共鳴圏と同様の事なのであります。抑もアロイス・ハーバが等分に細分化された微分音に視野を拡大する理由に、上方倍音列上に存する各オクターヴ相にある倍音列が微分音に嵌当させるという所に端を発しております。
第2〜4次倍音
第4〜8次倍音
第8〜16次倍音
第16〜32次倍音
第32〜64次倍音
という、各オクターヴ相内にてその間に存する倍音は微分音的にも配されている状況である為にこうした所に依拠して細分化する音階の音脈を用いている訳であります。四分音社会ですとオクターヴに24音がある音組織な訳ですが、取り敢えずは「テトラコルド」という4音列を用いて音組織を作ります。
各テトラコルドの連結は既知の音程である全音(=100セント)でディスジャンクトされていて、例えばC音を基本音とするならば、次のテトラコルドは650セント先にある訳です。650セントを全音でテトラコルドは割譲されるので、C音から550セント先が同一テトラコルド内の最果てであり、この550セントを使ってテトラコルドを組織する訳です。こうして重畳を繰り返し多層のテトラコルドが埋まる時には四分音階が成立する訳ですね。
この辺りを理解されるとエドモン・コステール著『和声の変貌』p.259《音高の論理と半音以外の平均率音梯》(※原訳文まま)を理解するに当たって補強されるかもしれませんが、『和声の変貌』自体も自家撞着に陥っている部分が多々有り、それは以前にも指摘したのは記憶に新しいかと思うのであまり参考にならないかもしれませんが、念のためこういう機会なので語っておくことにしました。
四分音という物は、意識すればする程音感を刺激してくれる物だと私は信じてやまないのでありますして、嘗て私が属和音上での第3度音を「枝葉」にして、通常の属七の構成音とは異なる完全四度等音程の一部を併存させた和音を取り上げた事があったモノでしたが、均齊を視野に入れた場合、等音程がどのような枝葉に吸着するのか!?という事を知る上でも興味深い事実を露にして呉れたのが「I'm Sorry」だったとも言えるでしょう。
例えば次のex.2の譜例では、基底にd音があり、その上にF#dimトライアドがあります。これらはセットとして考えれば「D7」というドミナント7thの和音の形であるのですが、マイケル・ブレッカーが使ったD音という基底音から見た短七度と長七度との間の中立音程を増三和音の第三度音として見立てると、ex.2の青色に見られる増三和音を併存している状況がお判りになるかと思いますが、私がこうして色彩的な音脈としてアレンジするとこうした響きも見えてくるのでありまして、同様に、マイケル・ブレッカーの奏する四分音を自然七度の脈として捉えると、ex.2譜例右側の緑色で示した増三和音の形も見えて来るのであります。
もちろん此れ等の拡大解釈した増三和音は、原曲「I'm Sorry」とは全く関係ありませんが、こうした均齊社会を色彩的に用いた和音として使った例として、坂本龍一の曲「夜のガスパール」ではやはり用いられている事を以前にもレコメンドした事があった様に、四分音社会へ拡大して捉える事のできる感覚という物をあらためて体得していたければコレ幸いであります。
大多数の人は、「I'm Sorry」の当該部分を四分音と捉えていないですし、おそらくやD7(♭13)から、何で態々装飾的に長七度から下降させてC音に滑らせて来るんだろう!?と感じてしまっている人すら少なくはないでしょう。ジャズ・シーンに於いても、こうした高次なプレイの現実があるにも拘らず、客観視して傍観している周囲の熟達が余りに浅い為、そんな素養の薄い連中が既知の体系(コード表記や単なる半音階社会)に均されてしまっている事が如何に愚かか!?という事があらためて判るかと思います。
このように四分音体系もあらためて取り上げつつ、次回は投影法を更に語って行く事にします。ハービー・ハンコックを取り上げるので、面白さも増すでありましょう。あとメディアント9thですね。是亦重要です。
2018年12月3日追記分
どうも我々の協和感の醸成というのは「完全音程」を半分に折半する事を志向する様です。シェーンベルクの十二音技法(セリー技法)に於て「半オクターヴ」という呼称が能く使われる様になったのは周知の事実でありまして、それも繙いてみれば完全八度を均等に2分割しているという状況なのであります。
では完全五度の均等な2分割はあるのかというと、此方も「中立三度」として平均律で見れば350セント近傍を標榜する音程でありまして、これも完全音程である完全五度の半分であるのです。アリストクセノスの『ハルモニア原論』の時代は固より、その後のザルザルでも用いられ中東地域で微分音が土着化したのはこういう背景があるからでもあります。
完全十二度音程=音程比 [1:3] である1オクターヴ+完全五度を半分にするとなると、こちらは平均律では950セントとなるのでありますが、奇しくも此方は自然七度の近傍値となるのでもありまして、人間の協和感というのはあらためて不思議な側面がある物です。
完全音程の内、完全四度は自然倍音列に現れる事はありません。なぜならこれは、完全八度と完全五度とによる「補充音程」という部分超過比となる「端切れ」なのである為、どうやっても純正音程として上方倍音列には現れない訳ですが、奇しくもこれも「半分」に2分割しようとすると「セプティマル・マイナー3rd」という250セントを標榜する近傍値を用いる事にもなり、以前にもサッフォーの「メティレーヌ」にて用いられていた事を解説したので記憶にある方もおられるかと思います。
同様にして完全十一度を2分割すると平均律では850セントとなり、中立六度が生ずる訳ですが、本記事のマイケル・ブレッカーはこの音脈を用いているという訳なのであります。ですので、徒らに微分音を用いた訳でもなく、単にプレイ上のピッチの悪い部分が偶々聴こえたという様な類の物では決して無い物であるのです。それは、ジャズやブルースが決して12等分平均律に靡くだけの物ではないとしてマイケル・ブレッカーは新たなる音脈を駆使していたというのがあらためてお判りになる事でありましょう。

前述の通り、アリスタ・オールスターズのアルバム『Blue Montreux 1』収録の「Rocks」でのマイク・マイニエリに依る投影法を扱ったばかりでもあり折角の機会なので、投影法の実例をもっと突き詰める前に先のアルバム「ブルー・モントルー」収録の他の曲にも語る価値が十二分にあるので、そうした意図でマイケル・ブレッカーの四分音の取り扱いを語る訳です。
サキソフォンを奏する事など無い門外漢の私がサキソフォンを語るのも烏滸がましいのでありますが、それならば一寸だけベース周りの事でも語ってみましょうか!?(笑)


オリジナル・アルバムで言うところのCDタイム0:28〜の部分、コードは「D7(♭13)」の部分にてマイケル・ブレッカーはCより1単位四分音高い「high C」からc音へ下行(アンブシュアもしくは四分音運指)させる部分がありますね。決してcis(=C#)として聴いてはならない音なのですが、お判りでしょうか!?
(※当該コードのルートから見た中立七度=Neutral seventhで、自然七度のSeptimal seventh および Harmonic seventh とは異なる)
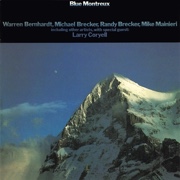
音を聴けばそれが四分音だというのは明確に判ります。つまり微分音的に誇張させた音から元にピッチを戻しているのではなく、明確な四分音運指を伴わせての1単位四分音高い「high C」の音を出してc音へポルタメントさせている訳ですね。
私がまだ微分音に不慣れな時というのは、どことなくそれを自分の記憶の中で「cis音」として歪めてしまっておりましたが、フレッテッド・ベースから弾き始めた私がベースを弾き始めて4年程してからフレットレスを弾く様になってからはこの差異が如実に実感できる様になった物です。半音階のそれでもどことなく釈然としない実感はあったものの身の回りに微分音を明確にする楽器が無いと確信を持てなかったという背景もありましたが、この時、半音階に均されてしまう危険性を痛切に感じ取ったモノでありましたし、フレットレス・ベースを手にする様になる事を機に、それまでジャコ・パストリアスの「トレイシーの肖像」で生ずる11次倍音のそれも、脳内で増四度と置換して聴いてしまう様な感覚が薄まり微分音の感覚が強化された事を実感するのでありました。慣れれば慣れるほど強化するのは凡ゆるシーンで実感した物です。

サキソフォンの四分音運指というのは実際には個体や製造モデルに依っても変化する様なのですが、ロチェスター大学のJ・W・ポールソンの"Quarter-tone Production on the Saxophone"ではセルマーのマークVIモデルにて、次の様な運指にて先のマイケル・ブレッカーの当該音が鳴るとの事で、それを示したのが次のex.1であります。
御存知の通りテナー・サキソフォンは移調楽器(=B♭)であるため、表記上は1オクターヴ+長二度高く記譜されるのでありまして、ですから譜例の様に、調号無しのハ長調では恰もd音より1単位四分音高い(異名同音はe音より3単位四分音低い)音として記譜され、実音は譜例の通り、c音より1単位四分音高い音(異名同音はd音より3単位四分音低い)として示しているのであります。
マイケル・ブレッカーが四分音そのものを使用する事に驚いた事はもとより、「D7(♭13)」というコードでの基底和音であるドミナント7th上の短七度と長七度の間にある中立音程にてその音脈を使うという事に、当時私は最も驚いた事だったのであります。なにしろ、こうした微分音的可動性を伴う音は3度で使う物だと盲信していたので、非常に驚いたものです。
然し乍らブルー・ノートの出現の歴史を鑑みれば七度の可動性をこの様に使っているのは非常に理に適っている事でありまして、短七度音よりも1単位6分音ほど低い自然七度の音を使っている訳でもありません。但し、コードの体系に頭デッカチになってしまっていると「D7」という基底和音上にて和音構成音の短七度よりも僅かに高い「high C」音を奏しても問題は無いのか!?という疑問を抱く人があるかと思いますが、実はこれも亦大変理に適っている事なのであります。
ドミナント7thコードというのは、和音構成音として生ずる長三度音と短七度が平均律にて600セントというトリトヌス=三全音を生ずる訳ですが、マイケル・ブレッカーが短七度と長七度の間の中立音程を使ったという事はトリトヌスが650セントに誇張されたと看做した状況でもある訳です。これはアロイス・ハーバの『新和声法』での四分音社会での取り扱いにて、24四分音階を650セントずつ円環にして「過大増四度圏」を創出させた共鳴圏と同様の事なのであります。抑もアロイス・ハーバが等分に細分化された微分音に視野を拡大する理由に、上方倍音列上に存する各オクターヴ相にある倍音列が微分音に嵌当させるという所に端を発しております。
第2〜4次倍音
第4〜8次倍音
第8〜16次倍音
第16〜32次倍音
第32〜64次倍音
という、各オクターヴ相内にてその間に存する倍音は微分音的にも配されている状況である為にこうした所に依拠して細分化する音階の音脈を用いている訳であります。四分音社会ですとオクターヴに24音がある音組織な訳ですが、取り敢えずは「テトラコルド」という4音列を用いて音組織を作ります。
各テトラコルドの連結は既知の音程である全音(=100セント)でディスジャンクトされていて、例えばC音を基本音とするならば、次のテトラコルドは650セント先にある訳です。650セントを全音でテトラコルドは割譲されるので、C音から550セント先が同一テトラコルド内の最果てであり、この550セントを使ってテトラコルドを組織する訳です。こうして重畳を繰り返し多層のテトラコルドが埋まる時には四分音階が成立する訳ですね。
この辺りを理解されるとエドモン・コステール著『和声の変貌』p.259《音高の論理と半音以外の平均率音梯》(※原訳文まま)を理解するに当たって補強されるかもしれませんが、『和声の変貌』自体も自家撞着に陥っている部分が多々有り、それは以前にも指摘したのは記憶に新しいかと思うのであまり参考にならないかもしれませんが、念のためこういう機会なので語っておくことにしました。
四分音という物は、意識すればする程音感を刺激してくれる物だと私は信じてやまないのでありますして、嘗て私が属和音上での第3度音を「枝葉」にして、通常の属七の構成音とは異なる完全四度等音程の一部を併存させた和音を取り上げた事があったモノでしたが、均齊を視野に入れた場合、等音程がどのような枝葉に吸着するのか!?という事を知る上でも興味深い事実を露にして呉れたのが「I'm Sorry」だったとも言えるでしょう。
例えば次のex.2の譜例では、基底にd音があり、その上にF#dimトライアドがあります。これらはセットとして考えれば「D7」というドミナント7thの和音の形であるのですが、マイケル・ブレッカーが使ったD音という基底音から見た短七度と長七度との間の中立音程を増三和音の第三度音として見立てると、ex.2の青色に見られる増三和音を併存している状況がお判りになるかと思いますが、私がこうして色彩的な音脈としてアレンジするとこうした響きも見えてくるのでありまして、同様に、マイケル・ブレッカーの奏する四分音を自然七度の脈として捉えると、ex.2譜例右側の緑色で示した増三和音の形も見えて来るのであります。
もちろん此れ等の拡大解釈した増三和音は、原曲「I'm Sorry」とは全く関係ありませんが、こうした均齊社会を色彩的に用いた和音として使った例として、坂本龍一の曲「夜のガスパール」ではやはり用いられている事を以前にもレコメンドした事があった様に、四分音社会へ拡大して捉える事のできる感覚という物をあらためて体得していたければコレ幸いであります。
大多数の人は、「I'm Sorry」の当該部分を四分音と捉えていないですし、おそらくやD7(♭13)から、何で態々装飾的に長七度から下降させてC音に滑らせて来るんだろう!?と感じてしまっている人すら少なくはないでしょう。ジャズ・シーンに於いても、こうした高次なプレイの現実があるにも拘らず、客観視して傍観している周囲の熟達が余りに浅い為、そんな素養の薄い連中が既知の体系(コード表記や単なる半音階社会)に均されてしまっている事が如何に愚かか!?という事があらためて判るかと思います。
このように四分音体系もあらためて取り上げつつ、次回は投影法を更に語って行く事にします。ハービー・ハンコックを取り上げるので、面白さも増すでありましょう。あとメディアント9thですね。是亦重要です。
2018年12月3日追記分
どうも我々の協和感の醸成というのは「完全音程」を半分に折半する事を志向する様です。シェーンベルクの十二音技法(セリー技法)に於て「半オクターヴ」という呼称が能く使われる様になったのは周知の事実でありまして、それも繙いてみれば完全八度を均等に2分割しているという状況なのであります。
では完全五度の均等な2分割はあるのかというと、此方も「中立三度」として平均律で見れば350セント近傍を標榜する音程でありまして、これも完全音程である完全五度の半分であるのです。アリストクセノスの『ハルモニア原論』の時代は固より、その後のザルザルでも用いられ中東地域で微分音が土着化したのはこういう背景があるからでもあります。
完全十二度音程=音程比 [1:3] である1オクターヴ+完全五度を半分にするとなると、こちらは平均律では950セントとなるのでありますが、奇しくも此方は自然七度の近傍値となるのでもありまして、人間の協和感というのはあらためて不思議な側面がある物です。
完全音程の内、完全四度は自然倍音列に現れる事はありません。なぜならこれは、完全八度と完全五度とによる「補充音程」という部分超過比となる「端切れ」なのである為、どうやっても純正音程として上方倍音列には現れない訳ですが、奇しくもこれも「半分」に2分割しようとすると「セプティマル・マイナー3rd」という250セントを標榜する近傍値を用いる事にもなり、以前にもサッフォーの「メティレーヌ」にて用いられていた事を解説したので記憶にある方もおられるかと思います。
同様にして完全十一度を2分割すると平均律では850セントとなり、中立六度が生ずる訳ですが、本記事のマイケル・ブレッカーはこの音脈を用いているという訳なのであります。ですので、徒らに微分音を用いた訳でもなく、単にプレイ上のピッチの悪い部分が偶々聴こえたという様な類の物では決して無い物であるのです。それは、ジャズやブルースが決して12等分平均律に靡くだけの物ではないとしてマイケル・ブレッカーは新たなる音脈を駆使していたというのがあらためてお判りになる事でありましょう。
2014-10-14 11:00





