『シェーンベルク音楽論選 様式と思想』(ちくま学芸文庫)待望の発刊 [書評]
2019年9月10日。筑摩書房から『シェーンベルク音楽論選 様式と思想』が文庫化として待望の発刊となった訳でありますが、文庫化が意味する様に過去の刊行物の復刻という事でもあります。

本書は嘗て三一書房から『音楽の様式と思想』というタイトルで刊行され、シェーンベルク自身が著す国内刊行物として十二音技法のそれが詳らかにされている物として筆頭に挙げられる物であり、古書でも市場価格として2万円を超えるのが珍しくなかった程(※2019年10月現在では文庫化もありだいぶ暴落している模様)で、なかなかの稀少本として扱われた物でした。私が入手したのは90年代にさしかかる頃でしたが、やはり1万円は優に超えていただろうと記憶しております。
他にも私の記憶では、神奈川県下の公共図書館で本書を読む事が出来たのは川崎市立図書館だけではなかったではなかろうか!? と思わんばかりです。神奈川県立図書館にも無い程の希少価値があったという意味です。こうした状況を鑑みれば如何に高値で取引されていたのかもあらためてお解りいただけるかと思います。
シェーンベルク自身が詳らかに十二音技法という体系を述べている本であるという事が重要であり、十二音技法を学ぶとなると意外にもシェーンベルクの著す書籍は他には無いと言っても過言ではないでしょう。何故なら、これまで国内で刊行されたシェーンベルクの著書は「調性音楽」を丁寧に取扱った上で、そこから発展される半音階的な転調や偽終止進行を詳らかにしているのが最たる特徴なのであり、本書以外でシェーンベルク自身の著す国内刊行物で十二音技法を学べる物はないと言っていいでしょう。
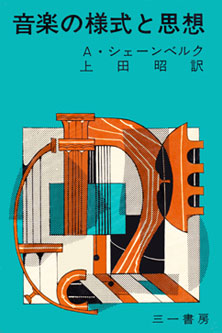
なにしろ十二音技法を学ぶに際して底本とされていた書籍・論文となると本書以外では、
『12音列におけるシンメトリー構造の研究 ─「6音グループとして」─』武田明倫(武蔵野音楽大学研究紀要)
『十二音技法に基づく 対位法の研究』クシェネーク 著/宗像敬 訳(音楽之友社)
『音楽の骸骨のはなし』柴田南雄 著(音楽之友社)
『アルバン・ベルク』フォルカー・シェルリース 著/岩下眞好・宮川尚理 訳(泰流社)
などを筆頭に挙げる事ができますが、これら以外にヴェーベルン関連図書や他の著者が十二音技法を取り上げる関連図書となれば枚挙に遑がありません。
総音程音列までを含めた上で抜萃すると上述の4つの物が最適な物であり、本書以外ではシェーンベルク本人の著書からは「調性」を学ぶ事になってしまう事でありましょう。ハンフレー・セアールや南弘明に依る十二音の解説はその後で読むべき物であり、それらは勿論シェーンベルク本人の刊行物ではありません。
実際に十二音技法を学ぶならば、シェーンベルクのそれとて決してオリジナルではなく多くの断章を取った物でもあるのは事実であり、ゲーテの『色彩論』のミレニアム機と他の分野で科学の発達と共に(ダーウィンの『進化論』やヘルムホルツの『音感覚論』もトレンドとなっていた)音楽界も他の分野から多くの援用に依って発展を目指し、特に絵画とは深い結びつきが起こっていた風潮がその後の十二音技法を作り上げたと言っても過言ではないでしょう。
事実、ブゾーニの三分音やヨーゼフ・マティアス・ハウアーのトロープなどのアイデアをもシェーンベルクが盗用(剽竊)したとも揶揄される物であり、実際に彼らと交流がありながらも袂別して非難されていたという背景もあったのであります。完全なオリジナルでもないという事を念頭に置いた上で「調性の暈滃」の世界観として軽い気持ちで読んでいただく方が真なる意味での十二音技法を捉えやすいかと思いますし、本書が最適な書籍であるという事も又事実であります。
そういう意味でも、新たに文庫化された事で寄せられた岡田暁生に依る跋文があらためて冴え渡っている事がお判りいただける事でしょう(無調の側面ばかりからシェーンベルクを観察していない部分など)。十二音技法とは平均律でなければ有り得ない「均齊」社会であり乍らも、均齊社会が平等→社会・共産主義に結び付けられた背景とは裏腹にシェーンベルク自身は保守主義を標榜していたにも拘らず国を追われ亡命せざるを得なかった状況など、遉の内容を鏤めている岡田の跋文には納得であると共に、調性社会を慮っていた事も詳密に語っている所も感服する事頻りなのであります。
シェーンベルク著となる国内刊行物(書簡物を除く)というのは、次に挙げる事ができます。
『和声学 第一巻』アーノルト・シェーンベルク 著/山根銀二 訳(『讀者の爲の飜譯』社)
『作曲法入門 初めて作曲を学ぶ人のための曲の範例』シェーンベルク 著/中村太郎 訳(カワイ楽譜)
『和声法』アルノルト・シェーンベルク 著/上田昭 訳(音楽之友社)
『和声法 新版』アルノルト・シェーンベルク 著/上田昭 訳(音楽之友社)
『音楽の様式と思想』A・シェーンベルク 著/上田昭 訳(三一書房)
『対位法入門』レナード・スタイン 編/山縣茂太郎・鴫原真一 訳(音楽之友社)
これらの書籍で意外にも誤解をされやすいのが上田昭が訳を手掛けた『和声法』(新版含)であり、それがシェーンベルクの和声の真髄だと思われている所です。シェーンベルクの和声の真髄とも言える書は 'Harmonielehre' および 'Theory of Harmony' ですが、こちらが訳された物は山根銀二が訳を手掛けた『和声学 第一巻』なのでありますが、残念乍ら完訳とはならずに「偽終止進行」に入る前までしか訳されていないので、もしも完訳されていたら恐らくは第三巻、第四巻位にはなっていたのではなかろうかと思います。
上田昭が訳を手掛けた『和声法』(新版含)は、版の新・旧で相当な程に文が改めてられており最早別物とも言えますし、比較考察するにも興味深い物となっておりますが、こちらは 'Structural Functions of Harmony' からの訳であり、過去の大家を例示し乍ら和声機能や調性を俯瞰する内容となっているので、十二音技法を駆使した時に生ずる和声というのは 'Harmonielehre' および 'Theory of Harmony' から学ばざるを得ないのが正直な所でありましょう。こうした誤解を招きつつ、市場でも遭遇する機会の少ないレア本である事から希少価値の側面が未だ見ぬ人々の欲求を不必要なまでに増幅させてしまい、本来有していない内容までもが謬見として人づてに誤って伝わってしまい、価値ばかりが独り歩きしてしまって本来の内容とそれに見合う市場価格が全く釣合いが採れぬままに高い値段で流通してしまっている典型的な例のひとつとして挙げる事が出来る物でありましょう。
音楽関連書籍というのはこうした謬見が価値を増幅させてしまう事は能くあります。概して西洋音楽界での正しい理解が他の音楽ジャンルへ正しく伝えられず、皮相的理解に及ぶ者が謬見に加えて市場価値の高騰を目論む連中が徒らな程に謬見を振りまいてしまうという例です。
例えば茲1四半世紀ほどを振り返ってみても『近代和声学』というのが典型的な例のひとつでもあるのですが、『近代和声学』がジャズにも広く援用可能な程に高次な和声を載せている本というのは実は、『近代和声学』松平頼則 著の方ではなく、A・イーグルフィールド・ハル 著/小松清 訳『近代和声の説明と応用』の方であったりします。《タイトルが違うではないか》と指摘する方もおられるかもしれませんが、ハルの『近代和声学の説明と応用』は直ぐに改題され『近代和声の説明と応用』という風になります。つまり、短縮された改題とて元々は『近代和声学〜』なのであります。
私の過去のブログをお読みいただければあらためてお判りになるでしょうが、ハルの目を瞠る和音の例示など十二分にジャズに援用可能な一世紀の時を経ても今猶新しい例を載せていたしていた物でありまして、古書市場となるといつの間にか松平頼則の方が役に立つとばかりにジャズやポピュラー音楽フィールドで謬見が蔓延る様になってしまった訳であります。
まあ恐らく想像に難くはないのですが、西洋音楽の方面からもポピュラー音楽からの方面からも皮相的理解にしか及ばぬ者が声だけは大きく吹聴する輩が居たのでありましょう。それが高じて謬見が伴う様になってしまい、いつしかジャズ/ポピュラー音楽フィールドでも松平頼則の方の『近代和声学』がバイブルの様に信奉されてしまう様になるという訳です。
どちらも良著ではありますが、ジャズ・フィールドで援用可能な程に新しい和声を載せているのは間違いなくハルの方なのである事は断言させていただきます。それにも気付かない連中が跋扈する様な世の中であってはいけないと思う事頻りです。まあ、これに酷似する側面が上田昭が訳を手掛けたシェーンベルクの『和声法』にもある、という事を述べたかった訳です。
十二音技法を学ぶにあたって重要な書籍は先にも挙げましたが、ヴェーベルン関連の書籍の方が詳らかに理解する事が出来るかと思います。トータル・セリエリズムにまで発展する事で真の均齊が理解できるからでありますが、国内刊行物でそれを詳らかにしてくれているのは矢張り柴田南雄の『音楽の骸骨のはなし』に右に出る物はなかろうかと思います。
ヴェーベルンの手で醸成された手法も四角連語(word square)ではまだまだ不充分であり、オーダー5としての連語の図版などを能く見かけるとは思いますが、オーダー12の連語というのは未だ発見されていないでありましょうし、オーダー10辺りが限度ある所が是亦辛い立ち位置にさせてしまうのも興味深い所です。
音楽というのは物理・数学の助力なしでは成立しない物の、殊更に協和・不協和の感覚的な側面というのは人間の感情に由来するので数学の公式の様に一義的な解を導く事はできない物です。処がこうした調性に靡く社会を数学的に捉える事には難儀するも、「無調」に於ける均齊社会を数学的に繙く事が出来てしまうというのが何とも皮肉な所でもあり、究極の均齊を数学の世界が導いてしまう事で、その可能性が意外にも少なく儚い社会を導いてしまったのも皮肉な側面であります。
坂本龍一曰く、セリーに基づいた音楽から歴時を無くして音楽全体の尺を「圧縮」した場合、その「紋様」となる音の分布は結局似た紋様に収束するという事を述べていた様に、十二音技法を俯瞰すれば結局はそういう事になるという訳です。松平頼暁が調性音楽の尺を際限なく引き延ばした時に調性の希釈化を狙った逆のアプローチとも言えますが、逆のアプローチを採られても調性が希釈化されてしまう事の現実と、無調を閉じ込めた時に収束してしまう可能性の少なさを露呈するのは実に儚い物です。
現在では、楽曲の徹頭徹尾でセリーに基づいて作曲するというよりも、曲の一部にセリーを導入したりする事があったりする物の、一時期持て囃された十二音技法は70年代に入ると途端に枯れていってしまった訳でもありますが、凡庸な線しか浮かんで来ない者が十二音技法を手にすれば、策に溺れてはいようとも己の素養を遥かに超えるクロマティシズムを具現化してくれるのは、その体系があまりに数学的な公式に酷似するかの様に見事な体系であるからです。逆を言えば、平時からクロマティシズムの素養に溢れている作曲家ほど十二音技法は重視していなかったと見る事も出来るでしょう。
とはいえ、ジャズの世界から見るとセリーというのは可能性がある物です。ジャズのクロマティックとて実際はドミナント・コードの引力に胡座をかいたテンション・ノートでどうにか「11音」を手繰り寄せ、逸音として生ずる12音目を用いて「半音階」を強弁する様な世界観に過ぎず、クロマティックな実際は増一度・短二度という隣接する「狭い音程」の連鎖が殆どの事であり、調性を薫らせない為に複音程や跳躍の大きな「leap」と呼ばれる音程がジャズに現われる事は稀でもあるのが現実で、そういう状況で「総音程音列」というクロマティシズムの用法は却って新鮮に映る事でありましょう。
なにしろ半音階は「12半音」なのでありますから音程種の数は1半音から11半音まで11種類ある事になります。これらの総数は66半音なので、12半音を形成する音程の組合せとして6組があるという風にも見る事が出来ます。それらの組合せとして、
11+1
10+2
9+3
8+4
7+5
6
という風にも見る事が出来ます。三全音が「6半音」という事を除いた他の半音数の音程の組合せは、それぞれが部分超過比となる転回音程を示しており(※長七度の部分超過比=転回=短二度)、古代ギリシャは上属音と下属音を形成するも、テトラコルドは五度ではなくその部分超過比となる音程=完全四度にテトラコルドとして形成させたのは実に示唆めいております。これにて大局的には全音階的テトラコルド、半音階的テトラコルド、四分音的テトラコルドを生じたのでありましたが、この時の体系で生じた最小の単位音程を継承しているのであるのならば、半音階など超越して四分音律(24EDO)が発展した筈でありますが実際にはそうではありません。
同時に、四分音的テトラコルドの単位微分音のそれよりも次点で狭く採られる「半音階」とて、この体系=半音階なのでもなく、12EDOが生じた訳でもありません。所謂「臨時記号」として可動的に生ずる半音階的な変化の正体の実際は、全音階テトラコルドの組合せに依って生ずる音階を為している一部の音列に於て本来期待される「半音」が「全音」へ可動的に変化して音程が拡大する事で生ずるのがムシカ・フィクタなのであり、半音階社会を唄おうとして半音を用いたのでは決してないのであります。
半音音程が全音音程に拡大する事はなにも、半音が全音へと「上行に拡大」するばかりでなく、下方にも拡大する事で全音を得る状況もあり得る訳でして、半音が全音に拡大する可動的変化=ムシカ・フィクタとはそういう事なのです。半音を唄おうとして形成されているのではないのです。本来期待されるべき半音の現われる位置に生ずる音を全音に拡大するのがムシカ・フィクタなのであります。
とはいえ13世紀のヨハネス・デ・ガルランディア(Johannes de Garlandia)の見解では可動的変化の動作をムジカ・ファルサとした上で「全音を半音に、あるいは半音を全音にするとき」という風に両義的に定義していたりもする物もありました。
ヨハネス・デ・ガルランディアの見解を私が援用したのは『ニュー・グローヴ世界音楽大事典 第18巻』p.124 からであるので、文中の「ムジカ某し」がムシカではない所にも注意すべき点でありますが、これまで私は幾度となく過去の記事で述べているように 'musica' をムジカとは呼びません。ムジカはイタリア語の発音であり、ムシカはそれよりももっと古いラテン語の発音であるからです(前掲「ムシカ・フィクタ」のURLリンクを参照)。
広義でのムシカ・フィクタというのは「B♭」音の出現の為にしか用いられなかったとか、「F♯」の出現は13世紀まで無かったとする研究(9世紀の時点で実際にはあった)など諸説ありますが、多くの体系が醸成されつつあったのは13世紀以降15世紀に到っての事であるという音楽の歴史が存在しているのは認めざるを得ない物であり、音階の成り立ちをギリシャ時代まであらためて遡ると、そこには全音階的テトラコルドの他に、半音階的テトラコルドと四分音的(異名同音的)テトラコルドがあった事を確認する必要があります。
三全音を回避する為の方策として体系化されたのが10世紀初頭のムシカ・エンキリアディスと言われるので、声部の独立性と共に複調的に生ずる世界観が存在していた事が判ります。そういう意味では、かなり制約のないムシカ・フィクタが横行していた事も同時に理解できるという訳です。
ただ、ギリシャ時代にはテトラコルド体系として用意されていたひとつの半音階的テトラコルドに属する採り方の内のひとつ、半音階が連続する(短二度の連続)が現在では増一度および短二度が連続する音程としてダブル・クロマティックがありますが、こうした音程の採り方が多くなるのは和声体系が整備されて以降、対位法のそれと和声法のそれとが組み合わさって生じて来てからではなかろうかと思います。
ダブル・クロマティックの例として、加山雄三の「君といつまでも」のメロディーの「つつむ〜♪」という様なそれもダブル・クロマティックですが、意外にもこうした線運びは歴史的にはかなり昔から存在してはいたものの、実際に使われる様になるのは相当後になっての事だという事でもあります。
ムシカ・フィクタは相当昔から使われていたにも拘らずそれを半音階として標榜する世界観として抱括的に使われていた訳でもなく、結果的に等分平均律を目指す事でより強化される事となるのがメルセンヌの時代にまで時を進めてしまうのですから実に皮肉な物です。
テトラコルド体系(=古代ギリシャ時代のシュステーマ・テレイオン〈大完全音列〉)まで目を向ければ自ずとお判りですが、真にそれらの体系の中で最小の単位音程を標榜する様にして音階が生じたのだと強弁するのであれば、その後には半音階が醸成されるのではなく四分音体系が広まっていた筈であります。
実際には四分音体系は廃れてしまっていた訳ですから当時の人々の標榜する最小の単位音程は四分音を強固なまでに採用してはいなかったという事でもあります。
つまりは半音階ありきでもなかったという事も同時に言える為、全音階的テトラコルドの中で全音音程に随伴する半音のそれらが組み合わさって音階を作ったのであるので、半音階を巧緻に設えて音階が生じていた訳でも無いのが実際なのです。半音階ありきで音楽を語ろうとするのはあまりにも近視眼的な視点であります。
現今社会において整備された音楽の大系を無意識なまでに利用する事が可能になっているとは雖も、現存する楽器の利便性や現在まで広く知られる過去の音楽の存在を規準に「十二等分平均律ありき」として半音階が常に音楽社会の礎となっていた訳では決して無く、半音階を12等分平均律として奏する事が出来る様になったのは工業的な技術の発達で楽器が整備された事に加え、科学が黎明期を終えて醸成されて行くと共に他の分野へ敷衍する事となって発達と整備が為されたからなのであり、そうした時代を経て不等分平均律が等分平均律として広く用いられる様になったというのが半音階の歴史とも言えるでしょう。
そうしてその後に成立する事となる半音階社会の醸成が、不等分平均律時代でも半音階を駆使する過去の大家の作品(J. S. バッハ)が、シェーンベルクの十二音技法という体系の中に対位法的和声法に巧妙に援用すると共に、等方に転調も可能な状況を生む音律としてメルセンヌが12EDOを提唱した矢張り是亦過去の大家の提唱を援用して等分平均律という体系は一定以上の地位を確保してきた訳であり、音律と音階がそもそも同じ物だと考えてしまう浅薄な知識をも正して理解して欲しいと思わんばかりです。
任意の音から開始された音がこれらの音程を「巧みに使って」終わる時、開始時の音から三全音離れた音で終わるという事を遵守すれば、全音程シリーズとして半音階の世界を実現させたという事になります。こういう音程を意識したフレージングなど、ジャズのウォーキング・ベースはまだまだ可能性が残されているであろうと思います。
ただ、こうした着想で半音階を眺めるにはシェーンベルクの著書では『音楽の様式と思想』が最も学べる物なのでありますが、私がジャズのウォーキング・ベースに対して十二音技法を対照させるのは、既知の体系整備される和音に対して「半音階的揺さぶり」をかける動機として用いる為の方策として取り上げているだけに過ぎません。凡ゆる調性の呪縛から逃れようとして体系整備を施した十二音技法のそれを都合良く援用しているに過ぎないので、私のその解釈が十二音技法だと近視眼的に捉えてしまうのは本末顛倒であります。
とはいえシェーンベルク自身も、過去の大家の作品が如何様にして半音階的な要素を纏って来たか!? という事を詳らかに傍証を取り上げて行くのです。無論、その先には突如として十二音技法という、音楽を構築する様に展開されて行くので、作曲をしようとは毛頭思ってもいない読者からすれば、その体系の最も根幹と成す部分がやたらと敷居が高くなってしまうかもしれません。
十二音技法以外の方策で半音階を纏って来た理由というのは、対位法社会に於て三全音回避に依る変応、倚音、逸音という声部の独立性と共に、原調は必ずしも一元的に採る必要のない定旋律と対旋律との関係にこそ多くの秘密が宿っているのであり、和声的体系というのは調性を一元的にしかねない側面もあるという事を知った上で、対位法の可能性の方を深く知る方が得策であろうかと思います。
調性が稀釈化される要素に鼻から十二音技法があった訳ではないという事を念頭に置きつつ、体系としての十二音技法とは別に、半音階が齎す暈滃の仕組みを知っておく必要があろうかと思いますが、シェーンベルクは過去の大家の作品を取り上げ乍ら自身の体系を語っているのが『Style And Idea』なのであります。

本書は嘗て三一書房から『音楽の様式と思想』というタイトルで刊行され、シェーンベルク自身が著す国内刊行物として十二音技法のそれが詳らかにされている物として筆頭に挙げられる物であり、古書でも市場価格として2万円を超えるのが珍しくなかった程(※2019年10月現在では文庫化もありだいぶ暴落している模様)で、なかなかの稀少本として扱われた物でした。私が入手したのは90年代にさしかかる頃でしたが、やはり1万円は優に超えていただろうと記憶しております。
他にも私の記憶では、神奈川県下の公共図書館で本書を読む事が出来たのは川崎市立図書館だけではなかったではなかろうか!? と思わんばかりです。神奈川県立図書館にも無い程の希少価値があったという意味です。こうした状況を鑑みれば如何に高値で取引されていたのかもあらためてお解りいただけるかと思います。
シェーンベルク自身が詳らかに十二音技法という体系を述べている本であるという事が重要であり、十二音技法を学ぶとなると意外にもシェーンベルクの著す書籍は他には無いと言っても過言ではないでしょう。何故なら、これまで国内で刊行されたシェーンベルクの著書は「調性音楽」を丁寧に取扱った上で、そこから発展される半音階的な転調や偽終止進行を詳らかにしているのが最たる特徴なのであり、本書以外でシェーンベルク自身の著す国内刊行物で十二音技法を学べる物はないと言っていいでしょう。
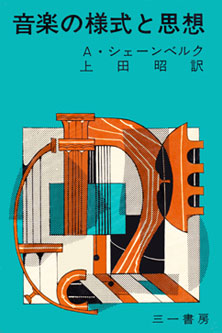
なにしろ十二音技法を学ぶに際して底本とされていた書籍・論文となると本書以外では、
『12音列におけるシンメトリー構造の研究 ─「6音グループとして」─』武田明倫(武蔵野音楽大学研究紀要)
『十二音技法に基づく 対位法の研究』クシェネーク 著/宗像敬 訳(音楽之友社)
『音楽の骸骨のはなし』柴田南雄 著(音楽之友社)
『アルバン・ベルク』フォルカー・シェルリース 著/岩下眞好・宮川尚理 訳(泰流社)
などを筆頭に挙げる事ができますが、これら以外にヴェーベルン関連図書や他の著者が十二音技法を取り上げる関連図書となれば枚挙に遑がありません。
総音程音列までを含めた上で抜萃すると上述の4つの物が最適な物であり、本書以外ではシェーンベルク本人の著書からは「調性」を学ぶ事になってしまう事でありましょう。ハンフレー・セアールや南弘明に依る十二音の解説はその後で読むべき物であり、それらは勿論シェーンベルク本人の刊行物ではありません。
実際に十二音技法を学ぶならば、シェーンベルクのそれとて決してオリジナルではなく多くの断章を取った物でもあるのは事実であり、ゲーテの『色彩論』のミレニアム機と他の分野で科学の発達と共に(ダーウィンの『進化論』やヘルムホルツの『音感覚論』もトレンドとなっていた)音楽界も他の分野から多くの援用に依って発展を目指し、特に絵画とは深い結びつきが起こっていた風潮がその後の十二音技法を作り上げたと言っても過言ではないでしょう。
事実、ブゾーニの三分音やヨーゼフ・マティアス・ハウアーのトロープなどのアイデアをもシェーンベルクが盗用(剽竊)したとも揶揄される物であり、実際に彼らと交流がありながらも袂別して非難されていたという背景もあったのであります。完全なオリジナルでもないという事を念頭に置いた上で「調性の暈滃」の世界観として軽い気持ちで読んでいただく方が真なる意味での十二音技法を捉えやすいかと思いますし、本書が最適な書籍であるという事も又事実であります。
そういう意味でも、新たに文庫化された事で寄せられた岡田暁生に依る跋文があらためて冴え渡っている事がお判りいただける事でしょう(無調の側面ばかりからシェーンベルクを観察していない部分など)。十二音技法とは平均律でなければ有り得ない「均齊」社会であり乍らも、均齊社会が平等→社会・共産主義に結び付けられた背景とは裏腹にシェーンベルク自身は保守主義を標榜していたにも拘らず国を追われ亡命せざるを得なかった状況など、遉の内容を鏤めている岡田の跋文には納得であると共に、調性社会を慮っていた事も詳密に語っている所も感服する事頻りなのであります。
シェーンベルク著となる国内刊行物(書簡物を除く)というのは、次に挙げる事ができます。
『和声学 第一巻』アーノルト・シェーンベルク 著/山根銀二 訳(『讀者の爲の飜譯』社)
『作曲法入門 初めて作曲を学ぶ人のための曲の範例』シェーンベルク 著/中村太郎 訳(カワイ楽譜)
『和声法』アルノルト・シェーンベルク 著/上田昭 訳(音楽之友社)
『和声法 新版』アルノルト・シェーンベルク 著/上田昭 訳(音楽之友社)
『音楽の様式と思想』A・シェーンベルク 著/上田昭 訳(三一書房)
『対位法入門』レナード・スタイン 編/山縣茂太郎・鴫原真一 訳(音楽之友社)
これらの書籍で意外にも誤解をされやすいのが上田昭が訳を手掛けた『和声法』(新版含)であり、それがシェーンベルクの和声の真髄だと思われている所です。シェーンベルクの和声の真髄とも言える書は 'Harmonielehre' および 'Theory of Harmony' ですが、こちらが訳された物は山根銀二が訳を手掛けた『和声学 第一巻』なのでありますが、残念乍ら完訳とはならずに「偽終止進行」に入る前までしか訳されていないので、もしも完訳されていたら恐らくは第三巻、第四巻位にはなっていたのではなかろうかと思います。
上田昭が訳を手掛けた『和声法』(新版含)は、版の新・旧で相当な程に文が改めてられており最早別物とも言えますし、比較考察するにも興味深い物となっておりますが、こちらは 'Structural Functions of Harmony' からの訳であり、過去の大家を例示し乍ら和声機能や調性を俯瞰する内容となっているので、十二音技法を駆使した時に生ずる和声というのは 'Harmonielehre' および 'Theory of Harmony' から学ばざるを得ないのが正直な所でありましょう。こうした誤解を招きつつ、市場でも遭遇する機会の少ないレア本である事から希少価値の側面が未だ見ぬ人々の欲求を不必要なまでに増幅させてしまい、本来有していない内容までもが謬見として人づてに誤って伝わってしまい、価値ばかりが独り歩きしてしまって本来の内容とそれに見合う市場価格が全く釣合いが採れぬままに高い値段で流通してしまっている典型的な例のひとつとして挙げる事が出来る物でありましょう。
音楽関連書籍というのはこうした謬見が価値を増幅させてしまう事は能くあります。概して西洋音楽界での正しい理解が他の音楽ジャンルへ正しく伝えられず、皮相的理解に及ぶ者が謬見に加えて市場価値の高騰を目論む連中が徒らな程に謬見を振りまいてしまうという例です。
例えば茲1四半世紀ほどを振り返ってみても『近代和声学』というのが典型的な例のひとつでもあるのですが、『近代和声学』がジャズにも広く援用可能な程に高次な和声を載せている本というのは実は、『近代和声学』松平頼則 著の方ではなく、A・イーグルフィールド・ハル 著/小松清 訳『近代和声の説明と応用』の方であったりします。《タイトルが違うではないか》と指摘する方もおられるかもしれませんが、ハルの『近代和声学の説明と応用』は直ぐに改題され『近代和声の説明と応用』という風になります。つまり、短縮された改題とて元々は『近代和声学〜』なのであります。
私の過去のブログをお読みいただければあらためてお判りになるでしょうが、ハルの目を瞠る和音の例示など十二分にジャズに援用可能な一世紀の時を経ても今猶新しい例を載せていたしていた物でありまして、古書市場となるといつの間にか松平頼則の方が役に立つとばかりにジャズやポピュラー音楽フィールドで謬見が蔓延る様になってしまった訳であります。
まあ恐らく想像に難くはないのですが、西洋音楽の方面からもポピュラー音楽からの方面からも皮相的理解にしか及ばぬ者が声だけは大きく吹聴する輩が居たのでありましょう。それが高じて謬見が伴う様になってしまい、いつしかジャズ/ポピュラー音楽フィールドでも松平頼則の方の『近代和声学』がバイブルの様に信奉されてしまう様になるという訳です。
どちらも良著ではありますが、ジャズ・フィールドで援用可能な程に新しい和声を載せているのは間違いなくハルの方なのである事は断言させていただきます。それにも気付かない連中が跋扈する様な世の中であってはいけないと思う事頻りです。まあ、これに酷似する側面が上田昭が訳を手掛けたシェーンベルクの『和声法』にもある、という事を述べたかった訳です。
十二音技法を学ぶにあたって重要な書籍は先にも挙げましたが、ヴェーベルン関連の書籍の方が詳らかに理解する事が出来るかと思います。トータル・セリエリズムにまで発展する事で真の均齊が理解できるからでありますが、国内刊行物でそれを詳らかにしてくれているのは矢張り柴田南雄の『音楽の骸骨のはなし』に右に出る物はなかろうかと思います。
ヴェーベルンの手で醸成された手法も四角連語(word square)ではまだまだ不充分であり、オーダー5としての連語の図版などを能く見かけるとは思いますが、オーダー12の連語というのは未だ発見されていないでありましょうし、オーダー10辺りが限度ある所が是亦辛い立ち位置にさせてしまうのも興味深い所です。
音楽というのは物理・数学の助力なしでは成立しない物の、殊更に協和・不協和の感覚的な側面というのは人間の感情に由来するので数学の公式の様に一義的な解を導く事はできない物です。処がこうした調性に靡く社会を数学的に捉える事には難儀するも、「無調」に於ける均齊社会を数学的に繙く事が出来てしまうというのが何とも皮肉な所でもあり、究極の均齊を数学の世界が導いてしまう事で、その可能性が意外にも少なく儚い社会を導いてしまったのも皮肉な側面であります。
坂本龍一曰く、セリーに基づいた音楽から歴時を無くして音楽全体の尺を「圧縮」した場合、その「紋様」となる音の分布は結局似た紋様に収束するという事を述べていた様に、十二音技法を俯瞰すれば結局はそういう事になるという訳です。松平頼暁が調性音楽の尺を際限なく引き延ばした時に調性の希釈化を狙った逆のアプローチとも言えますが、逆のアプローチを採られても調性が希釈化されてしまう事の現実と、無調を閉じ込めた時に収束してしまう可能性の少なさを露呈するのは実に儚い物です。
現在では、楽曲の徹頭徹尾でセリーに基づいて作曲するというよりも、曲の一部にセリーを導入したりする事があったりする物の、一時期持て囃された十二音技法は70年代に入ると途端に枯れていってしまった訳でもありますが、凡庸な線しか浮かんで来ない者が十二音技法を手にすれば、策に溺れてはいようとも己の素養を遥かに超えるクロマティシズムを具現化してくれるのは、その体系があまりに数学的な公式に酷似するかの様に見事な体系であるからです。逆を言えば、平時からクロマティシズムの素養に溢れている作曲家ほど十二音技法は重視していなかったと見る事も出来るでしょう。
とはいえ、ジャズの世界から見るとセリーというのは可能性がある物です。ジャズのクロマティックとて実際はドミナント・コードの引力に胡座をかいたテンション・ノートでどうにか「11音」を手繰り寄せ、逸音として生ずる12音目を用いて「半音階」を強弁する様な世界観に過ぎず、クロマティックな実際は増一度・短二度という隣接する「狭い音程」の連鎖が殆どの事であり、調性を薫らせない為に複音程や跳躍の大きな「leap」と呼ばれる音程がジャズに現われる事は稀でもあるのが現実で、そういう状況で「総音程音列」というクロマティシズムの用法は却って新鮮に映る事でありましょう。
なにしろ半音階は「12半音」なのでありますから音程種の数は1半音から11半音まで11種類ある事になります。これらの総数は66半音なので、12半音を形成する音程の組合せとして6組があるという風にも見る事が出来ます。それらの組合せとして、
11+1
10+2
9+3
8+4
7+5
6
という風にも見る事が出来ます。三全音が「6半音」という事を除いた他の半音数の音程の組合せは、それぞれが部分超過比となる転回音程を示しており(※長七度の部分超過比=転回=短二度)、古代ギリシャは上属音と下属音を形成するも、テトラコルドは五度ではなくその部分超過比となる音程=完全四度にテトラコルドとして形成させたのは実に示唆めいております。これにて大局的には全音階的テトラコルド、半音階的テトラコルド、四分音的テトラコルドを生じたのでありましたが、この時の体系で生じた最小の単位音程を継承しているのであるのならば、半音階など超越して四分音律(24EDO)が発展した筈でありますが実際にはそうではありません。
同時に、四分音的テトラコルドの単位微分音のそれよりも次点で狭く採られる「半音階」とて、この体系=半音階なのでもなく、12EDOが生じた訳でもありません。所謂「臨時記号」として可動的に生ずる半音階的な変化の正体の実際は、全音階テトラコルドの組合せに依って生ずる音階を為している一部の音列に於て本来期待される「半音」が「全音」へ可動的に変化して音程が拡大する事で生ずるのがムシカ・フィクタなのであり、半音階社会を唄おうとして半音を用いたのでは決してないのであります。
半音音程が全音音程に拡大する事はなにも、半音が全音へと「上行に拡大」するばかりでなく、下方にも拡大する事で全音を得る状況もあり得る訳でして、半音が全音に拡大する可動的変化=ムシカ・フィクタとはそういう事なのです。半音を唄おうとして形成されているのではないのです。本来期待されるべき半音の現われる位置に生ずる音を全音に拡大するのがムシカ・フィクタなのであります。
とはいえ13世紀のヨハネス・デ・ガルランディア(Johannes de Garlandia)の見解では可動的変化の動作をムジカ・ファルサとした上で「全音を半音に、あるいは半音を全音にするとき」という風に両義的に定義していたりもする物もありました。
ヨハネス・デ・ガルランディアの見解を私が援用したのは『ニュー・グローヴ世界音楽大事典 第18巻』p.124 からであるので、文中の「ムジカ某し」がムシカではない所にも注意すべき点でありますが、これまで私は幾度となく過去の記事で述べているように 'musica' をムジカとは呼びません。ムジカはイタリア語の発音であり、ムシカはそれよりももっと古いラテン語の発音であるからです(前掲「ムシカ・フィクタ」のURLリンクを参照)。
広義でのムシカ・フィクタというのは「B♭」音の出現の為にしか用いられなかったとか、「F♯」の出現は13世紀まで無かったとする研究(9世紀の時点で実際にはあった)など諸説ありますが、多くの体系が醸成されつつあったのは13世紀以降15世紀に到っての事であるという音楽の歴史が存在しているのは認めざるを得ない物であり、音階の成り立ちをギリシャ時代まであらためて遡ると、そこには全音階的テトラコルドの他に、半音階的テトラコルドと四分音的(異名同音的)テトラコルドがあった事を確認する必要があります。
三全音を回避する為の方策として体系化されたのが10世紀初頭のムシカ・エンキリアディスと言われるので、声部の独立性と共に複調的に生ずる世界観が存在していた事が判ります。そういう意味では、かなり制約のないムシカ・フィクタが横行していた事も同時に理解できるという訳です。
ただ、ギリシャ時代にはテトラコルド体系として用意されていたひとつの半音階的テトラコルドに属する採り方の内のひとつ、半音階が連続する(短二度の連続)が現在では増一度および短二度が連続する音程としてダブル・クロマティックがありますが、こうした音程の採り方が多くなるのは和声体系が整備されて以降、対位法のそれと和声法のそれとが組み合わさって生じて来てからではなかろうかと思います。
ダブル・クロマティックの例として、加山雄三の「君といつまでも」のメロディーの「つつむ〜♪」という様なそれもダブル・クロマティックですが、意外にもこうした線運びは歴史的にはかなり昔から存在してはいたものの、実際に使われる様になるのは相当後になっての事だという事でもあります。
ムシカ・フィクタは相当昔から使われていたにも拘らずそれを半音階として標榜する世界観として抱括的に使われていた訳でもなく、結果的に等分平均律を目指す事でより強化される事となるのがメルセンヌの時代にまで時を進めてしまうのですから実に皮肉な物です。
テトラコルド体系(=古代ギリシャ時代のシュステーマ・テレイオン〈大完全音列〉)まで目を向ければ自ずとお判りですが、真にそれらの体系の中で最小の単位音程を標榜する様にして音階が生じたのだと強弁するのであれば、その後には半音階が醸成されるのではなく四分音体系が広まっていた筈であります。
実際には四分音体系は廃れてしまっていた訳ですから当時の人々の標榜する最小の単位音程は四分音を強固なまでに採用してはいなかったという事でもあります。
つまりは半音階ありきでもなかったという事も同時に言える為、全音階的テトラコルドの中で全音音程に随伴する半音のそれらが組み合わさって音階を作ったのであるので、半音階を巧緻に設えて音階が生じていた訳でも無いのが実際なのです。半音階ありきで音楽を語ろうとするのはあまりにも近視眼的な視点であります。
現今社会において整備された音楽の大系を無意識なまでに利用する事が可能になっているとは雖も、現存する楽器の利便性や現在まで広く知られる過去の音楽の存在を規準に「十二等分平均律ありき」として半音階が常に音楽社会の礎となっていた訳では決して無く、半音階を12等分平均律として奏する事が出来る様になったのは工業的な技術の発達で楽器が整備された事に加え、科学が黎明期を終えて醸成されて行くと共に他の分野へ敷衍する事となって発達と整備が為されたからなのであり、そうした時代を経て不等分平均律が等分平均律として広く用いられる様になったというのが半音階の歴史とも言えるでしょう。
そうしてその後に成立する事となる半音階社会の醸成が、不等分平均律時代でも半音階を駆使する過去の大家の作品(J. S. バッハ)が、シェーンベルクの十二音技法という体系の中に対位法的和声法に巧妙に援用すると共に、等方に転調も可能な状況を生む音律としてメルセンヌが12EDOを提唱した矢張り是亦過去の大家の提唱を援用して等分平均律という体系は一定以上の地位を確保してきた訳であり、音律と音階がそもそも同じ物だと考えてしまう浅薄な知識をも正して理解して欲しいと思わんばかりです。
任意の音から開始された音がこれらの音程を「巧みに使って」終わる時、開始時の音から三全音離れた音で終わるという事を遵守すれば、全音程シリーズとして半音階の世界を実現させたという事になります。こういう音程を意識したフレージングなど、ジャズのウォーキング・ベースはまだまだ可能性が残されているであろうと思います。
ただ、こうした着想で半音階を眺めるにはシェーンベルクの著書では『音楽の様式と思想』が最も学べる物なのでありますが、私がジャズのウォーキング・ベースに対して十二音技法を対照させるのは、既知の体系整備される和音に対して「半音階的揺さぶり」をかける動機として用いる為の方策として取り上げているだけに過ぎません。凡ゆる調性の呪縛から逃れようとして体系整備を施した十二音技法のそれを都合良く援用しているに過ぎないので、私のその解釈が十二音技法だと近視眼的に捉えてしまうのは本末顛倒であります。
とはいえシェーンベルク自身も、過去の大家の作品が如何様にして半音階的な要素を纏って来たか!? という事を詳らかに傍証を取り上げて行くのです。無論、その先には突如として十二音技法という、音楽を構築する様に展開されて行くので、作曲をしようとは毛頭思ってもいない読者からすれば、その体系の最も根幹と成す部分がやたらと敷居が高くなってしまうかもしれません。
十二音技法以外の方策で半音階を纏って来た理由というのは、対位法社会に於て三全音回避に依る変応、倚音、逸音という声部の独立性と共に、原調は必ずしも一元的に採る必要のない定旋律と対旋律との関係にこそ多くの秘密が宿っているのであり、和声的体系というのは調性を一元的にしかねない側面もあるという事を知った上で、対位法の可能性の方を深く知る方が得策であろうかと思います。
調性が稀釈化される要素に鼻から十二音技法があった訳ではないという事を念頭に置きつつ、体系としての十二音技法とは別に、半音階が齎す暈滃の仕組みを知っておく必要があろうかと思いますが、シェーンベルクは過去の大家の作品を取り上げ乍ら自身の体系を語っているのが『Style And Idea』なのであります。
2019-10-07 12:00



