潜在倍音とか [楽理]
前回はソルミゼーション(視唱)も含めた話題にした為、多様な和音進行のみならず多くの音楽的な側面を述べる事ができたかと思います。私の意図はソルミゼーションの是非を語るのではなく、衒いのあるコード進行の実際を声高に語り度い訳です。
Twitterの方でも私は呟いていておりましたが、「衒いの無い」コード進行というのは、先行和音の根音を後続和音の構成音の上音(←これは倍音という解釈)に取り込めば素直なコード進行になります。こういう和音進行の妙味はトゥイレの『和声学』にて最も分り易く説明されていると個人的には感じておりますが、畢竟するにC△→F△というコード進行があれば、先行和音の根音c音が後続和音であるF△の上音(この場合第5音)のf音に取り込まれるのがお判りになる事でしょう。
こうした自然な進行とは別の側面の、自然な進行から「背いた」感のある和音進行を私は詳悉に語るという意図があるのです。ですから先のブログ記事でもTVアニメの初代のルパン三世「ルパン三世 その2」を題材に取上げたのも、その曲中には転調、移旋、弱進行などを学び取る事が出来るが故の事であり、何も私がサブカル方面に媚び諂うかの様にして門外漢が佞弁を振るっている訳では決してありません。とはいえ、どの関係各所からもグウの音も出ない程アカデミックな曲を例示した所で今度はポピュラー界隈とは縁遠い為、話題としては結び付ける事は出来ても、多くの人々の間で実感を伴わせにくい大きく乖離した物ともなり勝ちなので、敢えて転調やら移旋やらが著しい曲を選んで例示したのが偶々「ルパン三世 その2」だったので、その辺りはあらためて勘案していただきたい所です。
まあ、前回のソルミゼーションの階名読み替えの件は英国流に加え東川清一のそれに倣った物であり、他国では亦異なる所もあります。ソルミゼーションに関しては詳述はしないものの、一義的な理解であってもいけないので今回は前回のソルミゼーション部分に加筆する為に、アンリー・ビュッセル著『作曲提要』の巻末補遺に書かれているフランス式の階名を念の為に載せておく事にしましょう。

これはオブホフ(Nikolai Borisovich Obukhov)が示す半音階の階名なのでありますが、東川清一が歎息していた様に日本国内の発音というのは「L・R」の綴りの違いに無頓着である為、幹音以外の派生音に生ずる「Lo」はもとより「Ra」という発音は幹音の「La」との使い分けが困難になる事であるのは明々白々であり、こうした所からも前回の記事にて東川に倣って英国式ソルミゼーションを語ったのは日本語との整合性をどうにか維持する為の狙いがあっての事で、それは私の勝手な配慮でもない訳でありますのであらためて念頭に置いていただければ幸いです。
とはいうものの、嘗て私案として矢田部達郎が四分音まで視野に入れた音名にて読むそれが改革も含めて一番まとまりそうな気もしない訳ではありません。
「なにゆえ私はそこまで階名、若しくは半音階の音名に拘るのか!?」と言うと、それは長調や短調という風に主音を配置した時に生ずる各音の「機能」を音楽を遣る人はこっぴどく知らなくてはならないが故に詳悉に語る譯です。
調性社会というのは長調・短調以外にも教会旋法でそれが変格旋法であろうとも、属和音から主和音へと進行させる時に属和音に対して「導音欲求」を与えます。ポピュラー音楽ならばGミクソリディアンとやれば、Gに主音の性格を与えつつ第7音を半音下げ続けた音社会で鳴らし続ければ良いのですが、西洋音楽の場合は導音欲求を起す箇所は用意され、一時的にはト長調本来の音組織を見せる事があるのです。
これはミクソリディアンに限らず、どの教会旋法の変格旋法の取扱いでも西洋音楽では同じです。ですからロクリアンというのは「属音」という完全五度に匹敵する音を失う為、正格フリギアはロクリアンのそれを変格化して、つまりフリジアンを変格旋法という風にBロクリアンという風にフリギアの5度音を恰もオルタレーション(ヒポフリギア)させて導音欲求をフリギア終止として下行導音として限定して上行導音を起させぬ様にしていて、他の教会旋法の変格旋法では五度音と主和音を使った導音欲求を用いる訳です(あくまでもⅤ→Ⅰの際)。仮にフリギアで5度音上の和音に属和音としてのオルタレーションを与えてしまうと、Eフリギアが一時的に嬰ニ音を作る事になってしまい、これだと下行導音だけに限定するフリギアに背く事になるのでこの導音欲求は禁忌となります。
山下邦彦著『坂本龍一・全仕事』では坂本龍一自身が「君が代」に就いて調性格を載せている文言が載せられており、それに依れば坂本龍一の分析では「君が代」はミクソリディアンだという物です。
君が代はニ音から始まりニ音で終りますので、これはドリア旋法の一つ(然し導音欲求を起していないドリア旋法)とする人が居りますが、確かにエッケルト版の物は「八千代に~」の部分でミクソリディアの導音欲求が表れるので、導音欲求が現れている以上、ミクソリディアンという性格という解釈の方が正しくはあるでしょう。然し、和声付けをエッケルトのそれに拘らずに、新たな「旋法的和声」にて編曲した場合、《主音の上の音(=スーパートニック/上主音)で始まり上主音で終る》という在り方はもっと追究されてもよい部分ではあるかと思います。
よもや調性社会をこっぴどくやった人が、エッケルトの君が代の終止部分にてオクターヴ・ユニゾンのそれを連続八度などと揶揄する様では単なる声楽の和声法を持ち込んだだけの誤謬に過ぎぬ解釈となり、その様な誤った理解に陥る様な人達がもしかすると林達也著『新しい和声』にケチを付けているのではないかと思う事も多々ありではあります(笑)。そういう「旋法的和声」の振る舞いとやらをあらためて例示するが故に、前回は早坂文雄のそれも例示した訳なので私の言わんとする意図が少しでも伝われば之幸いです。
山下邦彦と言えば、同氏に依る『坂本龍一の音楽』では、小室哲哉が嘗てのキーボード・マガジン誌上にてコード理論を寄稿していた文章を論い、それを奇異の目で取上げている物があります。実はそれはシュテファン・クレールが嘗ての和声学で語っている事に繋がるもので結論から言えば小室哲哉の論の方に分があるのですが、畢竟するにC△7という和音はC△とEmが同居する。だからC△7という和音は物悲しげなのだという事を小室哲哉が述べている所を山下邦彦は、C△7というコードをそのような聴き方などしないという風に、その和音の捉え方のおかしさを挙げている所があるのですが、これは疑い無く小室哲哉の論に分があるのです。
とはいえジャズ界隈の人達というのは、重畳しい和音を「多即一」の様に、そのコードが持つ音響的性格や色彩をひとまとめにして硬い響きとして耽溺に浸る(もしくはその硬い響きを一音響として耳に馴らす)という所があるので、山下邦彦がよもやC△7というコードに対してCメジャー・トライアドやEマイナー・トライアドを見る様な所に違和を抱くのは理解できる所もあるのです。ジャズ的方面から体得して来た人の多くはこうした捉え方の方が自然でしょうから。
然し乍らクレールの時代の四和音の取扱い方法は矢張り小室哲哉と同等の考え方で教えます。旧くからこういう教え方なのです。
ジャズの場合、主旋律が稀薄であっても「和音を構成する音の束」がそれを補う事があります。然しジャズを除けば多くの音楽というのは、和音という音響集合体は複数の「音の線」が絡み合う事でそれが垂直的に和音を生じている訳ですから、《火の無い所に煙は立たぬ》という格言ではありませんが、線の無い所に和音構成音は作られない訳です。和音構成音として突然表れるのであれば、それに相応しい線が在って然るべきという考えが大前提であるからです。勿論、和声的な音楽観も高次に追究されれば、その和音とて「Timbre」(=音色)的な色彩として用いて、その色彩の塊をいくつも並べて「進行」させる事で、線は稀薄であっても音響的に進行するという技法も勿論あります。とはいえ大半は、「横の線」が在るべきとして教わっていく物です。
ジャズに限らず現今のポピュラー音楽というのは、和音が持っている響きの牽引力を借りた線の作り方の方が顕著であると言えます。和音の牽引力を必要としない程説得力のある単旋律を生み出せる様な人など、よほどの旋律としての牽引力がない限りそれだけで引っ張る事の出来る旋律を作れるというのは相当少なくなる事でありましょう。旋律としての力が卑近で牽引力も稀薄だけれども歌詞という、言葉の牽引力でどうにか体を保っているというケースですら珍しくはありません。言葉の牽引力がある為に卑近な側面に批判が向けられないで居る作品も決して珍しい物ではありません。
「素直な牽引力」というのは調性の持つ引力に由来している向きが往々にしてある為、単旋律であろうともそれに音程の牽引力をグイグイ感ずるのは、調性自身が本来持っている引力と言う「次の歩を進めるべきは此處ですよ」と音楽の神様の思し召しにも似た脳裡に誰もが映ずる事の出来る脈だと言える事ができるでしょう。然し乍ら「半音階的全音階」という調性を維持し乍ら半音階的作法を駆使する状況に於いては、全音階から逸脱する音にも「何等かの機能特性」的な響きがある訳です。
 DAISHI DANCE feat.麻衣の「Beautiful This Earth」という曲が毎週土曜日『朝です!旅サラダ』の中で掛かる4 on the floorで心地良い曲を聴く事ができますが、和音進行に於いて導音欲求の類の様にノン・ダイアトニックが出現して近親調の情緒を拝借するのとは違い、使われている和音はダイアトニックである為ノン・ダイアトニックと比較すれば「衒い」はありません。しかしメロディーが和音の1・3・5度の基底部を使わずそのアッパー部を使う事で、基底和音に「お天気雨」「嬉し泣き」にも似た情感の明暗の具有性を帯びて来て物悲しげにも聴こえる折衷感を生じます。これは先述した様に、例えばC△7コードにCメジャー・トライアドとEmトライアドが同居するそれと同じ様な物で、特に和音というのは「基底に背く」音が上声部にある事で明暗の折衷感を生ずる物です。
DAISHI DANCE feat.麻衣の「Beautiful This Earth」という曲が毎週土曜日『朝です!旅サラダ』の中で掛かる4 on the floorで心地良い曲を聴く事ができますが、和音進行に於いて導音欲求の類の様にノン・ダイアトニックが出現して近親調の情緒を拝借するのとは違い、使われている和音はダイアトニックである為ノン・ダイアトニックと比較すれば「衒い」はありません。しかしメロディーが和音の1・3・5度の基底部を使わずそのアッパー部を使う事で、基底和音に「お天気雨」「嬉し泣き」にも似た情感の明暗の具有性を帯びて来て物悲しげにも聴こえる折衷感を生じます。これは先述した様に、例えばC△7コードにCメジャー・トライアドとEmトライアドが同居するそれと同じ様な物で、特に和音というのは「基底に背く」音が上声部にある事で明暗の折衷感を生ずる物です。
特に先の曲の大サビは次の様なコード進行であり、特に4小節目に「付加四度」で長三度音と短二度でぶつけてストリングスを用いている部分は特筆に価する絶妙な響きでありましょう。
D△9 -> E6 -> F#m7(9、11) -> A△7(9、11)←※A△9+付加四度の本位11度は長三度と短二度のストリングス。下からa・e・gis・cis・d・gis・hというヴォイシングで弾くと感じが掴めるでしょう。
ダイアトニック(全音階)の音を固守しているにも拘らず、こうして曲の情感を多様に移ろわせる事が出来る訳ですね。特に付加四度の使い方というのは、通常ならば短七度を包含した長和音(つまりドミナント7thコード系統)で、ミクソリディアン・モードを移ろわせるような遣り方が多いのですが、長七度を内在させての付加四度へのセンスは素晴しいと思います。勿論A△7(9)から見た本位11度=付加四度を充てるのは一般的な和音の在り方すればアヴォイドなんですけどね。感性がアヴォイドという縛りを易々と跳越するのはこういう例に倣った上で、《盲人蛇を畏れぬ》と言われぬ様、音楽観をきっちりと「具備」してナンボだと思うんですなー。特にその辺のギター兄ちゃんとか肝に銘じておかないといけませんよ(笑)。
まあそうしてあらためて「調性」とやらを見つめた時、例えば長音階というヘプタトニック組織には7つの機能があります。
1…主音(=完全一度)
2…上主音(=長二度)
3…上中音(=長三度)
4…下属音(=完全四度)
5…上屬音(=完全五度)
6…下中音(=長六度)
7…導音(長七度)
これらの音階固有音の外にある音、例えば長音階の主音から「短六度」にあるフラット・サブメディアント、「短七度」にある「下主音」、「短三度」にあるフラット・メディアント、「増四度/減五度」にある三全音にも、本来の調性の余薫を漂わせた振る舞いがある訳です。そうした近親的な調性から得られるのを準音階固有音とも呼ぶ訳ですが、調性をこっぴどく学んだ次のステップというのはこうした半音階的全音階の社会を知る事が肝要である訳です。
先述の「君が代」というのは、長音階の主音を余薫として強固に脳裡に映じて他の音を吟味している訳ではありません。つまり「中心音」と為すべき音は主音に対しての役割が稀薄になっているからこその「旋法性」のある曲想なのであり、その旋法性という曲想は、倍音に逆らう事のない「素直な進行」に随っているだけでは生まれない情緒なのです。そういう意味でも嘗てクラウス・プリングスハイムが「管弦楽のための協奏曲」を作り日本的和声とやらを西洋音楽のそれにて作った物もありましたが、そこには日本的な情緒の移ろいは稀薄で、日本的な情緒として和声が付けられているとは感じにくい卑近な感を抱かざるを得ない所があるのは否めないかと思います。
箕作秋吉はポジティヴ方向(上行列)とネガティヴ方向(下行列)双方に五度和声を組み上げ、ポジティヴ側は根音をaに採りa・e・h・fis・cis・gisと積む事が可能で、それから得られた音列を転回させ「a、h、cis、e、fis、gis」という上行音列を生み、ネガティヴ側はf・c・g・d・a・eという風に辿りそれを転回させて「e、d、c、a、g、f」という下行音列を作った訳ですが、実はこれを生んだのは単純な振動比から導出された牽引力に端を発している訳です。
こうした例を踏まえると、単音がポツンと座している所に上方倍音を頼りにするだけではなく、下行形の音脈として結果的に下方五度にも作用する音脈を我々は普通に映ずる事が可能ですし、オクターヴが更に細かい音程へと細分化されていった「大完全音列」の時に、上方に作られる五度音程を「上屬音」、下方に作られる五度音程を「下属音」とした事で、下方の五度の音脈というのは、何の根拠もなく下方倍音列を唐突に持ち込まずとも、少なくとも下方五度の音脈はこうした所にも音脈としての牽引力は存在するものであり、和音進行の弱進行という音脈もこうした作用から生じている物であると謂える訳であります。
エドモン・コステールがヒンデミットのシュテムトンを断罪するのは、コステール自身が上方倍音ばかりに依拠した発想から立脚している事でヒンデミットのシュテムトンの出現順位の優位性とやらに反駁しているのですが、コステールが無視しているのは「結合差音」の作用であり、ヒンデミットは、協和音程からも生ずる結合差音の存在を無視できないからこそ結合差音を含めた順位によってシュテムトンという近親性をあの様な優位性としての順番で取上げている訳です。上方倍音列ばかりに依拠していたら弱進行の作用すら否定せざるを得ず、よもや12音技法から得られる「調性の音脈を掻き消す」振る舞いが必要である筈の無調社会が、それほどまでにコステールの様に上方倍音だけに頼ってしまっていたら自家撞着も甚だしい自己矛盾となってしまっている訳です。
コステール著『和声の変貌』では、ヒンデミットがシェーンベルクのOp.33aをして調性的痕跡を分析している例を取上げ、コステールは12音技法に対して調性の余薫を感ずるなど重箱の隅を突く様な物として反駁しつつ次のヒンデミットの「和声力・旋律力」の譜例を、単に「C音に対する親近性」という風に歪曲して論駁している点が残念な所なのである。
ヒンデミットは自著『作曲の手引』図版59では、次のex3の様な音程は「和声的」な断片として用い易い事と、和声的な断片ではなく「旋律」としての横の線として用い易い事の「対比」を単に挙げているだけの事であり、C音に対する親和性とは異なる理解なのであります。而もヒンデミットは「三全音」に対して狭い三全音から広い三全音まで例示して、それらの三全音の結合音(=差音)こそが三全音の根音を決定する為の特殊な音程として取上げている為、コステールが『和声の変貌』43頁で載せている譜例は抑も曲解であり、三全音の部分も端折り過ぎた断章取義(三全音の結合差音由来の一例しか挙げている一方でヒンデミットは三全音に対して3つ例示している)に過ぎないのです。
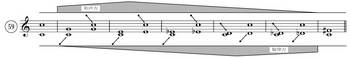
加えてコステールは『和声の変貌』48頁にてヒンデミットの中心音をひとまとめにして近親的な音として例示するものの、それは詳細を欠いていて、本来は次のex03のように近親音がある訳です。コステールは、早期に出現するes音=E♭音は、上方倍音列ではもっと高次な倍音由来ではないと得られない筈なので、これほど早期にes音の優位性がある筈が無いと断罪しているのですが、「旋律的親和性」は上方倍音を一挙に「和声的に」聴く見方とは異なるものであり、旋律的な欲求を音響的な垂直レベルで比較するのは全く埒外である。コステールの言うように、このヒンデミットの「旋律的親和性」が上方倍音に依拠する物でならないならば、旋律的な横の線として長六度の音程で跳躍しようとするよりも自然七度(第7次倍音由来)の方を優位的に選ぶ事になりかねず自己矛盾を秘めた暴論となってしまっており、これこそがコステールの価値を低めてしまっているものであります。

ましてやコステールは低次に出現する自然七度の「大きく外れたイントネーション」のそれを、上方倍音列の22次倍音までは四分音律から見た時それらの音程差は81/80というシントニック・コンマ以内に収まる因果関係を持っているから、四分音律から外れたコンマ以内の微小音程は某かの四分音に吸着される音程という風に冒頭から宣うのであるが、これは低次に発生する自然七度にアシストせざるを得ない詭弁にすぎず、コステールは四分音律を詳らかに語っているのではなく、12平均律における各音の親近性を語っているのですから、四分音に吸着されるイントネーションであるならば、四分音は12平均律のどの音に吸着されるのか!? 或いはヘプタトニックという調的な音階固有音から見たらノン・ダイアトニックの音はどの音階固有音に吸着されるのか!? という事を自身が全く明らかにしておらず、而もコステールの親和性というのはオイラーのそれに則って持論を強化しているだけの事に過ぎない物であるのに、オイラーはおろかヴァンサン・ダンディーの名前も挙げずに自身の親和性とやらを声高に叫ぶのは単なる強弁に過ぎない訳ですよ。
セリエルなど全く無かった時代にオイラーは音楽のそうしたシンクロニシティを「数理」で繙いていた訳ですが、人間が「均齊」へと赴く欲求は、細かな「音楽的訛り」というイントネーションが生じた音律の引力よりも「強い」からこそ、人間は平均律を手にした訳です。
処がコステールの、四分音の因果関係が上方倍音列第22次までは81/80のシントニック・コンマ以内に収まる物であるから、それらの音程的な「ズレ」が四分音律の音に吸着される因果関係を持つのであれば、人間はシントニックを半音階(12平均律)に均す前に、四分音側に均してしまって12平均律を得る事なく完全五度の「不完全な」螺旋音律を使ってしまっていたのではないかと思うのですね。
なぜなら、低次に自然七度という-31セントが生じているなら、相対的な差として19セント高くなった時点で四分音に吸着してしまう事と等しくなる訳ですから、シントニック・コンマよりも狭い19セントが発生した時点で人間の耳はそこで安堵してしまったでしょうかね!? そんな事ぁ詭弁に過ぎないでしょう。純正完全五度を1回重ねただけで「2セント」ズレるのが実際な訳です。19セントのズレは10回純正完全五度を重畳した時には既に超越してしまう訳です。シントニック・コンマは純正完全五度を11回重畳して生まれる物ですから、それを鑑みれば、コステールはよもや「人間はシントニック・コンマ程の差なら均齊の方へ均す」という風に誤解しているからこそ、このような詭弁を弄する事になっている訳です。
人間は、シントニック・コンマを相容れなかったから均した訳ですからね。シントニック・コンマ以内で無頓着なら、世界何処でもオーケストラの弦楽器奏者の調弦など滅茶苦茶ではないでしょうかね!?(笑)。
人間の耳が自然七度に対して寛容であるのは、その音が位置するのが不協和音程の所にあるからです。協和音程の所に現れていたらトンデモない騒ぎになる訳ですよ(笑)。
調弦・調律とやらをひとたびやれば誰もが実感できる事ですが、シントニック・コンマ以内の音が某かの音に吸着するという状況は、うなりを消す為に調弦する事と等しく、うなりから見れば、微小音程として「導音」が際限なく狭い音程で「解決」しようとしている事と何等変わりないのです。
その「導音」的作用という事を「旋律的親和性」とやらで見立てる事はできなかったでしょうかね!? と私はコステールに言いたいのですね。しかも四分音律にて(笑)。じゃあ、その四分音律の音は、12平均律のどの音に吸着されようとする欲求が起るのかな!? という疑問など全く忘却の彼方に葬り去って,唐突に12平均律の均齊社会での各音の親和性とやら話を進めるのです。しかしこれはオイラーのそれに倣って脚色しているだけの事でありましょう。長音階の重心はE音にある、というのは腑に落ちますけどね。それは全く別のハナシです。
自然七度が四分音に吸着しようとするなら間違いなく、更に低い方の根音から数えたら950セントの音へ吸着しようとするでしょう。下行導音的に潜在的な力を持っているのでしょうかね!?(笑)。ジャズが齎したブルー七度は本来、本位七度(※私が言う「本位」音程は、長音階を元にした音程を本位としているので、本位四度及び本位十一度=完全四度&完全十一度、本位六度=長六度、本位七度=長七度を意味します)から微分音的イントネーションで低く変化した物が半音階に「吸着」されてそれが短七度としてブルー七度は使われています。勿論長七度と短七度の間の中立音程をマイケル・ブレッカーの実例を挙げて例示した事も過去にありましたが、ブルーノートのブルー七度はそういう物です。しかし、倍音列に無頓着で居られない吹奏楽器奏者が、よもや自然七度に遭遇した際にそれが四分音律やらに吸着される様な意識に開眼しているとは到底思えない訳ですね(笑)。そのイントネーションを「ポジティヴ」(=上行的に)に打ち勝とうとして、本来の半音階のピッチに均すという風に克服するのが自然な動機であるのは疑いの無い所でありましょう。
ヒンデミットは、長三度と短三度の間に「明確な」情緒の境界などない(明るい・暗いの明確な線引きなどない)と説明するが為にリーマンの短和音発生根拠を否定していますが、実はコレ、同主調のみでヒンデミットは見ていて反論しているので、本来なら平行調との関係で見渡さなくてはいけない遣り方なので、ヒンデミット自身も下方倍音列を否定したいがあまりに広汎に目を向けていない事実はあるのですが、これは又ヴァンサン・ダンディやリーマンを扱う時に詳述しましょう。然し乍らヒンデミットの功績は上方倍音だけに依拠する事の無い差音の働きに加え、同主調の音脈の正当性を奇しくも露にした事であるでしょう。
例えば短和音の発生由来の根拠としてディミトリ・レヴィディスは「潜在倍音」を引き合いにして、短和音という音脈に対する近しく存在する親和性とやらを見出し決着を図ろうとしています。これはジャック・シャイエ著『音楽分析』でも語られているので興味のある方は一読される事をお勧めします。
次のex4の例を見れば、赤色の倍音列が本来の倍音列と仮定した場合、最初のC音の下方五度にあるf音は「類推」に依って仮想的に生じている倍音列を辿るに過ぎません。しかしこのf音の類推というのは、C音から下方に生ずる五度音である為、大完全音列の生ずる處から上屬音・下属音が発生した様に、この類推は在って誹りを受ける程でもない音脈の一つであると私は思います。
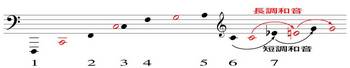
その類推に依ってf音からカウントした第7次倍音は、基から備わるc音からの倍音列であるc音に対して短和音の根拠となるes音を生じるのです(微分音的ですが)。その微分音的イントネーションの短三度とやらは、c音から上に250セントの中立音程に「吸着」されてしまいかねない音脈なのでしょうか、ねえ!?コステールさん(笑)。
しかも第7次倍音の大きく逸脱したそれを、矮小化させる為に使いもしない四分音律を根拠にして、それにてちゃっかり12平均律にてのうのうと近世社会に佞弁すればあまりにおこがましい物ですよ。アイヴズの例があるからといってd音のスリー・クォーターシャープに吸着するとでも断言してしまうのでしょうかね!?(笑)。申し訳ないけれど、12平均律でなくとも先の音は変ホに吸着しようとしますよ(笑)。
確かにあらゆる音は上方倍音列の作用を受ける為、どんな単音でも倍音列の作用から「属和音」としての性質を持っているとも言える訳ですが、その「音響的属音」と調性が生ずる音組織に於ける第5音に生ずる属和音の持つそれと「合致」した時に初めてドミナントとしての解決の為の作用が強化されていると以前にも述べた通りです。これについては『新しい和声』が刊行された時にも述べている事ですし、判り易い例で言えば諸井誠が自著『音楽の現代史』にて述べている事でもあります。
調性として強く働く音組織の第5音としての属和音と、音響的に生ずる上方倍音列の属七和音的性格が合致していない和音の振る舞いとやらが、音律の熟成と共に多様な和音進行を生んで来た訳ですから、そうした和音を駆使して上方倍音列を取り込まないという調性に背いた進行というのは「多様」と為して至極当然でもあります。加えて、こうした多様な世界観は長調よりも短調の世界が多様性を生んで来た背景があります。故に、短和音の在り方やら弱進行の例を見る事で、あらためて多様な現実を思い知らされる事になる訳です。
Twitterの方でも私は呟いていておりましたが、「衒いの無い」コード進行というのは、先行和音の根音を後続和音の構成音の上音(←これは倍音という解釈)に取り込めば素直なコード進行になります。こういう和音進行の妙味はトゥイレの『和声学』にて最も分り易く説明されていると個人的には感じておりますが、畢竟するにC△→F△というコード進行があれば、先行和音の根音c音が後続和音であるF△の上音(この場合第5音)のf音に取り込まれるのがお判りになる事でしょう。
こうした自然な進行とは別の側面の、自然な進行から「背いた」感のある和音進行を私は詳悉に語るという意図があるのです。ですから先のブログ記事でもTVアニメの初代のルパン三世「ルパン三世 その2」を題材に取上げたのも、その曲中には転調、移旋、弱進行などを学び取る事が出来るが故の事であり、何も私がサブカル方面に媚び諂うかの様にして門外漢が佞弁を振るっている訳では決してありません。とはいえ、どの関係各所からもグウの音も出ない程アカデミックな曲を例示した所で今度はポピュラー界隈とは縁遠い為、話題としては結び付ける事は出来ても、多くの人々の間で実感を伴わせにくい大きく乖離した物ともなり勝ちなので、敢えて転調やら移旋やらが著しい曲を選んで例示したのが偶々「ルパン三世 その2」だったので、その辺りはあらためて勘案していただきたい所です。
まあ、前回のソルミゼーションの階名読み替えの件は英国流に加え東川清一のそれに倣った物であり、他国では亦異なる所もあります。ソルミゼーションに関しては詳述はしないものの、一義的な理解であってもいけないので今回は前回のソルミゼーション部分に加筆する為に、アンリー・ビュッセル著『作曲提要』の巻末補遺に書かれているフランス式の階名を念の為に載せておく事にしましょう。

これはオブホフ(Nikolai Borisovich Obukhov)が示す半音階の階名なのでありますが、東川清一が歎息していた様に日本国内の発音というのは「L・R」の綴りの違いに無頓着である為、幹音以外の派生音に生ずる「Lo」はもとより「Ra」という発音は幹音の「La」との使い分けが困難になる事であるのは明々白々であり、こうした所からも前回の記事にて東川に倣って英国式ソルミゼーションを語ったのは日本語との整合性をどうにか維持する為の狙いがあっての事で、それは私の勝手な配慮でもない訳でありますのであらためて念頭に置いていただければ幸いです。
とはいうものの、嘗て私案として矢田部達郎が四分音まで視野に入れた音名にて読むそれが改革も含めて一番まとまりそうな気もしない訳ではありません。
「なにゆえ私はそこまで階名、若しくは半音階の音名に拘るのか!?」と言うと、それは長調や短調という風に主音を配置した時に生ずる各音の「機能」を音楽を遣る人はこっぴどく知らなくてはならないが故に詳悉に語る譯です。
調性社会というのは長調・短調以外にも教会旋法でそれが変格旋法であろうとも、属和音から主和音へと進行させる時に属和音に対して「導音欲求」を与えます。ポピュラー音楽ならばGミクソリディアンとやれば、Gに主音の性格を与えつつ第7音を半音下げ続けた音社会で鳴らし続ければ良いのですが、西洋音楽の場合は導音欲求を起す箇所は用意され、一時的にはト長調本来の音組織を見せる事があるのです。
これはミクソリディアンに限らず、どの教会旋法の変格旋法の取扱いでも西洋音楽では同じです。ですからロクリアンというのは「属音」という完全五度に匹敵する音を失う為、正格フリギアはロクリアンのそれを変格化して、つまりフリジアンを変格旋法という風にBロクリアンという風にフリギアの5度音を恰もオルタレーション(ヒポフリギア)させて導音欲求をフリギア終止として下行導音として限定して上行導音を起させぬ様にしていて、他の教会旋法の変格旋法では五度音と主和音を使った導音欲求を用いる訳です(あくまでもⅤ→Ⅰの際)。仮にフリギアで5度音上の和音に属和音としてのオルタレーションを与えてしまうと、Eフリギアが一時的に嬰ニ音を作る事になってしまい、これだと下行導音だけに限定するフリギアに背く事になるのでこの導音欲求は禁忌となります。
山下邦彦著『坂本龍一・全仕事』では坂本龍一自身が「君が代」に就いて調性格を載せている文言が載せられており、それに依れば坂本龍一の分析では「君が代」はミクソリディアンだという物です。
君が代はニ音から始まりニ音で終りますので、これはドリア旋法の一つ(然し導音欲求を起していないドリア旋法)とする人が居りますが、確かにエッケルト版の物は「八千代に~」の部分でミクソリディアの導音欲求が表れるので、導音欲求が現れている以上、ミクソリディアンという性格という解釈の方が正しくはあるでしょう。然し、和声付けをエッケルトのそれに拘らずに、新たな「旋法的和声」にて編曲した場合、《主音の上の音(=スーパートニック/上主音)で始まり上主音で終る》という在り方はもっと追究されてもよい部分ではあるかと思います。
よもや調性社会をこっぴどくやった人が、エッケルトの君が代の終止部分にてオクターヴ・ユニゾンのそれを連続八度などと揶揄する様では単なる声楽の和声法を持ち込んだだけの誤謬に過ぎぬ解釈となり、その様な誤った理解に陥る様な人達がもしかすると林達也著『新しい和声』にケチを付けているのではないかと思う事も多々ありではあります(笑)。そういう「旋法的和声」の振る舞いとやらをあらためて例示するが故に、前回は早坂文雄のそれも例示した訳なので私の言わんとする意図が少しでも伝われば之幸いです。
山下邦彦と言えば、同氏に依る『坂本龍一の音楽』では、小室哲哉が嘗てのキーボード・マガジン誌上にてコード理論を寄稿していた文章を論い、それを奇異の目で取上げている物があります。実はそれはシュテファン・クレールが嘗ての和声学で語っている事に繋がるもので結論から言えば小室哲哉の論の方に分があるのですが、畢竟するにC△7という和音はC△とEmが同居する。だからC△7という和音は物悲しげなのだという事を小室哲哉が述べている所を山下邦彦は、C△7というコードをそのような聴き方などしないという風に、その和音の捉え方のおかしさを挙げている所があるのですが、これは疑い無く小室哲哉の論に分があるのです。
とはいえジャズ界隈の人達というのは、重畳しい和音を「多即一」の様に、そのコードが持つ音響的性格や色彩をひとまとめにして硬い響きとして耽溺に浸る(もしくはその硬い響きを一音響として耳に馴らす)という所があるので、山下邦彦がよもやC△7というコードに対してCメジャー・トライアドやEマイナー・トライアドを見る様な所に違和を抱くのは理解できる所もあるのです。ジャズ的方面から体得して来た人の多くはこうした捉え方の方が自然でしょうから。
然し乍らクレールの時代の四和音の取扱い方法は矢張り小室哲哉と同等の考え方で教えます。旧くからこういう教え方なのです。
ジャズの場合、主旋律が稀薄であっても「和音を構成する音の束」がそれを補う事があります。然しジャズを除けば多くの音楽というのは、和音という音響集合体は複数の「音の線」が絡み合う事でそれが垂直的に和音を生じている訳ですから、《火の無い所に煙は立たぬ》という格言ではありませんが、線の無い所に和音構成音は作られない訳です。和音構成音として突然表れるのであれば、それに相応しい線が在って然るべきという考えが大前提であるからです。勿論、和声的な音楽観も高次に追究されれば、その和音とて「Timbre」(=音色)的な色彩として用いて、その色彩の塊をいくつも並べて「進行」させる事で、線は稀薄であっても音響的に進行するという技法も勿論あります。とはいえ大半は、「横の線」が在るべきとして教わっていく物です。
ジャズに限らず現今のポピュラー音楽というのは、和音が持っている響きの牽引力を借りた線の作り方の方が顕著であると言えます。和音の牽引力を必要としない程説得力のある単旋律を生み出せる様な人など、よほどの旋律としての牽引力がない限りそれだけで引っ張る事の出来る旋律を作れるというのは相当少なくなる事でありましょう。旋律としての力が卑近で牽引力も稀薄だけれども歌詞という、言葉の牽引力でどうにか体を保っているというケースですら珍しくはありません。言葉の牽引力がある為に卑近な側面に批判が向けられないで居る作品も決して珍しい物ではありません。
「素直な牽引力」というのは調性の持つ引力に由来している向きが往々にしてある為、単旋律であろうともそれに音程の牽引力をグイグイ感ずるのは、調性自身が本来持っている引力と言う「次の歩を進めるべきは此處ですよ」と音楽の神様の思し召しにも似た脳裡に誰もが映ずる事の出来る脈だと言える事ができるでしょう。然し乍ら「半音階的全音階」という調性を維持し乍ら半音階的作法を駆使する状況に於いては、全音階から逸脱する音にも「何等かの機能特性」的な響きがある訳です。

特に先の曲の大サビは次の様なコード進行であり、特に4小節目に「付加四度」で長三度音と短二度でぶつけてストリングスを用いている部分は特筆に価する絶妙な響きでありましょう。
D△9 -> E6 -> F#m7(9、11) -> A△7(9、11)←※A△9+付加四度の本位11度は長三度と短二度のストリングス。下からa・e・gis・cis・d・gis・hというヴォイシングで弾くと感じが掴めるでしょう。
ダイアトニック(全音階)の音を固守しているにも拘らず、こうして曲の情感を多様に移ろわせる事が出来る訳ですね。特に付加四度の使い方というのは、通常ならば短七度を包含した長和音(つまりドミナント7thコード系統)で、ミクソリディアン・モードを移ろわせるような遣り方が多いのですが、長七度を内在させての付加四度へのセンスは素晴しいと思います。勿論A△7(9)から見た本位11度=付加四度を充てるのは一般的な和音の在り方すればアヴォイドなんですけどね。感性がアヴォイドという縛りを易々と跳越するのはこういう例に倣った上で、《盲人蛇を畏れぬ》と言われぬ様、音楽観をきっちりと「具備」してナンボだと思うんですなー。特にその辺のギター兄ちゃんとか肝に銘じておかないといけませんよ(笑)。
まあそうしてあらためて「調性」とやらを見つめた時、例えば長音階というヘプタトニック組織には7つの機能があります。
1…主音(=完全一度)
2…上主音(=長二度)
3…上中音(=長三度)
4…下属音(=完全四度)
5…上屬音(=完全五度)
6…下中音(=長六度)
7…導音(長七度)
これらの音階固有音の外にある音、例えば長音階の主音から「短六度」にあるフラット・サブメディアント、「短七度」にある「下主音」、「短三度」にあるフラット・メディアント、「増四度/減五度」にある三全音にも、本来の調性の余薫を漂わせた振る舞いがある訳です。そうした近親的な調性から得られるのを準音階固有音とも呼ぶ訳ですが、調性をこっぴどく学んだ次のステップというのはこうした半音階的全音階の社会を知る事が肝要である訳です。
先述の「君が代」というのは、長音階の主音を余薫として強固に脳裡に映じて他の音を吟味している訳ではありません。つまり「中心音」と為すべき音は主音に対しての役割が稀薄になっているからこその「旋法性」のある曲想なのであり、その旋法性という曲想は、倍音に逆らう事のない「素直な進行」に随っているだけでは生まれない情緒なのです。そういう意味でも嘗てクラウス・プリングスハイムが「管弦楽のための協奏曲」を作り日本的和声とやらを西洋音楽のそれにて作った物もありましたが、そこには日本的な情緒の移ろいは稀薄で、日本的な情緒として和声が付けられているとは感じにくい卑近な感を抱かざるを得ない所があるのは否めないかと思います。
箕作秋吉はポジティヴ方向(上行列)とネガティヴ方向(下行列)双方に五度和声を組み上げ、ポジティヴ側は根音をaに採りa・e・h・fis・cis・gisと積む事が可能で、それから得られた音列を転回させ「a、h、cis、e、fis、gis」という上行音列を生み、ネガティヴ側はf・c・g・d・a・eという風に辿りそれを転回させて「e、d、c、a、g、f」という下行音列を作った訳ですが、実はこれを生んだのは単純な振動比から導出された牽引力に端を発している訳です。
こうした例を踏まえると、単音がポツンと座している所に上方倍音を頼りにするだけではなく、下行形の音脈として結果的に下方五度にも作用する音脈を我々は普通に映ずる事が可能ですし、オクターヴが更に細かい音程へと細分化されていった「大完全音列」の時に、上方に作られる五度音程を「上屬音」、下方に作られる五度音程を「下属音」とした事で、下方の五度の音脈というのは、何の根拠もなく下方倍音列を唐突に持ち込まずとも、少なくとも下方五度の音脈はこうした所にも音脈としての牽引力は存在するものであり、和音進行の弱進行という音脈もこうした作用から生じている物であると謂える訳であります。
エドモン・コステールがヒンデミットのシュテムトンを断罪するのは、コステール自身が上方倍音ばかりに依拠した発想から立脚している事でヒンデミットのシュテムトンの出現順位の優位性とやらに反駁しているのですが、コステールが無視しているのは「結合差音」の作用であり、ヒンデミットは、協和音程からも生ずる結合差音の存在を無視できないからこそ結合差音を含めた順位によってシュテムトンという近親性をあの様な優位性としての順番で取上げている訳です。上方倍音列ばかりに依拠していたら弱進行の作用すら否定せざるを得ず、よもや12音技法から得られる「調性の音脈を掻き消す」振る舞いが必要である筈の無調社会が、それほどまでにコステールの様に上方倍音だけに頼ってしまっていたら自家撞着も甚だしい自己矛盾となってしまっている訳です。
コステール著『和声の変貌』では、ヒンデミットがシェーンベルクのOp.33aをして調性的痕跡を分析している例を取上げ、コステールは12音技法に対して調性の余薫を感ずるなど重箱の隅を突く様な物として反駁しつつ次のヒンデミットの「和声力・旋律力」の譜例を、単に「C音に対する親近性」という風に歪曲して論駁している点が残念な所なのである。
ヒンデミットは自著『作曲の手引』図版59では、次のex3の様な音程は「和声的」な断片として用い易い事と、和声的な断片ではなく「旋律」としての横の線として用い易い事の「対比」を単に挙げているだけの事であり、C音に対する親和性とは異なる理解なのであります。而もヒンデミットは「三全音」に対して狭い三全音から広い三全音まで例示して、それらの三全音の結合音(=差音)こそが三全音の根音を決定する為の特殊な音程として取上げている為、コステールが『和声の変貌』43頁で載せている譜例は抑も曲解であり、三全音の部分も端折り過ぎた断章取義(三全音の結合差音由来の一例しか挙げている一方でヒンデミットは三全音に対して3つ例示している)に過ぎないのです。
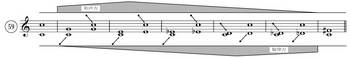
加えてコステールは『和声の変貌』48頁にてヒンデミットの中心音をひとまとめにして近親的な音として例示するものの、それは詳細を欠いていて、本来は次のex03のように近親音がある訳です。コステールは、早期に出現するes音=E♭音は、上方倍音列ではもっと高次な倍音由来ではないと得られない筈なので、これほど早期にes音の優位性がある筈が無いと断罪しているのですが、「旋律的親和性」は上方倍音を一挙に「和声的に」聴く見方とは異なるものであり、旋律的な欲求を音響的な垂直レベルで比較するのは全く埒外である。コステールの言うように、このヒンデミットの「旋律的親和性」が上方倍音に依拠する物でならないならば、旋律的な横の線として長六度の音程で跳躍しようとするよりも自然七度(第7次倍音由来)の方を優位的に選ぶ事になりかねず自己矛盾を秘めた暴論となってしまっており、これこそがコステールの価値を低めてしまっているものであります。

ましてやコステールは低次に出現する自然七度の「大きく外れたイントネーション」のそれを、上方倍音列の22次倍音までは四分音律から見た時それらの音程差は81/80というシントニック・コンマ以内に収まる因果関係を持っているから、四分音律から外れたコンマ以内の微小音程は某かの四分音に吸着される音程という風に冒頭から宣うのであるが、これは低次に発生する自然七度にアシストせざるを得ない詭弁にすぎず、コステールは四分音律を詳らかに語っているのではなく、12平均律における各音の親近性を語っているのですから、四分音に吸着されるイントネーションであるならば、四分音は12平均律のどの音に吸着されるのか!? 或いはヘプタトニックという調的な音階固有音から見たらノン・ダイアトニックの音はどの音階固有音に吸着されるのか!? という事を自身が全く明らかにしておらず、而もコステールの親和性というのはオイラーのそれに則って持論を強化しているだけの事に過ぎない物であるのに、オイラーはおろかヴァンサン・ダンディーの名前も挙げずに自身の親和性とやらを声高に叫ぶのは単なる強弁に過ぎない訳ですよ。
セリエルなど全く無かった時代にオイラーは音楽のそうしたシンクロニシティを「数理」で繙いていた訳ですが、人間が「均齊」へと赴く欲求は、細かな「音楽的訛り」というイントネーションが生じた音律の引力よりも「強い」からこそ、人間は平均律を手にした訳です。
処がコステールの、四分音の因果関係が上方倍音列第22次までは81/80のシントニック・コンマ以内に収まる物であるから、それらの音程的な「ズレ」が四分音律の音に吸着される因果関係を持つのであれば、人間はシントニックを半音階(12平均律)に均す前に、四分音側に均してしまって12平均律を得る事なく完全五度の「不完全な」螺旋音律を使ってしまっていたのではないかと思うのですね。
なぜなら、低次に自然七度という-31セントが生じているなら、相対的な差として19セント高くなった時点で四分音に吸着してしまう事と等しくなる訳ですから、シントニック・コンマよりも狭い19セントが発生した時点で人間の耳はそこで安堵してしまったでしょうかね!? そんな事ぁ詭弁に過ぎないでしょう。純正完全五度を1回重ねただけで「2セント」ズレるのが実際な訳です。19セントのズレは10回純正完全五度を重畳した時には既に超越してしまう訳です。シントニック・コンマは純正完全五度を11回重畳して生まれる物ですから、それを鑑みれば、コステールはよもや「人間はシントニック・コンマ程の差なら均齊の方へ均す」という風に誤解しているからこそ、このような詭弁を弄する事になっている訳です。
人間は、シントニック・コンマを相容れなかったから均した訳ですからね。シントニック・コンマ以内で無頓着なら、世界何処でもオーケストラの弦楽器奏者の調弦など滅茶苦茶ではないでしょうかね!?(笑)。
人間の耳が自然七度に対して寛容であるのは、その音が位置するのが不協和音程の所にあるからです。協和音程の所に現れていたらトンデモない騒ぎになる訳ですよ(笑)。
調弦・調律とやらをひとたびやれば誰もが実感できる事ですが、シントニック・コンマ以内の音が某かの音に吸着するという状況は、うなりを消す為に調弦する事と等しく、うなりから見れば、微小音程として「導音」が際限なく狭い音程で「解決」しようとしている事と何等変わりないのです。
その「導音」的作用という事を「旋律的親和性」とやらで見立てる事はできなかったでしょうかね!? と私はコステールに言いたいのですね。しかも四分音律にて(笑)。じゃあ、その四分音律の音は、12平均律のどの音に吸着されようとする欲求が起るのかな!? という疑問など全く忘却の彼方に葬り去って,唐突に12平均律の均齊社会での各音の親和性とやら話を進めるのです。しかしこれはオイラーのそれに倣って脚色しているだけの事でありましょう。長音階の重心はE音にある、というのは腑に落ちますけどね。それは全く別のハナシです。
自然七度が四分音に吸着しようとするなら間違いなく、更に低い方の根音から数えたら950セントの音へ吸着しようとするでしょう。下行導音的に潜在的な力を持っているのでしょうかね!?(笑)。ジャズが齎したブルー七度は本来、本位七度(※私が言う「本位」音程は、長音階を元にした音程を本位としているので、本位四度及び本位十一度=完全四度&完全十一度、本位六度=長六度、本位七度=長七度を意味します)から微分音的イントネーションで低く変化した物が半音階に「吸着」されてそれが短七度としてブルー七度は使われています。勿論長七度と短七度の間の中立音程をマイケル・ブレッカーの実例を挙げて例示した事も過去にありましたが、ブルーノートのブルー七度はそういう物です。しかし、倍音列に無頓着で居られない吹奏楽器奏者が、よもや自然七度に遭遇した際にそれが四分音律やらに吸着される様な意識に開眼しているとは到底思えない訳ですね(笑)。そのイントネーションを「ポジティヴ」(=上行的に)に打ち勝とうとして、本来の半音階のピッチに均すという風に克服するのが自然な動機であるのは疑いの無い所でありましょう。
ヒンデミットは、長三度と短三度の間に「明確な」情緒の境界などない(明るい・暗いの明確な線引きなどない)と説明するが為にリーマンの短和音発生根拠を否定していますが、実はコレ、同主調のみでヒンデミットは見ていて反論しているので、本来なら平行調との関係で見渡さなくてはいけない遣り方なので、ヒンデミット自身も下方倍音列を否定したいがあまりに広汎に目を向けていない事実はあるのですが、これは又ヴァンサン・ダンディやリーマンを扱う時に詳述しましょう。然し乍らヒンデミットの功績は上方倍音だけに依拠する事の無い差音の働きに加え、同主調の音脈の正当性を奇しくも露にした事であるでしょう。
例えば短和音の発生由来の根拠としてディミトリ・レヴィディスは「潜在倍音」を引き合いにして、短和音という音脈に対する近しく存在する親和性とやらを見出し決着を図ろうとしています。これはジャック・シャイエ著『音楽分析』でも語られているので興味のある方は一読される事をお勧めします。
次のex4の例を見れば、赤色の倍音列が本来の倍音列と仮定した場合、最初のC音の下方五度にあるf音は「類推」に依って仮想的に生じている倍音列を辿るに過ぎません。しかしこのf音の類推というのは、C音から下方に生ずる五度音である為、大完全音列の生ずる處から上屬音・下属音が発生した様に、この類推は在って誹りを受ける程でもない音脈の一つであると私は思います。
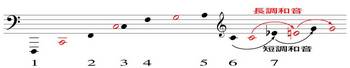
その類推に依ってf音からカウントした第7次倍音は、基から備わるc音からの倍音列であるc音に対して短和音の根拠となるes音を生じるのです(微分音的ですが)。その微分音的イントネーションの短三度とやらは、c音から上に250セントの中立音程に「吸着」されてしまいかねない音脈なのでしょうか、ねえ!?コステールさん(笑)。
しかも第7次倍音の大きく逸脱したそれを、矮小化させる為に使いもしない四分音律を根拠にして、それにてちゃっかり12平均律にてのうのうと近世社会に佞弁すればあまりにおこがましい物ですよ。アイヴズの例があるからといってd音のスリー・クォーターシャープに吸着するとでも断言してしまうのでしょうかね!?(笑)。申し訳ないけれど、12平均律でなくとも先の音は変ホに吸着しようとしますよ(笑)。
確かにあらゆる音は上方倍音列の作用を受ける為、どんな単音でも倍音列の作用から「属和音」としての性質を持っているとも言える訳ですが、その「音響的属音」と調性が生ずる音組織に於ける第5音に生ずる属和音の持つそれと「合致」した時に初めてドミナントとしての解決の為の作用が強化されていると以前にも述べた通りです。これについては『新しい和声』が刊行された時にも述べている事ですし、判り易い例で言えば諸井誠が自著『音楽の現代史』にて述べている事でもあります。
調性として強く働く音組織の第5音としての属和音と、音響的に生ずる上方倍音列の属七和音的性格が合致していない和音の振る舞いとやらが、音律の熟成と共に多様な和音進行を生んで来た訳ですから、そうした和音を駆使して上方倍音列を取り込まないという調性に背いた進行というのは「多様」と為して至極当然でもあります。加えて、こうした多様な世界観は長調よりも短調の世界が多様性を生んで来た背景があります。故に、短和音の在り方やら弱進行の例を見る事で、あらためて多様な現実を思い知らされる事になる訳です。
2015-11-12 18:00



