マイナー・コード上の11th音 [楽理]
今回はとても限定的な状況を語る事になる訳ですがタイトル通り、マイナー・コード上に於ける11th音を取扱う事とします。3度堆積型の和音であれば西洋音楽的解釈であればマイナー・トライアドに11度音だけが附与されるという事はありません。それは附加四度という解釈になります。とはいえジャズ/ポピュラー音楽を含めると省略された形も少なくありませんし、何より西洋音楽まで目を向ければ11度音が必ずしも本位11度ではなく増11度の場合もある、という重要な点は念頭に置いていただき乍らブログを読み進めて貰い度い所です。
扨て、マイナー・コード上の11度音の取扱と雖も色々な用例があると前述しましたが、それではまず一般的な本位11度音が存在する状況を例に挙げてみる事にしましょう。
一般的な例としては本位11度音が存在する状況では長九度音も存在する事がコード・ネーム上では不文律となる場合があります。ルート(=根音)をC音とした場合、「Cm11」と表記する時の不文律すなわち暗黙の了解となっているのは、包含する9度音は長九度という事ですね。長九度が決して短九度ではないのは、基底となるマイナー・トライアドの響きを短九度が疏外してしまう=アヴォイド・ノートとなる例を排他的に扱う表記であるが故の表記である訳です。
実際にはテンション・ノートを括弧で括った表記として「Cm7(9、11)」という様な表記を見る事の方が多いでしょう。因みに、コードの名称として「マイナー・イレヴンス」と称する時は、「マイナー・トライアド+短7度+長9度+完全11度」という構造の事を指しているのも不文律として知られる点でありましょう。
突き詰めると、マイナー・イレヴンス・コードの7度音が長7度としての和音も存在しますが、これについては特に名称がある訳ではありません。これはこれで特殊であり独得の情緒を齎して呉れる和音ですが、先ずはマイナー・イレヴンス・コードについて語って行く事にします。
私の個人的な主観でCm11というコードを耳にした時、特に11th音が主題で奏されている時というのは、まるでファッション・モデルが脇目もふれずに歩く様な周囲の観衆にも一瞥も呉れないままに膝を入れてランウェイを歩く、あの猛々しい程の状況が浮かび上がる様な、そうした勇猛さがあるのがマイナー・イレヴンス・コードの響きであると私は感じております。
これが単にCm9という状況だったら、横目で一瞥を呉れるかの様な横顔を見せる様な響きがあるのがマイナー・ナインス・コードの響きの様に私は感じているのですが、マイナー・イレヴンス・コードの猛々しさは鏡越しに見る映像の中をも凝視するかの様に、それこそ車のバック・ミラーを隈無く凝視する様でもあるかの様にも響くかもしれません。孰れにしても、直射日光を浴びている訳でもないのに、回折だけで充分明るさを得てしまうかの様な強い存在感を感じつつ、直視する事が不要な程重量感を伴うと言いますか、そういう感じを形容するかのように思えるコードなのです。
マイナー・イレヴンス・コードの響きを存分に感じ取る事の出来る典型的な用例となる曲は、最右翼として私はチャカ・カーンの『I'm Every Woman』を挙げます。マイナー・イレヴンス・コードというのは、それをトニックとして奏してもテンション・ノートが下属音である訳で、「明後日を向いた」様な響きである為、ワン・コードとしても成立しやすい状況であるので、コード進行が希薄である事も許容されるのは和音が6声と重畳しい為であるのは明白です。ですからそこで卑近と思える程のドミナントへの進行など不要になる位、2コードでも充分な程という風にも演出可能となる訳です。
他にもダリル・ホール&ジョン・オーツ「I Can't Go For That (No Can Do)」もそうですし、山下達郎の「メリー・ゴーラウンド」も好例として挙げる事が出来るでしょう。
これらの用例とは別に、マイナー7thコードを基底和音として持ち、それに本位11度音が附与されるタイプの「マイナー7th(11)」という和音もジャズ/ポピュラー体系では能く見受けられる物でもあります。これは実際は「四度和音」を表している物であります。
仮に「Cm7(11)」というコードがあった場合、g音から上方に完全四度を累積して行くと「G・C・F・B♭・E♭」という風に五声が積み上がる事となり、この基底音をg音からc音に変えた物という風に見做す事が出来る訳です。ハービー・ハンコックの「処女航海」もジャズ的表記ならばコードネーム表記の流儀に沿う物として表記せざるを得ないでしょうが、あれは四度和音であります。
四度和音で他にも有名なポピュラー音楽では坂本龍一の「千のナイフ」のイントロが四声の完全四度等音程による四度和音であります。
これらの四度和音の用例で顕著なのは、機能和声的な和音進行とは全く異なる旋法和声の在り方を示しているのであります。構成音そのものは某かの調性内に収まっているとしても、行き先となる後続の和音への音脈を辿るそれは調性のレールを踏もうとはしない自由度の高い音脈を醸し出そうとする物です。ある意味ではマイナー・イレヴンス・コードから9th音を省くだけで、そうした茫洋とした自由な動きが強化されるというのも興味深い点でありましょう。
扨て、マイナー・トライアドを基底に持つタイプで11度音を擁する物は必ずしも7度音が短七度とは限りません。長七度のタイプも使用例は少なくなって来ますが存在しうる物であるので、コード表記としてあまり見掛けないからと及び腰になる必要は無いのです。
マイナー・メジャー9thコードを包含するタイプの11度音を擁する物は通常、本位11度を使うとなるとその時点でトライトーンを包含するので響かせ方としては難しい物になりがちです。仮にCmM7(9、11)という和音があった場合、CmとG7を包含している状態ですが、これらをその様に響かせるだけでは卑近な迄の機能和声に準じた響きしか導出出来ない事になります。そこをもう少し工夫して、E♭M7augやE♭M9augとしての響きを演出しつつ、E♭音から下方3度にある音脈としてリラティヴにC音を下に付与する様な形でフレージングしたりするだけでも全く様相は変わります。つまり、C音側のリフの演出次第で、カタチとしては一見ドミナント7thコードを包含する、つまりトリトヌスを有している様な状況でも下方五度進行を感じさせるフレージングをしない様な響きを演出する事が重要、という事を意味する述べ方なのであります。
それを鑑みれば、チック・コリアが「Flamingo」にて「Ⅰm7→♭Ⅵ7/Ⅳ」というツーコード循環をする理由が判るかと思います。「Flamingo」の原曲キーはDmですから「Dm7→B♭7/G」となる訳ですが、この後続和音の「B♭7/G」を同軸で見ればGm7に短九度を付与してしまう(短九度はマイナー・コード上ではアヴォイド)と見做せるのですが、そういう解釈ではないからこそ実際にこうした使用例がある訳です。アヴォイドという解釈も機能和声のそれに従順である事に加えて、垂直レベルでダイアトニックな和音の響きを疏外させない為の用法なのですから、非機能和声の尺度やモードの世界観にてアヴォイド・ノートを持って来ても却って無駄な見立てなんですね。

例えばジェフ・ベックのアルバム『Wired』収録の「Play With Me」のBパターンでは「Dm7→Dm7 (on G)」の2コード・パターンが繰返されますが、後続和音のツー・オン・ファイヴのコードに機能和声的な響きを想定してしまってその後のコードとしてCに進んでしまう様な響きを演出してしまったら、それまでの一連の進行で直視していなかった筈の、折角の調性感の「暈滃」が台無しになってしまう訳ですね。
アヴォイド・ノートの定義をトリトヌスの包含とだけで判断してしまうと、所謂メロディック・マイナー・モードの音組織にアヴォイド・ノートが無いという所への誤解を生じてしまう陥穽がある訳ですが、この音組織を音階として「横の線」として見るのではなく、和声的に「縦の線」として見ると、メロディック・マイナー・モード上で生ずる和音のⅠ・Ⅳ・Ⅴ度上の和音はトニックとなるトライアドが「Ⅰm」となる意外は「Ⅳ△」「Ⅴ△」という風に、短調としての風合いが和声的には希薄になるという所から、調性感は二元的ではなく雌雄関係の様な両極性も希薄となり、世界観が混淆とする両性具有的な物になっているという事が確認出来ます。これはつまり、主音・下属音・属音という音が中心音となっているだけの状態で、この骨格に和声的には長調・短調の両性具有化が起きている状況と見做す事ができます。そしてⅤ度の和音の時導音欲求が生まれ、上行形の導音としてⅤ度上の和音の第3音が機能し、下行導音としてⅤ度上の第7音は半音下行ではない順次下行進行として機能するのです。
短調に於て、Ⅴ度上の和音の第7音の下行導音がⅠmに解決する際半音の導音ではないとはどういう事か!? という疑問を抱く人がいるかと思います。
短調とは本来終止和音はピカルディ終止であった為Ⅰ△で終るべき物だったのであります。そうすれば属和音にのみ七度音を附与する事を許された属七の第7音は下行導音が半音滑り落ちて解決する訳です。短調とてもっと古い時代ではドリア調が実際には短調であった訳です。そしてⅤ→Ⅰの時に導音欲求または導音傾向という仕組みで導音の変化を起していたのです。ですからジャズ界隈でのドリアン・モードというモードの仕来りと、西洋音楽でのドリア調という取扱はⅤ度上の和音を変化させる西洋音楽のそれとは全く異なる体系であるという事が判ります。
そうした、短調が同主調の主和音で終止するという流れから、旋法的変化を維持する動きが多様に見られる様になり、短調はエオリア調も生む様になった訳です。
現今社会でジャズ/ポピュラー音楽界隈の人が、短調の音楽を奏するにあたってⅤ7→Ⅰmの際、属七の第7音が後続和音に半音の勾配を作っていない事に歎息する人がどれほど居るでしょうか!?(笑) おそらくそんな事など気にせず相容れているのが当然の事として理解されている事でしょう。私とて通常の俗化された耳としてそれを許容する物です。
こういう「許容」が、短調の世界の多様な変化を生んで来た証でもある訳です。一方ではピカルディ終止を許容し、旋法的には短調の音組織を維持し乍ら和声的に他の箇所で置き換えが進むという体系が生じた訳ですね。例えば短調という短旋法を「ラシドレミファソラ」と見た場合、「ド」を旋法的に唄わせる事を維持させれば良いのです。ピカルディ終止の終止和音の時、和声的には「ド♯」として変化している訳ですが、主旋律が「ド♯」を唄わず伴奏に隠す。そうする事で他の短調への和音に進む際、主旋律は短旋法を維持できる訳ですね。こういう「ひた隠し」は、基の旋法的な流れを重視しただけの事であって、必ずしも伴奏に隠せという事を意味する物ではありません。
とはいえ、こうした例が多数生ずるのが短調の世界であった訳ですから、旋法的にも和声的も多様な世界観が生じた歴史はこういう事に依拠する物であって、結果的にメロディック・マイナー・モードの第Ⅰ・Ⅳ・Ⅴ度の和音に於て、トニック・マイナーのみがマイナー・コードであるという短調の音組織の和音と同主長調の音組織の和音が混淆とする様な音組織が生ずる様になったのは、こうした多様性の果てに見られる事だからです。リムスキー=コルサコフ著『和声法要義』を読めばこうした点は端的に説明され腑に落ちる事でしょう。
「導音」というのは一般的に、上行形に於て主音または到達音に対して「半音程」だと思われている方が居られると思いますが、導音が齎す作用を広く俯瞰すると必ずしも半音ではないのが導音の働きです。これはとても重要な理解なのです。
導音というのは「到達音」に対して強く作用する物です。それが半音でない場合、旋律における中心音として存在感を生じている音が到達音として存在する場合、これが《導音よりも音価が長く》更に《強勢に生じていれば》それが全音であったとしても「導音」という機能を持つのが真の導音の理解なのです。
その導音が到達音に対して全音階的ではない即ちノン・ダイアトニックの方面に半音で導音が生じた時は、それまでの調性が持っていた調的余薫とは全く別の欲求が生じて半音階的変化がこれにて生まれる訳で、和声的には多様性を増す局面である訳です。
一般的な例を挙げるとⅤ7→Ⅰ△での属七の、上と下からも導音でガッチリと万力で締め上げるかの様な情緒と「Ⅴ7 ->Ⅰm」でのⅤ7の第7音の進行を比較すれば、後者のそれは進行的には「弱い」牽引力でもあると言える訳です(何故なら全音の勾配)。これに弱さなどを感じていない人が殆どではないでしょうか。「弱い」と感じる事が正当でもありませんが(笑)。この「弱い」というのは全音の導音を意味します。
また導音は上行形ばかりではありません。フリギア終止にも代表される様に下行導音もあります。その下行導音とて常に半音でなくてはならないというルールなどありません。偶々属七の和音がトニック・メジャーに解決する際はトリトヌスが上からも下からも半音の勾配を作る為に先述の様に万力で締め上げると評したそれが生ずる訳ですが、属七からトニック・マイナーの場合の下行導音は全音の下行導音な訳です。
この全音の導音という私の説明に疑念を抱く方が居られるならば、下総皖一著『標準和声学』(音楽之友社刊)のp192を読めば深く首肯出来る事でありましょう。
また同時に短調の和音進行に於てはV7からⅥに進む事も少なくありません。このⅥ度上の和音というのは短調では多様な変化をする物でもあるので、こういう点にも注意を払うと良いかと思います。
扨て、YMOのアルバム『ソリッド・ステイト・サヴァイヴァー』収録の同名曲「Solid State Survivor」(高橋幸宏作曲)の冒頭は、実際ならばマイナー・コードに11度音が附与された和音とマイナー・トライアドとのコントラストを生ずる様な進行であるのでしょうが、「Dsus4 -> Dm ×2 →E♭sus4 -> E♭m ×2...」状況でもあるでしょう。併し実際には「Dsus4」と表記したのは便宜的であり、ベース・ラインがマイナー3rd音を強く主張する為「Dm(11)」というマイナー・トライアド+付加4度という解釈にすべき物でありますが、この4度音が後続である同度のマイナー・トライアドとの「全音音程」の勾配を作るのが興味深い所であります。これは全音音程に依る下行導音的活用です。個人的な意見ですがYMOの作品の中で私が最も好きな曲はこの曲であります。ロックとブルースの多様性がとてもシンプルに鏤められて居ります。こうしたシンプルに響くマイナー・コード上の本位11度音のさり気なさという所にも注目して欲しいと思わんばかり。
扨て、今回はマイナー・コード上の11th音を取扱っているので、メジャー・コード上での11度音の取扱は省く事になります。とはいえ本来11度音への和音重畳の由来というのは上方倍音列として存在する音脈を利用している物なので、そうした前提を考慮すると、長和音上で生ずる11度音が本位11度ではなく(こちらはアヴォイド)、増11度音を積み上げるのは合点の行く所であります。
とはいえ11度音の存在は9度音無しでは表れなかったのもあり、そうした適用が属和音以外の副和音にも適用され、調性を維持する音組織つまりモード・スケール内のダイアトニック・コードとして3度音程を累積させた物を適用したコードを利用する事になり、それがダイアトニック・コードとしてマイナー・コードを本体とする和音の11度音の場合、ダイアトニックを維持する為に本位11度音として存在を為しているのは言うに及ばずという点は充分に理解して貰い度い点であります。
それならば、短和音上の本位11度音は上方倍音列の由来とは意を異にする和音の解釈ではなかろうか!? という事まで考えが及べば宜しいのです。抑もマイナー・イレヴンス・コードとはトニック・マイナー上ではなく上主音、つまり長調のⅡ度上から全音階的に3度を累積していった所から端を発しております。
3度を全音階的に累積した状態で11度音まで積み上げれば、それがⅡ度上の和音かどうかは無関係に、本来ならば複調的解釈を伴う物です。更に複調的解釈が高まるシーンというのは、和音の第3&5音が省略される場合です。こういう時に現今持て囃されるタイプの2度ベース、喩えるならば「C△/D」が出来上る訳です。第3&5音が省略されないDm11の型とて西洋音楽方面ですら旧くからⅡ度上の和音として愛用されていた訳ですから。
両者を鑑みればDm11という6声をフル活用するそれはDmの上にC△があるアッパー・ストラクチャー・トライアドという捉え方に依る和音という風に見立てる事もできます。アッパー・ストラクチャー・トライアドというのは結果的に3度累積を連ねている状況で基底和音の上方に別のトライアドを形成する事で、結果的にトップノートから根音まで省かれる3度音程が無く「3度の類推」を可能とする物である為、省略しない限りは重々しい響きになる訳です。
それらの和音の現実を考慮した上で別のケースに目を向けてみると例えば、マイナー・コードを基底和音とした時に長7度及び増11度音が積まれて行くという類の和音をアーサー・イーグルフィールド・ハル著『近代和聲の説明と應用(近代和声の説明と応用/近代和声学の説明と応用)』で見付ける事が出来る訳ですが、著書のタイトル通り、その近代和聲とやらが上梓100年を経過しても猶その響きが新奇性を持っているという所に驚きを禁じ得ないと言いますか、音楽の世界の響きに対する一般の人々の受容というのは実に保守的であるという所もあらためてお判りになるかと思います。
無論、ハルの例示する短和音上にある増十一度の包含というのは第一次大戦の後にフランク・ブリッジの作品でも見つける事ができる様に、属調から手繰り寄せた更なる属調および六度調をも複調的に呼び込む事で得られる状況がポリコードと成しているのは言うまでもなく、そうした音脈となる経路を辿っているのは明白な事でありましょう。
長七度音を擁する短和音を母体として本位11度音はそこに長九度音も附与される事が通例なのですが、マイナー・トライアドを基底和音とし乍らアッパー・ストラクチャーにドミナント7thコードを包含してしまうのが用法としては難しい所ですが、Cm△7(9、11)とやれば、Cmに対してG7を包含してしまうという訳です。とはいえこれまでもドミナント7thコードの多義的解釈やら弱進行をやって来ていると思うので、このG7が後続和音に対してあざとい程に下方五度進行を醸す様な進行を回避すれば、こうした状況があっても良いのです。それが機能和声的な状況を生まなければそれも是とすべき物なのです。
つまり、そうした例外を理解すれば、マイナー・コードの上にどんどん3度音程を積み上げて13th音を導出する事がどういう事か!? という事もお判りになるでしょう。すなわち、マイナーコードに13度音まで積み上げればダイアトニック・トータルとなってしまいますが、モード的なアプローチ或いは機能和声的進行を回避する状況であるならば11th音を回避して使う、例えばDm7(9、13)として使うとか、そういう事をこれまで語って来ている意味があらためてお判りいただけるかと思います。*
余談ですが、13th音というのはマイナー・メジャー7thを擁する時はアヴォイドではありません。11度音をオミットした上でチック・コリアはジョン・パティトゥッチの1stソロ・アルバム収録「Baja Bajo」にて「Cm△7(9)」上で、シンセ・リード音の13th音を附与したアプローチを聴く事ができます。
 スパイロ・ジャイラのアルバム『Incognito(邦題:遥かなるサンファン)』収録の同名曲「Incognito」ではB♭m△7(9)が顕著な曲ですが、キーボード・イントロ部ではルートをオミットして「短調のⅢ度」つまりD♭オーギュメンテッド・メジャー7thを弾いているのですが、この時のB♭音から見た時のA音とは音階固有音として見れば導音ではありますが、短調での長七が必ずしも導音という動きを採らないという事をジャズで体現しているのです。
スパイロ・ジャイラのアルバム『Incognito(邦題:遥かなるサンファン)』収録の同名曲「Incognito」ではB♭m△7(9)が顕著な曲ですが、キーボード・イントロ部ではルートをオミットして「短調のⅢ度」つまりD♭オーギュメンテッド・メジャー7thを弾いているのですが、この時のB♭音から見た時のA音とは音階固有音として見れば導音ではありますが、短調での長七が必ずしも導音という動きを採らないという事をジャズで体現しているのです。
B♭m△9の響きが最も効果的に表れているのはCDタイム1:14〜の箇所なのですが、B♭m△9 -> B♭m7という風に、長七度→短七度という風にクリシェ下行しかも主音から長七度へのクリシェというのは全く用いずに、強い酸味を伴った短和音の様にマイナー・メジャー7thの響きを強調するのであります。その酸味を尻目に見るかの様に長九度音が附与されてB♭m△9というサウンドをあらためて強調しているのでありますね。絶妙です。
B♭m△9というコードを目の当たりにしてしまうと、広く知られている楽曲が他にあります。ジェフ・ベックのアルバム『ブロウ・バイ・ブロウ』収録のバーニー・ホランド作曲の「Diamond Dust」がそうです。もっと広く目を遣ればTBSドラマのキイハンターの終止和音やらザ・ピーナッツの「恋のバカンス」などでも短和音+長七+長九のタイプの終止和音というのは珍しくもありませんが、終止和音でもなく、長七度という音階固有音が主音と半音程であり乍ら導音とならない使い方という方に目を向ける事が、和音の高次な側面を見出す最も重要な点である事を忘れてはなりません。通常ならば導音→主音という半音の勾配とやらを、スパイロ・ジャイラの「Incognito」のコード進行は逆進する訳です。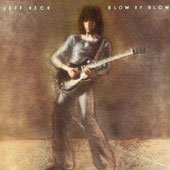
こうした「逆進」という例は、和声を高次に活用する為にとても必要な前提でもありまして、例えば和音が上方に重畳しく構成されて行く様は確かに上方倍音列の高次に聳える音を頼りに導出する音空間であります。それは一体何を意味しているのか!? と言いますと、和音が他の和音と連結・進行して和声を生じます。1つの和音の構成音が高次に重畳しく聳えさせようとも、その連結が下方五度進行にある様な余りに卑近な進行であるならば、和音はよほど主音と遠い音程関係にある音を奏でていない限り、高次な和音を使う意味もなくなってしまうものでもあります。主旋律も卑近、和音進行も卑近なのに単に伴奏で奏される和音だけが重畳しいのであれば響きのバランスを欠いてしまい却ってメロディの卑近さが露になり、伴奏からの音脈を主旋律に変更する必要が出て来る程おかしな響きとなりかねません。
極言すれば、重畳しい和音を用いて和音進行する際、卑近な和音進行ではなくそれまでの機能和声の世界では見掛けなかった遠隔的な音程に進行するという弱進行や一時転調や偽終止に分類される様な世界観の追究が始まった訳であり、これに貢献をしたのは熟成された音律に外ならない訳です。
ですから、機能和声の持つ強力な世界観だけに裏打ちされた真理とやらをこっぴどく学ぶ事も大事ですが、その後の和声感の熟達を高めるには、調性が希薄に感じられて了う様な音世界の響きを体得する事がとても重要になる訳です。そういう意味でも先日、島岡版舊・藝大和声から林達也著『新しい和声』へシフトした際、保守的な立場に固守する様な人であればあるほど舊島岡版のそれを是とするような嫌いがあり、Amazonレビューを見ても言わずもがな、と言った所でしょう。私がこれほど迄に、機能和声的枠組みとは意を異にする和音進行を取上げつつ、弱進行やドミナント7thコードの多義性、ブルース/ジャズの出自、戸田邦雄に依る洗足論叢で語られる島岡版の藝大和声では是とされないⅤ→Ⅳ進行の論文をレコメンドしていたのはこうした意図があっての事だったからであります。
先のマイナー・メジャー7thコードにしても、音階固有音としては導音であろうとも、和声的に用いる時にそれが必ずしも導音にならない時もあり、一般的「導音」とやらは到達音に対して「半音」である理解であれば大抵は事足りる理解ではありますが、導音は須く半音であるのではなく、全音の場合もあると述べてきたそれらの違いをきちんと理解した上で音楽の響きを体得しなくてはいけないのです。
マイナー・メジャー7thコードの第7音を導音として使わないのであれば、マイナー・メジャー7th+長九度+完全11度(本位11度)を附与した時、この和音のルートをC音と見立てるならばCm△7(9、11)の構成音には確かにG7を包含してしまうものの、B音(独名:H)を導音としないのであれば、包含されるG7というコードは見かけ上ドミナント7thコードであるだけであってG7から明確に下方五度進行を行おうとしてG7に更に包含されているトリトヌスが限定進行しようとするそれとは全く別の体系の物だという事を理解しなくてはいけないのです。
処が和声学の原理主義の部分ばかりに拘泥してしまうと、こうした例を是としないばかりか、思弁で原理的な世界観を考えているだけなので、実際の響きの体得の前に「悪しき例」として断罪してしまう嫌いがある物なのです。ですから、保守的な耳、特に和声の熟達に甘い耳を持つ人ほどCm△7(9、11)という和音に、己の拙劣な和声感覚のそれがG7という姿の方を強く響く様に感覚が働いてしまうという物でもあるのです。これが是正されぬまま、新たな和声的な世界観を語れる訳もありません。
ですから、マイナー・コード上に於て13th音というのは確かに機能和声的社会の尺度から見ればアヴォイド・ノートの扱いであるのはそれはそれで間違いではありませんが、非機能的和声進行であるならばそれは問題ありませんし、どうしても包含されてしまう属七の体を稀釈化する上でもマイナー・コードで13th音を使うならば5度音よりも11th音をオミットした方が良いのであり、且つそのコードから後続和音が下方五度進行しない様な状況やモードの世界であれば臆する事なく使える和音なのであります。
例えばダイアトニック・トータルとなる全音階の総合=総和音を例に取れば、Ⅳ若しくはⅡをルートとする和音は機能和声の世界でも最も柔和に響いてくれるからであり、それはサブドミナント機能を持つ和音が後続へ進行しないという力が働いている状況と見做し得る物で、且つワン・コード的に聳える事が出来る様に響くからでありましょう。
スパイロ・ジャイラ「Incognito」の大半は、先の当該部分のコード進行を次の様に
B♭m△9 -> B♭m7 -> E♭7 (on B♭) -> G♭△9 (on B♭) -> B♭m11
奏しておりますが、CDタイム2:04〜の部分ではE♭7 (on B♭)というコードをE♭音を基底とする和音に変えた上でマイナー7thコードに対して増11度音が附与されるタイプ畢竟するに「B♭m7(9、♯11)」という風に、マイナー・トライアド+短7度+長9度+増11度という風に11度音をオルタレーションさせたアーサー・イーグルフィールド・ハル流の和音を忍ばせているのも特長でありましょう。こういう所を聴き逃してはいけません。
「B♭m7(9、♯11)」というコードはポリ・コードという風にして見ると、下にB♭mトライアド、上にA♭augトライアド(増三和音)が生じているという事になります。
これらを鑑みると「Incognito」ではB♭マイナーに於ける第7音と第4音を如何にオルタレーションさせて変化を付けているかという工夫が見られる所に着目しなくてはなりません。短調にて単にブルー5度としてではなくオルタレーションされた音と元の5度音を和声的に同居させるという事は、同度由来としてではなく異度由来として和声的に発展させるという見方で分析する必要があります。
ご存知の様に短調の曲というのは第7音は猫の目の様に変化させる事も少なくありませんし、それこそブルー五度とは異なるジプシー由来の音なども入って来たり、時には2度が下行形でフリギア終止の為に変化したりする事など珍しくありません。こうした短調の曲想にて、それらの変化が齎す和声感の余薫を旋法的にも和声的にも一即多多即一として採り入れた顕著なジャズ・マンの一人に私はディジー・ガレスピーを挙げます。その次にバド・パウエル。例えるならば伴奏としての和音はマイナー7thコードであるのに、その上のインプロヴァイズはメロディック・マイナーを奏していたりとか、そうしたスーパー・インポーズが見られる様になったのをジャズ界隈で見付けるならば私は真っ先にディジー・ガレスピーの名を挙げたという訳です。
スーパー・インポーズ系の音脈の表し方というのは実際にはパーシケッティ及び水野久一郎訳に依る「投影法」にて分析する必要があるでしょう。これは私も再三ブログで述べて来ているのであらためて語りはしませんが、投影法を根拠にそうした音脈を引っ張って来る根拠というのは結果的に下方倍音列を語らなくてはいけないのですが、これについては何れヴァンサン・ダンディの『作曲法講義』やディエニの『生きている和声』を参考にし乍らあらためて語る日もあるかと思います。とはいえそれに待ち切れない方は先の著書を手に取って学んでも良いのですし、私の述べている事など単なるヒントに過ぎない訳ですから、著書からきちんと本質を学ぶ事が肝要でありましょう。
そういう訳で、マイナー・メジャー7thコード上に増11度音が附与される和音もあらためて知った訳ですが、私が以前にGreensleevesをアレンジして用いた「Bm△7/C△」という和音も、私がローカルで云う所の「マイナーのペレアス」という物の発展形でもありますし、最近では顕著な例としてスタンリー・カウエルのアルバム『Juneteenth』にてやはり聴く事ができる物です。マーク・レヴィン著『The Jazz Theory Book』では、ペレアス和音という風にも語られてはおりませんし、Ⅶ△/Ⅰ△というポリ・コードの筈なのに同度由来(例としてE♭/Eなど)で語られてしまっているのは残念な所であり、それらの和音の実例がジャズ系統の譜例が載っているものの、それが西洋音楽からのどういう影響などという様な根拠などは一切語られておらず、単なる奇異な和音が突如登場するかのように語られてしまうのが非常に残念な所です。ペレアスとメリザンド、春の祭典など語られるべき西洋音楽などある筈なのに、そうした所にリスペクトの欠片も無いのは残念な所。
こうした本をジャズ/ポピュラー界隈しか知らない人間が手にした時、彼等の知識は誤謬を増して周囲に喧伝する事になってしまう訳です。ただでさえ体系を遵守せずに己の色を落としたがるジャズの連中が、浅薄な知識を基に己の解釈を喧伝するようなStrongly recommenderとしてそれこそネットなどをフル活用して宣おう物なら、ネット情報を過剰なほどに頼りにしてしまう人からすれば後々迷惑を被る事になりかねません。そういう危険性を孕んでいるからこそ私は西洋音楽の方からも、また己の勝手な解釈と思われぬ様に著書や論文を示す訳であります。
科学的な方面の追究となると、その時点の文明が思弁的考察を突き破れない事で時代を追う毎に信憑性が失われてしまったり改編が必要な研究というのはあります。併しそれが音楽の場合は心理学や脳神経内科など医療レベルが音楽界に波及する分野にて研究を追う毎に改編される側面はあろうかと思いますが、科学の追究で調性や協和性がまるっきり変わって了う様な事はありませんので、他の科学分野での変質をそのまま音楽界に投影してしまう事で、自身の知らない事であってもそれが「時代を重ねればどうせ信憑性に足りぬ物になるであろうから知る必要がない」と決め付けてしまって、何時の時代にも変わる事が無いであろう普遍的な始原性の部分だけを音楽に見出してしまうのは良くない傾向であります。己の音楽感覚が熟達しないからといって高次な和声を相容れないのは早計であると言わざるを得ません。
そういう事を肝に銘じた上で、機能和声、導音、導音欲求、オルタレーション、弱進行、半音階的全音階の曲想、13度の和音、旋法和声とやらを今一度それぞれ知る必要があると思います。自身の音楽的熟達度が甘い人ほど、それら総てを機能和声のテーブルに乗っけてしまい、その尺度で推し量ろうとするのです。そこをまず矯正すべきでしょう。
再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら
最後に、今回作ったデモのコード進行は次の様になります。
B△7(on C♯) -> G♭△9 -> Fm△9 -> E△7(9、♯11) -> Dm7/E♭m = E♭m△7(9、♯11、13)
これらの和音は2度ベースによるメジャー7thから始まります。前にも語った様に、2度ベースというのは下声部に存在した筈の第3&5音を省略する事でも得られる音脈であります。無い音を類推するのではなく、上声部と下声部との分離感という複調性を伴う響きを感じ取る事が重要でありますし、今度は九の和音を連結させて増11度のメジャー9thへ進行する。マイナー・メジャー9thコードの経過を除けばどれもが能く使われるタイプのコードではあります。そうして最後には所謂マイナーのペレアスとも言えるポリ・コードとなる訳です。
能く見掛ける和音、或いはあまり見掛けない和音、それは各自の音楽嗜好度に依って全く異なる物ですが、自身の和声的熟達度はどうあれ、こうした響きを目の当たりにする場合、自身の感覚が熟達度に甘かろうともこうした響きを一旦耳にしたら忘れない様に焼き付ける事が出来る or 出来ないかで和声感という物は変わる物です。換言すれば自身の好き嫌いに依って感覚的に受け入れ易い響きは記憶するに容易く、嫌いな音は記憶するに及ばない様な感覚では和声的感覚は身に付かないという事を述べたいのです。
たとえ自身にとって嫌いな響きであろうとも、取りこぼす事なく響きを体得する。そんな嫌いな響きであろうとも記憶が手繰り寄せて和音構成、或いはヴォイシングまで再現させてこそ和声的な熟達を高める物なのです。すなわち、好き嫌いだけで音楽を選択しているだけでは能力が研ぎ澄まされる訳ではなく、得意の音ばかり見付けてしまう事になります。その得意であった音を、本来は機能和声的感覚から見てしまう事を避けなくてはならない響きに対して機能和声的尺度で見てしまう悪癖を伴わせる事を意味します。
ですから、ドミナント7thコードにおけるオルタード・テンションがふんだんに使われているかの様に和音を捉えてしまう悪癖だとか、Cm△7(9、11)というコードの中にG7を見付けてしまい本来のCm△7(9、11)というコードの在るべき姿を捉え切れないという陥穽に陥る危険性を述べてきた訳です。特に、トニック・マイナー上で導音という働きをしない第7音(=メジャー7th)に対して、強固に下行五度進行をしてしまおうとするG7が持つトライトーンの限定進行音ばかりが脳裡に蔓延ってしまっている様な感覚では実際にCm△7(9、11)を吟味しきれていない事を同時に意味する物なのです。
処が和音構成の体系というシステマティックな側面からはその和音の成立状況は理解してはいる。響きを体得していないのに思弁では如何様にも語れてしまう。こういう所にコード表記が齎すワナという物があるのです。見慣れない和音ならば目の当たりにしている和音ですら受け入れようとしない者すら居るのですから。
今回のデモはシンセとローズを使っている為、自身のイメージする音楽観に於てマッチしないアンサンブルの音の場合、それだけで毛嫌いする人もいる訳です。歪んだギターの音でなければ受け入れようとしない人だったり、或いはフィルターやレゾナンスがギンギンに掛かった音ではないと駄目だったり、シンフォニックな音だったりすると途端に駄目だったりなど。
処が自身の興味をくすぐってくれる類の、視覚から入るジャンルとの融合によって奏された音楽のアンサンブルがどうであろうと今度はそれを受け入れて了う者も居る訳です。アニメやゲームの場合特に顕著だと思います。聴覚とは異なる感覚が下支えとなっていないと補強されないタイプ。これだと聴き馴れた音楽には興味を示しても、first sight 且つ聴覚だけで音楽を判断せざるを得ない時には非常に不利に左右される訳です。音楽的な熟達に甘い人であろうとも自身の感覚こそが絶対的な基準である為、これを妄信してしまい判断を誤ってしまう罠に陥っている様では、和声的な世界観をどれほど追究しても徒労に終ってしまう事でありましょう。そういう罠には気を付けて和音とやらをきちんと捉える事が肝要と思う事頻りです。
扨て、マイナー・コード上の11度音の取扱と雖も色々な用例があると前述しましたが、それではまず一般的な本位11度音が存在する状況を例に挙げてみる事にしましょう。
一般的な例としては本位11度音が存在する状況では長九度音も存在する事がコード・ネーム上では不文律となる場合があります。ルート(=根音)をC音とした場合、「Cm11」と表記する時の不文律すなわち暗黙の了解となっているのは、包含する9度音は長九度という事ですね。長九度が決して短九度ではないのは、基底となるマイナー・トライアドの響きを短九度が疏外してしまう=アヴォイド・ノートとなる例を排他的に扱う表記であるが故の表記である訳です。
実際にはテンション・ノートを括弧で括った表記として「Cm7(9、11)」という様な表記を見る事の方が多いでしょう。因みに、コードの名称として「マイナー・イレヴンス」と称する時は、「マイナー・トライアド+短7度+長9度+完全11度」という構造の事を指しているのも不文律として知られる点でありましょう。
突き詰めると、マイナー・イレヴンス・コードの7度音が長7度としての和音も存在しますが、これについては特に名称がある訳ではありません。これはこれで特殊であり独得の情緒を齎して呉れる和音ですが、先ずはマイナー・イレヴンス・コードについて語って行く事にします。
私の個人的な主観でCm11というコードを耳にした時、特に11th音が主題で奏されている時というのは、まるでファッション・モデルが脇目もふれずに歩く様な周囲の観衆にも一瞥も呉れないままに膝を入れてランウェイを歩く、あの猛々しい程の状況が浮かび上がる様な、そうした勇猛さがあるのがマイナー・イレヴンス・コードの響きであると私は感じております。
これが単にCm9という状況だったら、横目で一瞥を呉れるかの様な横顔を見せる様な響きがあるのがマイナー・ナインス・コードの響きの様に私は感じているのですが、マイナー・イレヴンス・コードの猛々しさは鏡越しに見る映像の中をも凝視するかの様に、それこそ車のバック・ミラーを隈無く凝視する様でもあるかの様にも響くかもしれません。孰れにしても、直射日光を浴びている訳でもないのに、回折だけで充分明るさを得てしまうかの様な強い存在感を感じつつ、直視する事が不要な程重量感を伴うと言いますか、そういう感じを形容するかのように思えるコードなのです。
マイナー・イレヴンス・コードの響きを存分に感じ取る事の出来る典型的な用例となる曲は、最右翼として私はチャカ・カーンの『I'm Every Woman』を挙げます。マイナー・イレヴンス・コードというのは、それをトニックとして奏してもテンション・ノートが下属音である訳で、「明後日を向いた」様な響きである為、ワン・コードとしても成立しやすい状況であるので、コード進行が希薄である事も許容されるのは和音が6声と重畳しい為であるのは明白です。ですからそこで卑近と思える程のドミナントへの進行など不要になる位、2コードでも充分な程という風にも演出可能となる訳です。
他にもダリル・ホール&ジョン・オーツ「I Can't Go For That (No Can Do)」もそうですし、山下達郎の「メリー・ゴーラウンド」も好例として挙げる事が出来るでしょう。
これらの用例とは別に、マイナー7thコードを基底和音として持ち、それに本位11度音が附与されるタイプの「マイナー7th(11)」という和音もジャズ/ポピュラー体系では能く見受けられる物でもあります。これは実際は「四度和音」を表している物であります。
仮に「Cm7(11)」というコードがあった場合、g音から上方に完全四度を累積して行くと「G・C・F・B♭・E♭」という風に五声が積み上がる事となり、この基底音をg音からc音に変えた物という風に見做す事が出来る訳です。ハービー・ハンコックの「処女航海」もジャズ的表記ならばコードネーム表記の流儀に沿う物として表記せざるを得ないでしょうが、あれは四度和音であります。
四度和音で他にも有名なポピュラー音楽では坂本龍一の「千のナイフ」のイントロが四声の完全四度等音程による四度和音であります。
これらの四度和音の用例で顕著なのは、機能和声的な和音進行とは全く異なる旋法和声の在り方を示しているのであります。構成音そのものは某かの調性内に収まっているとしても、行き先となる後続の和音への音脈を辿るそれは調性のレールを踏もうとはしない自由度の高い音脈を醸し出そうとする物です。ある意味ではマイナー・イレヴンス・コードから9th音を省くだけで、そうした茫洋とした自由な動きが強化されるというのも興味深い点でありましょう。
扨て、マイナー・トライアドを基底に持つタイプで11度音を擁する物は必ずしも7度音が短七度とは限りません。長七度のタイプも使用例は少なくなって来ますが存在しうる物であるので、コード表記としてあまり見掛けないからと及び腰になる必要は無いのです。
マイナー・メジャー9thコードを包含するタイプの11度音を擁する物は通常、本位11度を使うとなるとその時点でトライトーンを包含するので響かせ方としては難しい物になりがちです。仮にCmM7(9、11)という和音があった場合、CmとG7を包含している状態ですが、これらをその様に響かせるだけでは卑近な迄の機能和声に準じた響きしか導出出来ない事になります。そこをもう少し工夫して、E♭M7augやE♭M9augとしての響きを演出しつつ、E♭音から下方3度にある音脈としてリラティヴにC音を下に付与する様な形でフレージングしたりするだけでも全く様相は変わります。つまり、C音側のリフの演出次第で、カタチとしては一見ドミナント7thコードを包含する、つまりトリトヌスを有している様な状況でも下方五度進行を感じさせるフレージングをしない様な響きを演出する事が重要、という事を意味する述べ方なのであります。
それを鑑みれば、チック・コリアが「Flamingo」にて「Ⅰm7→♭Ⅵ7/Ⅳ」というツーコード循環をする理由が判るかと思います。「Flamingo」の原曲キーはDmですから「Dm7→B♭7/G」となる訳ですが、この後続和音の「B♭7/G」を同軸で見ればGm7に短九度を付与してしまう(短九度はマイナー・コード上ではアヴォイド)と見做せるのですが、そういう解釈ではないからこそ実際にこうした使用例がある訳です。アヴォイドという解釈も機能和声のそれに従順である事に加えて、垂直レベルでダイアトニックな和音の響きを疏外させない為の用法なのですから、非機能和声の尺度やモードの世界観にてアヴォイド・ノートを持って来ても却って無駄な見立てなんですね。

例えばジェフ・ベックのアルバム『Wired』収録の「Play With Me」のBパターンでは「Dm7→Dm7 (on G)」の2コード・パターンが繰返されますが、後続和音のツー・オン・ファイヴのコードに機能和声的な響きを想定してしまってその後のコードとしてCに進んでしまう様な響きを演出してしまったら、それまでの一連の進行で直視していなかった筈の、折角の調性感の「暈滃」が台無しになってしまう訳ですね。
アヴォイド・ノートの定義をトリトヌスの包含とだけで判断してしまうと、所謂メロディック・マイナー・モードの音組織にアヴォイド・ノートが無いという所への誤解を生じてしまう陥穽がある訳ですが、この音組織を音階として「横の線」として見るのではなく、和声的に「縦の線」として見ると、メロディック・マイナー・モード上で生ずる和音のⅠ・Ⅳ・Ⅴ度上の和音はトニックとなるトライアドが「Ⅰm」となる意外は「Ⅳ△」「Ⅴ△」という風に、短調としての風合いが和声的には希薄になるという所から、調性感は二元的ではなく雌雄関係の様な両極性も希薄となり、世界観が混淆とする両性具有的な物になっているという事が確認出来ます。これはつまり、主音・下属音・属音という音が中心音となっているだけの状態で、この骨格に和声的には長調・短調の両性具有化が起きている状況と見做す事ができます。そしてⅤ度の和音の時導音欲求が生まれ、上行形の導音としてⅤ度上の和音の第3音が機能し、下行導音としてⅤ度上の第7音は半音下行ではない順次下行進行として機能するのです。
短調に於て、Ⅴ度上の和音の第7音の下行導音がⅠmに解決する際半音の導音ではないとはどういう事か!? という疑問を抱く人がいるかと思います。
短調とは本来終止和音はピカルディ終止であった為Ⅰ△で終るべき物だったのであります。そうすれば属和音にのみ七度音を附与する事を許された属七の第7音は下行導音が半音滑り落ちて解決する訳です。短調とてもっと古い時代ではドリア調が実際には短調であった訳です。そしてⅤ→Ⅰの時に導音欲求または導音傾向という仕組みで導音の変化を起していたのです。ですからジャズ界隈でのドリアン・モードというモードの仕来りと、西洋音楽でのドリア調という取扱はⅤ度上の和音を変化させる西洋音楽のそれとは全く異なる体系であるという事が判ります。
そうした、短調が同主調の主和音で終止するという流れから、旋法的変化を維持する動きが多様に見られる様になり、短調はエオリア調も生む様になった訳です。
— 左近治 (@sakonosamu) 2017年2月26日
現今社会でジャズ/ポピュラー音楽界隈の人が、短調の音楽を奏するにあたってⅤ7→Ⅰmの際、属七の第7音が後続和音に半音の勾配を作っていない事に歎息する人がどれほど居るでしょうか!?(笑) おそらくそんな事など気にせず相容れているのが当然の事として理解されている事でしょう。私とて通常の俗化された耳としてそれを許容する物です。
こういう「許容」が、短調の世界の多様な変化を生んで来た証でもある訳です。一方ではピカルディ終止を許容し、旋法的には短調の音組織を維持し乍ら和声的に他の箇所で置き換えが進むという体系が生じた訳ですね。例えば短調という短旋法を「ラシドレミファソラ」と見た場合、「ド」を旋法的に唄わせる事を維持させれば良いのです。ピカルディ終止の終止和音の時、和声的には「ド♯」として変化している訳ですが、主旋律が「ド♯」を唄わず伴奏に隠す。そうする事で他の短調への和音に進む際、主旋律は短旋法を維持できる訳ですね。こういう「ひた隠し」は、基の旋法的な流れを重視しただけの事であって、必ずしも伴奏に隠せという事を意味する物ではありません。
とはいえ、こうした例が多数生ずるのが短調の世界であった訳ですから、旋法的にも和声的も多様な世界観が生じた歴史はこういう事に依拠する物であって、結果的にメロディック・マイナー・モードの第Ⅰ・Ⅳ・Ⅴ度の和音に於て、トニック・マイナーのみがマイナー・コードであるという短調の音組織の和音と同主長調の音組織の和音が混淆とする様な音組織が生ずる様になったのは、こうした多様性の果てに見られる事だからです。リムスキー=コルサコフ著『和声法要義』を読めばこうした点は端的に説明され腑に落ちる事でしょう。
「導音」というのは一般的に、上行形に於て主音または到達音に対して「半音程」だと思われている方が居られると思いますが、導音が齎す作用を広く俯瞰すると必ずしも半音ではないのが導音の働きです。これはとても重要な理解なのです。
導音というのは「到達音」に対して強く作用する物です。それが半音でない場合、旋律における中心音として存在感を生じている音が到達音として存在する場合、これが《導音よりも音価が長く》更に《強勢に生じていれば》それが全音であったとしても「導音」という機能を持つのが真の導音の理解なのです。
その導音が到達音に対して全音階的ではない即ちノン・ダイアトニックの方面に半音で導音が生じた時は、それまでの調性が持っていた調的余薫とは全く別の欲求が生じて半音階的変化がこれにて生まれる訳で、和声的には多様性を増す局面である訳です。
一般的な例を挙げるとⅤ7→Ⅰ△での属七の、上と下からも導音でガッチリと万力で締め上げるかの様な情緒と「Ⅴ7 ->Ⅰm」でのⅤ7の第7音の進行を比較すれば、後者のそれは進行的には「弱い」牽引力でもあると言える訳です(何故なら全音の勾配)。これに弱さなどを感じていない人が殆どではないでしょうか。「弱い」と感じる事が正当でもありませんが(笑)。この「弱い」というのは全音の導音を意味します。
また導音は上行形ばかりではありません。フリギア終止にも代表される様に下行導音もあります。その下行導音とて常に半音でなくてはならないというルールなどありません。偶々属七の和音がトニック・メジャーに解決する際はトリトヌスが上からも下からも半音の勾配を作る為に先述の様に万力で締め上げると評したそれが生ずる訳ですが、属七からトニック・マイナーの場合の下行導音は全音の下行導音な訳です。
この全音の導音という私の説明に疑念を抱く方が居られるならば、下総皖一著『標準和声学』(音楽之友社刊)のp192を読めば深く首肯出来る事でありましょう。
また同時に短調の和音進行に於てはV7からⅥに進む事も少なくありません。このⅥ度上の和音というのは短調では多様な変化をする物でもあるので、こういう点にも注意を払うと良いかと思います。
扨て、YMOのアルバム『ソリッド・ステイト・サヴァイヴァー』収録の同名曲「Solid State Survivor」(高橋幸宏作曲)の冒頭は、実際ならばマイナー・コードに11度音が附与された和音とマイナー・トライアドとのコントラストを生ずる様な進行であるのでしょうが、「Dsus4 -> Dm ×2 →E♭sus4 -> E♭m ×2...」状況でもあるでしょう。併し実際には「Dsus4」と表記したのは便宜的であり、ベース・ラインがマイナー3rd音を強く主張する為「Dm(11)」というマイナー・トライアド+付加4度という解釈にすべき物でありますが、この4度音が後続である同度のマイナー・トライアドとの「全音音程」の勾配を作るのが興味深い所であります。これは全音音程に依る下行導音的活用です。個人的な意見ですがYMOの作品の中で私が最も好きな曲はこの曲であります。ロックとブルースの多様性がとてもシンプルに鏤められて居ります。こうしたシンプルに響くマイナー・コード上の本位11度音のさり気なさという所にも注目して欲しいと思わんばかり。
扨て、今回はマイナー・コード上の11th音を取扱っているので、メジャー・コード上での11度音の取扱は省く事になります。とはいえ本来11度音への和音重畳の由来というのは上方倍音列として存在する音脈を利用している物なので、そうした前提を考慮すると、長和音上で生ずる11度音が本位11度ではなく(こちらはアヴォイド)、増11度音を積み上げるのは合点の行く所であります。
とはいえ11度音の存在は9度音無しでは表れなかったのもあり、そうした適用が属和音以外の副和音にも適用され、調性を維持する音組織つまりモード・スケール内のダイアトニック・コードとして3度音程を累積させた物を適用したコードを利用する事になり、それがダイアトニック・コードとしてマイナー・コードを本体とする和音の11度音の場合、ダイアトニックを維持する為に本位11度音として存在を為しているのは言うに及ばずという点は充分に理解して貰い度い点であります。
それならば、短和音上の本位11度音は上方倍音列の由来とは意を異にする和音の解釈ではなかろうか!? という事まで考えが及べば宜しいのです。抑もマイナー・イレヴンス・コードとはトニック・マイナー上ではなく上主音、つまり長調のⅡ度上から全音階的に3度を累積していった所から端を発しております。
3度を全音階的に累積した状態で11度音まで積み上げれば、それがⅡ度上の和音かどうかは無関係に、本来ならば複調的解釈を伴う物です。更に複調的解釈が高まるシーンというのは、和音の第3&5音が省略される場合です。こういう時に現今持て囃されるタイプの2度ベース、喩えるならば「C△/D」が出来上る訳です。第3&5音が省略されないDm11の型とて西洋音楽方面ですら旧くからⅡ度上の和音として愛用されていた訳ですから。
両者を鑑みればDm11という6声をフル活用するそれはDmの上にC△があるアッパー・ストラクチャー・トライアドという捉え方に依る和音という風に見立てる事もできます。アッパー・ストラクチャー・トライアドというのは結果的に3度累積を連ねている状況で基底和音の上方に別のトライアドを形成する事で、結果的にトップノートから根音まで省かれる3度音程が無く「3度の類推」を可能とする物である為、省略しない限りは重々しい響きになる訳です。
それらの和音の現実を考慮した上で別のケースに目を向けてみると例えば、マイナー・コードを基底和音とした時に長7度及び増11度音が積まれて行くという類の和音をアーサー・イーグルフィールド・ハル著『近代和聲の説明と應用(近代和声の説明と応用/近代和声学の説明と応用)』で見付ける事が出来る訳ですが、著書のタイトル通り、その近代和聲とやらが上梓100年を経過しても猶その響きが新奇性を持っているという所に驚きを禁じ得ないと言いますか、音楽の世界の響きに対する一般の人々の受容というのは実に保守的であるという所もあらためてお判りになるかと思います。
無論、ハルの例示する短和音上にある増十一度の包含というのは第一次大戦の後にフランク・ブリッジの作品でも見つける事ができる様に、属調から手繰り寄せた更なる属調および六度調をも複調的に呼び込む事で得られる状況がポリコードと成しているのは言うまでもなく、そうした音脈となる経路を辿っているのは明白な事でありましょう。
長七度音を擁する短和音を母体として本位11度音はそこに長九度音も附与される事が通例なのですが、マイナー・トライアドを基底和音とし乍らアッパー・ストラクチャーにドミナント7thコードを包含してしまうのが用法としては難しい所ですが、Cm△7(9、11)とやれば、Cmに対してG7を包含してしまうという訳です。とはいえこれまでもドミナント7thコードの多義的解釈やら弱進行をやって来ていると思うので、このG7が後続和音に対してあざとい程に下方五度進行を醸す様な進行を回避すれば、こうした状況があっても良いのです。それが機能和声的な状況を生まなければそれも是とすべき物なのです。
つまり、そうした例外を理解すれば、マイナー・コードの上にどんどん3度音程を積み上げて13th音を導出する事がどういう事か!? という事もお判りになるでしょう。すなわち、マイナーコードに13度音まで積み上げればダイアトニック・トータルとなってしまいますが、モード的なアプローチ或いは機能和声的進行を回避する状況であるならば11th音を回避して使う、例えばDm7(9、13)として使うとか、そういう事をこれまで語って来ている意味があらためてお判りいただけるかと思います。*
余談ですが、13th音というのはマイナー・メジャー7thを擁する時はアヴォイドではありません。11度音をオミットした上でチック・コリアはジョン・パティトゥッチの1stソロ・アルバム収録「Baja Bajo」にて「Cm△7(9)」上で、シンセ・リード音の13th音を附与したアプローチを聴く事ができます。

B♭m△9の響きが最も効果的に表れているのはCDタイム1:14〜の箇所なのですが、B♭m△9 -> B♭m7という風に、長七度→短七度という風にクリシェ下行しかも主音から長七度へのクリシェというのは全く用いずに、強い酸味を伴った短和音の様にマイナー・メジャー7thの響きを強調するのであります。その酸味を尻目に見るかの様に長九度音が附与されてB♭m△9というサウンドをあらためて強調しているのでありますね。絶妙です。
B♭m△9というコードを目の当たりにしてしまうと、広く知られている楽曲が他にあります。ジェフ・ベックのアルバム『ブロウ・バイ・ブロウ』収録のバーニー・ホランド作曲の「Diamond Dust」がそうです。もっと広く目を遣ればTBSドラマのキイハンターの終止和音やらザ・ピーナッツの「恋のバカンス」などでも短和音+長七+長九のタイプの終止和音というのは珍しくもありませんが、終止和音でもなく、長七度という音階固有音が主音と半音程であり乍ら導音とならない使い方という方に目を向ける事が、和音の高次な側面を見出す最も重要な点である事を忘れてはなりません。通常ならば導音→主音という半音の勾配とやらを、スパイロ・ジャイラの「Incognito」のコード進行は逆進する訳です。
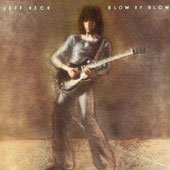
こうした「逆進」という例は、和声を高次に活用する為にとても必要な前提でもありまして、例えば和音が上方に重畳しく構成されて行く様は確かに上方倍音列の高次に聳える音を頼りに導出する音空間であります。それは一体何を意味しているのか!? と言いますと、和音が他の和音と連結・進行して和声を生じます。1つの和音の構成音が高次に重畳しく聳えさせようとも、その連結が下方五度進行にある様な余りに卑近な進行であるならば、和音はよほど主音と遠い音程関係にある音を奏でていない限り、高次な和音を使う意味もなくなってしまうものでもあります。主旋律も卑近、和音進行も卑近なのに単に伴奏で奏される和音だけが重畳しいのであれば響きのバランスを欠いてしまい却ってメロディの卑近さが露になり、伴奏からの音脈を主旋律に変更する必要が出て来る程おかしな響きとなりかねません。
極言すれば、重畳しい和音を用いて和音進行する際、卑近な和音進行ではなくそれまでの機能和声の世界では見掛けなかった遠隔的な音程に進行するという弱進行や一時転調や偽終止に分類される様な世界観の追究が始まった訳であり、これに貢献をしたのは熟成された音律に外ならない訳です。
ですから、機能和声の持つ強力な世界観だけに裏打ちされた真理とやらをこっぴどく学ぶ事も大事ですが、その後の和声感の熟達を高めるには、調性が希薄に感じられて了う様な音世界の響きを体得する事がとても重要になる訳です。そういう意味でも先日、島岡版舊・藝大和声から林達也著『新しい和声』へシフトした際、保守的な立場に固守する様な人であればあるほど舊島岡版のそれを是とするような嫌いがあり、Amazonレビューを見ても言わずもがな、と言った所でしょう。私がこれほど迄に、機能和声的枠組みとは意を異にする和音進行を取上げつつ、弱進行やドミナント7thコードの多義性、ブルース/ジャズの出自、戸田邦雄に依る洗足論叢で語られる島岡版の藝大和声では是とされないⅤ→Ⅳ進行の論文をレコメンドしていたのはこうした意図があっての事だったからであります。
先のマイナー・メジャー7thコードにしても、音階固有音としては導音であろうとも、和声的に用いる時にそれが必ずしも導音にならない時もあり、一般的「導音」とやらは到達音に対して「半音」である理解であれば大抵は事足りる理解ではありますが、導音は須く半音であるのではなく、全音の場合もあると述べてきたそれらの違いをきちんと理解した上で音楽の響きを体得しなくてはいけないのです。
マイナー・メジャー7thコードの第7音を導音として使わないのであれば、マイナー・メジャー7th+長九度+完全11度(本位11度)を附与した時、この和音のルートをC音と見立てるならばCm△7(9、11)の構成音には確かにG7を包含してしまうものの、B音(独名:H)を導音としないのであれば、包含されるG7というコードは見かけ上ドミナント7thコードであるだけであってG7から明確に下方五度進行を行おうとしてG7に更に包含されているトリトヌスが限定進行しようとするそれとは全く別の体系の物だという事を理解しなくてはいけないのです。
処が和声学の原理主義の部分ばかりに拘泥してしまうと、こうした例を是としないばかりか、思弁で原理的な世界観を考えているだけなので、実際の響きの体得の前に「悪しき例」として断罪してしまう嫌いがある物なのです。ですから、保守的な耳、特に和声の熟達に甘い耳を持つ人ほどCm△7(9、11)という和音に、己の拙劣な和声感覚のそれがG7という姿の方を強く響く様に感覚が働いてしまうという物でもあるのです。これが是正されぬまま、新たな和声的な世界観を語れる訳もありません。
ですから、マイナー・コード上に於て13th音というのは確かに機能和声的社会の尺度から見ればアヴォイド・ノートの扱いであるのはそれはそれで間違いではありませんが、非機能的和声進行であるならばそれは問題ありませんし、どうしても包含されてしまう属七の体を稀釈化する上でもマイナー・コードで13th音を使うならば5度音よりも11th音をオミットした方が良いのであり、且つそのコードから後続和音が下方五度進行しない様な状況やモードの世界であれば臆する事なく使える和音なのであります。
例えばダイアトニック・トータルとなる全音階の総合=総和音を例に取れば、Ⅳ若しくはⅡをルートとする和音は機能和声の世界でも最も柔和に響いてくれるからであり、それはサブドミナント機能を持つ和音が後続へ進行しないという力が働いている状況と見做し得る物で、且つワン・コード的に聳える事が出来る様に響くからでありましょう。
スパイロ・ジャイラ「Incognito」の大半は、先の当該部分のコード進行を次の様に
B♭m△9 -> B♭m7 -> E♭7 (on B♭) -> G♭△9 (on B♭) -> B♭m11
奏しておりますが、CDタイム2:04〜の部分ではE♭7 (on B♭)というコードをE♭音を基底とする和音に変えた上でマイナー7thコードに対して増11度音が附与されるタイプ畢竟するに「B♭m7(9、♯11)」という風に、マイナー・トライアド+短7度+長9度+増11度という風に11度音をオルタレーションさせたアーサー・イーグルフィールド・ハル流の和音を忍ばせているのも特長でありましょう。こういう所を聴き逃してはいけません。
「B♭m7(9、♯11)」というコードはポリ・コードという風にして見ると、下にB♭mトライアド、上にA♭augトライアド(増三和音)が生じているという事になります。
これらを鑑みると「Incognito」ではB♭マイナーに於ける第7音と第4音を如何にオルタレーションさせて変化を付けているかという工夫が見られる所に着目しなくてはなりません。短調にて単にブルー5度としてではなくオルタレーションされた音と元の5度音を和声的に同居させるという事は、同度由来としてではなく異度由来として和声的に発展させるという見方で分析する必要があります。
ご存知の様に短調の曲というのは第7音は猫の目の様に変化させる事も少なくありませんし、それこそブルー五度とは異なるジプシー由来の音なども入って来たり、時には2度が下行形でフリギア終止の為に変化したりする事など珍しくありません。こうした短調の曲想にて、それらの変化が齎す和声感の余薫を旋法的にも和声的にも一即多多即一として採り入れた顕著なジャズ・マンの一人に私はディジー・ガレスピーを挙げます。その次にバド・パウエル。例えるならば伴奏としての和音はマイナー7thコードであるのに、その上のインプロヴァイズはメロディック・マイナーを奏していたりとか、そうしたスーパー・インポーズが見られる様になったのをジャズ界隈で見付けるならば私は真っ先にディジー・ガレスピーの名を挙げたという訳です。
スーパー・インポーズ系の音脈の表し方というのは実際にはパーシケッティ及び水野久一郎訳に依る「投影法」にて分析する必要があるでしょう。これは私も再三ブログで述べて来ているのであらためて語りはしませんが、投影法を根拠にそうした音脈を引っ張って来る根拠というのは結果的に下方倍音列を語らなくてはいけないのですが、これについては何れヴァンサン・ダンディの『作曲法講義』やディエニの『生きている和声』を参考にし乍らあらためて語る日もあるかと思います。とはいえそれに待ち切れない方は先の著書を手に取って学んでも良いのですし、私の述べている事など単なるヒントに過ぎない訳ですから、著書からきちんと本質を学ぶ事が肝要でありましょう。
そういう訳で、マイナー・メジャー7thコード上に増11度音が附与される和音もあらためて知った訳ですが、私が以前にGreensleevesをアレンジして用いた「Bm△7/C△」という和音も、私がローカルで云う所の「マイナーのペレアス」という物の発展形でもありますし、最近では顕著な例としてスタンリー・カウエルのアルバム『Juneteenth』にてやはり聴く事ができる物です。マーク・レヴィン著『The Jazz Theory Book』では、ペレアス和音という風にも語られてはおりませんし、Ⅶ△/Ⅰ△というポリ・コードの筈なのに同度由来(例としてE♭/Eなど)で語られてしまっているのは残念な所であり、それらの和音の実例がジャズ系統の譜例が載っているものの、それが西洋音楽からのどういう影響などという様な根拠などは一切語られておらず、単なる奇異な和音が突如登場するかのように語られてしまうのが非常に残念な所です。ペレアスとメリザンド、春の祭典など語られるべき西洋音楽などある筈なのに、そうした所にリスペクトの欠片も無いのは残念な所。
— 左近治 (@sakonosamu) 2016年12月29日
— 左近治 (@sakonosamu) 2016年12月16日
こうした本をジャズ/ポピュラー界隈しか知らない人間が手にした時、彼等の知識は誤謬を増して周囲に喧伝する事になってしまう訳です。ただでさえ体系を遵守せずに己の色を落としたがるジャズの連中が、浅薄な知識を基に己の解釈を喧伝するようなStrongly recommenderとしてそれこそネットなどをフル活用して宣おう物なら、ネット情報を過剰なほどに頼りにしてしまう人からすれば後々迷惑を被る事になりかねません。そういう危険性を孕んでいるからこそ私は西洋音楽の方からも、また己の勝手な解釈と思われぬ様に著書や論文を示す訳であります。
科学的な方面の追究となると、その時点の文明が思弁的考察を突き破れない事で時代を追う毎に信憑性が失われてしまったり改編が必要な研究というのはあります。併しそれが音楽の場合は心理学や脳神経内科など医療レベルが音楽界に波及する分野にて研究を追う毎に改編される側面はあろうかと思いますが、科学の追究で調性や協和性がまるっきり変わって了う様な事はありませんので、他の科学分野での変質をそのまま音楽界に投影してしまう事で、自身の知らない事であってもそれが「時代を重ねればどうせ信憑性に足りぬ物になるであろうから知る必要がない」と決め付けてしまって、何時の時代にも変わる事が無いであろう普遍的な始原性の部分だけを音楽に見出してしまうのは良くない傾向であります。己の音楽感覚が熟達しないからといって高次な和声を相容れないのは早計であると言わざるを得ません。
そういう事を肝に銘じた上で、機能和声、導音、導音欲求、オルタレーション、弱進行、半音階的全音階の曲想、13度の和音、旋法和声とやらを今一度それぞれ知る必要があると思います。自身の音楽的熟達度が甘い人ほど、それら総てを機能和声のテーブルに乗っけてしまい、その尺度で推し量ろうとするのです。そこをまず矯正すべきでしょう。
再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら
最後に、今回作ったデモのコード進行は次の様になります。
B△7(on C♯) -> G♭△9 -> Fm△9 -> E△7(9、♯11) -> Dm7/E♭m = E♭m△7(9、♯11、13)
これらの和音は2度ベースによるメジャー7thから始まります。前にも語った様に、2度ベースというのは下声部に存在した筈の第3&5音を省略する事でも得られる音脈であります。無い音を類推するのではなく、上声部と下声部との分離感という複調性を伴う響きを感じ取る事が重要でありますし、今度は九の和音を連結させて増11度のメジャー9thへ進行する。マイナー・メジャー9thコードの経過を除けばどれもが能く使われるタイプのコードではあります。そうして最後には所謂マイナーのペレアスとも言えるポリ・コードとなる訳です。
能く見掛ける和音、或いはあまり見掛けない和音、それは各自の音楽嗜好度に依って全く異なる物ですが、自身の和声的熟達度はどうあれ、こうした響きを目の当たりにする場合、自身の感覚が熟達度に甘かろうともこうした響きを一旦耳にしたら忘れない様に焼き付ける事が出来る or 出来ないかで和声感という物は変わる物です。換言すれば自身の好き嫌いに依って感覚的に受け入れ易い響きは記憶するに容易く、嫌いな音は記憶するに及ばない様な感覚では和声的感覚は身に付かないという事を述べたいのです。
たとえ自身にとって嫌いな響きであろうとも、取りこぼす事なく響きを体得する。そんな嫌いな響きであろうとも記憶が手繰り寄せて和音構成、或いはヴォイシングまで再現させてこそ和声的な熟達を高める物なのです。すなわち、好き嫌いだけで音楽を選択しているだけでは能力が研ぎ澄まされる訳ではなく、得意の音ばかり見付けてしまう事になります。その得意であった音を、本来は機能和声的感覚から見てしまう事を避けなくてはならない響きに対して機能和声的尺度で見てしまう悪癖を伴わせる事を意味します。
ですから、ドミナント7thコードにおけるオルタード・テンションがふんだんに使われているかの様に和音を捉えてしまう悪癖だとか、Cm△7(9、11)というコードの中にG7を見付けてしまい本来のCm△7(9、11)というコードの在るべき姿を捉え切れないという陥穽に陥る危険性を述べてきた訳です。特に、トニック・マイナー上で導音という働きをしない第7音(=メジャー7th)に対して、強固に下行五度進行をしてしまおうとするG7が持つトライトーンの限定進行音ばかりが脳裡に蔓延ってしまっている様な感覚では実際にCm△7(9、11)を吟味しきれていない事を同時に意味する物なのです。
処が和音構成の体系というシステマティックな側面からはその和音の成立状況は理解してはいる。響きを体得していないのに思弁では如何様にも語れてしまう。こういう所にコード表記が齎すワナという物があるのです。見慣れない和音ならば目の当たりにしている和音ですら受け入れようとしない者すら居るのですから。
今回のデモはシンセとローズを使っている為、自身のイメージする音楽観に於てマッチしないアンサンブルの音の場合、それだけで毛嫌いする人もいる訳です。歪んだギターの音でなければ受け入れようとしない人だったり、或いはフィルターやレゾナンスがギンギンに掛かった音ではないと駄目だったり、シンフォニックな音だったりすると途端に駄目だったりなど。
処が自身の興味をくすぐってくれる類の、視覚から入るジャンルとの融合によって奏された音楽のアンサンブルがどうであろうと今度はそれを受け入れて了う者も居る訳です。アニメやゲームの場合特に顕著だと思います。聴覚とは異なる感覚が下支えとなっていないと補強されないタイプ。これだと聴き馴れた音楽には興味を示しても、first sight 且つ聴覚だけで音楽を判断せざるを得ない時には非常に不利に左右される訳です。音楽的な熟達に甘い人であろうとも自身の感覚こそが絶対的な基準である為、これを妄信してしまい判断を誤ってしまう罠に陥っている様では、和声的な世界観をどれほど追究しても徒労に終ってしまう事でありましょう。そういう罠には気を付けて和音とやらをきちんと捉える事が肝要と思う事頻りです。
2015-09-21 11:00




