ブルーノートを下支え [楽理]
先の続きとなりますが、「ミニマル」的な少ない音群・・・というクダリは覚えていただいていらっしゃるとは思いますが、先ずはこの言葉の意図を今一度語っておこうと思います。
基本的に、シンプルな音群でメロディを形成している類の楽曲というのは、それらの音群というのは得てしてペンタトニックやペンタトニックよりも少ない音群である事も珍しくありません。ところが2音程度だとその音群というのは「中心音」としての立ち居振る舞いが少々身じろぎしているかの様な感じで強固に据えている程とは呼べる感じでもありません。
例えば、ペンタトニック(=5音音階)という5音程度、またはペンタトニック・ユニット(ペンタトニックのスケール・トニックのrelativeにある音=長六度を回避した音)という4音程度から形成される楽音の状況にて、これらの音群が振る舞うのは「中心音」が持つ振る舞いです。
中心音とは、その音が主音として聴かれたり、または下属音・属音として聴かれたり、長短的な旋法性を示唆する三度音として現われたりする物であったりするのですが、オクターヴという立場から俯瞰してみると、4、5音位の音群というのは、概ね2組のテトラコルドで巧い事持ち合っている様に組織されるものです。5音の場合二組のテトラコルドを完全に分け合う事は出来ませんが、少なくとも一つのテトラコルドに偏るような分布がされないのも特徴の一つであります。
こうした音群に対して音価(歴時)を長く与えて遣ると、それが概ね主音の様に振る舞う事があります。これは言い換えれば、同じ音組織(おんそしき)で4、5音を操っていてなんとなく別の音にスケール・トニック的な要素を感じていたのに、そのスケール・トニック的な音以外の音に音価を長く与えてやったら、転調っぽいフィーリング起った!という風に思っていただいても構いませんが、つまり「ミニマル」的要素が齎す中心音の変化の振る舞いというのは得てして、こういう事を意味しているのだという風に理解していただきたいのであります。
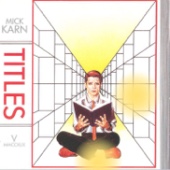 例えば、ベーシストのミック・カーンというのは、ペンタトニック的な音列を扱い乍らいつしか、その旋律がスケール・トニックを変化させて振る舞うかのような中心音をひとつの音だけに主音としての地位を与えずに調性感というちゃぶ台をひっくり返してしまうかのような朴訥な音楽観を備えている音楽家の一人であったと言えるでしょう。ややもするとこうした音楽観というのは幼い(いとけない)頃の己の姿をも思い起こさせるかの様な、非常に無学に思えてしまう事もあるかもしれませんが、こういう音楽観というのは通常、一般的な音楽の組織を習得していくと消失していく感覚なので、こうした感覚を残して音楽を嗜む事が出来るというのは私個人からすればこうしたシーンへの遭遇は羨望の一つでもあり、エリック・サティにもそういう感覚が宿っているのではないかと思う事しきりです。
例えば、ベーシストのミック・カーンというのは、ペンタトニック的な音列を扱い乍らいつしか、その旋律がスケール・トニックを変化させて振る舞うかのような中心音をひとつの音だけに主音としての地位を与えずに調性感というちゃぶ台をひっくり返してしまうかのような朴訥な音楽観を備えている音楽家の一人であったと言えるでしょう。ややもするとこうした音楽観というのは幼い(いとけない)頃の己の姿をも思い起こさせるかの様な、非常に無学に思えてしまう事もあるかもしれませんが、こういう音楽観というのは通常、一般的な音楽の組織を習得していくと消失していく感覚なので、こうした感覚を残して音楽を嗜む事が出来るというのは私個人からすればこうしたシーンへの遭遇は羨望の一つでもあり、エリック・サティにもそういう感覚が宿っているのではないかと思う事しきりです。
「Tribal Dawn」に於いては音使いは多様ですが、単一の旋法性が明確です。バルビエリの奇異なバックのハーモニー付けも単なるモーダルな世界からの抜萃という風になるのが功を奏しております。
「Weather the Windmill」に関して言えば、これこそ中心音をコロコロ変えて調性は中心音の行き当たりバッタリ感が非常に良く表現されている例です。
勿論ミニマル・ミュージックに関して言えば、その後のラ・モンテ・ヤング、フィリップ・グラス、スティーヴ・ライヒ等にも同様の事が言えるのでしょうが、つまり謂わんとする事はお判りいただけたと思いますが、一般的な音組織に耳慣らされた人がペンタトニックを耳にしても大抵はヘプタトニックの断片として聴いてしまって調性格を強固に映じてしまい、唐突な中心音の変化に伴う転調感を払拭してしまいがちであるのです。
ところが、奴隷として連れて来られた黒人達の中には、ヘプタトニックなどなんのその!(※茲で云うヘプタトニックは教会旋法に収まるドレミファソラシドに収まる体系の七音列)
長音階というのは前回にも述べていた様に「ファ──ド──ソ──レ──ラ──ミ──シ」という完全五度という協和音程の累積から生じる協和的な音組織である筈です。つまり、これほど共鳴的な音組織という網の目に、彼等黒人の楽音の感覚が補足されてもやむなしであるのに、彼等は協和的音程の重畳の脈を追って来ない。その都度生じる音に対して平行三度を維持できる感覚というのが素晴しいのでありますね。つまり「ファ──ド──ソ──レ──ラ──ミ──シ」という「幹音」以外の派生音を前後の振る舞いに強要される事なく振る舞えるのであった訳です。
とはいえ、それら「幹音」以外の派生音が12平均律の半音階にきっちりと収まる物ではなかったのも事実。それは微分音的な逸脱ですが、サージェントを筆頭とするそのジャズ独得の「ブルーノート(微分音的)」の出現のそれをイントネーションと呼んでおります。これは伊福部昭著の『管絃楽法』でも触れられているので参照されるのをお勧めします。
また、国内書物では湯川氏の訳では先の微分音的「訛り」=イントネーションに「調音」という言葉を充てております。この「調音」は、音響心理学方面である「音調」と似ているので混同せぬよう御願いしたい所です。茲で湯川新の名が出て来たので更に述べておきますが、彼が訳を手がけている法政大学出版局刊のりぶらりあシリーズで大変興味深いジャズ関連の名著のひとつであるガンサー・シューラー著『初期のジャズ』では、「ブルー5度」のそれが詳述されております。
つまるところ、ブルー3度という音は殆どのケースでブルー5度に依拠する(ハモる)形で現われ、他方ブルー七度も「和声的に」ブルー3度を五度音程の連関で支えており、ブルー五度が上方三度として支えているという指摘が素晴しいのであります。
つまり、それらブルー3・5・7度はブルー五度を中心に下方三度(=長三度下)で和声的に支える事となり、ブルー五度の上方三度(=短三度上)でブルー七度があり、それらが連関する事で和声的な支柱を得ているのだという事です。つまり、平行三度が齎したその後のジャズ独得の世界観の構築がこうして強められたという訳であります。
茲で気転が働く人は、ブルー七度とブルー五度の二声のハーモニーしか無い状況と、ブルー三度とブルー七度の二声のハーモニーしかない時の状況を想起した上で、これらの音楽社会観が成立した背景には結合差音が働いているという風に想起するには容易い事でありましょう。二声による差音は、実音が長三度音程を形成している時の差音は短三度(単音程転回)由来の音を生みますし、実音が短三度音程を形成している時の差音は長三度(単音程転回)由来の音を生む訳ですから当然と言えば当然です。
無論、黒人達が差音をどれほど意識していたかは重要ではなく、少し考えを及ばせればこうした下支えに依って補強されて居た事が判るでしょう。そうしたブルーノートが出来上って来ると共に、調的な社会は変格化が進み、調的な香りは長短の両性具有化が強まり、その上で半音階社会に均そうとすれば、和声空間は飽和に近しい状況を生みます。こうした「飽和」の状況では和声進行は静的になって行くので、和音そのものが重畳化していきその場の響きを形成し、重畳化した和声では後続の和音との機能和声的進行ではなく、平行の動機がより強く現われ、二度進行的な脈を向く様になる訳です。
例えばハ調域にて「F△/G△」というポリコードは、g音を根音とする属十一の和音(本位十一度型)と見る事も可能ですが、調性社会ではこれらはサブドミナントとドミナントであるのに、その進行は妨げられ垂直的に鎮座しているのであり、Gメジャー・トライアドの各構成音の夫々二度下に「房」を形成するかの様にしてF△が纏い付いて居るという事もお判りになるでありましょう。
調性社会に於けるハ調域にて「F→G」を循環させれば、トニックの訪れの無い、まるで曇り空の下で地面に影も作らないようなコントラストとも言えるかのような物とも言えるかもしれません。これぞ、モーダルであります。二度進行の循環がモーダルの雰囲気を強く醸し、一方で、その進行すらも拏攫して一つのコード(=ポリコード)として聴かせてもそこでモーダルな雰囲気が伴うのは、調性社会が持つ劇的(動的)な和声進行が無いからであります。
つまり、豊かな音空間というのは得てして調性社会の仕来りを備えつつも、その機能性が稀薄になり、その都度生じる和声の力が増すのであり、和音そのものの体に拘泥する様になる訳です。ただ、勿論ビバップの頃でも、機能和声が持っていた和声的な「力学」を利用していたのは間違いありませんが、この力学はチャーリー・パーカーが、和音進行が稀薄な状況でもそこにツーファイヴ的力学を、relativeな音方向に基底とする和音との共有をさせ乍ら仮想的に四度進行を想起する事で使った音脈なのですが、この体系がその後涸渇するとモード・ジャズが生まれ、動的進行はやはり下火となった訳です。
チャーリー・パーカーのその語法については、濱瀬元彦著の『チャーリー・パーカーの技法』を読めば直ぐに理解出来る事でしょう。また、同著以外にパーカーの語法を知る事の出来る著書は、音楽之友社刊エドワード・リー著『ジャズ入門』150〜151頁にて理解できるとは思いますが、その論述から濱瀬元彦の様に繙く事の出来る人間は極く僅かでありましょう。あの一文から濱瀬元彦の様に詳悉に論述可能とするには厖大な経験と知識が背景になければ先ず無理でありましょう。濱瀬元彦はそれをやってのけた(『ブルー・ノートと調性』の逆の手法なので或る意味では彼にとっては簡単だったかもしれない)訳ですね。
ジャズ(ブルース含)の起源での「音の訛り」=つまり湯川新の云う「調音」は、ジャズ方面でなくとも西洋音楽では起こり得るものでした。余談ですが、法政大学出版局刊ウィンスロップ・サージェント著『ジャズ ─熱い血の混血─』の邦訳も湯川新に依る物ですが、実は単なる邦訳だけではなく、新旧四版有るサージェントの原著を編纂して纏めているのが湯川新訳の秀逸な部分です。伊福部昭が『管絃楽法』でレコメンドしているのは原著の方であるのは疑いの無い事実でありましょう。伊福部昭の名前が出た所で加えて述べておきますが、先述の「差音」に於て同氏はS. S. Stevens, H. Davisの文献を引き合いに「29kHzと30kHz(どちらも可聴帯域外)の同時に鳴らしても1kHzの差音は生じない」というレコメンドをしておりまして、こうした差音の内容は現在刊行されている『完本 管絃楽法』でも同様ですが、現今社会に於てはこの可聴帯域外の差音の論述は誤りであります。
二つの音波どちらもが可聴帯域外であっても、それらのエネルギーが一定以上強い場合、差音を人間の耳が聴き取るのは既に研究報告されております。そのような研究は非線形音響の分野に括られ、国内では鎌倉友男に依る研究や関連書籍に詳しく、Googleでひとたび「鎌倉友男 非線形音響 差音」とでもググれば幾つかの論文PDFをダウンロードできるでしょう。確かこの手の可聴帯域外の非線形音響は近年、記憶が定かではありませんが、ギズモードジャパンかamassでも取り上げていた様に思います(2014年頃)。加えて、曲がりなりにも日本音響学会に於ても非線形音響の可聴帯域外の音波に依る結合差音認知の研究報告は幾多にも及びますので、差音に対して誤謬を正す必要があります。無論、伊福部昭著の『管絃楽法』は単なるオーケストレーションを超越した音楽周辺の凡ゆる智識の宝庫である為、重宝されている方も少なくはないでしょうが、古い本であるため、現今社会との間でズレが生じているにも拘らずこうした所を『完本 管絃楽法』でも修正されなかったのは残念な所です。次の版を待った方が宜しいかと思いますな。決して安くはない本なのですから、音楽之友社さんにも頑張って欲しい所ですな。
国内図書に於て「純正律半音階」に就いて非常に的確に論述されている著書は溝部國光著『正しい音階 音楽音響学』を筆頭に挙げる事ができますが、「純正律半音階」が生ずる、平均律とは異なる「半音」の音程幅という物をあらためて知る事ができるでしょうし、平均律社会ではエンハーモニック(異名同音)であっても、それは微分音的には全く異なる変化で、四分音的変化、または五分音的変化(この五分音についてはアロイス・ハーバが作品に残さなかったものの全音を5等分する物で、ブゾーニ流に考えれば既知の全音階組織では二種のホールトーン・スケールを生ずるので、全音を5等分する音律は2種の全音音階によって10分音に成るというのは推察に容易い)との類似性によって四分音に均されていくという微分音社会の背景を念頭に置くと、純正律半音階という音脈を疎かに出来ない事はあらためて実感する事でありましょう。ピアノしか奏する事の無い人は少し苦労するかもしれませんが。
ブルーノートが三分音、四分音、五分音、六分音、八分音、九分音・・・などの孰れかに該当していたのかどうかという所まで探るのは無益な労力でありましょう。しかし、ブルーノートというのは下方の音度に吸着していく特性があるとするのは実に腑に落ちる論述であり、先の、マイケル・ブレッカーが「I'm Sorry」にて短七度より1単位四分音高い音を長前打音風に奏してから短七度へ帰結するのは、重減八度から短七度へ結ぶと考えた方がより正しい解釈なのかもしれません。
また、協和音程である5度や3度よりも、7度を可動的変化で彩るのは調子っ外れな印象を与えないのも功を奏する点でありましょう。元々基音から七度周辺というのは不協和音程であるため違和感が少なく済むのでありましょうが、例えば、ジェフ・ベックのアルバム『Wired』収録の「Blue Wind」(邦題:「蒼き風」)での、6弦開放弦上のハーモニクスで自然七度音(あらゆる楽譜ではこの自然七度音はd音と記譜されております)が出て来ます。この六分音と考えて差し支えない音は、d音より1単位6分音低い(≒33セント)ものであります。
※自然七度と1単位六分音は2セント程の音程差がある物で完全な同一視はできないものですが、ほぼ同じ様に捉えて述べているので「六分音と考えて差し支えない音云々〜」として話題を進めております。但し、幾つかの純正音程を重ねて目的とする微分音を得ようとする場合、たった数セントの違いでもそれがその後大きな差異となってズレてしまう事もあるので、今回の様な単純に自然七度のそれと1単位六分音の単一音程同士の差が僅少だからといって他のケースに於て同様に無頓着になってしまわない様注意が必要です。幾つかの純正音程同士を重ね合わせて四分音や五分音を得るケースなどもあるからです。
ギターをチューニングした人であれば、33セントもずれた音は相当に大きく振れた音である筈ですが、それを自然七度として聴くと、そのズレ具合は不思議と大きなズレに聴こえないのが、七度周辺に存する音の成せる業でありましょう。人によっては、自然七度は本当に七度なのか!?と疑問を呈する人も居るのですが、これを七度としようと提唱した有名な音楽家のひとりにドビュッシーが居るのは有名な所です。
和声進行の「勾配」は、先行和音の根音を上音(倍音)に取り込む、という事は覚えておられるでしょう。「倍音」でも構わない訳ですから、平均律から外れた方への音脈に往来する事も可能ですし、微分音組織が根音である事も視野に入る様になるわけですが、少なくともジャズの現在はここまで微分音を使ってはおりません。然し乍ら「香り付け」という側面での微分音は、特にソロ奏者は使っていたりするのですが、聴き手が「イントネーションの一部」として看過してしまっている向きが非常に多いのも事実です。ただ、微分音的なイントネーションが特にブルー3度とブルー7度として強く現われた状況を次回はブルース・スケールやサージェントの論を引き合いにし乍ら語っていこうかと思います。
余談ではありますが、私が情報の出自を列挙するのは剽窃だと思われ度くは無いからであります。私のオリジナルな意見など音楽体系からしたら目に見えぬホコリ程度の物でしかありません(笑)。そうすれば胡散臭さも無くなる訳で、音楽を真摯に向き合う事で高次な音の獲得がスンナリと可能となる訳であります。その辺りを今一度念頭に置いてもらえれば助かります。
ということで、今度は中心音とテトラコルドとブルース・スケールという音階を中心に語る事になるので、なにゆえ中心音という事を語っていたのかという意図などを繙く事が可能となると思います。加えて、ブルース・スケールからパーシケッティにまで理解を及ばせるのは、サージェントも伊福部昭も濱瀬元彦もして来なかったと思うので、徐々に投影法への道に近付いているのでありまして、その辺りをきっちり踏まえて調性社会とは異なる仕来りを知っていただければと思うのであります(つづく)。
基本的に、シンプルな音群でメロディを形成している類の楽曲というのは、それらの音群というのは得てしてペンタトニックやペンタトニックよりも少ない音群である事も珍しくありません。ところが2音程度だとその音群というのは「中心音」としての立ち居振る舞いが少々身じろぎしているかの様な感じで強固に据えている程とは呼べる感じでもありません。
例えば、ペンタトニック(=5音音階)という5音程度、またはペンタトニック・ユニット(ペンタトニックのスケール・トニックのrelativeにある音=長六度を回避した音)という4音程度から形成される楽音の状況にて、これらの音群が振る舞うのは「中心音」が持つ振る舞いです。
中心音とは、その音が主音として聴かれたり、または下属音・属音として聴かれたり、長短的な旋法性を示唆する三度音として現われたりする物であったりするのですが、オクターヴという立場から俯瞰してみると、4、5音位の音群というのは、概ね2組のテトラコルドで巧い事持ち合っている様に組織されるものです。5音の場合二組のテトラコルドを完全に分け合う事は出来ませんが、少なくとも一つのテトラコルドに偏るような分布がされないのも特徴の一つであります。
こうした音群に対して音価(歴時)を長く与えて遣ると、それが概ね主音の様に振る舞う事があります。これは言い換えれば、同じ音組織(おんそしき)で4、5音を操っていてなんとなく別の音にスケール・トニック的な要素を感じていたのに、そのスケール・トニック的な音以外の音に音価を長く与えてやったら、転調っぽいフィーリング起った!という風に思っていただいても構いませんが、つまり「ミニマル」的要素が齎す中心音の変化の振る舞いというのは得てして、こういう事を意味しているのだという風に理解していただきたいのであります。
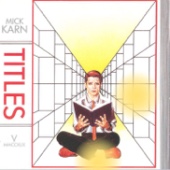
「Tribal Dawn」に於いては音使いは多様ですが、単一の旋法性が明確です。バルビエリの奇異なバックのハーモニー付けも単なるモーダルな世界からの抜萃という風になるのが功を奏しております。
「Weather the Windmill」に関して言えば、これこそ中心音をコロコロ変えて調性は中心音の行き当たりバッタリ感が非常に良く表現されている例です。
勿論ミニマル・ミュージックに関して言えば、その後のラ・モンテ・ヤング、フィリップ・グラス、スティーヴ・ライヒ等にも同様の事が言えるのでしょうが、つまり謂わんとする事はお判りいただけたと思いますが、一般的な音組織に耳慣らされた人がペンタトニックを耳にしても大抵はヘプタトニックの断片として聴いてしまって調性格を強固に映じてしまい、唐突な中心音の変化に伴う転調感を払拭してしまいがちであるのです。
ところが、奴隷として連れて来られた黒人達の中には、ヘプタトニックなどなんのその!(※茲で云うヘプタトニックは教会旋法に収まるドレミファソラシドに収まる体系の七音列)
長音階というのは前回にも述べていた様に「ファ──ド──ソ──レ──ラ──ミ──シ」という完全五度という協和音程の累積から生じる協和的な音組織である筈です。つまり、これほど共鳴的な音組織という網の目に、彼等黒人の楽音の感覚が補足されてもやむなしであるのに、彼等は協和的音程の重畳の脈を追って来ない。その都度生じる音に対して平行三度を維持できる感覚というのが素晴しいのでありますね。つまり「ファ──ド──ソ──レ──ラ──ミ──シ」という「幹音」以外の派生音を前後の振る舞いに強要される事なく振る舞えるのであった訳です。
とはいえ、それら「幹音」以外の派生音が12平均律の半音階にきっちりと収まる物ではなかったのも事実。それは微分音的な逸脱ですが、サージェントを筆頭とするそのジャズ独得の「ブルーノート(微分音的)」の出現のそれをイントネーションと呼んでおります。これは伊福部昭著の『管絃楽法』でも触れられているので参照されるのをお勧めします。
また、国内書物では湯川氏の訳では先の微分音的「訛り」=イントネーションに「調音」という言葉を充てております。この「調音」は、音響心理学方面である「音調」と似ているので混同せぬよう御願いしたい所です。茲で湯川新の名が出て来たので更に述べておきますが、彼が訳を手がけている法政大学出版局刊のりぶらりあシリーズで大変興味深いジャズ関連の名著のひとつであるガンサー・シューラー著『初期のジャズ』では、「ブルー5度」のそれが詳述されております。
つまるところ、ブルー3度という音は殆どのケースでブルー5度に依拠する(ハモる)形で現われ、他方ブルー七度も「和声的に」ブルー3度を五度音程の連関で支えており、ブルー五度が上方三度として支えているという指摘が素晴しいのであります。
つまり、それらブルー3・5・7度はブルー五度を中心に下方三度(=長三度下)で和声的に支える事となり、ブルー五度の上方三度(=短三度上)でブルー七度があり、それらが連関する事で和声的な支柱を得ているのだという事です。つまり、平行三度が齎したその後のジャズ独得の世界観の構築がこうして強められたという訳であります。
茲で気転が働く人は、ブルー七度とブルー五度の二声のハーモニーしか無い状況と、ブルー三度とブルー七度の二声のハーモニーしかない時の状況を想起した上で、これらの音楽社会観が成立した背景には結合差音が働いているという風に想起するには容易い事でありましょう。二声による差音は、実音が長三度音程を形成している時の差音は短三度(単音程転回)由来の音を生みますし、実音が短三度音程を形成している時の差音は長三度(単音程転回)由来の音を生む訳ですから当然と言えば当然です。
無論、黒人達が差音をどれほど意識していたかは重要ではなく、少し考えを及ばせればこうした下支えに依って補強されて居た事が判るでしょう。そうしたブルーノートが出来上って来ると共に、調的な社会は変格化が進み、調的な香りは長短の両性具有化が強まり、その上で半音階社会に均そうとすれば、和声空間は飽和に近しい状況を生みます。こうした「飽和」の状況では和声進行は静的になって行くので、和音そのものが重畳化していきその場の響きを形成し、重畳化した和声では後続の和音との機能和声的進行ではなく、平行の動機がより強く現われ、二度進行的な脈を向く様になる訳です。
例えばハ調域にて「F△/G△」というポリコードは、g音を根音とする属十一の和音(本位十一度型)と見る事も可能ですが、調性社会ではこれらはサブドミナントとドミナントであるのに、その進行は妨げられ垂直的に鎮座しているのであり、Gメジャー・トライアドの各構成音の夫々二度下に「房」を形成するかの様にしてF△が纏い付いて居るという事もお判りになるでありましょう。
調性社会に於けるハ調域にて「F→G」を循環させれば、トニックの訪れの無い、まるで曇り空の下で地面に影も作らないようなコントラストとも言えるかのような物とも言えるかもしれません。これぞ、モーダルであります。二度進行の循環がモーダルの雰囲気を強く醸し、一方で、その進行すらも拏攫して一つのコード(=ポリコード)として聴かせてもそこでモーダルな雰囲気が伴うのは、調性社会が持つ劇的(動的)な和声進行が無いからであります。
つまり、豊かな音空間というのは得てして調性社会の仕来りを備えつつも、その機能性が稀薄になり、その都度生じる和声の力が増すのであり、和音そのものの体に拘泥する様になる訳です。ただ、勿論ビバップの頃でも、機能和声が持っていた和声的な「力学」を利用していたのは間違いありませんが、この力学はチャーリー・パーカーが、和音進行が稀薄な状況でもそこにツーファイヴ的力学を、relativeな音方向に基底とする和音との共有をさせ乍ら仮想的に四度進行を想起する事で使った音脈なのですが、この体系がその後涸渇するとモード・ジャズが生まれ、動的進行はやはり下火となった訳です。
チャーリー・パーカーのその語法については、濱瀬元彦著の『チャーリー・パーカーの技法』を読めば直ぐに理解出来る事でしょう。また、同著以外にパーカーの語法を知る事の出来る著書は、音楽之友社刊エドワード・リー著『ジャズ入門』150〜151頁にて理解できるとは思いますが、その論述から濱瀬元彦の様に繙く事の出来る人間は極く僅かでありましょう。あの一文から濱瀬元彦の様に詳悉に論述可能とするには厖大な経験と知識が背景になければ先ず無理でありましょう。濱瀬元彦はそれをやってのけた(『ブルー・ノートと調性』の逆の手法なので或る意味では彼にとっては簡単だったかもしれない)訳ですね。
ジャズ(ブルース含)の起源での「音の訛り」=つまり湯川新の云う「調音」は、ジャズ方面でなくとも西洋音楽では起こり得るものでした。余談ですが、法政大学出版局刊ウィンスロップ・サージェント著『ジャズ ─熱い血の混血─』の邦訳も湯川新に依る物ですが、実は単なる邦訳だけではなく、新旧四版有るサージェントの原著を編纂して纏めているのが湯川新訳の秀逸な部分です。伊福部昭が『管絃楽法』でレコメンドしているのは原著の方であるのは疑いの無い事実でありましょう。伊福部昭の名前が出た所で加えて述べておきますが、先述の「差音」に於て同氏はS. S. Stevens, H. Davisの文献を引き合いに「29kHzと30kHz(どちらも可聴帯域外)の同時に鳴らしても1kHzの差音は生じない」というレコメンドをしておりまして、こうした差音の内容は現在刊行されている『完本 管絃楽法』でも同様ですが、現今社会に於てはこの可聴帯域外の差音の論述は誤りであります。
二つの音波どちらもが可聴帯域外であっても、それらのエネルギーが一定以上強い場合、差音を人間の耳が聴き取るのは既に研究報告されております。そのような研究は非線形音響の分野に括られ、国内では鎌倉友男に依る研究や関連書籍に詳しく、Googleでひとたび「鎌倉友男 非線形音響 差音」とでもググれば幾つかの論文PDFをダウンロードできるでしょう。確かこの手の可聴帯域外の非線形音響は近年、記憶が定かではありませんが、ギズモードジャパンかamassでも取り上げていた様に思います(2014年頃)。加えて、曲がりなりにも日本音響学会に於ても非線形音響の可聴帯域外の音波に依る結合差音認知の研究報告は幾多にも及びますので、差音に対して誤謬を正す必要があります。無論、伊福部昭著の『管絃楽法』は単なるオーケストレーションを超越した音楽周辺の凡ゆる智識の宝庫である為、重宝されている方も少なくはないでしょうが、古い本であるため、現今社会との間でズレが生じているにも拘らずこうした所を『完本 管絃楽法』でも修正されなかったのは残念な所です。次の版を待った方が宜しいかと思いますな。決して安くはない本なのですから、音楽之友社さんにも頑張って欲しい所ですな。
国内図書に於て「純正律半音階」に就いて非常に的確に論述されている著書は溝部國光著『正しい音階 音楽音響学』を筆頭に挙げる事ができますが、「純正律半音階」が生ずる、平均律とは異なる「半音」の音程幅という物をあらためて知る事ができるでしょうし、平均律社会ではエンハーモニック(異名同音)であっても、それは微分音的には全く異なる変化で、四分音的変化、または五分音的変化(この五分音についてはアロイス・ハーバが作品に残さなかったものの全音を5等分する物で、ブゾーニ流に考えれば既知の全音階組織では二種のホールトーン・スケールを生ずるので、全音を5等分する音律は2種の全音音階によって10分音に成るというのは推察に容易い)との類似性によって四分音に均されていくという微分音社会の背景を念頭に置くと、純正律半音階という音脈を疎かに出来ない事はあらためて実感する事でありましょう。ピアノしか奏する事の無い人は少し苦労するかもしれませんが。
ブルーノートが三分音、四分音、五分音、六分音、八分音、九分音・・・などの孰れかに該当していたのかどうかという所まで探るのは無益な労力でありましょう。しかし、ブルーノートというのは下方の音度に吸着していく特性があるとするのは実に腑に落ちる論述であり、先の、マイケル・ブレッカーが「I'm Sorry」にて短七度より1単位四分音高い音を長前打音風に奏してから短七度へ帰結するのは、重減八度から短七度へ結ぶと考えた方がより正しい解釈なのかもしれません。
また、協和音程である5度や3度よりも、7度を可動的変化で彩るのは調子っ外れな印象を与えないのも功を奏する点でありましょう。元々基音から七度周辺というのは不協和音程であるため違和感が少なく済むのでありましょうが、例えば、ジェフ・ベックのアルバム『Wired』収録の「Blue Wind」(邦題:「蒼き風」)での、6弦開放弦上のハーモニクスで自然七度音(あらゆる楽譜ではこの自然七度音はd音と記譜されております)が出て来ます。この六分音と考えて差し支えない音は、d音より1単位6分音低い(≒33セント)ものであります。
※自然七度と1単位六分音は2セント程の音程差がある物で完全な同一視はできないものですが、ほぼ同じ様に捉えて述べているので「六分音と考えて差し支えない音云々〜」として話題を進めております。但し、幾つかの純正音程を重ねて目的とする微分音を得ようとする場合、たった数セントの違いでもそれがその後大きな差異となってズレてしまう事もあるので、今回の様な単純に自然七度のそれと1単位六分音の単一音程同士の差が僅少だからといって他のケースに於て同様に無頓着になってしまわない様注意が必要です。幾つかの純正音程同士を重ね合わせて四分音や五分音を得るケースなどもあるからです。
ギターをチューニングした人であれば、33セントもずれた音は相当に大きく振れた音である筈ですが、それを自然七度として聴くと、そのズレ具合は不思議と大きなズレに聴こえないのが、七度周辺に存する音の成せる業でありましょう。人によっては、自然七度は本当に七度なのか!?と疑問を呈する人も居るのですが、これを七度としようと提唱した有名な音楽家のひとりにドビュッシーが居るのは有名な所です。
和声進行の「勾配」は、先行和音の根音を上音(倍音)に取り込む、という事は覚えておられるでしょう。「倍音」でも構わない訳ですから、平均律から外れた方への音脈に往来する事も可能ですし、微分音組織が根音である事も視野に入る様になるわけですが、少なくともジャズの現在はここまで微分音を使ってはおりません。然し乍ら「香り付け」という側面での微分音は、特にソロ奏者は使っていたりするのですが、聴き手が「イントネーションの一部」として看過してしまっている向きが非常に多いのも事実です。ただ、微分音的なイントネーションが特にブルー3度とブルー7度として強く現われた状況を次回はブルース・スケールやサージェントの論を引き合いにし乍ら語っていこうかと思います。
余談ではありますが、私が情報の出自を列挙するのは剽窃だと思われ度くは無いからであります。私のオリジナルな意見など音楽体系からしたら目に見えぬホコリ程度の物でしかありません(笑)。そうすれば胡散臭さも無くなる訳で、音楽を真摯に向き合う事で高次な音の獲得がスンナリと可能となる訳であります。その辺りを今一度念頭に置いてもらえれば助かります。
ということで、今度は中心音とテトラコルドとブルース・スケールという音階を中心に語る事になるので、なにゆえ中心音という事を語っていたのかという意図などを繙く事が可能となると思います。加えて、ブルース・スケールからパーシケッティにまで理解を及ばせるのは、サージェントも伊福部昭も濱瀬元彦もして来なかったと思うので、徐々に投影法への道に近付いているのでありまして、その辺りをきっちり踏まえて調性社会とは異なる仕来りを知っていただければと思うのであります(つづく)。
2014-11-05 01:00



