ウォルター・ベッカー新譜「Circus Money」 [スティーリー・ダン]
ベッカーの1stソロ・アルバム「11tracks of whack(11の心象)」から何年経過したでしょうか?
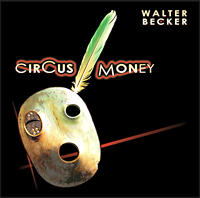
15年くらい?
まあ、当時を振り返ればそういや恵比寿ガーデンプレイスなんてまだ無かったです(笑)。恵比寿駅を降りてビール工場の方へ足を運ぶと、どことなく静観で他とは隔絶されたような独特な落ち着きのある空間、とても好きでした。何と形容すればいいのか、都会の喧騒を尻目に下町の風情がありながら、巨大な工場が溶け込んでいるというか。ああいう場所って鹿島田とかガス橋付近とか鶴見とか、ひょんなところから巨大な施設が同居するインダストリアルな空間、羽沢駅とか。それをもっと庶民的にしたような昭和30年代を想起させるような「ぬくもりのあるインダストリアル」と形容すれば判っていただけるでしょうか(笑)。
恵比寿ガーデンプレイスが完成する前辺りにリリースされた「11の心象」からどれだけの月日が流れたでしょう。その時生まれた子だっておそらく高校生!?そりゃ左近治もトシ取るモンですわ。
以前にも述べましたが、ベッカーの「11の心象」に出会うまでは、スティーリー・ダンは「フェイゲンありき!」と誤解していた時期がありまして、ベッカーの特異なコード・プログレッションを目の当たりにした時は本当に驚かされたものでした。これぞ、スティーリー・ダンの音だ、と。
先日もメロディック・マイナーのトーナリティーの重要性やらマイナー・メジャー7thとか、その辺りの楽理的な話題を散々述べてきたと思いますが、重要なのはオルタード・テンションというのはメロディック・マイナーを内包する場合があるので、それを見逃さず、母体のドミナント7thによる進行感(ドミナント・モーション)に頼らず、メロディック・マイナー・トーナリティーとして解釈して新たな複調感を得る、ということこそが重要なのでありまして、ウォルター・ベッカーという人はそういう「あちらの世界」を実に巧みに演出しているワケでありますな。もっと簡単に言えば、コード表記上オルタード7thが現れていたとしてもドミナント・モーションを用いないで楽曲を構築する方法ということでもあります。メロディック・マイナー・トーナリティーやらハンガリアン・マイナー・トーナリティーやら他の馴染みの薄いモードの導入によって構築されている曲のそんな特長的な部分を単に「オルタード7th」と理解して弾いてしまえば咀嚼しきれていない能力と言い換えることができるんですね。
リディアン7thスケールだの、ドリアン♭2だの、メロディック・マイナー・トーナリティーにおいてもそれらの旋法には名前が冠せられたりしていますが、7種類全ての旋法にスケール名が与えられているかどうかは定かではないですが、少なくともそれらの名前はメロディック・マイナー・トーナリティーの中においてポピュラーなのは2、3種類ほどで、他は便宜的に馴染みの薄い名称が割り当ててあるくらいのものでしかないでしょう。
重要なのは、それらのスケールの名称を全部体系的に覚えることではなく、メロディック・マイナー・トーナリティーを自身でどう昇華させるか、どれだけ咀嚼できるかということこそが重要で、メロディック・マイナー・トーナリティーのイロハなどただ単に音楽へ少々足突っ込めば誰でもそういう楽理面では通る道でウンチクのひとつやふたつなど語れるものでありますが、左近治の提示しているのはその先のフェーズなのだということをお判りいただければな、と。
真砂の数ほどある多くの楽曲の中から、メロディック・マイナー・トーナリティーを用いて他とはひときわ違った和声感を演出している曲をピックアップしてリリースしているというワケですな。和声に酔う、という感覚について少しでも伝えられればと思っているワケであります。
とまあ、小難しいハナシはさておき、ロックにおけるリフ主体の楽曲においても実はこういう複調的な世界というのはありまして、和声に欲張らずに「あっちの世界」を演出するという、いわばシンプルな発想と、ジャズという少々和声に欲張ったタイプのイイ所取りというかそういうバランスが絶妙なのがウォルター・ベッカーの最たる部分ではないかと。こういうことを「11の心象」を聴いて気付かされたからこそ、新譜の「Circus Money」が楽しみなのは言うまでもありません。
ベッカーの1stソロアルバムリリース以前はというと、スティーリー・ダンは一旦解散(状態)に陥り、彼ら独特のコードワークのそれはフェイゲンこそがスティーリー・ダンの肝であるとばかりに崇拝されていた向きもあり、私自身そう感じていた部分もありました。ただ、フェイゲンのそれには「なぜ、ブルージィな感じが多いのだろう?」と疑問を抱きながらも崇拝していた左近治がありましたし、多くのスティーリー・ダン・フリークの方々も同じような印象を抱いていたのではないかと。
個人的には「Deacon Blues」「Glamour Profession」「Black Cow」「Green Earrings」などにあるようなタイプの曲を欲していたところに、「Nightfly」や「Kamakiriad」に収録されていた曲の多くには肩透かしを食らっていた左近治でありました。もちろんそれらはそれで非常にイイものではあるんですが。
というわけで、「11の心象」がリリースされて聴いてみたら、「この人こそが!」と驚いてしまったワケなんですよ。その後数年が経過して、よもやスティーリー・ダンの新しいアルバムが聴くことなど出来ると思わなかった「Two Against Nature」における「Almost Gothic」や「Negative Girl」で完全ノックアウト(笑)。「West of Hollywood」のイントロも大好きですが。いかにベッカーが重要なのかをあらためて知ることができたワケでした。
オルタード・テンションにおいてドミナント感を排除しつつ、それらの構成音を一旦解体するかのように、とことんシンプルにオミットしていく。そうすることで「解体前」に内包していた複調感の世界を強調するかのように響かせ、奇をてらうかのように次へのコードへ進行させていく、と。Medical Scienceなど聴くと、本当にその凄さを堪能できるワケでありますが、和声への習熟度が必要とされるというか、少し敷居が高いのもベッカーの特長であると言えましょうか。
そういう複調感の操り方で最もバランスが取れているのはやはりロック的なリフを利用したアプローチが功を奏するというか、一般的にはその世界に近づきやすいパターンではあるんですが、「イチロクニーゴー」を基本として、こういう部分について後日詳しく語りたいと思うので、今回はこの辺で。
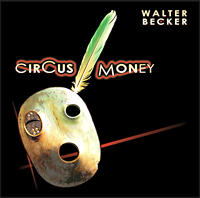
15年くらい?
まあ、当時を振り返ればそういや恵比寿ガーデンプレイスなんてまだ無かったです(笑)。恵比寿駅を降りてビール工場の方へ足を運ぶと、どことなく静観で他とは隔絶されたような独特な落ち着きのある空間、とても好きでした。何と形容すればいいのか、都会の喧騒を尻目に下町の風情がありながら、巨大な工場が溶け込んでいるというか。ああいう場所って鹿島田とかガス橋付近とか鶴見とか、ひょんなところから巨大な施設が同居するインダストリアルな空間、羽沢駅とか。それをもっと庶民的にしたような昭和30年代を想起させるような「ぬくもりのあるインダストリアル」と形容すれば判っていただけるでしょうか(笑)。
恵比寿ガーデンプレイスが完成する前辺りにリリースされた「11の心象」からどれだけの月日が流れたでしょう。その時生まれた子だっておそらく高校生!?そりゃ左近治もトシ取るモンですわ。
以前にも述べましたが、ベッカーの「11の心象」に出会うまでは、スティーリー・ダンは「フェイゲンありき!」と誤解していた時期がありまして、ベッカーの特異なコード・プログレッションを目の当たりにした時は本当に驚かされたものでした。これぞ、スティーリー・ダンの音だ、と。
先日もメロディック・マイナーのトーナリティーの重要性やらマイナー・メジャー7thとか、その辺りの楽理的な話題を散々述べてきたと思いますが、重要なのはオルタード・テンションというのはメロディック・マイナーを内包する場合があるので、それを見逃さず、母体のドミナント7thによる進行感(ドミナント・モーション)に頼らず、メロディック・マイナー・トーナリティーとして解釈して新たな複調感を得る、ということこそが重要なのでありまして、ウォルター・ベッカーという人はそういう「あちらの世界」を実に巧みに演出しているワケでありますな。もっと簡単に言えば、コード表記上オルタード7thが現れていたとしてもドミナント・モーションを用いないで楽曲を構築する方法ということでもあります。メロディック・マイナー・トーナリティーやらハンガリアン・マイナー・トーナリティーやら他の馴染みの薄いモードの導入によって構築されている曲のそんな特長的な部分を単に「オルタード7th」と理解して弾いてしまえば咀嚼しきれていない能力と言い換えることができるんですね。
リディアン7thスケールだの、ドリアン♭2だの、メロディック・マイナー・トーナリティーにおいてもそれらの旋法には名前が冠せられたりしていますが、7種類全ての旋法にスケール名が与えられているかどうかは定かではないですが、少なくともそれらの名前はメロディック・マイナー・トーナリティーの中においてポピュラーなのは2、3種類ほどで、他は便宜的に馴染みの薄い名称が割り当ててあるくらいのものでしかないでしょう。
重要なのは、それらのスケールの名称を全部体系的に覚えることではなく、メロディック・マイナー・トーナリティーを自身でどう昇華させるか、どれだけ咀嚼できるかということこそが重要で、メロディック・マイナー・トーナリティーのイロハなどただ単に音楽へ少々足突っ込めば誰でもそういう楽理面では通る道でウンチクのひとつやふたつなど語れるものでありますが、左近治の提示しているのはその先のフェーズなのだということをお判りいただければな、と。
真砂の数ほどある多くの楽曲の中から、メロディック・マイナー・トーナリティーを用いて他とはひときわ違った和声感を演出している曲をピックアップしてリリースしているというワケですな。和声に酔う、という感覚について少しでも伝えられればと思っているワケであります。
とまあ、小難しいハナシはさておき、ロックにおけるリフ主体の楽曲においても実はこういう複調的な世界というのはありまして、和声に欲張らずに「あっちの世界」を演出するという、いわばシンプルな発想と、ジャズという少々和声に欲張ったタイプのイイ所取りというかそういうバランスが絶妙なのがウォルター・ベッカーの最たる部分ではないかと。こういうことを「11の心象」を聴いて気付かされたからこそ、新譜の「Circus Money」が楽しみなのは言うまでもありません。
ベッカーの1stソロアルバムリリース以前はというと、スティーリー・ダンは一旦解散(状態)に陥り、彼ら独特のコードワークのそれはフェイゲンこそがスティーリー・ダンの肝であるとばかりに崇拝されていた向きもあり、私自身そう感じていた部分もありました。ただ、フェイゲンのそれには「なぜ、ブルージィな感じが多いのだろう?」と疑問を抱きながらも崇拝していた左近治がありましたし、多くのスティーリー・ダン・フリークの方々も同じような印象を抱いていたのではないかと。
個人的には「Deacon Blues」「Glamour Profession」「Black Cow」「Green Earrings」などにあるようなタイプの曲を欲していたところに、「Nightfly」や「Kamakiriad」に収録されていた曲の多くには肩透かしを食らっていた左近治でありました。もちろんそれらはそれで非常にイイものではあるんですが。
というわけで、「11の心象」がリリースされて聴いてみたら、「この人こそが!」と驚いてしまったワケなんですよ。その後数年が経過して、よもやスティーリー・ダンの新しいアルバムが聴くことなど出来ると思わなかった「Two Against Nature」における「Almost Gothic」や「Negative Girl」で完全ノックアウト(笑)。「West of Hollywood」のイントロも大好きですが。いかにベッカーが重要なのかをあらためて知ることができたワケでした。
オルタード・テンションにおいてドミナント感を排除しつつ、それらの構成音を一旦解体するかのように、とことんシンプルにオミットしていく。そうすることで「解体前」に内包していた複調感の世界を強調するかのように響かせ、奇をてらうかのように次へのコードへ進行させていく、と。Medical Scienceなど聴くと、本当にその凄さを堪能できるワケでありますが、和声への習熟度が必要とされるというか、少し敷居が高いのもベッカーの特長であると言えましょうか。
そういう複調感の操り方で最もバランスが取れているのはやはりロック的なリフを利用したアプローチが功を奏するというか、一般的にはその世界に近づきやすいパターンではあるんですが、「イチロクニーゴー」を基本として、こういう部分について後日詳しく語りたいと思うので、今回はこの辺で。
2008-04-09 11:25



