属七提要 貳 [楽理]
扨て、界隈ではドリアン・モードを堅持しながら「IV」上で発生するドミナント7thコードの垂直的な有り体を稀釈化させる事が広く体系化する様になります。
それは「IV」上において「I/IV」となるか「III/IV」という形を採るか、という風に変化していく様にもなります(※余談ですが調性社会の様にT・S・Dを経由してしまうとモーダルではなく調性が表れるので、モードを堅持という事はどういう事かあらためて語る必要はないかと思いますが念のため混同せぬ様ご理解のほどを)。
後者の「III/IV」のタイプは、ジャズ/ポピュラー界隈の表記ルールでは長音階の配列を基にしてディグリー表記を形成するので、ローマ数字に附与させる嬰変記号はそれに倣う形で表記すると「♭III/IV」という形になりますので、イ短調を中心に考えれば、前者は「Am7/D または Am7 (on D)」となり、後者は「CM7/D または CM7 (on D)」となります。
イ短調における解釈なので短調のIII度上が「♭III」に見えなくしてしまっているのには注意が必要なのですが、先述の様にジャズ/ポピュラー界隈では長音階(自然長音階)を基にしているので短調のIII度は「♭III」と表記されるのですがAマイナー組織に於て主音から短三度上では単なる幹音で派生音として表わさなくともよくなるので、注意が必要です。また、短調のIII度上の四和音はCM7を堅持するよりも、CM7+5(または CM7aug)のタイプとして変化する事が往々にしてある事も念頭に置いておく必要があるでしょう。
抑も短調のIII度上の和音が増和音化するのは、短調の七度が導音化する事によって、その導音化がドミナントばかりで使われるのではなく、トニック、サブドミナントで現れる和音構成音上でも使うように発展したからであり、西洋音楽では19世紀では既に顕著な例となっています。
ごく初歩的なポピュラー音楽理論ですと短調組織がドミナント時のみ導音化させて他のシーンでは導音を下主音化させているゴッタ煮状態の組織を学ばせますが、これはもっと深く教えなくてはいけない事で短調組織をこっぴどく理解させないとその後の減三和音と減七和音の区別やハーフ・ディミニッシュ、硬減和音の取扱方も全く判らなくさせてしまうものなので、ジャズ/ポピュラー界隈の音楽理論書の殆どがこうした所を見誤っている所が、根幹の音楽をも阻碍してしまう様になってしまったというのは決して過言ではないでしょう。
 ツー・ファイヴ進行というのは実は他にもあり、次の様な例を「ツー・ファイヴ進行」とは実際に耳にする事は非常に少ないでしょうが、例えばジェフ・ベックのアルバム「There And Back」収録の「El Becko」のイントロは「H dur/f moll(三全音複調) → B♭7」であり、その後B♭7はB♭7sus4に稀釈化します。内含する三全音が機能和声的な調性機能を十把一絡げにして多声的に演出しているとも言えるでしょう。
ツー・ファイヴ進行というのは実は他にもあり、次の様な例を「ツー・ファイヴ進行」とは実際に耳にする事は非常に少ないでしょうが、例えばジェフ・ベックのアルバム「There And Back」収録の「El Becko」のイントロは「H dur/f moll(三全音複調) → B♭7」であり、その後B♭7はB♭7sus4に稀釈化します。内含する三全音が機能和声的な調性機能を十把一絡げにして多声的に演出しているとも言えるでしょう。
謬見として広く知られている「Fm7(♭5)」というコード表記は市販のバンドスコアの物でありますが、それをパッと見で確認するならば、この当該和音進行は短調における「ツーファイヴ」なのであります。市販のスコアの誤りは扨措くとして「El Becko」をひとたび聴けばお判りになりますが、一見短調のツーファイヴと思しきそれがE♭mというトニックを目指そうとしていないのは明白です。主題が本位十一度音を使うから稀釈化されていくのがお判りでありましょう。
近々『トリスタン和音』について触れる事でもあるので、今回「El Becko」で用いられているハーフ・ディミニッシュの和音はトリスタン和音(※f、h、dis、gis)とは微妙に違うのですが、和音の体としてトリスタン和音にインスパイアされた使い方というのは判ります。それは、作曲者であるアンソニー・ハイマス&サイモン・フィリップス左手がトリスタン和音の下方の3音と異名同音で同一の五度・四度堆積で和音を積みつつ、上声部でgis音と異名同音のas音も経過的に用いているのは確かにトリスタン和音から依拠したものであろうとは思いますが、これが「ジャズ的だなぁ」と私がつくづく感じるのは次の通りです。
Fm7(♭5)から得られる音は「f、as、ces、es」です。「El Becko」のイントロでは、Fm7(♭5)上で現れるトリトヌスに対して「5つの音」を示唆するかの様な音並びを伴います。
つまり、イントロのピアノの右手はルートのF音から見た完全四度音=B♭音と減五度音=C♭音を使いつつ、短三度のA♭音をと短七度音のE♭音を鏤めたフレーズとなっているのでありますが、F音とC♭音という音程間にB♭とA♭音を使っているので、FからA♭音をFとG#という増二度という風に見るのは不自然と思います。
つまり、Fm7(♭5)という和音のsuppositionという関係にあるD♭7に伴う和音として見ると、D♭7の和音が持つとリトヌス(F - C♭)に5音を嵌当するというやり方でA♭とB♭音を得ているのだという風に想起する方がずっと自然でして、そうするとこのトリトヌスに対して5音を嵌当するというのがジャズ的な見渡しであるという事に加え、ジャズ的な勾配を誘う和音を使いつつも稀釈化を狙っているのは、E♭方面への解決をさせたくないが故の変格的な嘯きが基にあるからに他ありません。
念のために西洋音楽方面での最も初歩的な対位法でのトリトヌスの取扱というのは、全音階(ダイアトニック組織)で生じるトリトヌスをさらに細かく砕こうとはしません。増四度内の全音音程のどこかに半音の楔を入れはしない、という事を意味します。とはいえジャズやポピュラー音楽がそれに倣え!という事を私は言っているのではないのです。
先の「El Becko」の様な用法は、単純に和音そのものの固有の響きだけを利用している用い方で、それに対して「線」が附随させているがピアノの右手のフレーズと言えます。ところが、西洋音楽の初歩としては、特定の和音の響きだけを用いようとはせずに線的な勾配を聴き手に対しても踏みにじることなく自然に勾配を付けようとするが為に慮っている事であり、両者から生ずる全体的な和声感というのは全く異質の物なのだという事を念頭に置いた上で、ジャズ方面が西洋音楽からまだまだヒントを得る事が多いものなのだ、という事を詳らかに取り上げたいが為にこのように私は述べているのであります。
西洋音楽のそれが全音階的組織にてトリトヌスを忌避するのは、例えばアナタが長音階に於いて、一人が「ファソラシー♪」と唄っている旋律の3度上をハモるように「ラシドレー♪」と唄ったとしましょうか。すると、アナタが「シ」の音を唄った時点でアウトなのです(笑)。
それは、アナタが「ラ」を唄った時、下方の人は「ファ」を唄っていた事で、アナタが「シ」を唄うと、先のファとシで増四度が生まれます。これがトリトヌスの対斜です。こうした響きは二声間の上下で見ると忌避すべしとなる対斜が見え、一方、横から傍観するように見ると、長三度音程同士の「平行」が見られるワケです。
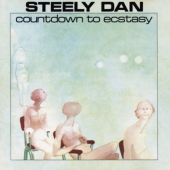 つまり、パラレル・モーションというのは極々単純な所に対斜が潜んでいるモノでもあるのです。そういった意味ではスティーリー・ダンのアルバム「Countdown to Ecstasy」収録の「King of the World」のイントロの様に「♭VI△→♭VII△→I△」(※C△→D△→E△ 最初のC音は次のD△の構成音F#との対斜を作る、以後E△とも同様)と進行する各音程間にもトリトヌスは生じているのでありますが、西洋音楽が平行やトリトヌスを避ける意味がこうすると能く判るのではないかと思います。
つまり、パラレル・モーションというのは極々単純な所に対斜が潜んでいるモノでもあるのです。そういった意味ではスティーリー・ダンのアルバム「Countdown to Ecstasy」収録の「King of the World」のイントロの様に「♭VI△→♭VII△→I△」(※C△→D△→E△ 最初のC音は次のD△の構成音F#との対斜を作る、以後E△とも同様)と進行する各音程間にもトリトヌスは生じているのでありますが、西洋音楽が平行やトリトヌスを避ける意味がこうすると能く判るのではないかと思います。
折角ジャズ方面を覚えようとしてこうした事が足枷になってしまうようなら、そんな人に和声感が鍛えられている訳はありません(笑)。ある程度和声感が出来ているならば、こうした事ばかりに頭デッカチになって及び腰になる必要は全くないのです。
然し乍ら、トリスタン和音を「ハーフ・ディミニッシュ」としてだけ捉えるのは早計です。奇しくもジャン=ジャック・ナティエ著『音楽記号学』には希代の31人の作曲家の夫々のトリスタン和音の解釈を詳らかに掲載させています。
トリスタン和音をハーフ・ディミニッシュとして捉えるのは、それらの中ではヤダスゾーンの解釈が現今社会のそれと近しい程度のもので、色々な解釈がある事をまざまざと見せ付けてくれる名著である事を実感させてくれるでありましょう。寧ろジャズ界隈に生きる人こそ、このナティエの著書『音楽記号学』には多くの大変有用なヒントがある事を実感するでありましょう。ですから、トリスタン和音は必ずしもハーフ・ディミニッシュという解釈だけではないのであります。
たった一つのトリトヌスに5つの音を嵌当する事でモード想起を図るのは、和音の響きに対して「線を欲しがる」からであります。とはいえ、先の「El Becko」でのFm7(♭5)上で、ヘプタトニックな組織が全て経過的にでも表れている訳ではないのです。それなのになぜモード想起を朧げながらも感じていたいのか!?というと、線としての拡大が予期せぬほど突拍子も無い調域の方へ拡大させたくない狙いがあるからでありましょう。つまり、Fm7(♭5)→B♭7またはFm7(♭5)→B♭7sus4において、聴き手に対して、これらの2コード・パターンで映じてほしい世界観(調性感を裏切らない程度の嘯き)を伴わせたいが故の事でありましょう。それらを一旦構築してからコード進行は他の調域に歩を進めようとするのでありまして。
トリスタン和音を「不等四度」音程の和音として見立てて、多くの複調的なモード想起も可能なのでありますが、ジャズが形骸化しているのはトリトヌスに対して5つの音を嵌当してしまう事で、その和音に対して容易くヘプタトニック組織を想起する事で、結果的に和音の体と横の線がヘプタトニックというモノで調的世界観を容易く埋め切って飽和してしまう為、それを和音進行の目紛しさで目くらまししているだけに過ぎず、一つの和音に対して一つの調域しか見れなくなってしまっている事が、近視眼的なジャズ理論の理解にしか伴っていないような者でも「なんちゃって」なジャズを体系に凭れ掛かって操る事が出来てしまっている悲哀なる側面を生んでいるのが現今のジャズなのであります。
複調性というのはメンバーがインプロヴァイズで勝手に他の調性に行く様なら返って不味いワケですよ。誰か一人が逸脱するだけで根幹が据わっているならまだしも。ですからこの手の世界観が構築されるのは、下僕共に延々単一的な調性の世界観でのリフを奏させておいて、自身が逸脱するか(晩年のマイルス)、皆が勝手にインプロヴァイズしてしまったらあらゆる調域がバラバラになりかねず結果的に垂直的な複調感を容易く得られるのはピアノ奏者に依る潤沢な和声感にて構築させるか位のものになってしまい、後は予定調和として複調を予め計画しておかないとなかなかそうした世界観を統率できないのがジャズのネックとなっている部分なのです。
ところが、ジャズもsus4化、ポリ・コード化させる事によってドミナント7thコードそのものの勾配が稀釈化して、横の複調感が出て来ます。これに気が利くパートは本位十一度の音を下支えとして奏してくれるので、複調感が増す背景にソロ奏者が更に気を利かせた逸脱した線を奏でる事も可能となるワケです。
そうすると、調的社会がトニックへ解決するという「成就」という図式はそれほど必要なモノではなく、起承転結の「結び」が要らない、要所要所で楽しんでいれば十分という静的な空間で音楽を嗜む世界観が登場するワケです。そうすると、本位十一度を下支えする和声的空間はもっと稀釈化され、3度堆積型の和音ですら調的な成分を示すため、この辺りが稀釈化する事でポリ・コードから、分子構造がもっとマトリクスな組み合わせと呼べるに相応しい和音のハイブリッド化とマトリクス化が進むワケです。
とはいえ、ドミナント7thコードが次の全音階的勾配を求める動的な振る舞いとは別に、稀釈化する「静的」なそれはまだまだほんの序の口であるのも事実。
ドミナント7thを包含する、或いはトリトヌスを包含する不協和音とやらが、その対称的・均齊的な枝葉を伴って、その触手にはオクターヴを等分割する音程を伴った体をさらに結び付けようとします。その等しい分割は、トリトヌスという半オクターヴは勿論、長三度等音程分割(増三和音の骨格)、短三度等音程(減七和音の骨格)、半音階、四全音、二全音、五全音+2半音やら、等分平均律に依拠する微分音の骨格やらも枝葉に付ける様に多様な構造となっていくのでありますが、今回述べているドミナント7thコードはあくまで、本来の動的な機能とそれが稀釈化する静的な方面を語っているのみである事もあらためて注意してもらいたい所です。コードネームにすら記す事のできない微分音をまとった和声空間を今茲で述べてしまうのは余りに早計でありましょう(笑)。
但し、不協和音で満たされた音空間で音がそれぞれ「粒」として溶けている様な状況を想像してもらうとして、そこから「粒」をそれぞれ任意に抽出して組み合わせた時には、調性社会を遵守していた時のそれとは趣の異なる和音を得られるという風に考えてみましょう。仮に「2コード・パターン」として記す事ができたとしても、それら2つの和音夫々の構成音が溶け込んでいる状況を考えてもらいたいワケです。すると、その2コードとは、協和⇆不協和というメリハリを付けるだけでメリハリ感が生じ、このメリハリはごく簡単な「勾配」でもありますが、その勾配が調的な世界の道順で描かれるコースとは違うだけの事なのです。
例えば、メロディック・マイナー・スケールをダイアトニック・スケールと考えて、その音階上に出来るダイアトニック・コードを列挙すると、IV度上とV度上で2つのドミナント7thコードを生む事になります。IV度上に現れる「ドミナント」とはけしからん!と思うかもしれませんが(笑)、ドミナント7thコードという和音の体は、V度の位置以外で副次的に発生しようとも和音の有り体の名前はドミナント7thコードと呼ぶのでありまして、この辺ばかりに拘っているようでは、今回私が述べている事を何一つ理解できない事でありましょう(笑)。
扨て、メロディック・マイナーを全音階組織とするダイアトニック・コードでIV7はどう扱えばイイのか!?これは私のブログでも過去に少し述べている事です。ドミナント7thコードが常に四度進行という勾配を欲しているだけの物ならば、この体系でのIV7は行き場を失います。III度は実際は♭IIIですし、四度進行先のVII度は♭VIIではありません。
こうした時のIV7という和音の有り体が稀釈化すれば良いのです。最も容易に考えが及ぶのは本位11度音附与かもしれませんが、残念な事にメロディック・マイナー体系でのIV度上の11度は増11度である必要性があるため、和音の有り体としての稀釈化は、ドミナント7th+本位十一度のタイプとは別の体系を考える必要性が生じます。
そこで、基底和音を稀釈化します。メロディック・マイナーを全音階組織としてIV度に生ずる四声体の和音はF7。この基底和音は七度音を除いたF△。つまりこれを稀釈化するのは3度音と5度音を省く。さらに七度音から不足分の2音を3度ずつメロディック・マイナーのダイアトニック列で積み上げる。すると、基底和音は単音のベース音=F音となり、上部にE♭、G、Bという風にEaugという増三和音を形成することになります。つまりコードとしては
「E♭aug (on F)」という風になった訳です。こうすることで「ImM7 → E♭aug (on F)」とやると非常に味わい深くなるのですが、各々のコードのメリハリを出す為に、最初の「I」のコードではドリアンを想起して、♭III on IVの所で♭IIIのリディアン・オーギュメントを想起するととてもメリハリが付くのです。
 奇しくも、Fm9 → A♭M7aug (on B♭)という風にイントロを奏していますが、アジムスの「A Presa」であり、本テーマ部は単純に「Im7 → Im7/IV」のタイプにして使い分けているのがお判りいただけることでしょう。AテーマではFm9 → Fm7 (on B♭)に微妙に変えているのも特徴的です。
奇しくも、Fm9 → A♭M7aug (on B♭)という風にイントロを奏していますが、アジムスの「A Presa」であり、本テーマ部は単純に「Im7 → Im7/IV」のタイプにして使い分けているのがお判りいただけることでしょう。AテーマではFm9 → Fm7 (on B♭)に微妙に変えているのも特徴的です。
※「A Presa」のイントロ部のコード解釈=A♭M7aug (on B♭)というのは、実際にはオルタード・テンションを纏った「B♭7(9、♯11、13)」の断片です。
これらの例から言いたい事は、ドミナント7thコードは本位11度を持つ事で複調化の到来により和音の体系がシンプル化して分数コード化を招く様になっているのが現今の音楽シーンであり、ドミナント7thコードが必ずしも進行感を強める為に勾配を付けて使用されているものばかりではない、という事があらためて判ります。短調組織においてですら、導音の性格を中性化させて「V7」がエオリア調の「Vm」のままという事も珍しくはありません。
近視眼的ジャズ的アプローチからすれば、ドミナント7thコード上では多くのオルタード・テンションを示唆するので、それこそ半音階を満たさんばかりの音を使用できる音脈がありますが、これとて、和音の有り体を維持したいが為に、ドミナント7thコードが本来持っている勾配は同主調であれば行き先のトニックがトニック・マイナーであるかトニック・メジャーであるか、ジャズ的な勾配からすれば行き先のそれはメジャーもマイナーも双方が混淆としている世界観を意味する物から依拠しているのがオルタード・テンションとして一緒くたに取り扱える体系なのであります。且つ本位11度音を和音の有り体の為に避けて増11度化させているので和音の振る舞いとしての音楽的な使用可能なスペースが増えるのであり、短調組織と長調組織由来でのテンション・ノートを一括りにした事からオルタード・テンションというのは音脈として使える様に到っているのであります。
ですからその様な体系に有り難がっているだけの人からすれば、オルタード・テンションをドミナント7thコード上でふんだんに使えば、恰も半音階的動作をこなしているかの様に聴かせる事が可能なワケですが、ドミナント7thコードの有り体がどんどん稀釈化されている現状において、今度はどうやってオルタード・テンションを有り難がろうとするのか!?と問うてみたくなりますな(笑)。単にポリコードの体に形を変えたり、sus4などの体に形を変えた時に、勾配を強める仕来りの音脈ばかり使っていては唾棄すべき行為でありましょう(笑)。
しかも、音楽的な和声空間の発展は間違い無く西洋音楽やジャズ/ポピュラー問わずポリ・コード(分数コード)&複調化が著しくなっているのが現実です。
例えば、先のアジムスの「A Presa」で出て来たA♭M7aug (on B♭)は、ドミナント7thコード体系に慣れ切ってしまった人間から見たら、B♭7(9、#11、13)のM3rdとP5thがオミットされた物として映ずるかもしれません。これじゃあ駄目なのです。基底和音としてB♭△はおろかB♭7を示唆する体として在って欲しくないが故にA♭M7aug (on B♭)の姿で振る舞う必要があるのですが、それをドミナント7th系統の解釈でアプローチの選択を採るのであれば、それは結果的に勾配を強めるだけで複調性すら踏み躙る事に等しいのであります。
更に、減八度「的」音脈を最も得易い体系として、短調に於ける「V7/♭VI」という和音を使う時があります。ハ短調ならば「G7/A♭」という分数コードです。仮にG7の方にE音を付与してしまう様な音を使ってしまったら、体としてはE7(#9)系列の3度ベースに見てしまうかもしれませんし、この手の例に限らずドミナント7thの体に慣れ切ってしまった人というのはその「勾配」がドミナント7thに付与する体系を見抜きやすいのでありますが、これを中和化させない限り、複調性の感覚が養われる事はありません。この点を最も注意しなくてはいけないでしょう。
 このような和音を聴く事のできるのは渡辺香津美のアルバム「Olive's Step」収録の初期の名曲のひとつ「Inner Wind」で確認する事ができます。
このような和音を聴く事のできるのは渡辺香津美のアルバム「Olive's Step」収録の初期の名曲のひとつ「Inner Wind」で確認する事ができます。
 加えて、近年の物だとスティーリー・ダンのアルバム「Two Against Nature」収録の「Almost Gothic」に用いられているD7/E♭という使い方がとても参考になるのではないかと思います。まあ、これらの用法も私のブログ開始初期から述べている事なのでありますが、声高に述べているかサラリと述べているかの違い程度なもので、昔も今も、私が語ろうとするのは一貫しているつもりです(笑)。
加えて、近年の物だとスティーリー・ダンのアルバム「Two Against Nature」収録の「Almost Gothic」に用いられているD7/E♭という使い方がとても参考になるのではないかと思います。まあ、これらの用法も私のブログ開始初期から述べている事なのでありますが、声高に述べているかサラリと述べているかの違い程度なもので、昔も今も、私が語ろうとするのは一貫しているつもりです(笑)。
抑も、先のコードは何らかの1音を映じてしまう事で、何らかのドミナント7thコード体系を見付けてしまう状況であります。しかし、それを判った上で作曲者が和音を提示しているにも関わらず、「G7/A♭」にてE7(#9)系統のアプローチを採られた日にゃ掌底の2、3発じゃ済まない事でありましょう。「G7/A♭」から「B」へ進んでしまえば、これはG7からの半音階的偽終止進行ではなくE7由来の勾配を示唆する物とは思えるでしょうが、「G7/A♭」で稀釈化させてCに進んだり、或いはG7/A♭が静的な茫洋とした形である事すら珍しくはないのです。
どうしても耳が勾配付けを伴ってしまうタイプの人は、つまり、熟達に足りないと言えるのであります。ですので、こうした音感を持ってしまっている人が、ジャズの体系を存分に堪能していたとしても、モード・ジャズとなると途端に駄目になるかと思います。そういうモンなんですね、現実は。勾配ジャズですか。せめて有り難がってくらはいな(笑)。軈ては、此の世に明治生まれの人が居なくなってしまう頃にはそんなジャズは過去の遺作としてでしか耳にされない様になるのは目に見える様でもあります。
それは「IV」上において「I/IV」となるか「III/IV」という形を採るか、という風に変化していく様にもなります(※余談ですが調性社会の様にT・S・Dを経由してしまうとモーダルではなく調性が表れるので、モードを堅持という事はどういう事かあらためて語る必要はないかと思いますが念のため混同せぬ様ご理解のほどを)。
後者の「III/IV」のタイプは、ジャズ/ポピュラー界隈の表記ルールでは長音階の配列を基にしてディグリー表記を形成するので、ローマ数字に附与させる嬰変記号はそれに倣う形で表記すると「♭III/IV」という形になりますので、イ短調を中心に考えれば、前者は「Am7/D または Am7 (on D)」となり、後者は「CM7/D または CM7 (on D)」となります。
イ短調における解釈なので短調のIII度上が「♭III」に見えなくしてしまっているのには注意が必要なのですが、先述の様にジャズ/ポピュラー界隈では長音階(自然長音階)を基にしているので短調のIII度は「♭III」と表記されるのですがAマイナー組織に於て主音から短三度上では単なる幹音で派生音として表わさなくともよくなるので、注意が必要です。また、短調のIII度上の四和音はCM7を堅持するよりも、CM7+5(または CM7aug)のタイプとして変化する事が往々にしてある事も念頭に置いておく必要があるでしょう。
抑も短調のIII度上の和音が増和音化するのは、短調の七度が導音化する事によって、その導音化がドミナントばかりで使われるのではなく、トニック、サブドミナントで現れる和音構成音上でも使うように発展したからであり、西洋音楽では19世紀では既に顕著な例となっています。
ごく初歩的なポピュラー音楽理論ですと短調組織がドミナント時のみ導音化させて他のシーンでは導音を下主音化させているゴッタ煮状態の組織を学ばせますが、これはもっと深く教えなくてはいけない事で短調組織をこっぴどく理解させないとその後の減三和音と減七和音の区別やハーフ・ディミニッシュ、硬減和音の取扱方も全く判らなくさせてしまうものなので、ジャズ/ポピュラー界隈の音楽理論書の殆どがこうした所を見誤っている所が、根幹の音楽をも阻碍してしまう様になってしまったというのは決して過言ではないでしょう。

謬見として広く知られている「Fm7(♭5)」というコード表記は市販のバンドスコアの物でありますが、それをパッと見で確認するならば、この当該和音進行は短調における「ツーファイヴ」なのであります。市販のスコアの誤りは扨措くとして「El Becko」をひとたび聴けばお判りになりますが、一見短調のツーファイヴと思しきそれがE♭mというトニックを目指そうとしていないのは明白です。主題が本位十一度音を使うから稀釈化されていくのがお判りでありましょう。
近々『トリスタン和音』について触れる事でもあるので、今回「El Becko」で用いられているハーフ・ディミニッシュの和音はトリスタン和音(※f、h、dis、gis)とは微妙に違うのですが、和音の体としてトリスタン和音にインスパイアされた使い方というのは判ります。それは、作曲者であるアンソニー・ハイマス&サイモン・フィリップス左手がトリスタン和音の下方の3音と異名同音で同一の五度・四度堆積で和音を積みつつ、上声部でgis音と異名同音のas音も経過的に用いているのは確かにトリスタン和音から依拠したものであろうとは思いますが、これが「ジャズ的だなぁ」と私がつくづく感じるのは次の通りです。
Fm7(♭5)から得られる音は「f、as、ces、es」です。「El Becko」のイントロでは、Fm7(♭5)上で現れるトリトヌスに対して「5つの音」を示唆するかの様な音並びを伴います。
つまり、イントロのピアノの右手はルートのF音から見た完全四度音=B♭音と減五度音=C♭音を使いつつ、短三度のA♭音をと短七度音のE♭音を鏤めたフレーズとなっているのでありますが、F音とC♭音という音程間にB♭とA♭音を使っているので、FからA♭音をFとG#という増二度という風に見るのは不自然と思います。
つまり、Fm7(♭5)という和音のsuppositionという関係にあるD♭7に伴う和音として見ると、D♭7の和音が持つとリトヌス(F - C♭)に5音を嵌当するというやり方でA♭とB♭音を得ているのだという風に想起する方がずっと自然でして、そうするとこのトリトヌスに対して5音を嵌当するというのがジャズ的な見渡しであるという事に加え、ジャズ的な勾配を誘う和音を使いつつも稀釈化を狙っているのは、E♭方面への解決をさせたくないが故の変格的な嘯きが基にあるからに他ありません。
念のために西洋音楽方面での最も初歩的な対位法でのトリトヌスの取扱というのは、全音階(ダイアトニック組織)で生じるトリトヌスをさらに細かく砕こうとはしません。増四度内の全音音程のどこかに半音の楔を入れはしない、という事を意味します。とはいえジャズやポピュラー音楽がそれに倣え!という事を私は言っているのではないのです。
先の「El Becko」の様な用法は、単純に和音そのものの固有の響きだけを利用している用い方で、それに対して「線」が附随させているがピアノの右手のフレーズと言えます。ところが、西洋音楽の初歩としては、特定の和音の響きだけを用いようとはせずに線的な勾配を聴き手に対しても踏みにじることなく自然に勾配を付けようとするが為に慮っている事であり、両者から生ずる全体的な和声感というのは全く異質の物なのだという事を念頭に置いた上で、ジャズ方面が西洋音楽からまだまだヒントを得る事が多いものなのだ、という事を詳らかに取り上げたいが為にこのように私は述べているのであります。
西洋音楽のそれが全音階的組織にてトリトヌスを忌避するのは、例えばアナタが長音階に於いて、一人が「ファソラシー♪」と唄っている旋律の3度上をハモるように「ラシドレー♪」と唄ったとしましょうか。すると、アナタが「シ」の音を唄った時点でアウトなのです(笑)。
それは、アナタが「ラ」を唄った時、下方の人は「ファ」を唄っていた事で、アナタが「シ」を唄うと、先のファとシで増四度が生まれます。これがトリトヌスの対斜です。こうした響きは二声間の上下で見ると忌避すべしとなる対斜が見え、一方、横から傍観するように見ると、長三度音程同士の「平行」が見られるワケです。
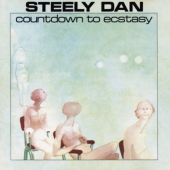
折角ジャズ方面を覚えようとしてこうした事が足枷になってしまうようなら、そんな人に和声感が鍛えられている訳はありません(笑)。ある程度和声感が出来ているならば、こうした事ばかりに頭デッカチになって及び腰になる必要は全くないのです。
然し乍ら、トリスタン和音を「ハーフ・ディミニッシュ」としてだけ捉えるのは早計です。奇しくもジャン=ジャック・ナティエ著『音楽記号学』には希代の31人の作曲家の夫々のトリスタン和音の解釈を詳らかに掲載させています。
トリスタン和音をハーフ・ディミニッシュとして捉えるのは、それらの中ではヤダスゾーンの解釈が現今社会のそれと近しい程度のもので、色々な解釈がある事をまざまざと見せ付けてくれる名著である事を実感させてくれるでありましょう。寧ろジャズ界隈に生きる人こそ、このナティエの著書『音楽記号学』には多くの大変有用なヒントがある事を実感するでありましょう。ですから、トリスタン和音は必ずしもハーフ・ディミニッシュという解釈だけではないのであります。
たった一つのトリトヌスに5つの音を嵌当する事でモード想起を図るのは、和音の響きに対して「線を欲しがる」からであります。とはいえ、先の「El Becko」でのFm7(♭5)上で、ヘプタトニックな組織が全て経過的にでも表れている訳ではないのです。それなのになぜモード想起を朧げながらも感じていたいのか!?というと、線としての拡大が予期せぬほど突拍子も無い調域の方へ拡大させたくない狙いがあるからでありましょう。つまり、Fm7(♭5)→B♭7またはFm7(♭5)→B♭7sus4において、聴き手に対して、これらの2コード・パターンで映じてほしい世界観(調性感を裏切らない程度の嘯き)を伴わせたいが故の事でありましょう。それらを一旦構築してからコード進行は他の調域に歩を進めようとするのでありまして。
トリスタン和音を「不等四度」音程の和音として見立てて、多くの複調的なモード想起も可能なのでありますが、ジャズが形骸化しているのはトリトヌスに対して5つの音を嵌当してしまう事で、その和音に対して容易くヘプタトニック組織を想起する事で、結果的に和音の体と横の線がヘプタトニックというモノで調的世界観を容易く埋め切って飽和してしまう為、それを和音進行の目紛しさで目くらまししているだけに過ぎず、一つの和音に対して一つの調域しか見れなくなってしまっている事が、近視眼的なジャズ理論の理解にしか伴っていないような者でも「なんちゃって」なジャズを体系に凭れ掛かって操る事が出来てしまっている悲哀なる側面を生んでいるのが現今のジャズなのであります。
複調性というのはメンバーがインプロヴァイズで勝手に他の調性に行く様なら返って不味いワケですよ。誰か一人が逸脱するだけで根幹が据わっているならまだしも。ですからこの手の世界観が構築されるのは、下僕共に延々単一的な調性の世界観でのリフを奏させておいて、自身が逸脱するか(晩年のマイルス)、皆が勝手にインプロヴァイズしてしまったらあらゆる調域がバラバラになりかねず結果的に垂直的な複調感を容易く得られるのはピアノ奏者に依る潤沢な和声感にて構築させるか位のものになってしまい、後は予定調和として複調を予め計画しておかないとなかなかそうした世界観を統率できないのがジャズのネックとなっている部分なのです。
ところが、ジャズもsus4化、ポリ・コード化させる事によってドミナント7thコードそのものの勾配が稀釈化して、横の複調感が出て来ます。これに気が利くパートは本位十一度の音を下支えとして奏してくれるので、複調感が増す背景にソロ奏者が更に気を利かせた逸脱した線を奏でる事も可能となるワケです。
そうすると、調的社会がトニックへ解決するという「成就」という図式はそれほど必要なモノではなく、起承転結の「結び」が要らない、要所要所で楽しんでいれば十分という静的な空間で音楽を嗜む世界観が登場するワケです。そうすると、本位十一度を下支えする和声的空間はもっと稀釈化され、3度堆積型の和音ですら調的な成分を示すため、この辺りが稀釈化する事でポリ・コードから、分子構造がもっとマトリクスな組み合わせと呼べるに相応しい和音のハイブリッド化とマトリクス化が進むワケです。
とはいえ、ドミナント7thコードが次の全音階的勾配を求める動的な振る舞いとは別に、稀釈化する「静的」なそれはまだまだほんの序の口であるのも事実。
ドミナント7thを包含する、或いはトリトヌスを包含する不協和音とやらが、その対称的・均齊的な枝葉を伴って、その触手にはオクターヴを等分割する音程を伴った体をさらに結び付けようとします。その等しい分割は、トリトヌスという半オクターヴは勿論、長三度等音程分割(増三和音の骨格)、短三度等音程(減七和音の骨格)、半音階、四全音、二全音、五全音+2半音やら、等分平均律に依拠する微分音の骨格やらも枝葉に付ける様に多様な構造となっていくのでありますが、今回述べているドミナント7thコードはあくまで、本来の動的な機能とそれが稀釈化する静的な方面を語っているのみである事もあらためて注意してもらいたい所です。コードネームにすら記す事のできない微分音をまとった和声空間を今茲で述べてしまうのは余りに早計でありましょう(笑)。
但し、不協和音で満たされた音空間で音がそれぞれ「粒」として溶けている様な状況を想像してもらうとして、そこから「粒」をそれぞれ任意に抽出して組み合わせた時には、調性社会を遵守していた時のそれとは趣の異なる和音を得られるという風に考えてみましょう。仮に「2コード・パターン」として記す事ができたとしても、それら2つの和音夫々の構成音が溶け込んでいる状況を考えてもらいたいワケです。すると、その2コードとは、協和⇆不協和というメリハリを付けるだけでメリハリ感が生じ、このメリハリはごく簡単な「勾配」でもありますが、その勾配が調的な世界の道順で描かれるコースとは違うだけの事なのです。
例えば、メロディック・マイナー・スケールをダイアトニック・スケールと考えて、その音階上に出来るダイアトニック・コードを列挙すると、IV度上とV度上で2つのドミナント7thコードを生む事になります。IV度上に現れる「ドミナント」とはけしからん!と思うかもしれませんが(笑)、ドミナント7thコードという和音の体は、V度の位置以外で副次的に発生しようとも和音の有り体の名前はドミナント7thコードと呼ぶのでありまして、この辺ばかりに拘っているようでは、今回私が述べている事を何一つ理解できない事でありましょう(笑)。
扨て、メロディック・マイナーを全音階組織とするダイアトニック・コードでIV7はどう扱えばイイのか!?これは私のブログでも過去に少し述べている事です。ドミナント7thコードが常に四度進行という勾配を欲しているだけの物ならば、この体系でのIV7は行き場を失います。III度は実際は♭IIIですし、四度進行先のVII度は♭VIIではありません。
こうした時のIV7という和音の有り体が稀釈化すれば良いのです。最も容易に考えが及ぶのは本位11度音附与かもしれませんが、残念な事にメロディック・マイナー体系でのIV度上の11度は増11度である必要性があるため、和音の有り体としての稀釈化は、ドミナント7th+本位十一度のタイプとは別の体系を考える必要性が生じます。
そこで、基底和音を稀釈化します。メロディック・マイナーを全音階組織としてIV度に生ずる四声体の和音はF7。この基底和音は七度音を除いたF△。つまりこれを稀釈化するのは3度音と5度音を省く。さらに七度音から不足分の2音を3度ずつメロディック・マイナーのダイアトニック列で積み上げる。すると、基底和音は単音のベース音=F音となり、上部にE♭、G、Bという風にEaugという増三和音を形成することになります。つまりコードとしては
「E♭aug (on F)」という風になった訳です。こうすることで「ImM7 → E♭aug (on F)」とやると非常に味わい深くなるのですが、各々のコードのメリハリを出す為に、最初の「I」のコードではドリアンを想起して、♭III on IVの所で♭IIIのリディアン・オーギュメントを想起するととてもメリハリが付くのです。

※「A Presa」のイントロ部のコード解釈=A♭M7aug (on B♭)というのは、実際にはオルタード・テンションを纏った「B♭7(9、♯11、13)」の断片です。
これらの例から言いたい事は、ドミナント7thコードは本位11度を持つ事で複調化の到来により和音の体系がシンプル化して分数コード化を招く様になっているのが現今の音楽シーンであり、ドミナント7thコードが必ずしも進行感を強める為に勾配を付けて使用されているものばかりではない、という事があらためて判ります。短調組織においてですら、導音の性格を中性化させて「V7」がエオリア調の「Vm」のままという事も珍しくはありません。
— 左近治 (@sakonosamu) 2017年2月26日
近視眼的ジャズ的アプローチからすれば、ドミナント7thコード上では多くのオルタード・テンションを示唆するので、それこそ半音階を満たさんばかりの音を使用できる音脈がありますが、これとて、和音の有り体を維持したいが為に、ドミナント7thコードが本来持っている勾配は同主調であれば行き先のトニックがトニック・マイナーであるかトニック・メジャーであるか、ジャズ的な勾配からすれば行き先のそれはメジャーもマイナーも双方が混淆としている世界観を意味する物から依拠しているのがオルタード・テンションとして一緒くたに取り扱える体系なのであります。且つ本位11度音を和音の有り体の為に避けて増11度化させているので和音の振る舞いとしての音楽的な使用可能なスペースが増えるのであり、短調組織と長調組織由来でのテンション・ノートを一括りにした事からオルタード・テンションというのは音脈として使える様に到っているのであります。
ですからその様な体系に有り難がっているだけの人からすれば、オルタード・テンションをドミナント7thコード上でふんだんに使えば、恰も半音階的動作をこなしているかの様に聴かせる事が可能なワケですが、ドミナント7thコードの有り体がどんどん稀釈化されている現状において、今度はどうやってオルタード・テンションを有り難がろうとするのか!?と問うてみたくなりますな(笑)。単にポリコードの体に形を変えたり、sus4などの体に形を変えた時に、勾配を強める仕来りの音脈ばかり使っていては唾棄すべき行為でありましょう(笑)。
しかも、音楽的な和声空間の発展は間違い無く西洋音楽やジャズ/ポピュラー問わずポリ・コード(分数コード)&複調化が著しくなっているのが現実です。
例えば、先のアジムスの「A Presa」で出て来たA♭M7aug (on B♭)は、ドミナント7thコード体系に慣れ切ってしまった人間から見たら、B♭7(9、#11、13)のM3rdとP5thがオミットされた物として映ずるかもしれません。これじゃあ駄目なのです。基底和音としてB♭△はおろかB♭7を示唆する体として在って欲しくないが故にA♭M7aug (on B♭)の姿で振る舞う必要があるのですが、それをドミナント7th系統の解釈でアプローチの選択を採るのであれば、それは結果的に勾配を強めるだけで複調性すら踏み躙る事に等しいのであります。
更に、減八度「的」音脈を最も得易い体系として、短調に於ける「V7/♭VI」という和音を使う時があります。ハ短調ならば「G7/A♭」という分数コードです。仮にG7の方にE音を付与してしまう様な音を使ってしまったら、体としてはE7(#9)系列の3度ベースに見てしまうかもしれませんし、この手の例に限らずドミナント7thの体に慣れ切ってしまった人というのはその「勾配」がドミナント7thに付与する体系を見抜きやすいのでありますが、これを中和化させない限り、複調性の感覚が養われる事はありません。この点を最も注意しなくてはいけないでしょう。


抑も、先のコードは何らかの1音を映じてしまう事で、何らかのドミナント7thコード体系を見付けてしまう状況であります。しかし、それを判った上で作曲者が和音を提示しているにも関わらず、「G7/A♭」にてE7(#9)系統のアプローチを採られた日にゃ掌底の2、3発じゃ済まない事でありましょう。「G7/A♭」から「B」へ進んでしまえば、これはG7からの半音階的偽終止進行ではなくE7由来の勾配を示唆する物とは思えるでしょうが、「G7/A♭」で稀釈化させてCに進んだり、或いはG7/A♭が静的な茫洋とした形である事すら珍しくはないのです。
どうしても耳が勾配付けを伴ってしまうタイプの人は、つまり、熟達に足りないと言えるのであります。ですので、こうした音感を持ってしまっている人が、ジャズの体系を存分に堪能していたとしても、モード・ジャズとなると途端に駄目になるかと思います。そういうモンなんですね、現実は。勾配ジャズですか。せめて有り難がってくらはいな(笑)。軈ては、此の世に明治生まれの人が居なくなってしまう頃にはそんなジャズは過去の遺作としてでしか耳にされない様になるのは目に見える様でもあります。
2014-06-26 02:00



