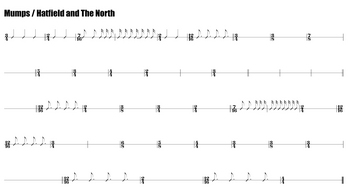胎児の夢/佐井好子 [クロスオーバー]
5〜6年くらい前にKクリでケータイサイトのショート・コメントでチラッと語った事があったような記憶のある佐井好子。アルバム「胎児の夢」は名盤なのでありますが、私が一番最初に耳にしたのは久保田早紀の「異邦人」がヒットしている最中の頃、叔父貴が「オマエはコレを聴け!」と差し出されたアルバムが「胎児の夢」。

夢にまで出て来ちゃいそうなアルバムのジャケに圧倒され、後に石川鷹彦はもちろん、今やルパン関連で有名な大野雄二が参加していたことに驚くことになるんですが、当時はカセットに録音したモノでしか持っていなかったんですね。数年前にようやくCDで入手したんですが。
当時は、アコースティック・ギターにも少々興味を抱いていた頃の左近治。当時の物欲のそそるものはというと、
・ウォークマン(初期型)
・シンセ
まあ、シンセなんてなんでも良くて、ポータサウンドがありゃイイか!みたいな(笑)、当時、対面座席の電車の中で弾くポータサウンドのCMシーンを見ながら、汚れの知らぬ青ッ鼻垂らした朴訥な少年(汚れていましたが)は、ドラム興味を示そうとも(左近治の当時のメイン楽器はドラム)、和声への欲求が高まっていた時代だったんでしょうなあ。
それで、アリスの「秋止符」を弾きたくなり、叔父貴から古いアコギを譲ってもらうことになり、「センイチ」買って、当時自分のギターで弾いてみたい曲などを色々練習してみた頃もあったという当時。1980〜81年頃でしたでしょうか。
んでまあ、拙い指使いながらもギターをどうにか弾けるようになった所で叔父貴が持って来たレコードが佐井好子の「胎児の夢」だったというワケであります。
ジャケのあまりのインパクトに及び腰になって(笑)、心の片隅には「不気味で聴きたくねーなー」なんて思っていたんですが、ついついその音楽性の高さに引き込まれてしまったのでありました。正直、プログレ耳としても十分聴くことができます(笑)。
色んなプログレ好きが集まるような所ではやはり佐井好子を好む人間に多く出会ってきたワケで、あらためて佐井好子とはプログレ度も高い作品なのだとあらためて認識させられたワケですが、キャラヴァンやカンタベリー系が好きなタイプの人でなくともすぐに食い付けるような気がします。
当時は「大貫妙子より絶対イイから聴いてみろ!」って叔父貴に言われて聴かされたんですなあ(笑)。
で、左近治も自分の好きな楽曲を制作する上で、初心に返る意味でも当時作ろうとしていた曲を今一度作ろうかなと思い、楽理面の解説でもリンクしていくことになる関連作品を取り上げつつ、そろそろ佐井好子の出番だな、と思うようになったワケです。
数年前にはリリースの可否すら不透明で、権利関係片っ端から事務局に問い合わせたコトもあったんですな、実は(笑)。「佐井好子の着メロなんてそうそうねーだろ」みたいな心意気で(笑)。
今やiTunes Storeでも取り扱っていて、レコードすら探すのに難しかった佐井好子のアルバムが、こうも簡単に入手できるようになったとは、本当に隔世の感を覚える左近治であります。
「青いガラス玉」
「遍路」
この2曲、もし佐井好子をご存知でなく、興味がある方は是非とも聴いていただきたい2曲です。アルバム全編素晴らしい曲ですけどね。「青いガラス玉」のリード・ギターなんてモロにフィル・ミラーだろ!と思わせるような音(笑)。
70年代中後期辺りの日本のスタジオ界というのは結構カンタベリー系の音に出会うことが多いので今のJ-POP界隈(笑)よりもよほど聴く価値があったかと思います。
かくいう日本でも77〜80年頃はクロスオーバー・ブームがありました。でもジャズ/フュージョン界ではインプロヴィゼーションが求められるワケで、うだつのあがらないソロを延々弾くよりも、カンタベリー系のような緻密に計算された世界の方がバランスが取れていたりする、と。そういうバランスの良さも受け入れられやすいのがカンタベリー系だったのではないかと思うんですな。
そんな影響がさらに歌謡界でのモンド化が顕著になってゆく、という時代。あらためて昔は良かったと思うものであります(笑)。

夢にまで出て来ちゃいそうなアルバムのジャケに圧倒され、後に石川鷹彦はもちろん、今やルパン関連で有名な大野雄二が参加していたことに驚くことになるんですが、当時はカセットに録音したモノでしか持っていなかったんですね。数年前にようやくCDで入手したんですが。
当時は、アコースティック・ギターにも少々興味を抱いていた頃の左近治。当時の物欲のそそるものはというと、
・ウォークマン(初期型)
・シンセ
まあ、シンセなんてなんでも良くて、ポータサウンドがありゃイイか!みたいな(笑)、当時、対面座席の電車の中で弾くポータサウンドのCMシーンを見ながら、汚れの知らぬ青ッ鼻垂らした朴訥な少年(汚れていましたが)は、ドラム興味を示そうとも(左近治の当時のメイン楽器はドラム)、和声への欲求が高まっていた時代だったんでしょうなあ。
それで、アリスの「秋止符」を弾きたくなり、叔父貴から古いアコギを譲ってもらうことになり、「センイチ」買って、当時自分のギターで弾いてみたい曲などを色々練習してみた頃もあったという当時。1980〜81年頃でしたでしょうか。
んでまあ、拙い指使いながらもギターをどうにか弾けるようになった所で叔父貴が持って来たレコードが佐井好子の「胎児の夢」だったというワケであります。
ジャケのあまりのインパクトに及び腰になって(笑)、心の片隅には「不気味で聴きたくねーなー」なんて思っていたんですが、ついついその音楽性の高さに引き込まれてしまったのでありました。正直、プログレ耳としても十分聴くことができます(笑)。
色んなプログレ好きが集まるような所ではやはり佐井好子を好む人間に多く出会ってきたワケで、あらためて佐井好子とはプログレ度も高い作品なのだとあらためて認識させられたワケですが、キャラヴァンやカンタベリー系が好きなタイプの人でなくともすぐに食い付けるような気がします。
当時は「大貫妙子より絶対イイから聴いてみろ!」って叔父貴に言われて聴かされたんですなあ(笑)。
で、左近治も自分の好きな楽曲を制作する上で、初心に返る意味でも当時作ろうとしていた曲を今一度作ろうかなと思い、楽理面の解説でもリンクしていくことになる関連作品を取り上げつつ、そろそろ佐井好子の出番だな、と思うようになったワケです。
数年前にはリリースの可否すら不透明で、権利関係片っ端から事務局に問い合わせたコトもあったんですな、実は(笑)。「佐井好子の着メロなんてそうそうねーだろ」みたいな心意気で(笑)。
今やiTunes Storeでも取り扱っていて、レコードすら探すのに難しかった佐井好子のアルバムが、こうも簡単に入手できるようになったとは、本当に隔世の感を覚える左近治であります。
「青いガラス玉」
「遍路」
この2曲、もし佐井好子をご存知でなく、興味がある方は是非とも聴いていただきたい2曲です。アルバム全編素晴らしい曲ですけどね。「青いガラス玉」のリード・ギターなんてモロにフィル・ミラーだろ!と思わせるような音(笑)。
70年代中後期辺りの日本のスタジオ界というのは結構カンタベリー系の音に出会うことが多いので今のJ-POP界隈(笑)よりもよほど聴く価値があったかと思います。
かくいう日本でも77〜80年頃はクロスオーバー・ブームがありました。でもジャズ/フュージョン界ではインプロヴィゼーションが求められるワケで、うだつのあがらないソロを延々弾くよりも、カンタベリー系のような緻密に計算された世界の方がバランスが取れていたりする、と。そういうバランスの良さも受け入れられやすいのがカンタベリー系だったのではないかと思うんですな。
そんな影響がさらに歌謡界でのモンド化が顕著になってゆく、という時代。あらためて昔は良かったと思うものであります(笑)。
2008-11-07 15:00
なんちゃってアラン・ホールズワース [クロスオーバー]
10月24日にKクリリリースの「EFX43」について解説します。
ついつい左近治は今回、ホールズワースっぽい曲を作ってしまったのでありますが、以前にもブログ用のサンプル曲でホールズワースっぽい曲を作ったことがありましたね。
まあ、あの後にとりあえずKクリリリース用にホールズワースっぽい曲でも作ってみるか!となりまして、今回のリリースにつなげたというワケであります。EFX42はEFX43のギター・パートの無いバージョン。すなわちマイナス・ワンですな(笑)。
ゲイリー・ハズバンド、ジミー・ジョンソンというメンバーを彷彿とさせるようなイメージを抱いて作ってみたんですけどね(笑)。
ただ、実際にはホールズワースというよりも、スコット・ヘンダーソンっぽい音になりました(笑)。
過去にKYLYNの「Sonic Boom」をリリースする際、スネアの音が低ビットレート配信用で音が破綻してしまった反省も踏まえ、今回のドラムサウンドは低ビットレートでも破綻しないように努めました。
というのも夏場にリリースした時から結構間を置いてしまったので、その反省期間があまりにも月日を要したのではないのでありますが(笑)、いくら制作サイドが反省しようとも聴き手となる顧客の方々の大半は、小難しい理屈抜きにして音が気に入る or NOTで判断されると思うのですが、私のブログに書き連ねる事は、講釈たれるか弁明にすぎないかもしれませんが(笑)、in depthな部分を語っていこうと思っておりますのでご容赦を。
テスト的な意味合いもあるワケですが、ケータイはファイルサイズ制限はある上に、オーディオストリーミングなど非常に高いビットレートで配信しようものならケータイのインフラの再編成すら必要になってしまう(笑)。まあ次世代のケータイインフラは避けて通れないのも事実でしょうが、現実としては全ての端末に等しいサービスではなく端末ごとにファイルサイズ制限があったりする訳で。この制限下で原曲の尺を稼ごうとしてしまえばビットレートを落とさざるを得ない、というワケですね。
配信モノ全てが悪いのではないんですが、低いビットレートでコーデックによっては非常に粗悪なモノになってしまうのも正直あるワケで(笑)、こーゆー事態に遭遇しても大丈夫なような音作りや一定のミックスというのはやはり難しいものがあります。
自分が作っているものだからこそ、自分なりの音のクセや好みが音となって反映されてしまうのは仕方ないといいますか、これを長所にしなくてはならないワケですが、音そのものが着信音向けになったとしても、楽曲の持つハーモニーなどが童謡よりも幼いレベルの音楽を作ろうとは思いませんので、好みが反映されるとはまずこういう所でしょうか。
まあ、うまいことコーデックの圧縮具合になじむように、持続音系と減衰系を織り交ぜながら、左近治の好むような和声の世界を手っ取り早く作ってみたというワケです。
今回はEFX43のギター・パートのスコアを載せておきますので、ギター小僧の方はヒマがあったら弾いてみてください(笑)。ご自分でこのフレーズをbpm90くらいでフレーズの「歌心」を味わっていただければ幸いです。速いパッセージだと「歌心」をつかむ前に音が通り過ぎるような聞き方になってしまう方もいると思うので、遅いbpmから耳を慣らしていただければな、と。

ついつい左近治は今回、ホールズワースっぽい曲を作ってしまったのでありますが、以前にもブログ用のサンプル曲でホールズワースっぽい曲を作ったことがありましたね。
まあ、あの後にとりあえずKクリリリース用にホールズワースっぽい曲でも作ってみるか!となりまして、今回のリリースにつなげたというワケであります。EFX42はEFX43のギター・パートの無いバージョン。すなわちマイナス・ワンですな(笑)。
ゲイリー・ハズバンド、ジミー・ジョンソンというメンバーを彷彿とさせるようなイメージを抱いて作ってみたんですけどね(笑)。
ただ、実際にはホールズワースというよりも、スコット・ヘンダーソンっぽい音になりました(笑)。
過去にKYLYNの「Sonic Boom」をリリースする際、スネアの音が低ビットレート配信用で音が破綻してしまった反省も踏まえ、今回のドラムサウンドは低ビットレートでも破綻しないように努めました。
というのも夏場にリリースした時から結構間を置いてしまったので、その反省期間があまりにも月日を要したのではないのでありますが(笑)、いくら制作サイドが反省しようとも聴き手となる顧客の方々の大半は、小難しい理屈抜きにして音が気に入る or NOTで判断されると思うのですが、私のブログに書き連ねる事は、講釈たれるか弁明にすぎないかもしれませんが(笑)、in depthな部分を語っていこうと思っておりますのでご容赦を。
テスト的な意味合いもあるワケですが、ケータイはファイルサイズ制限はある上に、オーディオストリーミングなど非常に高いビットレートで配信しようものならケータイのインフラの再編成すら必要になってしまう(笑)。まあ次世代のケータイインフラは避けて通れないのも事実でしょうが、現実としては全ての端末に等しいサービスではなく端末ごとにファイルサイズ制限があったりする訳で。この制限下で原曲の尺を稼ごうとしてしまえばビットレートを落とさざるを得ない、というワケですね。
配信モノ全てが悪いのではないんですが、低いビットレートでコーデックによっては非常に粗悪なモノになってしまうのも正直あるワケで(笑)、こーゆー事態に遭遇しても大丈夫なような音作りや一定のミックスというのはやはり難しいものがあります。
自分が作っているものだからこそ、自分なりの音のクセや好みが音となって反映されてしまうのは仕方ないといいますか、これを長所にしなくてはならないワケですが、音そのものが着信音向けになったとしても、楽曲の持つハーモニーなどが童謡よりも幼いレベルの音楽を作ろうとは思いませんので、好みが反映されるとはまずこういう所でしょうか。
まあ、うまいことコーデックの圧縮具合になじむように、持続音系と減衰系を織り交ぜながら、左近治の好むような和声の世界を手っ取り早く作ってみたというワケです。
今回はEFX43のギター・パートのスコアを載せておきますので、ギター小僧の方はヒマがあったら弾いてみてください(笑)。ご自分でこのフレーズをbpm90くらいでフレーズの「歌心」を味わっていただければ幸いです。速いパッセージだと「歌心」をつかむ前に音が通り過ぎるような聞き方になってしまう方もいると思うので、遅いbpmから耳を慣らしていただければな、と。

2008-10-24 13:00
ローズ名演 [クロスオーバー]
今思えばDX7が席巻していた時代とは何だったのかと自問自答してしまうほどDXサウンドは廃れ、エレピといえばいまだにローズが席巻している現在。
ウーリッツァーの立場を無視するな!という声もあるのは勿論判っておりますが、ローズのそれとはやはり数馬身以上の差は付けられているのが実情でありましょう。無論、ウーリの魅力もありますが。
DX7が練習スタジオに常備されるような時代の前というのは、普通にローズやCPがスタジオには勿論、ライヴハウスにもあったモンです。ただ、普通の練習スタジオに常備されている機材の多く(アンプ関連)というのは、破損防止のために概ねアッテネータ噛ませていたりするものが多く、ツマミ上ではフルテン刻んでいても実際にはそんな設定が出ないようになっているモノが多いのであります。全部が全部そうではないんですけどね。
車で言えばリミッター噛まされて180km/h出ないようにされているのと同じ。リミッター解除されてないと突然「ググッ」と引っ張られたような挙動になりますよね(つーか、よいこのみんなは公道で確認しちゃダメですよ)。
スタジオのアンプ類の大半もそういう風に手を施しているのが実はあるんですな。それでもゲインを稼ごうとすると後段のゲインが稼げない設計になっているためか、プリ部のゲイン弄るのと等しくなって歪みが増す、と。これはギター&ベースのアンプに限らず、キーボードやらボーカル類のためのパワードミキサーにも同様のコトが言えます。
んで、普通のシンセをブチ込んでもアッテネータ噛まされてりゃ出音は結局抑え込まれ音量は稼げない。それでも稼ごうとして音が歪むとなると、ローズなんてぇのはモロにブーミーになって嫌悪されやすい、と。
それでも尚使いこなせるようなアンサンブルの音を重視するバンドであれば、その手の練習スタジオにおいてもローズの特徴を活かした音を使いこなしていたでありましょうが、大半は使いこなせず、当時の音楽シーンからは蔑ろにされやすい「イナタい音」として嫌悪されていたのが実情ではなかったでしょうか。
DX7ですらまともな音を出せずに、ウブの素人でも「とりあえず」心満たせる音をシンセで出せるようになってきたのはM1がリリースされて練習スタジオに常備されるようになってからではないでしょうか。それでも使いこなせない人がいて、そんな人達を満足させられるレベルになってきたのは01Wの出現を待たねばならなかったというのが真相ではないかと。
エレピの醍醐味と言っても、ハウスやらスムース・ジャズ畑で重用されるローズの音というものは、透き通るような高域とコーラスをかけたリチャード・ティー系のサウンドだったりします。加えて、ローズの音はそれ系じゃないとNG!タイプという人の多くはだいたいローズ慣れしていないタイプの人が多いように思えます。あくまでも私が見てきた感想ですが。
ローズの深みを知れば知るほど、その手の音よりも、本来の少々ブーミーでエグみの強い若干歪んだような音を好むと思うんですが、この手のイナタいローズの音の曲をたまには作らないとなぁと思い、「Tenemos Roads」の進捗状況は遅々として進まず(笑)、またまた最近浮気をしていた曲があったんですね。
下記の曲は、いずれ私がリリースするだろうと思われる作品であります。
Diamond Dust / Jeff Beck
Foxtrot / Spyro Gyra
Sophie / Jeff Beck
Miles Beyond / The Mahavishnu Orchestra
First Class Vagabond / Hiram Bullock
Underdub / Hatfield and the North
A Creature of Many Faces / The Brecker Brothers
Same Old Same Old / The Section(←コレ、追加です。なんで書き忘れちゃってたんだろ?)
これらの中でも「A Creature of Many Faces」はブレッカー・ブラザーズの中でもかなり好きな曲のひとつでもあり、実際にもう作っている最中なのでありますが、先頃集中的に語っていた「ベッカー・サウンド」をさらに強くしたような和声の世界観を有しているのがブレッカー・ブラザーズと思っていただいて差し支えないと思います(笑)。
まあ、音を味覚に例えるとしたらベッカーの音は「ピクルス」で、ブレッカー・ブラザーズのそれは「らっきょう」や「わさび漬け」みたいなモノ(笑)。
余談ですが、ブレッカー・ブラザーズにおいてはインプロヴィゼーションに関してはマイケルの方が極めて秀でていると思いますが、コンポージング能力においては兄のランディの方がマイケルよりも秀でていると私は思います。
ところで上記の曲は私の好きなローズの曲をただ単に列挙したのではなく、エグさがあって、独特の箱鳴り系の「ポコ感」がオイシイ音を吟味できるという意味で挙げております。ヤン・ハマーの場合、ローズは透き通った音とは対局的なブーミーなエグい音を好むタイプだと思われますが、マックス・ミドルトンもやはりそのタイプだと思います。
ジョー・サンプルが出てこないやん!と思われる方も居るとは思いますが(笑)、ジョー・サンプルの曲でも実は育んでいる曲が1つあるのでいずれリリースするかもしれません。70〜80年代ではなく比較的近年の90年代の某曲なんですけどね。
ウーリッツァーの立場を無視するな!という声もあるのは勿論判っておりますが、ローズのそれとはやはり数馬身以上の差は付けられているのが実情でありましょう。無論、ウーリの魅力もありますが。
DX7が練習スタジオに常備されるような時代の前というのは、普通にローズやCPがスタジオには勿論、ライヴハウスにもあったモンです。ただ、普通の練習スタジオに常備されている機材の多く(アンプ関連)というのは、破損防止のために概ねアッテネータ噛ませていたりするものが多く、ツマミ上ではフルテン刻んでいても実際にはそんな設定が出ないようになっているモノが多いのであります。全部が全部そうではないんですけどね。
車で言えばリミッター噛まされて180km/h出ないようにされているのと同じ。リミッター解除されてないと突然「ググッ」と引っ張られたような挙動になりますよね(つーか、よいこのみんなは公道で確認しちゃダメですよ)。
スタジオのアンプ類の大半もそういう風に手を施しているのが実はあるんですな。それでもゲインを稼ごうとすると後段のゲインが稼げない設計になっているためか、プリ部のゲイン弄るのと等しくなって歪みが増す、と。これはギター&ベースのアンプに限らず、キーボードやらボーカル類のためのパワードミキサーにも同様のコトが言えます。
んで、普通のシンセをブチ込んでもアッテネータ噛まされてりゃ出音は結局抑え込まれ音量は稼げない。それでも稼ごうとして音が歪むとなると、ローズなんてぇのはモロにブーミーになって嫌悪されやすい、と。
それでも尚使いこなせるようなアンサンブルの音を重視するバンドであれば、その手の練習スタジオにおいてもローズの特徴を活かした音を使いこなしていたでありましょうが、大半は使いこなせず、当時の音楽シーンからは蔑ろにされやすい「イナタい音」として嫌悪されていたのが実情ではなかったでしょうか。
DX7ですらまともな音を出せずに、ウブの素人でも「とりあえず」心満たせる音をシンセで出せるようになってきたのはM1がリリースされて練習スタジオに常備されるようになってからではないでしょうか。それでも使いこなせない人がいて、そんな人達を満足させられるレベルになってきたのは01Wの出現を待たねばならなかったというのが真相ではないかと。
エレピの醍醐味と言っても、ハウスやらスムース・ジャズ畑で重用されるローズの音というものは、透き通るような高域とコーラスをかけたリチャード・ティー系のサウンドだったりします。加えて、ローズの音はそれ系じゃないとNG!タイプという人の多くはだいたいローズ慣れしていないタイプの人が多いように思えます。あくまでも私が見てきた感想ですが。
ローズの深みを知れば知るほど、その手の音よりも、本来の少々ブーミーでエグみの強い若干歪んだような音を好むと思うんですが、この手のイナタいローズの音の曲をたまには作らないとなぁと思い、「Tenemos Roads」の進捗状況は遅々として進まず(笑)、またまた最近浮気をしていた曲があったんですね。
下記の曲は、いずれ私がリリースするだろうと思われる作品であります。
Diamond Dust / Jeff Beck
Foxtrot / Spyro Gyra
Sophie / Jeff Beck
Miles Beyond / The Mahavishnu Orchestra
First Class Vagabond / Hiram Bullock
Underdub / Hatfield and the North
A Creature of Many Faces / The Brecker Brothers
Same Old Same Old / The Section(←コレ、追加です。なんで書き忘れちゃってたんだろ?)
これらの中でも「A Creature of Many Faces」はブレッカー・ブラザーズの中でもかなり好きな曲のひとつでもあり、実際にもう作っている最中なのでありますが、先頃集中的に語っていた「ベッカー・サウンド」をさらに強くしたような和声の世界観を有しているのがブレッカー・ブラザーズと思っていただいて差し支えないと思います(笑)。
まあ、音を味覚に例えるとしたらベッカーの音は「ピクルス」で、ブレッカー・ブラザーズのそれは「らっきょう」や「わさび漬け」みたいなモノ(笑)。
余談ですが、ブレッカー・ブラザーズにおいてはインプロヴィゼーションに関してはマイケルの方が極めて秀でていると思いますが、コンポージング能力においては兄のランディの方がマイケルよりも秀でていると私は思います。
ところで上記の曲は私の好きなローズの曲をただ単に列挙したのではなく、エグさがあって、独特の箱鳴り系の「ポコ感」がオイシイ音を吟味できるという意味で挙げております。ヤン・ハマーの場合、ローズは透き通った音とは対局的なブーミーなエグい音を好むタイプだと思われますが、マックス・ミドルトンもやはりそのタイプだと思います。
ジョー・サンプルが出てこないやん!と思われる方も居るとは思いますが(笑)、ジョー・サンプルの曲でも実は育んでいる曲が1つあるのでいずれリリースするかもしれません。70〜80年代ではなく比較的近年の90年代の某曲なんですけどね。
2008-10-18 02:00
リチャード・アルダーソンのミックス [クロスオーバー]
さて、本日はKクリにて2曲リリースされるワケでありますが、その内の1曲「Making Love To You」について。
この曲はグローヴァー・ワシントンJrのソロ・アルバム「Come Morning」収録のモノでして、国内のiTunes Storeでも購入することが可能となっておりますね。
グローヴァー・ワシントンJrと言えば本作の前のアルバム「ワインライト」がお化けヒットとなったため、本作「Come Morning」は全体的にマニア好みっぽく陰鬱な感じをより強く出しているため、セールス的にはそれほどでもなかったと記憶しておりますが、リチャード・アルダーソンの手掛けるこのアルバムの音は実に聴いていて心地よいんですな。特にニーヴ・サウンドが好きな方なら、その音だけでも酔える!と言えるくらいの深みのある音です。また、アルバム全体においてスローな曲が多いので各プレイヤーの一音一音を聴いてミックスの勉強になること間違いなしでありましょう(笑)。少なくとも左近治はこのアルバムはミックスのお手本にしているアルバムのひとつであります。
ベースはマーカス・ミラーなんですが、大抵マーカス君というのはスラップがもてはやされる人なので、指弾きとなるとスラップ全面に押し出した曲の合間の指弾きだと概ね埋もれているタイプの曲が多かったりするんですが(それでも多くのドンシャリタイプのスラップ系ベーシストと比較すれば、マーカスのそれは音程感が豊かな指弾きサウンドを満たしている方だとは思います)、この曲のマーカス・ミラーの音は理想的な音のひとつと言えるでしょう。
左近治が好きなマーカス・サウンドというのは数少ないながらも(笑)、このアルバムのマーカス・ミラーと「ささやくシルエット」、初期〜中期の頃のデイヴ・ヴァレンティンの「Land of the Third Eye」の音は私に取っては三つ巴サウンドと呼べるかもしれません。
アンプ・ミックスをしていると思われますが、ゴリ感の残る、それでいてスラップの音の特徴も踏襲しているというイイ所取りの音のひとつとも言えるでしょう。
また、ガッドのハットとリム・ショットの巧みなEQとコンプの処理具合は、この曲と次の曲「I'm All Yours」を利き比べると、スネアとハットの処理加減の違いが非常にタメになると思います。
「I'm All Yours」の方はかなり前にイントロ部を着うたでリリースしたコトもありますが、ミックスの妙を聴きたい方は是非とも原曲の2曲を聴き比べてみることをオススメします。「同じアルバムなのに全く違う音」というワケではありません。素人耳で聴けば違いは判らないかもしれません(笑)。
まあ、それくらい雰囲気を踏襲しながら曲によってミックスを使い分けているという妙味が知れるというシロモノだというコトを知っていただければな、と思う作品なのであります。
前作の「ワインライト」において左近治が最も好きな曲というか、ミックスの勉強になるのは、ロバータ・フラックも別アルバムにて自身のソロ・アルバムで歌詞を付けたバージョンを謳っておりますが「In The Name of Love」のフルアコ・ギターの距離感など、非常に勉強になります。ミックスにおいてロバータ・フラックの方は無関係ですけどね(笑)。
ミックスを学ぶなら「ワインライト」よりも「Come Morning」だろ!と念押ししちゃいます(笑)。「ワインライト」が日本人受けするようなソニーの音と形容するならば、「Come Morning」はマランツの音、みたいな(笑)。「ワインライト」は中域のスポイルされた部分が「Come Morning」より強く感じるので。
ともあれ、本日リリースするこの曲は本来7月にはリリースするはずだったんですね(笑)。もう季節変わってしまいました!本来ならこのブログも7月の時点で読む事ができたはずだったという、如何に左近治がマイペースなのかというのもあらためて知ることが出来ましょう。巷じゃポニョポニョ唄っている辺りの頃だったんですな(笑)。
いくら着うた作っているとはいえ、あの手の誰もがやりそうな曲を作ろうとは思わず(笑)、場合によってはどこかで初音ミクにでも唄わせていたかもしれません(笑)。そんな時流に流されずに未だ1981年の辺りの音に没頭できるというのは我ながら驚いております。ジョン・レノンの死後や「なんとなくクリスタル」が出版された1年後〜15ヶ月後辺りの時代と思っていただければお判りになるでしょうか(笑)。82年に変わろうとする辺りの時代と言いましょうか。生まれていない人だっているかもしれませんが、私が振り返るとこういう見方になってしまうんですなあ。
この曲はグローヴァー・ワシントンJrのソロ・アルバム「Come Morning」収録のモノでして、国内のiTunes Storeでも購入することが可能となっておりますね。
グローヴァー・ワシントンJrと言えば本作の前のアルバム「ワインライト」がお化けヒットとなったため、本作「Come Morning」は全体的にマニア好みっぽく陰鬱な感じをより強く出しているため、セールス的にはそれほどでもなかったと記憶しておりますが、リチャード・アルダーソンの手掛けるこのアルバムの音は実に聴いていて心地よいんですな。特にニーヴ・サウンドが好きな方なら、その音だけでも酔える!と言えるくらいの深みのある音です。また、アルバム全体においてスローな曲が多いので各プレイヤーの一音一音を聴いてミックスの勉強になること間違いなしでありましょう(笑)。少なくとも左近治はこのアルバムはミックスのお手本にしているアルバムのひとつであります。
ベースはマーカス・ミラーなんですが、大抵マーカス君というのはスラップがもてはやされる人なので、指弾きとなるとスラップ全面に押し出した曲の合間の指弾きだと概ね埋もれているタイプの曲が多かったりするんですが(それでも多くのドンシャリタイプのスラップ系ベーシストと比較すれば、マーカスのそれは音程感が豊かな指弾きサウンドを満たしている方だとは思います)、この曲のマーカス・ミラーの音は理想的な音のひとつと言えるでしょう。
左近治が好きなマーカス・サウンドというのは数少ないながらも(笑)、このアルバムのマーカス・ミラーと「ささやくシルエット」、初期〜中期の頃のデイヴ・ヴァレンティンの「Land of the Third Eye」の音は私に取っては三つ巴サウンドと呼べるかもしれません。
アンプ・ミックスをしていると思われますが、ゴリ感の残る、それでいてスラップの音の特徴も踏襲しているというイイ所取りの音のひとつとも言えるでしょう。
また、ガッドのハットとリム・ショットの巧みなEQとコンプの処理具合は、この曲と次の曲「I'm All Yours」を利き比べると、スネアとハットの処理加減の違いが非常にタメになると思います。
「I'm All Yours」の方はかなり前にイントロ部を着うたでリリースしたコトもありますが、ミックスの妙を聴きたい方は是非とも原曲の2曲を聴き比べてみることをオススメします。「同じアルバムなのに全く違う音」というワケではありません。素人耳で聴けば違いは判らないかもしれません(笑)。
まあ、それくらい雰囲気を踏襲しながら曲によってミックスを使い分けているという妙味が知れるというシロモノだというコトを知っていただければな、と思う作品なのであります。
前作の「ワインライト」において左近治が最も好きな曲というか、ミックスの勉強になるのは、ロバータ・フラックも別アルバムにて自身のソロ・アルバムで歌詞を付けたバージョンを謳っておりますが「In The Name of Love」のフルアコ・ギターの距離感など、非常に勉強になります。ミックスにおいてロバータ・フラックの方は無関係ですけどね(笑)。
ミックスを学ぶなら「ワインライト」よりも「Come Morning」だろ!と念押ししちゃいます(笑)。「ワインライト」が日本人受けするようなソニーの音と形容するならば、「Come Morning」はマランツの音、みたいな(笑)。「ワインライト」は中域のスポイルされた部分が「Come Morning」より強く感じるので。
ともあれ、本日リリースするこの曲は本来7月にはリリースするはずだったんですね(笑)。もう季節変わってしまいました!本来ならこのブログも7月の時点で読む事ができたはずだったという、如何に左近治がマイペースなのかというのもあらためて知ることが出来ましょう。巷じゃポニョポニョ唄っている辺りの頃だったんですな(笑)。
いくら着うた作っているとはいえ、あの手の誰もがやりそうな曲を作ろうとは思わず(笑)、場合によってはどこかで初音ミクにでも唄わせていたかもしれません(笑)。そんな時流に流されずに未だ1981年の辺りの音に没頭できるというのは我ながら驚いております。ジョン・レノンの死後や「なんとなくクリスタル」が出版された1年後〜15ヶ月後辺りの時代と思っていただければお判りになるでしょうか(笑)。82年に変わろうとする辺りの時代と言いましょうか。生まれていない人だっているかもしれませんが、私が振り返るとこういう見方になってしまうんですなあ。
2008-10-10 12:00
過去に大ヒットしたシンセサイザー [クロスオーバー]
なんだかんだ言って「大ヒット」と形容するに相応しいシンセの代名詞となるとYAMAHA DX7という位置付けになるのでありましょうが、聞く所によればその後のKORG M1はもとより、KORG 01WはDXよりもヒットしたと言いますし、その後の「大ヒット」なるともはや存在しないのではないかと思える現在であります。
かな〜り昔に、左近治宅にあるDX7というのは実は知人から超長期間借りているモノだということをカミング・アウトしたワケでありますが、当時はホントにDX7を弄くり倒したとはいえ、その一方ではDW-8000やらJX-8P、D-50、M1が左近治ののめり込んでいたシンセでありました。
当時はMatrix-12やらOSCarなども欲しかったモノですが(笑)、DX7じゃ出せない「実直な」シンセ・サウンドをどこかで求めていたんですな。
まあ、いわゆる「デジアナ」なシンセの音を欲していたというワケですが、そんな当時はどんどんPCMの流れに移っていって、どこかデジアナの独特のキャラクターを持つ中途半端さをポジティヴに強化されることはなく、PCMを大容量かつ原音に近いクオリティを求めるのが時代の流れでしたでしょうか。
ただし、PCMに流れが移ってもJD-800が登場した頃やSY99がフィルターを搭載してきた頃となると、徐々にアナログ・シンセ時代の音が求められつつあるようにもなり、その後のアナクロニカルな流れへと移行するのであります。
90年代から殆ど大きく変わることなくシンセ・サウンドというのは確立されているように思えるワケですが、デジアナな音を今求めるとなるとチト難しかったりするんですな。
で、今回はTriple Cheeseを使って当時のデジアナ風な音にしていかにもホールズワース風なデモを作ってみたというワケです(笑)。Synthaxeを使っていた頃のアラン・ホールスワースの音源はMatrix-12の鍵盤部ノコギリ切り落とし(笑)が主だったりするんですが、アタヴァクロンやサンド辺りの頃の音というのは多くの世に出回っている音がDX漬けだったものの、DXに染まらないタイプの音楽として非常に好きだったんですね。
DX7があまりに標準化しすぎて、見落とされていた向きもあるデジアナシンセの数々。Vintage KeysやJV-80が売られていた時代の頃になると、逆にDW-8000やらJX-8P辺りのシンセを懐かしむことが皮肉に思えたものでありました。
そんなデジアナ風な音、今左近治自身は結構マイブームで没頭している所であります。
ゲイリー・ハズバンド、ジミー・ジョンソンをイメージしつつ、全然安直なデモになってしまっておりますが(笑)、コードはホールズワースはもとより、ウォルター・ベッカー風にもしておりますので、多くの人に分析してもらいつつ楽しんでもらおっかな、と。
余談ですが、ジミー・ジョンソンのアレンビックのベースは弦間こそナローですが、ネックはエボニーで34インチよりも長いのを所有していたようで、80年代中期辺りからエクストラ・ロングスケールに目を向けていたのはアレンビックやカール・トンプソン、国内ではアトランシアのみではなかったのではないかと思うばかりでついつい懐かしくなってしまいます。84年頃、私が欲しかったベースはMVペデュラだったことが懐かしいです。
再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら
余談ですが、先日のエレピ聴き比べですが、後半の方がS-760用のサンプルです。
かな〜り昔に、左近治宅にあるDX7というのは実は知人から超長期間借りているモノだということをカミング・アウトしたワケでありますが、当時はホントにDX7を弄くり倒したとはいえ、その一方ではDW-8000やらJX-8P、D-50、M1が左近治ののめり込んでいたシンセでありました。
当時はMatrix-12やらOSCarなども欲しかったモノですが(笑)、DX7じゃ出せない「実直な」シンセ・サウンドをどこかで求めていたんですな。
まあ、いわゆる「デジアナ」なシンセの音を欲していたというワケですが、そんな当時はどんどんPCMの流れに移っていって、どこかデジアナの独特のキャラクターを持つ中途半端さをポジティヴに強化されることはなく、PCMを大容量かつ原音に近いクオリティを求めるのが時代の流れでしたでしょうか。
ただし、PCMに流れが移ってもJD-800が登場した頃やSY99がフィルターを搭載してきた頃となると、徐々にアナログ・シンセ時代の音が求められつつあるようにもなり、その後のアナクロニカルな流れへと移行するのであります。
90年代から殆ど大きく変わることなくシンセ・サウンドというのは確立されているように思えるワケですが、デジアナな音を今求めるとなるとチト難しかったりするんですな。
で、今回はTriple Cheeseを使って当時のデジアナ風な音にしていかにもホールズワース風なデモを作ってみたというワケです(笑)。Synthaxeを使っていた頃のアラン・ホールスワースの音源はMatrix-12の鍵盤部ノコギリ切り落とし(笑)が主だったりするんですが、アタヴァクロンやサンド辺りの頃の音というのは多くの世に出回っている音がDX漬けだったものの、DXに染まらないタイプの音楽として非常に好きだったんですね。
DX7があまりに標準化しすぎて、見落とされていた向きもあるデジアナシンセの数々。Vintage KeysやJV-80が売られていた時代の頃になると、逆にDW-8000やらJX-8P辺りのシンセを懐かしむことが皮肉に思えたものでありました。
そんなデジアナ風な音、今左近治自身は結構マイブームで没頭している所であります。
ゲイリー・ハズバンド、ジミー・ジョンソンをイメージしつつ、全然安直なデモになってしまっておりますが(笑)、コードはホールズワースはもとより、ウォルター・ベッカー風にもしておりますので、多くの人に分析してもらいつつ楽しんでもらおっかな、と。
余談ですが、ジミー・ジョンソンのアレンビックのベースは弦間こそナローですが、ネックはエボニーで34インチよりも長いのを所有していたようで、80年代中期辺りからエクストラ・ロングスケールに目を向けていたのはアレンビックやカール・トンプソン、国内ではアトランシアのみではなかったのではないかと思うばかりでついつい懐かしくなってしまいます。84年頃、私が欲しかったベースはMVペデュラだったことが懐かしいです。
再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら
余談ですが、先日のエレピ聴き比べですが、後半の方がS-760用のサンプルです。
2008-08-28 00:00
エレピお試し [クロスオーバー]
扨て、今日も懲りずにサンプルのデモでも用意すると致しまして、今回はちょっとセミ・バラード風のリフで攻めてみよっかな、と。
再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら
今回のデモでは4小節ごとにエレピが変わります。コードチェンジは2小節ずつ変わりますんで念のため。
で、どちらか一方のエレピはですね、Logic Pro内蔵のEVP88を使用しています。アナタは判るかな!?
Logicのプロジェクトのサンプルレート周波数が44.1k/48kですと、このような音で鳴りません。それはEVPのパラメータおよび外部のプラグインでも然り。
仮に低いサンプルレート周波数で作っても今回のようなエフェクトセッティングを適用しても全然違った音になるんですね。まず中低域がブーミーになりすぎて、高域のレスポンスが鈍化する。それを補おうとEQやらコンプを深めに設定しても、目標とすべき音は別次元のパラレル・ワールドに存在してしまっているような感じで全く辿り着けません(笑)。
そこでローカットしようともやはり無理でツヤも失います。というわけで比較的高いサンプルレート周波数で制作した方がメリット大きいぞ、ということを言いたいのでありますが、物理モデリングはもとよりLogic標準のインストゥルメント音源に限らず、サードパーティーのソフト音源だろうがエフェクトプラグインだろうが、やはりそういう効果というのは出てきます。もう何度も左近治はこれについて述べておりますが。
サンプルレート周波数が低ければDAWアプリケーションを変えようがMacやWindowsに限らず、何試してもダメです(笑)。
例えば、サンプルレート周波数44.1k/48kで制作していた頃のエフェクトプラグインのパラメータをチャンネルストリップ設定として保存して、その設定を高いサンプルレート周波数環境下で適用しても全く異質な音になってしまうワケですね。それが例えばEQで、高域部分などまったく弄っていないような設定であっても違います。
目先のソフト音源の負荷を気にするがあまり、ついつい低い負荷で済む環境を選んでしまってトラックが増えてくるとどんなに定位を弄っても飽和感が目立つようになってしまうのが関の山だと思うんですね(笑)。仮にマシンが非力であろうともLogicならばとりあえずはノードも可能なので、Logicのメリットを語ってしまいました(笑)。
とはいえノードもBusやAuxトラックに挟んだプラグインはノードできないのがLogicの悩みでもありますが、この辺りが改善されてくると一挙にコンシューマレベルでも分散処理化が進んで、サンプルレート周波数の環境も一気にハイ・サンプルレート化するように思います。ハイ・サンプルレート周波数を扱う場合は、外部HDDにソフト音源のライブラリやらRAIDで高速化、あるいは起動ドライブそのものを高速化しようとも、空き容量の方が重要になりますのでその辺りは注意する点でしょうか。起動ドライブは6割空きが上限だと思ってハイ・サンプルレート周波数を選択すると快適だと思います。
あとは安価メモリを併用したりしないことですね(笑)。安価なメモリなどMac対応などと謳っていてもCL=4だったりするんで、Appleプロ・アプリケーションを使用すると特にそれが足引っ張ってアプリやOSを強制終了させてしまうことに陥ったりするんで(CLばかりが原因ではないですが)、高くともApple純正メモリを使って制作することをオススメします。こういう状況に陥って安物買いの銭失いに陥っている者は私の周囲にもおりますんで情けないハナシです(笑)。
再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら
今回のデモでは4小節ごとにエレピが変わります。コードチェンジは2小節ずつ変わりますんで念のため。
で、どちらか一方のエレピはですね、Logic Pro内蔵のEVP88を使用しています。アナタは判るかな!?
Logicのプロジェクトのサンプルレート周波数が44.1k/48kですと、このような音で鳴りません。それはEVPのパラメータおよび外部のプラグインでも然り。
仮に低いサンプルレート周波数で作っても今回のようなエフェクトセッティングを適用しても全然違った音になるんですね。まず中低域がブーミーになりすぎて、高域のレスポンスが鈍化する。それを補おうとEQやらコンプを深めに設定しても、目標とすべき音は別次元のパラレル・ワールドに存在してしまっているような感じで全く辿り着けません(笑)。
そこでローカットしようともやはり無理でツヤも失います。というわけで比較的高いサンプルレート周波数で制作した方がメリット大きいぞ、ということを言いたいのでありますが、物理モデリングはもとよりLogic標準のインストゥルメント音源に限らず、サードパーティーのソフト音源だろうがエフェクトプラグインだろうが、やはりそういう効果というのは出てきます。もう何度も左近治はこれについて述べておりますが。
サンプルレート周波数が低ければDAWアプリケーションを変えようがMacやWindowsに限らず、何試してもダメです(笑)。
例えば、サンプルレート周波数44.1k/48kで制作していた頃のエフェクトプラグインのパラメータをチャンネルストリップ設定として保存して、その設定を高いサンプルレート周波数環境下で適用しても全く異質な音になってしまうワケですね。それが例えばEQで、高域部分などまったく弄っていないような設定であっても違います。
目先のソフト音源の負荷を気にするがあまり、ついつい低い負荷で済む環境を選んでしまってトラックが増えてくるとどんなに定位を弄っても飽和感が目立つようになってしまうのが関の山だと思うんですね(笑)。仮にマシンが非力であろうともLogicならばとりあえずはノードも可能なので、Logicのメリットを語ってしまいました(笑)。
とはいえノードもBusやAuxトラックに挟んだプラグインはノードできないのがLogicの悩みでもありますが、この辺りが改善されてくると一挙にコンシューマレベルでも分散処理化が進んで、サンプルレート周波数の環境も一気にハイ・サンプルレート化するように思います。ハイ・サンプルレート周波数を扱う場合は、外部HDDにソフト音源のライブラリやらRAIDで高速化、あるいは起動ドライブそのものを高速化しようとも、空き容量の方が重要になりますのでその辺りは注意する点でしょうか。起動ドライブは6割空きが上限だと思ってハイ・サンプルレート周波数を選択すると快適だと思います。
あとは安価メモリを併用したりしないことですね(笑)。安価なメモリなどMac対応などと謳っていてもCL=4だったりするんで、Appleプロ・アプリケーションを使用すると特にそれが足引っ張ってアプリやOSを強制終了させてしまうことに陥ったりするんで(CLばかりが原因ではないですが)、高くともApple純正メモリを使って制作することをオススメします。こういう状況に陥って安物買いの銭失いに陥っている者は私の周囲にもおりますんで情けないハナシです(笑)。
2008-08-23 17:00
ミックス裏舞台 [クロスオーバー]
3月14日のリリース楽曲の概要については前回のブログで語りましたが、今回はin Depthな方向でハナシを進めてみようと思いますね。
ではまず「Kiska」から。
原曲は山下達郎作曲、坂本龍一編曲という曲ですね。坂本龍一の弾くポリムーグとおぼしきシンセのリフとローズ。今ではこういう演奏はなかなか聴くことは難しいのではないかと。
それもこれも、この曲はYMO結成直後辺りの時代なので、YMOお三方のアルバムで例えるなら細野晴臣の「はらいそ」や高橋幸宏(ユキヒロ時代)の「Saravah!」、カクトウギ・セッションの「Summer Nerves」の辺り。おそらくや「千のナイフ」の前あたりでありましょう。
当時のCBSソニーから出ていたオムニバス企画アルバムで「エーゲ海」やら「New York」やら「Pacific」などと、リリースされていた曲。後にベストアルバムで「Island Music」やら「Off Shore」というアルバムで再編集されるワケですが、「Kiska」は「New York」とその後のベスト盤「Off Shore」に収録されているモノであります。
これらの企画アルバムにはYMOが半ば実験的にYMOたるスタンスを探るような実験場としての動きを垣間見ることができまして、「コズミック・サーフィン」やら「ミコノスの花嫁」やら、「Reggae Aege Woman」(←個人的に左近治の好きな曲)やらも聴くことができて、YMO黎明期におけるシンセサウンドの在り方を模索しているような所が実に素朴で、且つ味わい深い親しみがあると言いますか(笑)、YMOのコアなファンの方なら左近治がわざわざ述べる必要はないかもしれませんが、実に興味深いアルバムであったワケです。
作曲の山下達郎はコーラスで参加しているのが「Kiska」でありますが、そのさりげないスタンスとは裏腹に、「達郎節」とも言えるコードワークは見過ごせないモノがあります。そんなコードワークに水を得た魚のように和声とポリムーグやローズに酔いしれる坂本龍一の姿が目の前に浮かんできそうな、プレイヤビリティに溢れた演奏を繰り広げるのがこの曲なんですね。
以前にもローズに用いる空間系エフェクトの妙味について語りましたが、骨っぽさを残しながら薄くコーラスをかけたい場合は、シリーズ接続よりもバス・アサインの方が功を奏することがあるというようなことについて語ったものでした。
通常、オーディオ畑の「モノラル」の扱いはLch、すなわち左側の信号を優先していることが多く、右チャンネルや両チャンネルミックスのモノラルというのは少ないワケですね。この辺の事情については語りませんが(笑)。
ましてや両チャンネルミックスによるモノラルとなると、場合によっては位相を反転させているだけのシーンも想定できるため、これを単純に両チャンネルミックスとしてしまうと音が失せてしまいかねません。
しかしながら単純な空間系エフェクトというのは、例えばコーラスならモノラルでコーラス効果が得られれば別にそれはそれで越したことはないんですが、ステレオコーラスとなると、片チャンネルを単純に逆相にしていたりとか、ある帯域だけ位相をずらしただけのものとか意外に多いんですね。単純に左右のパノラマ感を微妙にずらして位相各を変える程度くらいのものとか。まあ、この辺を細かく制御するようなパラメータを持つコーラスはもはやコーラスではなく別名称で製品化されていたりするものでもありますが。ま、言いたいことは、ステレオ感を演出する空間系エフェクトの多くは右と左のFXバランスは結構違ったり(だからこそステレオイメージでもあるんですが)して、中には安直なものがあったりするんで注意が必要ってこってす。
そうなると、モノラル再生端末も実際には多く存在するケータイ市場において着信音をまんべんなくコーラス感を得ようとするとそれなりに注意を払う必要が出てきます。別にコーラスに限ったことではなく、ステレオ間を演出する類のエフェクト全般に言えることであります(だからといって全てのエフェクトが左チャンネル優先というわけではないので誤解のないように)。
とまあ、そういう所に配慮しながら作っているのだということを知ってもらえればコレ幸いでして(笑)、単純にオーディオファイルを作っているだけではないのであります(笑)。
チャーリーズ・エンジェルのアイキャッチも、これもよ~く聴かなくとも「ローズ」だということが判っていただけると思うんですが、実は用いているコーラスはリリース日が同一であろうと、ローズの音のキャラクターはもとより、空間系エフェクトも全く異質だということをあらためて比較できるのではないかと思っております。
リディアン・メジャー7th、すなわち、#11th音を足したメジャー7thの音となるとYMO好きな方なら「東風」やら「Castalia」ひいては坂本龍一っぽさを連想するかと思うんですが、別に坂本龍一のための特別な和声ではないんですが(笑)、坂本龍一はやはりこの手の響きの咀嚼が実に巧みだからこそそういう印象になるワケで、YMO関連を引っ張っている左近治なので、坂本龍一ではなくとも、それとなく「っぽさ」を感じるジングルも関連付けてリリースしてみたというのが今回のチャーリーズ・エンジェルのアイキャッチに繋がったというワケです。
さらに、このアイキャッチで特徴的なのはSolinaですけどね(笑)。ローズと共に必要不可欠なこの音(笑)。まあ、時代を感じさせる機材達ではあるものの、いまだにその音の魅力は通用すると言いましょうか。こういうモノがPSEによって消えなくて本当に良かったと痛感するのであります(笑)。あの時動いたひとりに坂本龍一も含まれておりましたね。
骨のあるローズの音という視点で音を探ると、左近治が最も好きなその手の音はマハビシュヌ・オーケストラにおけるヤン・ハマーだったりしますが、マックス・ミドルトンやヤン・ハマー、ハービー・ハンコック、ジョー・サンプルという人達の特徴は、飽和感とエグみある骨っぽいローズの音を好む類の代表とも言えるかもしれません。勿論他にもたくさんおりますし(笑)、「チック・コリアは?」とか訊かれそうでありますが(笑)、チック・コリアはリチャード・ティーっぽい方の音かなあと私は感じております(笑)。いずれも好きではありますが。
10年くらい前なら「インコグニートとブラン・ニュー・ヘヴィーズのどっちのローズが好き?」と言われれば私は後者のBNHの方を答えておりましたが、BNHはコードワークやヴォイシングなどプレイヤビリティに関してはインコグニートよりも遥かに乏しい(笑)、だけど音が良かったりするんですね(笑)。インコグニートは二人居ますけど(笑)。
イイとこ取り系の音はアジムスだったり、初期スパイロ・ジャイラのジェレミー・ウォールだったり、と。この辺を挙げればキリがないのがローズの多様な側面でありましょう。一日あっても語り尽くせるモノではありません(笑)。ローズの音だけやストラトやレス・ポール、あるいはフルアコの音だけのテーマで議論されるようなテレビ番組とかあってほしいですね(笑)。
チャーリーズ・エンジェルもただ単に現在放映中だからという理由で取り上げただけではないということが判っていただけたかと思いますが、テレビコンテンツにまで話を引っ張るとなると次は「ごきげんようサイコロトーク」のジングル(笑)。
これはですね、週末の夕方テレ朝でやっている「クイズマンショー」にて、たまたまテレビコンテンツの音楽やらをやっていた時があって、左近治の制作魂に火がついてしまったというワケでした(笑)。ジングルに用いられているアレンジの方は作ってみてあらためて気付いたんですが、リバーブが結構深めなんですね。
ローズとかだとプレート・リバーブは結構相性良かったりするんですが、ローズやらウーリッツァーの発音構造なんて実際には音叉やら鉄琴みたいなモンで、さらに金属系であるプレート・リバーブで馴染ませるという、実は結構理にかなっている組み合わせ。EMTなんて金箔使ってるんだぜ!とまあ、別にEMTじゃなくともプレート・リバーブなど沢山あるワケですが、音になっていない段階の信号においても鉄板で残響が加えられたり、バネで残響加わったりするという実にアナクロでアナログな発想というのは、実に興味深く、残響が付加されるほどまで影響を及ぼさなくとも回路のパーツ類で音が変わるというのは寓意であることかもしれませんね。
左近治自身は、どちらかというと浅いリバーブが好きです。ただ、デジタルの世界というのはパノラマを積極的に弄らないと音像はセンター付近に集中して、左右両チャンネルで同じ音を倍加させるようなもんなんで、ただでさえデジタル領域で周波数やら処理の帯域が限定されている所に詰め込まれるようなモノなんで、低域がどんどん強められてしまうんですな。まあデジタルでなくとも低域ソースなどこんなモンですが。
そこに単純に残響を付加させてしまうと音は濁るわ、かといってリバーブ・タイム稼ぎたくなってしまったりと、EQでうまいこと探りつつ、低域が集中して飽和した音をあらかじめイメージしながらEQを弄りながらトータルの音をコーディネイトしていくと結構功を奏するといいますか、リバーブやらFX音もEQ活用したりして、深いリバーブを「不快」にさせないポイントが結構あるといいますか。今回そういう意味ではリバーブの難しさをあらためて思い知ることができましたね。そういう意味でも今週のローズ関連やら、ごきげんようのジングルは多くの共通点があったというワケです。
ではまず「Kiska」から。
原曲は山下達郎作曲、坂本龍一編曲という曲ですね。坂本龍一の弾くポリムーグとおぼしきシンセのリフとローズ。今ではこういう演奏はなかなか聴くことは難しいのではないかと。
それもこれも、この曲はYMO結成直後辺りの時代なので、YMOお三方のアルバムで例えるなら細野晴臣の「はらいそ」や高橋幸宏(ユキヒロ時代)の「Saravah!」、カクトウギ・セッションの「Summer Nerves」の辺り。おそらくや「千のナイフ」の前あたりでありましょう。
当時のCBSソニーから出ていたオムニバス企画アルバムで「エーゲ海」やら「New York」やら「Pacific」などと、リリースされていた曲。後にベストアルバムで「Island Music」やら「Off Shore」というアルバムで再編集されるワケですが、「Kiska」は「New York」とその後のベスト盤「Off Shore」に収録されているモノであります。
これらの企画アルバムにはYMOが半ば実験的にYMOたるスタンスを探るような実験場としての動きを垣間見ることができまして、「コズミック・サーフィン」やら「ミコノスの花嫁」やら、「Reggae Aege Woman」(←個人的に左近治の好きな曲)やらも聴くことができて、YMO黎明期におけるシンセサウンドの在り方を模索しているような所が実に素朴で、且つ味わい深い親しみがあると言いますか(笑)、YMOのコアなファンの方なら左近治がわざわざ述べる必要はないかもしれませんが、実に興味深いアルバムであったワケです。
作曲の山下達郎はコーラスで参加しているのが「Kiska」でありますが、そのさりげないスタンスとは裏腹に、「達郎節」とも言えるコードワークは見過ごせないモノがあります。そんなコードワークに水を得た魚のように和声とポリムーグやローズに酔いしれる坂本龍一の姿が目の前に浮かんできそうな、プレイヤビリティに溢れた演奏を繰り広げるのがこの曲なんですね。
以前にもローズに用いる空間系エフェクトの妙味について語りましたが、骨っぽさを残しながら薄くコーラスをかけたい場合は、シリーズ接続よりもバス・アサインの方が功を奏することがあるというようなことについて語ったものでした。
通常、オーディオ畑の「モノラル」の扱いはLch、すなわち左側の信号を優先していることが多く、右チャンネルや両チャンネルミックスのモノラルというのは少ないワケですね。この辺の事情については語りませんが(笑)。
ましてや両チャンネルミックスによるモノラルとなると、場合によっては位相を反転させているだけのシーンも想定できるため、これを単純に両チャンネルミックスとしてしまうと音が失せてしまいかねません。
しかしながら単純な空間系エフェクトというのは、例えばコーラスならモノラルでコーラス効果が得られれば別にそれはそれで越したことはないんですが、ステレオコーラスとなると、片チャンネルを単純に逆相にしていたりとか、ある帯域だけ位相をずらしただけのものとか意外に多いんですね。単純に左右のパノラマ感を微妙にずらして位相各を変える程度くらいのものとか。まあ、この辺を細かく制御するようなパラメータを持つコーラスはもはやコーラスではなく別名称で製品化されていたりするものでもありますが。ま、言いたいことは、ステレオ感を演出する空間系エフェクトの多くは右と左のFXバランスは結構違ったり(だからこそステレオイメージでもあるんですが)して、中には安直なものがあったりするんで注意が必要ってこってす。
そうなると、モノラル再生端末も実際には多く存在するケータイ市場において着信音をまんべんなくコーラス感を得ようとするとそれなりに注意を払う必要が出てきます。別にコーラスに限ったことではなく、ステレオ間を演出する類のエフェクト全般に言えることであります(だからといって全てのエフェクトが左チャンネル優先というわけではないので誤解のないように)。
とまあ、そういう所に配慮しながら作っているのだということを知ってもらえればコレ幸いでして(笑)、単純にオーディオファイルを作っているだけではないのであります(笑)。
チャーリーズ・エンジェルのアイキャッチも、これもよ~く聴かなくとも「ローズ」だということが判っていただけると思うんですが、実は用いているコーラスはリリース日が同一であろうと、ローズの音のキャラクターはもとより、空間系エフェクトも全く異質だということをあらためて比較できるのではないかと思っております。
リディアン・メジャー7th、すなわち、#11th音を足したメジャー7thの音となるとYMO好きな方なら「東風」やら「Castalia」ひいては坂本龍一っぽさを連想するかと思うんですが、別に坂本龍一のための特別な和声ではないんですが(笑)、坂本龍一はやはりこの手の響きの咀嚼が実に巧みだからこそそういう印象になるワケで、YMO関連を引っ張っている左近治なので、坂本龍一ではなくとも、それとなく「っぽさ」を感じるジングルも関連付けてリリースしてみたというのが今回のチャーリーズ・エンジェルのアイキャッチに繋がったというワケです。
さらに、このアイキャッチで特徴的なのはSolinaですけどね(笑)。ローズと共に必要不可欠なこの音(笑)。まあ、時代を感じさせる機材達ではあるものの、いまだにその音の魅力は通用すると言いましょうか。こういうモノがPSEによって消えなくて本当に良かったと痛感するのであります(笑)。あの時動いたひとりに坂本龍一も含まれておりましたね。
骨のあるローズの音という視点で音を探ると、左近治が最も好きなその手の音はマハビシュヌ・オーケストラにおけるヤン・ハマーだったりしますが、マックス・ミドルトンやヤン・ハマー、ハービー・ハンコック、ジョー・サンプルという人達の特徴は、飽和感とエグみある骨っぽいローズの音を好む類の代表とも言えるかもしれません。勿論他にもたくさんおりますし(笑)、「チック・コリアは?」とか訊かれそうでありますが(笑)、チック・コリアはリチャード・ティーっぽい方の音かなあと私は感じております(笑)。いずれも好きではありますが。
10年くらい前なら「インコグニートとブラン・ニュー・ヘヴィーズのどっちのローズが好き?」と言われれば私は後者のBNHの方を答えておりましたが、BNHはコードワークやヴォイシングなどプレイヤビリティに関してはインコグニートよりも遥かに乏しい(笑)、だけど音が良かったりするんですね(笑)。インコグニートは二人居ますけど(笑)。
イイとこ取り系の音はアジムスだったり、初期スパイロ・ジャイラのジェレミー・ウォールだったり、と。この辺を挙げればキリがないのがローズの多様な側面でありましょう。一日あっても語り尽くせるモノではありません(笑)。ローズの音だけやストラトやレス・ポール、あるいはフルアコの音だけのテーマで議論されるようなテレビ番組とかあってほしいですね(笑)。
チャーリーズ・エンジェルもただ単に現在放映中だからという理由で取り上げただけではないということが判っていただけたかと思いますが、テレビコンテンツにまで話を引っ張るとなると次は「ごきげんようサイコロトーク」のジングル(笑)。
これはですね、週末の夕方テレ朝でやっている「クイズマンショー」にて、たまたまテレビコンテンツの音楽やらをやっていた時があって、左近治の制作魂に火がついてしまったというワケでした(笑)。ジングルに用いられているアレンジの方は作ってみてあらためて気付いたんですが、リバーブが結構深めなんですね。
ローズとかだとプレート・リバーブは結構相性良かったりするんですが、ローズやらウーリッツァーの発音構造なんて実際には音叉やら鉄琴みたいなモンで、さらに金属系であるプレート・リバーブで馴染ませるという、実は結構理にかなっている組み合わせ。EMTなんて金箔使ってるんだぜ!とまあ、別にEMTじゃなくともプレート・リバーブなど沢山あるワケですが、音になっていない段階の信号においても鉄板で残響が加えられたり、バネで残響加わったりするという実にアナクロでアナログな発想というのは、実に興味深く、残響が付加されるほどまで影響を及ぼさなくとも回路のパーツ類で音が変わるというのは寓意であることかもしれませんね。
左近治自身は、どちらかというと浅いリバーブが好きです。ただ、デジタルの世界というのはパノラマを積極的に弄らないと音像はセンター付近に集中して、左右両チャンネルで同じ音を倍加させるようなもんなんで、ただでさえデジタル領域で周波数やら処理の帯域が限定されている所に詰め込まれるようなモノなんで、低域がどんどん強められてしまうんですな。まあデジタルでなくとも低域ソースなどこんなモンですが。
そこに単純に残響を付加させてしまうと音は濁るわ、かといってリバーブ・タイム稼ぎたくなってしまったりと、EQでうまいこと探りつつ、低域が集中して飽和した音をあらかじめイメージしながらEQを弄りながらトータルの音をコーディネイトしていくと結構功を奏するといいますか、リバーブやらFX音もEQ活用したりして、深いリバーブを「不快」にさせないポイントが結構あるといいますか。今回そういう意味ではリバーブの難しさをあらためて思い知ることができましたね。そういう意味でも今週のローズ関連やら、ごきげんようのジングルは多くの共通点があったというワケです。
2008-03-14 17:31
ローズに酔う [クロスオーバー]
今週のリリース曲には幾つか「マジ曲」がありまして、ローズに注力しております。
ローズに注力するとは言ってもスティーリー・ダンの「Cousin Dupree」の歌詞に見られるような「アレでナニな」ローズではなく(あちらはroseですね)、エレピのRhodesです。
まあ、お医者さんごっこやOREO(=黒人男性2人+白人女性1人による「大人の遊び」のスラング)を連想させる暗喩をタップリ含んだスティーリー・ダンの歌詞のシニカルな面を楽しみつつ、あの曲だってローズの単音でジャーキングやらイレクションを(笑)Nastyに表現しているのですから、ローズとは実に奥が深いモノであります。
YMOや坂本龍一ファンにはうってつけの曲を制作しまして、坂本龍一がイナタくローズを弾いている曲ですね。山下達郎作曲の「Kiska」。
モーダルな曲調でアレンジは坂本龍一。確かにこの曲調なら坂本龍一なら水を得た魚のように得意分野であろうことは音聴けばすぐに判ります。面子は高橋ユキヒロ時代の「Saravah!」やKYLYNに通じるものがあるでしょう。クロスオーバーな雰囲気を漂わせておりますね。
YMO結成30周年となる2008年。当時リアルタイムにYMOを聴いていたことを振り返れば、当時、よもやココまで歳を取ることなど想像すらつかなかったものでありますが(笑)、飽くなき音楽への欲求というのは衰えるどころか増すばかり。
「音楽人生 これからだ」
とまあ、どっかのインシュランスのキャッチコピーにも似た言葉を肝に銘じて、ガタ付いて、いつ焼きが回ってもおかしくないカラダに鞭打って制作している左近治であります(笑)。
30年前の1978年と言いますと、山口百恵の「プレイバックPart2」とかの辺りでしたでしょうか。トヨタのターセルやコルサのCMに山口百恵が起用されていた頃を思い出します(笑)。
その頃の坂本龍一はシンセにも注力はしていたでしょうが、いわゆるスタジオ・ミュージシャン系としてのスタンスを保っていた感がありまして、りりィのバイバイ・セッションバンド→東映のピラニア軍団のアルバムを手掛けたりして、その後YMO結成という風になる過渡期でもある時代。
ピラニア軍団なんて知らない人が多いとは思いますが、ドラマの相棒見てるだけでも警視庁刑事部長役の片桐竜次さんがまさしくそうですね(笑)。トラック野郎ファンやら東映ファンの方なら無粋とも思えるかもしれませんが、なにせ今は2008年。色んな情報鏤めないといけません(笑)。
まあ、その頃の坂本龍一の特徴はローズやハモンド、特にハモンドの音色は実にセンスを感じます。ローズにも良さはあるんですが、それ以上にハモンドの音作りというか、非常にイイ音出しておりまして、その後ポリムーグを手にポリムーグにてローズ系やハモンド系を模した音が結構良かったりするんですな。フィルター・エンベロープによるエグくて判りやすいアナログ・シンセ・サウンド一辺倒ではない所が後のYMOの音色にもつながるといいますか。
まあ、千のナイフではシンベ系で結構ミャンミャン言ってますけど(笑)、レゾナンス利かせてフィルターグイグイ言わせたいかにもシンセチックな音というのは坂本龍一はもとよりYMOの面々は多用してはおりませんね。そういうのもYMOの特徴だったのかもしれません。
「Kiska」については後に詳しく語るとして、今回のローズにこだわった部分はというとやはり「エグみ」に尽きます。
強く打鍵した時の飽和感、ニュートラルなタッチではブーミー過ぎずかすかに響く艶やかな音、ソフトな時はローズの箱鳴り感と同化するトーンピンの囁きetc
とまあ、こういう感じを演出して、コーラスかけても中抜けしない音にしてみたり。
ローズを巧みに使う人は、トレモロのスピードをリアルタイムに可変するプレイヤーも多く、坂本龍一は結構トレモロのかかったローズを嗜好するタイプと言いましょうか、ジョー・ヴァネリっぽさを感じるような所もあります。「Kiska」では結構速めのモノラルのトレモロを用いているようですが、今回はトレモロを使いませんでした。
というのも、ケータイ端末にはモノラル再生のものも多く、トレモロのアンプリチュード幅を浅く設定することは可能ではあるものの、ケータイ端末のスピーカーの感応性の高い周波数帯域とローズの音域や周波数成分を考慮すると、やたらとうねりを出すよりスッキリと鳴ってくれるんですな。勿論曲によりけりですけどね。非常にテンポが遅いタイプの曲ならそれもアリかもしれませんが今回はトレモロの演出は割愛ということに。
ローズの醍醐味は以前にも語りましたが、鍵盤のタッチ。弾いた途端、「下まで落ちる」というようなリニアなタッチとは大違い(笑)。ロガリズミックに落ちていくような感じでしょうか(笑)。
ローズのみならず鍵盤楽器というのは黒鍵と白鍵では物理的に全く同じ形状や位置にマウントされているのではなく、それが微妙なニュアンスの演出を生むわけであります。もちろん全て移調しても流麗なタッチを身に付けてこそ鍵盤奏者なのでありますが、やはり構造的な面から来るニュアンスの違いというのはあるワケですね。その各指で弾かれたニュアンスはC△7を平行移動でヴォイシングをトランスポーズしてA△7のヴォイシングとのニュアンスとは全く異なる(物理的な音高を無視しても)わけでして、これがオイシイ部分ですな。
その物理的な構造の違いからローズの場合だと非常にダイナミクス溢れるといいますか、黒鍵を弾かなくとも白鍵を弾くためのマージンとして「ふりかぶる」ような、もたれて支えるような感じから生まれるニュアンスやら実に味わい深いものであります。
ローズに注力するとは言ってもスティーリー・ダンの「Cousin Dupree」の歌詞に見られるような「アレでナニな」ローズではなく(あちらはroseですね)、エレピのRhodesです。
まあ、お医者さんごっこやOREO(=黒人男性2人+白人女性1人による「大人の遊び」のスラング)を連想させる暗喩をタップリ含んだスティーリー・ダンの歌詞のシニカルな面を楽しみつつ、あの曲だってローズの単音でジャーキングやらイレクションを(笑)Nastyに表現しているのですから、ローズとは実に奥が深いモノであります。
YMOや坂本龍一ファンにはうってつけの曲を制作しまして、坂本龍一がイナタくローズを弾いている曲ですね。山下達郎作曲の「Kiska」。
モーダルな曲調でアレンジは坂本龍一。確かにこの曲調なら坂本龍一なら水を得た魚のように得意分野であろうことは音聴けばすぐに判ります。面子は高橋ユキヒロ時代の「Saravah!」やKYLYNに通じるものがあるでしょう。クロスオーバーな雰囲気を漂わせておりますね。
YMO結成30周年となる2008年。当時リアルタイムにYMOを聴いていたことを振り返れば、当時、よもやココまで歳を取ることなど想像すらつかなかったものでありますが(笑)、飽くなき音楽への欲求というのは衰えるどころか増すばかり。
「音楽人生 これからだ」
とまあ、どっかのインシュランスのキャッチコピーにも似た言葉を肝に銘じて、ガタ付いて、いつ焼きが回ってもおかしくないカラダに鞭打って制作している左近治であります(笑)。
30年前の1978年と言いますと、山口百恵の「プレイバックPart2」とかの辺りでしたでしょうか。トヨタのターセルやコルサのCMに山口百恵が起用されていた頃を思い出します(笑)。
その頃の坂本龍一はシンセにも注力はしていたでしょうが、いわゆるスタジオ・ミュージシャン系としてのスタンスを保っていた感がありまして、りりィのバイバイ・セッションバンド→東映のピラニア軍団のアルバムを手掛けたりして、その後YMO結成という風になる過渡期でもある時代。
ピラニア軍団なんて知らない人が多いとは思いますが、ドラマの相棒見てるだけでも警視庁刑事部長役の片桐竜次さんがまさしくそうですね(笑)。トラック野郎ファンやら東映ファンの方なら無粋とも思えるかもしれませんが、なにせ今は2008年。色んな情報鏤めないといけません(笑)。
まあ、その頃の坂本龍一の特徴はローズやハモンド、特にハモンドの音色は実にセンスを感じます。ローズにも良さはあるんですが、それ以上にハモンドの音作りというか、非常にイイ音出しておりまして、その後ポリムーグを手にポリムーグにてローズ系やハモンド系を模した音が結構良かったりするんですな。フィルター・エンベロープによるエグくて判りやすいアナログ・シンセ・サウンド一辺倒ではない所が後のYMOの音色にもつながるといいますか。
まあ、千のナイフではシンベ系で結構ミャンミャン言ってますけど(笑)、レゾナンス利かせてフィルターグイグイ言わせたいかにもシンセチックな音というのは坂本龍一はもとよりYMOの面々は多用してはおりませんね。そういうのもYMOの特徴だったのかもしれません。
「Kiska」については後に詳しく語るとして、今回のローズにこだわった部分はというとやはり「エグみ」に尽きます。
強く打鍵した時の飽和感、ニュートラルなタッチではブーミー過ぎずかすかに響く艶やかな音、ソフトな時はローズの箱鳴り感と同化するトーンピンの囁きetc
とまあ、こういう感じを演出して、コーラスかけても中抜けしない音にしてみたり。
ローズを巧みに使う人は、トレモロのスピードをリアルタイムに可変するプレイヤーも多く、坂本龍一は結構トレモロのかかったローズを嗜好するタイプと言いましょうか、ジョー・ヴァネリっぽさを感じるような所もあります。「Kiska」では結構速めのモノラルのトレモロを用いているようですが、今回はトレモロを使いませんでした。
というのも、ケータイ端末にはモノラル再生のものも多く、トレモロのアンプリチュード幅を浅く設定することは可能ではあるものの、ケータイ端末のスピーカーの感応性の高い周波数帯域とローズの音域や周波数成分を考慮すると、やたらとうねりを出すよりスッキリと鳴ってくれるんですな。勿論曲によりけりですけどね。非常にテンポが遅いタイプの曲ならそれもアリかもしれませんが今回はトレモロの演出は割愛ということに。
ローズの醍醐味は以前にも語りましたが、鍵盤のタッチ。弾いた途端、「下まで落ちる」というようなリニアなタッチとは大違い(笑)。ロガリズミックに落ちていくような感じでしょうか(笑)。
ローズのみならず鍵盤楽器というのは黒鍵と白鍵では物理的に全く同じ形状や位置にマウントされているのではなく、それが微妙なニュアンスの演出を生むわけであります。もちろん全て移調しても流麗なタッチを身に付けてこそ鍵盤奏者なのでありますが、やはり構造的な面から来るニュアンスの違いというのはあるワケですね。その各指で弾かれたニュアンスはC△7を平行移動でヴォイシングをトランスポーズしてA△7のヴォイシングとのニュアンスとは全く異なる(物理的な音高を無視しても)わけでして、これがオイシイ部分ですな。
その物理的な構造の違いからローズの場合だと非常にダイナミクス溢れるといいますか、黒鍵を弾かなくとも白鍵を弾くためのマージンとして「ふりかぶる」ような、もたれて支えるような感じから生まれるニュアンスやら実に味わい深いものであります。
2008-03-12 22:31
たまにゃRhodesに酔いしれる [クロスオーバー]
そもそもDX7が出現してから練習スタジオに備えてある鍵盤はガラリと変容してしまいました(笑)。ごく普通にSuitcaseやMkIIなんて見たものでしたが、その後M1や01Wに置き換わっていったワケでありましたっけ(笑)。
しかし01Wの頃になると、モノホンのRhodesが姿を消していたにも関わらず音はトコトン求められるようにニーズは変化していきました。そうです、DX7の爆発的な普及は確かに凄かったものですが、席巻していた時代など僅かなモノだったんですな。
Rhodesの場合音作りは結構力入るモノでして、特にサンプル音源を使ってDAW環境で音を得るような時、フェイザーやコーラスやトレモロの各エフェクトのセッティングよりもルーティングに頭悩ませるコトもしばしば。何故かと言えば、チャンネルインサートにシリーズで掛けるのか、Busルーティングでパラってしまうかだけでも音はかなり変わるからなんですな。当然と言えば当然ですが、音色の変わりっぷりはかなり大きいポイントなんですね。これらのルーティングは。Rhodesに限ったコトではないんですが。
とまあ、要所々々でそれらを使い分けながら、さらにエフェクトのパラメータを細かく編集していくというのがRhodesを用いた時の左近治の実際です。
先日も、坂本龍一がイナタくローズを弾く山下達郎作曲の「Kiska」を作っていたこともあって、「このフレーズ、かなりマックス・ミドルトンっぽいよなあ」などと、クロマチックのフレーズなんか聴いた日にゃあついつい「ニヤリ」としてしまった左近治でありました。まあ坂本龍一の場合離鍵がキレイなのでマックス・ミドルトンよりもソフィスティケイトされるワケですが、マックス・ミドルトンのモタったような離鍵もそれはそれでかなりイナタく味わい深いものであります。ジョー・サンプルの弾きムラたっぷりのタッチもローズだからこそ得られる快感であり(笑)、アコピ弾かせた日にゃあピアノ線ブチ切れそうな臨界状態の変な倍音も聴けてしまうのがジョー・サンプルではあるものの(笑)、ローズだと本当にNastyで絶妙です(笑)。
エフェクトのシリーズorパラレルという点は、どちらが良いor悪いかではなく、ルーティングによって生まれた相乗効果をどう選択するかという好みの問題であるというのを前提にして語らなければならないと思うのですが、例えばローズにコーラスをかけるシーンがあったとしましょうか。
ローズ音源側にコーラスが内蔵されているモノも少なくないものの、ここでは外部のコーラスエフェクトを使うという事を前提に語ります。
コーラスというのはつまるところ位相をLFOで揺らしているため、補強される周波数と相殺される周波数は確実に現れるワケです。ただ、そこでデッドになってしまったとしても、ステレオ感を演出できるように施されたコーラスであれば、相殺されてしまった周波数よりも僅かなピッチの揺れと左右の拡大感の効果の方がより大きいため、実際に相殺されてしまった周波数帯をネガティヴに捕らえるよりも、そういったコーラスならではの効果をポジティヴに利用しているケースの方が多いと思います。
また、元ソースに高域成分が豊かだと、さらにその成分がコーラスの位相の違いによって強化されたりするのも当然のように現れます。
そういう特徴(特長)があるのを念頭に置いた上でコーラスを直結で掛けると、ステレオトラックだったりコーラスそのものをモノ・コーラスとして扱わない限りはステレオの拡大感は増えると同時に、相対的にセンターが抜けるような音になります。
一方、バスルーティングによってコーラスをパラレルに掛ければ、コーラスをoffにしていればEQや別のエフェクトを使わない限りは、同一ソースを並列に、同時に鳴らしているコトになるワケですね。アナログならこれだけでも音が若干変わる要素を秘めているかもしれませんが、デジタルの場合だと同一ソースを重複させればレベルは増大するし、場合によってはとんでもないほど音が破綻してしまって、デジタルクリップの飽和状態にもなりかねません(笑)。
実際にはパストラックに持っていっただけでは音が破綻するようなことはまず有り得ないと思うんですが(笑)、要はルーティングによって生まれる相乗効果を利用した音作りに発想を変える、と。
ま、そんなんでサンプルを用意したんですが、最初に現れるコードは直結でコーラスを掛けたもの。後半が同じパラメータ設定のコーラスをバスアサインしたもの、となっております。後半の方が多少レベルは増加しちゃっているものの(笑)、拡大感よりも中央を補強した感じは十分伝わると思いますし、レベルの増大によって耳がそう聴こえる、という程度のモノではないということも判っていただけるのではないか、と。
再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら
ローズの方はコンプとEQしか掛けていませんし、バスルーティング側ではコーラスのみで他はEQもしていません(笑)。2ミックス用のリミッターを掛けるのもすっかり忘れて省きました(笑)。
肝心な点は、ローズの元のトラックのアウトプットとバスルーティング用のBusトラックのアウトプットを同時に使う、という所ですか。
更に細かく編集したい場合は、Busリターンを使ったセッティングなど色々方法はあるでしょうが、単純にコーラスを使うだけでも並列と直列では結構変わるということをあらためて知るというのが今回のポイントです。
今回のデモで弾いている左手のヴォイシングは、チック・コリアがよくやる「ルート+5度+13度」で5度と13度は長二度というヴォイシングによるメジャー9th(13)のコードですね。どんな音域にも使えるってェわけじゃないですけどね(笑)。このヴォインシングは7度またはそれ以上の音がとても綺麗に響くので、左近治は結構好きなヴォイシングのひとつなので今回用いました(笑)。
ヴェロシティを全く同じく上下に平行移動させてサンプル音源やらシンセを鳴らしてしまえば普通に同じように鳴ってくれるかもしれませんが、鍵盤楽器の面白さというのは黒鍵と白鍵の物理的な構造や大きさの違いがあって、どんなに流麗に弾こうともその構造が独特の情感が現れるといいましょうか。特にローズだとそれが顕著に表れるます。黒鍵鳴らさないように指宛てがいながら、白鍵のストロークの深い鍵盤に勢い付けて落とし込む!みたいな(笑)。
ベースに例えるなら、4弦をそのまま弾くんじゃなくて、3弦に宛てがってた指を4弦に向って弾く!みたいな(笑)。
物理的な構造の違いによって生まれるヴォイシングの巧みさというか、綺麗なヴォイシングって結構あると思うんですね、鍵盤楽器は。私などチェルニーですらヒーコラ言っているようなモノなんで大したコト言えませんけど(笑)。
しかし01Wの頃になると、モノホンのRhodesが姿を消していたにも関わらず音はトコトン求められるようにニーズは変化していきました。そうです、DX7の爆発的な普及は確かに凄かったものですが、席巻していた時代など僅かなモノだったんですな。
Rhodesの場合音作りは結構力入るモノでして、特にサンプル音源を使ってDAW環境で音を得るような時、フェイザーやコーラスやトレモロの各エフェクトのセッティングよりもルーティングに頭悩ませるコトもしばしば。何故かと言えば、チャンネルインサートにシリーズで掛けるのか、Busルーティングでパラってしまうかだけでも音はかなり変わるからなんですな。当然と言えば当然ですが、音色の変わりっぷりはかなり大きいポイントなんですね。これらのルーティングは。Rhodesに限ったコトではないんですが。
とまあ、要所々々でそれらを使い分けながら、さらにエフェクトのパラメータを細かく編集していくというのがRhodesを用いた時の左近治の実際です。
先日も、坂本龍一がイナタくローズを弾く山下達郎作曲の「Kiska」を作っていたこともあって、「このフレーズ、かなりマックス・ミドルトンっぽいよなあ」などと、クロマチックのフレーズなんか聴いた日にゃあついつい「ニヤリ」としてしまった左近治でありました。まあ坂本龍一の場合離鍵がキレイなのでマックス・ミドルトンよりもソフィスティケイトされるワケですが、マックス・ミドルトンのモタったような離鍵もそれはそれでかなりイナタく味わい深いものであります。ジョー・サンプルの弾きムラたっぷりのタッチもローズだからこそ得られる快感であり(笑)、アコピ弾かせた日にゃあピアノ線ブチ切れそうな臨界状態の変な倍音も聴けてしまうのがジョー・サンプルではあるものの(笑)、ローズだと本当にNastyで絶妙です(笑)。
エフェクトのシリーズorパラレルという点は、どちらが良いor悪いかではなく、ルーティングによって生まれた相乗効果をどう選択するかという好みの問題であるというのを前提にして語らなければならないと思うのですが、例えばローズにコーラスをかけるシーンがあったとしましょうか。
ローズ音源側にコーラスが内蔵されているモノも少なくないものの、ここでは外部のコーラスエフェクトを使うという事を前提に語ります。
コーラスというのはつまるところ位相をLFOで揺らしているため、補強される周波数と相殺される周波数は確実に現れるワケです。ただ、そこでデッドになってしまったとしても、ステレオ感を演出できるように施されたコーラスであれば、相殺されてしまった周波数よりも僅かなピッチの揺れと左右の拡大感の効果の方がより大きいため、実際に相殺されてしまった周波数帯をネガティヴに捕らえるよりも、そういったコーラスならではの効果をポジティヴに利用しているケースの方が多いと思います。
また、元ソースに高域成分が豊かだと、さらにその成分がコーラスの位相の違いによって強化されたりするのも当然のように現れます。
そういう特徴(特長)があるのを念頭に置いた上でコーラスを直結で掛けると、ステレオトラックだったりコーラスそのものをモノ・コーラスとして扱わない限りはステレオの拡大感は増えると同時に、相対的にセンターが抜けるような音になります。
一方、バスルーティングによってコーラスをパラレルに掛ければ、コーラスをoffにしていればEQや別のエフェクトを使わない限りは、同一ソースを並列に、同時に鳴らしているコトになるワケですね。アナログならこれだけでも音が若干変わる要素を秘めているかもしれませんが、デジタルの場合だと同一ソースを重複させればレベルは増大するし、場合によってはとんでもないほど音が破綻してしまって、デジタルクリップの飽和状態にもなりかねません(笑)。
実際にはパストラックに持っていっただけでは音が破綻するようなことはまず有り得ないと思うんですが(笑)、要はルーティングによって生まれる相乗効果を利用した音作りに発想を変える、と。
ま、そんなんでサンプルを用意したんですが、最初に現れるコードは直結でコーラスを掛けたもの。後半が同じパラメータ設定のコーラスをバスアサインしたもの、となっております。後半の方が多少レベルは増加しちゃっているものの(笑)、拡大感よりも中央を補強した感じは十分伝わると思いますし、レベルの増大によって耳がそう聴こえる、という程度のモノではないということも判っていただけるのではないか、と。
再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら
ローズの方はコンプとEQしか掛けていませんし、バスルーティング側ではコーラスのみで他はEQもしていません(笑)。2ミックス用のリミッターを掛けるのもすっかり忘れて省きました(笑)。
肝心な点は、ローズの元のトラックのアウトプットとバスルーティング用のBusトラックのアウトプットを同時に使う、という所ですか。
更に細かく編集したい場合は、Busリターンを使ったセッティングなど色々方法はあるでしょうが、単純にコーラスを使うだけでも並列と直列では結構変わるということをあらためて知るというのが今回のポイントです。
今回のデモで弾いている左手のヴォイシングは、チック・コリアがよくやる「ルート+5度+13度」で5度と13度は長二度というヴォイシングによるメジャー9th(13)のコードですね。どんな音域にも使えるってェわけじゃないですけどね(笑)。このヴォインシングは7度またはそれ以上の音がとても綺麗に響くので、左近治は結構好きなヴォイシングのひとつなので今回用いました(笑)。
ヴェロシティを全く同じく上下に平行移動させてサンプル音源やらシンセを鳴らしてしまえば普通に同じように鳴ってくれるかもしれませんが、鍵盤楽器の面白さというのは黒鍵と白鍵の物理的な構造や大きさの違いがあって、どんなに流麗に弾こうともその構造が独特の情感が現れるといいましょうか。特にローズだとそれが顕著に表れるます。黒鍵鳴らさないように指宛てがいながら、白鍵のストロークの深い鍵盤に勢い付けて落とし込む!みたいな(笑)。
ベースに例えるなら、4弦をそのまま弾くんじゃなくて、3弦に宛てがってた指を4弦に向って弾く!みたいな(笑)。
物理的な構造の違いによって生まれるヴォイシングの巧みさというか、綺麗なヴォイシングって結構あると思うんですね、鍵盤楽器は。私などチェルニーですらヒーコラ言っているようなモノなんで大したコト言えませんけど(笑)。
2008-02-27 12:26
ジェフ・ミロノフに酔いしれる [クロスオーバー]
最近左近治がやっていたマジ曲のひとつにジェフ・ミロノフが参加している某曲がありましてですね、この人のシングル・ノート・カッティングは非常に好きな左近治であります。
先日リリースしたKYLYNの「Mother Terra」のハウス・バージョンのギター・リフだってA Taste of Honeyを意識して作ったものの、この手のリフはやはりシングル・ノートといえども侮れない、アンサンブルに彩りを添えるモノなんですな。フレージングのセンスは勿論、コード感覚が絶妙じゃないと、その辺のギター初心者ならルートと5度でしか遊べなさそうな(笑)。
インコグニートのブルーイもそういうセンスを感じさせる人ですね。ジェフ・ミロノフやブルーイは13th音の使い方が巧いというか、ドリアン・モードでの六度の使い方じゃないんですね。さらにはジェフ・ミロノフの場合、ドリアン一発でナチュラル6th音を普通なら使いそうな時に♭6thの音を巧みに使う人でもあります。
「VIm6 add9 / I」の使い方はもはや鍵盤弾きのようなセンスすら感じます。キーがAマイナーだとしたら「Dm69 / A」ってこってすな。このコードは♭6と9thのぶつかり具合が絶妙で、強烈な叙情性を放つ響きですよね。
若かりし日の左近治はベース小僧で、特にベース必聴タイプの曲はベースパートばかり耳を注力して、そのまま何年も聴いていない曲が多くてですね、着メロ&着うた耳コピ作業というのはそういう古い曲をあらためて知る絶好の機会なので続けていけるのでありましょう(笑)。やっぱり全パート、全ての音符を譜面に書き出すくらい曲は聞き込んでナンボだなあと気付かされるのあります。
ついさっきも色んな曲の制作をしていて一寸くつろいだらそのまま寝てしまい(笑)、変な時間に起きてしまったのでこのまま起きてるか、となってこのブログ、と。
直近で作っていた曲はYMO関連(少し遠いですが)、坂本龍一がポリムーグとローズを使って参加している山下達郎作曲の「KISKA」であります。達郎の「左手五度」の分数コードは結構クセがあって、この分母5度系は坂本龍一もよく使うし、ジャズどころだとチック・コリアがこうやってヴォイシングしたりしますね。B♭ on Cでも左手はC音とG音なので「Gm7 on C」とか「B♭6 / C」風になるというアレですな。坂本龍一も当時はKYLYNの「I’ll Be There」とかでこの手のヴォイシングは多用しているかな、と。
この曲は当時のCBSソニーからリリースしていた企画オムニバスアルバムで、レコーディングは確か信濃町スタジオだったのではないかと。「New York」や「Off Shore」に収録されておりますね。これらのアルバムはYMO関連を追いかけていた人なら間違いなく知っているであろうアルバムでありましょう。YMO名義ではないのにお三方チャッカリ参加してYMO黎明期の実験場のようにしていた感じがあります。
もう2年くらい前からやっていてすっかり手をつけずに月日だけが経過していたんですが(笑)、古い制作ファイル群を整理しようかと眺めていて、ちゃんと作らないとなーと思ってやっていたというワケですね。
村上ポン太秀一のガッド・フリークな音の時代なので、ドラムトラックをアレコレとアサインして音作りが終わった所で一休みしてしまったら寝てしまった、というワケです。左手側にもロー・ミッドのタムを配置しているキット構成がKYLYN Liveのアルバムジャケからも判るんですが、今までで一番驚いたのが、渡辺香津美率いるMobo III時代では全てがロートタムで、ハットは4インチくらいしかない「リン」のシンバルを使っていたのをテレビで見た時ですか。
84~85年頃の金曜日フジテレビ深夜でやっていた、ナントカ倶楽部という番組で渡辺徹が司会をやっていたような記憶が。この番組は年に1回くらい渡辺香津美が出演するので結構チェックしていたモノです。
実は左近治がドラムを叩いていた時に使用していたのがポン太モデルのスティック。その後ピーター・アースキンのスティックを使ってましたっけ。
左近治による「KISKA」の制作が2年ほど頓挫してしまった当時の大きな理由は、ポリムーグの音作りに当時は満足できなかったから、というのは大ウソで(笑)、当時の着うた事情でこの手の曲をリリースするにはまだ早いかな、と思ったのが最大の理由。
2~3年前の着うたは私個人で言えばまだ着メロ引きずったデフォルメ感や音色面で着メロでは再現できないような部分を活かしたかった時代でしたので、こうなったのであります。もちろんそれくらいの辺りから路線を変えずに制作やリリースは可能ではあったんですが、そうなると完全に自分が作りたい(というか心底好きな曲)モノしか作らなくなってしまうであろうことは明白だったので(笑)、他の飛び道具系やら脳幹直撃系が等閑になるな、と思ってそれを回避したというワケです。
メシとスイーツは別腹、という人も多いのと同じ。それらのジャンルでは「別脳」の観点で作らないとダメなので。あ、メシとご飯は違います(笑)。
ところで、「スイーツ」という言葉は受け入れられているのに、オヤジがアウトを「アウツ」と言ったりするのが受け入れられないのは何故でしょうか?。スイーツすらオヤジっぽく聴こえるのに(笑)。
別脳の方で作っているのもアレコレ作ってます。ピンク系が多いかな、と(笑)。
先日リリースしたKYLYNの「Mother Terra」のハウス・バージョンのギター・リフだってA Taste of Honeyを意識して作ったものの、この手のリフはやはりシングル・ノートといえども侮れない、アンサンブルに彩りを添えるモノなんですな。フレージングのセンスは勿論、コード感覚が絶妙じゃないと、その辺のギター初心者ならルートと5度でしか遊べなさそうな(笑)。
インコグニートのブルーイもそういうセンスを感じさせる人ですね。ジェフ・ミロノフやブルーイは13th音の使い方が巧いというか、ドリアン・モードでの六度の使い方じゃないんですね。さらにはジェフ・ミロノフの場合、ドリアン一発でナチュラル6th音を普通なら使いそうな時に♭6thの音を巧みに使う人でもあります。
「VIm6 add9 / I」の使い方はもはや鍵盤弾きのようなセンスすら感じます。キーがAマイナーだとしたら「Dm69 / A」ってこってすな。このコードは♭6と9thのぶつかり具合が絶妙で、強烈な叙情性を放つ響きですよね。
若かりし日の左近治はベース小僧で、特にベース必聴タイプの曲はベースパートばかり耳を注力して、そのまま何年も聴いていない曲が多くてですね、着メロ&着うた耳コピ作業というのはそういう古い曲をあらためて知る絶好の機会なので続けていけるのでありましょう(笑)。やっぱり全パート、全ての音符を譜面に書き出すくらい曲は聞き込んでナンボだなあと気付かされるのあります。
ついさっきも色んな曲の制作をしていて一寸くつろいだらそのまま寝てしまい(笑)、変な時間に起きてしまったのでこのまま起きてるか、となってこのブログ、と。
直近で作っていた曲はYMO関連(少し遠いですが)、坂本龍一がポリムーグとローズを使って参加している山下達郎作曲の「KISKA」であります。達郎の「左手五度」の分数コードは結構クセがあって、この分母5度系は坂本龍一もよく使うし、ジャズどころだとチック・コリアがこうやってヴォイシングしたりしますね。B♭ on Cでも左手はC音とG音なので「Gm7 on C」とか「B♭6 / C」風になるというアレですな。坂本龍一も当時はKYLYNの「I’ll Be There」とかでこの手のヴォイシングは多用しているかな、と。
この曲は当時のCBSソニーからリリースしていた企画オムニバスアルバムで、レコーディングは確か信濃町スタジオだったのではないかと。「New York」や「Off Shore」に収録されておりますね。これらのアルバムはYMO関連を追いかけていた人なら間違いなく知っているであろうアルバムでありましょう。YMO名義ではないのにお三方チャッカリ参加してYMO黎明期の実験場のようにしていた感じがあります。
もう2年くらい前からやっていてすっかり手をつけずに月日だけが経過していたんですが(笑)、古い制作ファイル群を整理しようかと眺めていて、ちゃんと作らないとなーと思ってやっていたというワケですね。
村上ポン太秀一のガッド・フリークな音の時代なので、ドラムトラックをアレコレとアサインして音作りが終わった所で一休みしてしまったら寝てしまった、というワケです。左手側にもロー・ミッドのタムを配置しているキット構成がKYLYN Liveのアルバムジャケからも判るんですが、今までで一番驚いたのが、渡辺香津美率いるMobo III時代では全てがロートタムで、ハットは4インチくらいしかない「リン」のシンバルを使っていたのをテレビで見た時ですか。
84~85年頃の金曜日フジテレビ深夜でやっていた、ナントカ倶楽部という番組で渡辺徹が司会をやっていたような記憶が。この番組は年に1回くらい渡辺香津美が出演するので結構チェックしていたモノです。
実は左近治がドラムを叩いていた時に使用していたのがポン太モデルのスティック。その後ピーター・アースキンのスティックを使ってましたっけ。
左近治による「KISKA」の制作が2年ほど頓挫してしまった当時の大きな理由は、ポリムーグの音作りに当時は満足できなかったから、というのは大ウソで(笑)、当時の着うた事情でこの手の曲をリリースするにはまだ早いかな、と思ったのが最大の理由。
2~3年前の着うたは私個人で言えばまだ着メロ引きずったデフォルメ感や音色面で着メロでは再現できないような部分を活かしたかった時代でしたので、こうなったのであります。もちろんそれくらいの辺りから路線を変えずに制作やリリースは可能ではあったんですが、そうなると完全に自分が作りたい(というか心底好きな曲)モノしか作らなくなってしまうであろうことは明白だったので(笑)、他の飛び道具系やら脳幹直撃系が等閑になるな、と思ってそれを回避したというワケです。
メシとスイーツは別腹、という人も多いのと同じ。それらのジャンルでは「別脳」の観点で作らないとダメなので。あ、メシとご飯は違います(笑)。
ところで、「スイーツ」という言葉は受け入れられているのに、オヤジがアウトを「アウツ」と言ったりするのが受け入れられないのは何故でしょうか?。スイーツすらオヤジっぽく聴こえるのに(笑)。
別脳の方で作っているのもアレコレ作ってます。ピンク系が多いかな、と(笑)。
2008-02-17 06:26
ジャズ心を鍛える [クロスオーバー]
シアトル出身の某外国人(男性)と話をしている時。
互いにこれまでの事を話し合っていて、左近治は「やり直せるなら~」という表現をする時に、スティーリー・ダンの「Any World」の歌詞を拝借。「If I had my way」の部分。
これを使って会話をしたら、その人はスティーリー・ダンの「Do It Again」は聴いたことがあるものの、他は全く知らないという人。話が終わって「If I had my way」って凄く胸を打つ表現だと褒められてしまいました(笑)。「ありがとう、フェイゲン!」(笑)。

すぐさま「実はスティーリー・ダンの歌詞なんだ」という事を告げましたけどね(笑)。それほどイイ表現だったとは思いもよらなかったんですが、日本人同士ですら言葉を交わしてもどれだけ通じ合うかは判らないのに、他言語がゆえになせる業なのか!?そんな経験をした覚えがありました。
さてさて本題に戻すとして、ツーファイヴ覚えた程度やモード・スケール一所懸命体系的に覚えた程度じゃまだまだジャズと呼べるにはほど遠く、鍵盤で左手ようやく七度(クラシック的なアカデミック系ヴォイシングはオクターブ)でヴォイシングしようともまだまだ遠いのがジャズ。
ジャズを咀嚼しているという点で左近治が判断するのは、メロディック・マイナーの咀嚼とオルタード・テンションの7thコードを使い分けているか否か!?という点。
例えばA7(♭9、♭13)というコードがあったとすると、このコードの構成音は
=A、C#、E、G + B♭、Fという音ですね。
では、B♭mM7のコードの構成音はというと、
=B♭、D♭(=C#の異名同音)、F、Aという音となりますね。
つまるところ、○○7(-9、-13)というオルタード・テンションのコードがあったら、そこでは半音上のメロディック・マイナーを使ったアプローチが可能ということであり、B♭メロディック・マイナーのモードとして当てはめることができるワケですね。
両者のコードを選択する場合、決定的に違うのはベース音。A音かB♭音ということになりまして、A7(-9、-13)を選択するよりもB♭mM7を選択する方が次のコードへ進行するための調性としては制限されません。
こういう使い分けが出来る人がジャズの造詣が深い(というか、ジャズはこれを使い分けてナンボ)というか、これを使い分ける人は確固たるメロディック・マイナー感を有している人であります。
ところが、メロディック・マイナーの音階は叙情性が希薄なので、「唄える」ほどに咀嚼するのが難しい音階でもあります。ゆえに使いこなせずに、A7(-9、13)を呈示すると水を得た魚のように遊ぶ人が多いのに、B♭mM7を呈示すると途端に目隠しして外歩かせるようなアプローチになってしまう自称「腕自慢」の人もかなり多いワケです(笑)。
B♭mM7をマイナー・メジャー7thコードと捕らえずに、オルタード・テンションをベースに持ってきた分数コードという解釈をして、和声をシンプルに、且つ、上声部で浮遊感のある自由なトライアドとして解釈するのもアリです。これの最たる人がスティーリー・ダンのウォルター・ベッカーが代表的です。
上記の2つのコードの使い分けはジャズでは常套手段でありますので、これからジャズを覚えようとする人には是非知ってもらいたい部分でもあるんですが、実は左近治がリリースする着メロや着うたというのは、楽曲の中に垣間見ることのできる和声で長七度や増四度の面白さがある曲を抜粋しているのを信条としているので、それらの共通項を探って聴いてもらえると楽曲の楽理的な部分での興味深さがお判りいただけると思います。この共通項を見いだせないと、ただ単に「雑多な」ラインナップとして見られてしまうかもしれませんね。別になんでもかんでもやりたい放題の「よろず屋」的な陳列をしているワケではないんですね(笑)。
左近治にとってのスティーリー・ダンとは、当初は「ドナルド・フェイゲンありき」という穿った見方をしていた時期がありまして、ウォルター・ベッカーは殆ど眼中に無かったと言っても過言ではありません。ベッカーが初のソロ・アルバム「11の心象」をリリースして私が耳にするまでは。
「11の心象」を聴いて、ようやくスティーリー・ダンの音はウォルター・ベッカーこそが不可欠だということをまざまざと思い知らされたというワケなんです。その理由は先述にある通り。
それまではフェイゲンの「ナイトフライ」や「KAMAKIRIAD」が既にリリースされていたものですが、心のどこかではブルージィーな曲よりも、「Deacon Blues」や「Glamour Profession」や「Green Earrings」や「Josie」、「Black Friday」のような曲を耳にしたかったんですが、フェイゲンのそれらのアルバムからは私が嘱望していたタイプの曲はそれまで聴くことはできなかったんですね。勿論いい曲ありますけど。「Tomorrrow’s Girls」のイントロはベッカー風(笑)。
なんだかんだで、ベッカーのアルバムの中は一気にそういうフェーズの和声達がこれでもか、とばかりに鏤められており、その後数年が経過して「Negative Giri」を耳にした時は完全ノックアウト状態でありました(笑)。
「もはや、ここまでモノにしないとこの次元に到達できないのか」という感じ。本当に、彼らは「見えないモノが見えちゃってる」位、先行ってると感じました(笑)。
YMO関連曲を手掛けていてもついつい坂本龍一の作品が多くなってしまうのもそういう理由。「A Tribute to NJP」を最近じゃ着うたで3バージョンリリースしている左近治ですが、Kクリデビューの3&4和音時代で既にリリースしていたのは、そういう「テーマ」を名刺代わりにしたつもりでリリースしていた、というワケなんですね。
中にはYMOは盲滅法好きなんだけどジャズは嫌い!というような人、私の周囲にもYMO世代ドンピシャの人が多いんですがそういう人結構居ます(笑)。
でも、共通点を呈示させると食わず嫌いだったのがもの凄く好きになったり、と。そういう人も多いワケですね。
今度リリースされるであろう日野皓正の「Key Breeze」、ジョン・パティトゥッチの「Baja Bajo」やらで是非ともそういう和声の魅力を探ってもらえたらな、と思うワケですね。特に日野皓正のコード・プログレッションは特筆に値します。というか、YMOがバンバン流行ってた頃、左近治は日野皓正の「City Connection」に酔いしれ(笑)、スピノザのチョーキングとアンソニー・ジャクソンのプレベに虜になっていたという当時。周囲はYMOやらホール&オーツの「Maneater」に狂喜乱舞していた時代でしたっけ。
別にジャズやらなくても、アレンジの妙味として知っておきたいMUSTなコードワークとして覚えるのもよろしいかと。
ただ、音楽界というのは楽理など頓珍漢な知識なのに、音質やら音楽の好みという話題になると途端に上から目線の評論家が出現してしまうのが残念なところ。確かな機材や確かな耳に裏打ちされているのはごく僅か。
しかし、そういう人達でも音楽が好きなのは同じ。その人達が理解できるような酒宴の席にてちょっとしたネタにでもなるようなディープな話題があればハナシもはずむってぇワケであります。
楽理なんて音楽やってる人だって敬遠されやすい部分。中にはそんなこと覚える前に自分のセンスだけで勝負したいと言い出す人までいる。しかし平均律の世の中で、耳の鋭敏な人が好むであろう音というのは共通するようで、その音の魅力を追究するとどうしても楽理を覚えてしまうことに。ただ、楽理が最初にあって咀嚼できるのではなく、自分自身が「その音」が好きなのかどうかで道筋は変わるのではないかと思うわけであります。
楽理にほど遠いと思われるであろうロックの世界でも、そういう音は普通に存在するわけでして。共通項を見いだすともはや音楽ジャンルなどは全く無関係になってしまうものでもあります(笑)。
互いにこれまでの事を話し合っていて、左近治は「やり直せるなら~」という表現をする時に、スティーリー・ダンの「Any World」の歌詞を拝借。「If I had my way」の部分。
これを使って会話をしたら、その人はスティーリー・ダンの「Do It Again」は聴いたことがあるものの、他は全く知らないという人。話が終わって「If I had my way」って凄く胸を打つ表現だと褒められてしまいました(笑)。「ありがとう、フェイゲン!」(笑)。

すぐさま「実はスティーリー・ダンの歌詞なんだ」という事を告げましたけどね(笑)。それほどイイ表現だったとは思いもよらなかったんですが、日本人同士ですら言葉を交わしてもどれだけ通じ合うかは判らないのに、他言語がゆえになせる業なのか!?そんな経験をした覚えがありました。
さてさて本題に戻すとして、ツーファイヴ覚えた程度やモード・スケール一所懸命体系的に覚えた程度じゃまだまだジャズと呼べるにはほど遠く、鍵盤で左手ようやく七度(クラシック的なアカデミック系ヴォイシングはオクターブ)でヴォイシングしようともまだまだ遠いのがジャズ。
ジャズを咀嚼しているという点で左近治が判断するのは、メロディック・マイナーの咀嚼とオルタード・テンションの7thコードを使い分けているか否か!?という点。
例えばA7(♭9、♭13)というコードがあったとすると、このコードの構成音は
=A、C#、E、G + B♭、Fという音ですね。
では、B♭mM7のコードの構成音はというと、
=B♭、D♭(=C#の異名同音)、F、Aという音となりますね。
つまるところ、○○7(-9、-13)というオルタード・テンションのコードがあったら、そこでは半音上のメロディック・マイナーを使ったアプローチが可能ということであり、B♭メロディック・マイナーのモードとして当てはめることができるワケですね。
両者のコードを選択する場合、決定的に違うのはベース音。A音かB♭音ということになりまして、A7(-9、-13)を選択するよりもB♭mM7を選択する方が次のコードへ進行するための調性としては制限されません。
こういう使い分けが出来る人がジャズの造詣が深い(というか、ジャズはこれを使い分けてナンボ)というか、これを使い分ける人は確固たるメロディック・マイナー感を有している人であります。
ところが、メロディック・マイナーの音階は叙情性が希薄なので、「唄える」ほどに咀嚼するのが難しい音階でもあります。ゆえに使いこなせずに、A7(-9、13)を呈示すると水を得た魚のように遊ぶ人が多いのに、B♭mM7を呈示すると途端に目隠しして外歩かせるようなアプローチになってしまう自称「腕自慢」の人もかなり多いワケです(笑)。
B♭mM7をマイナー・メジャー7thコードと捕らえずに、オルタード・テンションをベースに持ってきた分数コードという解釈をして、和声をシンプルに、且つ、上声部で浮遊感のある自由なトライアドとして解釈するのもアリです。これの最たる人がスティーリー・ダンのウォルター・ベッカーが代表的です。
上記の2つのコードの使い分けはジャズでは常套手段でありますので、これからジャズを覚えようとする人には是非知ってもらいたい部分でもあるんですが、実は左近治がリリースする着メロや着うたというのは、楽曲の中に垣間見ることのできる和声で長七度や増四度の面白さがある曲を抜粋しているのを信条としているので、それらの共通項を探って聴いてもらえると楽曲の楽理的な部分での興味深さがお判りいただけると思います。この共通項を見いだせないと、ただ単に「雑多な」ラインナップとして見られてしまうかもしれませんね。別になんでもかんでもやりたい放題の「よろず屋」的な陳列をしているワケではないんですね(笑)。
左近治にとってのスティーリー・ダンとは、当初は「ドナルド・フェイゲンありき」という穿った見方をしていた時期がありまして、ウォルター・ベッカーは殆ど眼中に無かったと言っても過言ではありません。ベッカーが初のソロ・アルバム「11の心象」をリリースして私が耳にするまでは。
「11の心象」を聴いて、ようやくスティーリー・ダンの音はウォルター・ベッカーこそが不可欠だということをまざまざと思い知らされたというワケなんです。その理由は先述にある通り。
それまではフェイゲンの「ナイトフライ」や「KAMAKIRIAD」が既にリリースされていたものですが、心のどこかではブルージィーな曲よりも、「Deacon Blues」や「Glamour Profession」や「Green Earrings」や「Josie」、「Black Friday」のような曲を耳にしたかったんですが、フェイゲンのそれらのアルバムからは私が嘱望していたタイプの曲はそれまで聴くことはできなかったんですね。勿論いい曲ありますけど。「Tomorrrow’s Girls」のイントロはベッカー風(笑)。
なんだかんだで、ベッカーのアルバムの中は一気にそういうフェーズの和声達がこれでもか、とばかりに鏤められており、その後数年が経過して「Negative Giri」を耳にした時は完全ノックアウト状態でありました(笑)。
「もはや、ここまでモノにしないとこの次元に到達できないのか」という感じ。本当に、彼らは「見えないモノが見えちゃってる」位、先行ってると感じました(笑)。
YMO関連曲を手掛けていてもついつい坂本龍一の作品が多くなってしまうのもそういう理由。「A Tribute to NJP」を最近じゃ着うたで3バージョンリリースしている左近治ですが、Kクリデビューの3&4和音時代で既にリリースしていたのは、そういう「テーマ」を名刺代わりにしたつもりでリリースしていた、というワケなんですね。
中にはYMOは盲滅法好きなんだけどジャズは嫌い!というような人、私の周囲にもYMO世代ドンピシャの人が多いんですがそういう人結構居ます(笑)。
でも、共通点を呈示させると食わず嫌いだったのがもの凄く好きになったり、と。そういう人も多いワケですね。
今度リリースされるであろう日野皓正の「Key Breeze」、ジョン・パティトゥッチの「Baja Bajo」やらで是非ともそういう和声の魅力を探ってもらえたらな、と思うワケですね。特に日野皓正のコード・プログレッションは特筆に値します。というか、YMOがバンバン流行ってた頃、左近治は日野皓正の「City Connection」に酔いしれ(笑)、スピノザのチョーキングとアンソニー・ジャクソンのプレベに虜になっていたという当時。周囲はYMOやらホール&オーツの「Maneater」に狂喜乱舞していた時代でしたっけ。
別にジャズやらなくても、アレンジの妙味として知っておきたいMUSTなコードワークとして覚えるのもよろしいかと。
ただ、音楽界というのは楽理など頓珍漢な知識なのに、音質やら音楽の好みという話題になると途端に上から目線の評論家が出現してしまうのが残念なところ。確かな機材や確かな耳に裏打ちされているのはごく僅か。
しかし、そういう人達でも音楽が好きなのは同じ。その人達が理解できるような酒宴の席にてちょっとしたネタにでもなるようなディープな話題があればハナシもはずむってぇワケであります。
楽理なんて音楽やってる人だって敬遠されやすい部分。中にはそんなこと覚える前に自分のセンスだけで勝負したいと言い出す人までいる。しかし平均律の世の中で、耳の鋭敏な人が好むであろう音というのは共通するようで、その音の魅力を追究するとどうしても楽理を覚えてしまうことに。ただ、楽理が最初にあって咀嚼できるのではなく、自分自身が「その音」が好きなのかどうかで道筋は変わるのではないかと思うわけであります。
楽理にほど遠いと思われるであろうロックの世界でも、そういう音は普通に存在するわけでして。共通項を見いだすともはや音楽ジャンルなどは全く無関係になってしまうものでもあります(笑)。
2008-02-11 13:56
サンプリング・ピアノをふりかえる [クロスオーバー]
今でこそ全鍵サンプリングが珍しくなくなったサンプリング・ピアノでありますが、PCM音源、すなわちデジタル・ピアノ黎明期の頃はですね、それはもう倍音部分を聴くとハチャメチャなモノが実に多くてですね(笑)、「コレでピアノと呼んでイイのか!?」と感じたことしきり。
現在と違ってメモリの容量なんて非常に限られていてその制約の中でやりくりしていた、と。しかし、例えば「ド」の音をサンプリングしても、お隣の鍵盤「レ」もデジタル的に再生スピードを変えてピッチを保っている。すなわち同じサンプルを他の鍵盤でも代用することで、再生スピードはもとより、ループ部分の範囲すらもサンプルを代用しつつ再生スピードを変えているだけですから、場合によっては高次倍音成分のフェイジングとか起きたりしていたんですね。
判りやすく言えば、倍音成分に顕著に現れる音の周期的なゆらぎ。これが「モワ~ン」といううなりでゆったりとしたLFO(笑)で空間系エフェクト施したのか!?と思わんばかりの音になってしまったり、或いはトライアドを普通に弾いているだけなのに、ヴォイシングによっては長九度部分の音が付加されてadd9のコードに聴こえてしまったり(笑)、果ては増4度の音まで聴こえてきたりするサンプリング・ピアノなど非常に多く出くわしたモノでありました。(※ あくまでも和声を鳴らした時のバラつきでそうなるので、鍵盤1つ弾いた程度ではサンプルのループポイントが判る程度ですので混同しないように)
「こんなに変な音になるようじゃ、マイナー・メジャー7thなんか綺麗に響くワケがない!」
左近治は別にピアノ弾きではない(笑)。だけれどもそこまでピアノ音にこだわる必要もないから、そういうサンプリング・ピアノは敬遠していた時期がありました。
アップライト・ピアノですら反響版を開けて弾いている人なんて実際は少ない(笑)。中古ピアノの展示場なんて調律こそされているものの、音域によっては音ムラが非常にバラつきの多いモノが圧倒的(笑)。前オーナーは結構巧かった人だったんだなぁと思わせるピアノに出会うのは意外に少ないモノです。
サンプリングではないモノホンのピアノの音の素顔も知らないまま弾いている人が多いから騙せてしまうものなのでしょうかね(笑)。
マイナー・メジャー7thというコードは、長七度音程に慣れていない人ならばメジャー7thの和声よりも取っ付きにくい和声でありましょう。ビートルズのミシェルのように経過音的にクリシェで出現させるような展開ならまだしも、独立した和声で響かせた場合、多くの人はその魅力が解らない敬遠されがちな和声でもありますが、左近治は非常に好きな和声でもあります(笑)。
旋律的短音階=メロディック・マイナーとは、Cを基準にすれば「ミ」だけがフラットした音で後は白鍵であります。さらに全音音階(=ホールトーン・スケール)を除けば、音階中に最も全音音程が連続して出現する特異な音階でもありまして、マイナー・メジャー7thの和声はこういう音階を示唆してくれるんですな。
とりわけ半音(=転回すれば長七度)の響きが好きな左近治でありますが、モードとしてのダイアトニック・スケールで見ると、半音の音程が多く出現する音階というのは意外に少なく、ジプシー・スケール(=ハンガリアン・マイナー・スケール)は半音が4つも現れてくれる。すなわちダイアトニック・コードを形成すると長七度音程を持つコードが4種類も現れてくれる、と(笑)。これで楽曲を成立させてしまった代表曲は以前にも取り上げた坂本龍一作曲の「Elastic Dummy」。高橋ユキヒロのソロ・アルバム「Saravah!」に収録されている曲ですね。
半音の追究を「陽」とするならば、全音は「陰」とでも呼べるといいますか(笑)。半音の美しさと全音音程の連なりで中性的な響きの両方を兼備しているようなメロディック・マイナーは実に多様な魅力を備えているんですな。
マイナー・メジャーをうまく咀嚼できていないと、マイナー・メジャー7thコードを弾いてもトライトーンを示唆する音程関係(増5度間に内包される音列に増四度も含んでいるから)を有しているため、ボキャブラリーの少ない人だと使いこなせないワケです(笑)。和声として巧く機能させるには、少々安定感を得る為にマイナー・メジャー7thに9thや11th音を加えたりします。こうすることでマイナー・メジャーの本来持っている性格が理解しやすくなるモンなんですな。
さらにはマイナー・メジャー9thの根音の下方に3度音程を加えるとして、例えばCmM9にA♭音を加えれば、G△/A♭△というポリ・コードの出来上がり、と(笑)。マイナー・メジャー7thから音を重畳させるだけでこれだけの多様性を演出できて、VI♭音を加えればディミニッシュの応用にも繋がる、と。半音を意識しつつ全音音程の多くの連なりを有して減三和音への発想にも応用できる、と。
ひとつのモードで一挙両得どころか3倍オイシイ和声なんですな(笑)。
まあ、こういう発想で重畳させた和声の一部をomitして、もっとシンプルに響かせるコトも可能です。見慣れない分数コードになったりしますが、こういうのを追究するとウォルター・ベッカー風になります。Kクリで着うたが開始される前、私はウォルター・ベッカーの1stソロ・アルバム「11の心象」にボーナストラックとして収録の「Medical Science」という曲を当初はリリースしたくですね(笑)、出先でGaragaBand使いながら打ち込んでいた時があったんですが、あんなにシンプルな楽曲なのに、そのトンデモない和声構造をあらためて分析してみたら「コレはリリースできない(笑)」と、当時は断念した覚えがあります。見事なまでの音のomitと、その空間をモーダルに唄っているベッカーのフレーズはもはや計算されているんですね。ただ単にシンプルな音なのではないということを思い知ったワケです。他に全くアイデアを浮かばせてくれないほどだったんです(笑)。
今まで「断念」した曲というのは意外と少ない方ですが(お暗入りはまた別)、Medical Scienceは本当に鬼門です(笑)。
まあ、ハナシは長くなりましたが、そういう興味深い和声を「より汚く」聴かせてしまうコトだけは回避したいのでありまして、昔はそれがサンプリング・ピアノだったなあと痛感したワケでした。それと同時に難解な和声の響きを本当に理解するには、きちんとした発音による音ではないともはや倍音成分でジャマされる、というコトもあらためてその当時認識したワケだったんですね。
現在と違ってメモリの容量なんて非常に限られていてその制約の中でやりくりしていた、と。しかし、例えば「ド」の音をサンプリングしても、お隣の鍵盤「レ」もデジタル的に再生スピードを変えてピッチを保っている。すなわち同じサンプルを他の鍵盤でも代用することで、再生スピードはもとより、ループ部分の範囲すらもサンプルを代用しつつ再生スピードを変えているだけですから、場合によっては高次倍音成分のフェイジングとか起きたりしていたんですね。
判りやすく言えば、倍音成分に顕著に現れる音の周期的なゆらぎ。これが「モワ~ン」といううなりでゆったりとしたLFO(笑)で空間系エフェクト施したのか!?と思わんばかりの音になってしまったり、或いはトライアドを普通に弾いているだけなのに、ヴォイシングによっては長九度部分の音が付加されてadd9のコードに聴こえてしまったり(笑)、果ては増4度の音まで聴こえてきたりするサンプリング・ピアノなど非常に多く出くわしたモノでありました。(※ あくまでも和声を鳴らした時のバラつきでそうなるので、鍵盤1つ弾いた程度ではサンプルのループポイントが判る程度ですので混同しないように)
「こんなに変な音になるようじゃ、マイナー・メジャー7thなんか綺麗に響くワケがない!」
左近治は別にピアノ弾きではない(笑)。だけれどもそこまでピアノ音にこだわる必要もないから、そういうサンプリング・ピアノは敬遠していた時期がありました。
アップライト・ピアノですら反響版を開けて弾いている人なんて実際は少ない(笑)。中古ピアノの展示場なんて調律こそされているものの、音域によっては音ムラが非常にバラつきの多いモノが圧倒的(笑)。前オーナーは結構巧かった人だったんだなぁと思わせるピアノに出会うのは意外に少ないモノです。
サンプリングではないモノホンのピアノの音の素顔も知らないまま弾いている人が多いから騙せてしまうものなのでしょうかね(笑)。
マイナー・メジャー7thというコードは、長七度音程に慣れていない人ならばメジャー7thの和声よりも取っ付きにくい和声でありましょう。ビートルズのミシェルのように経過音的にクリシェで出現させるような展開ならまだしも、独立した和声で響かせた場合、多くの人はその魅力が解らない敬遠されがちな和声でもありますが、左近治は非常に好きな和声でもあります(笑)。
旋律的短音階=メロディック・マイナーとは、Cを基準にすれば「ミ」だけがフラットした音で後は白鍵であります。さらに全音音階(=ホールトーン・スケール)を除けば、音階中に最も全音音程が連続して出現する特異な音階でもありまして、マイナー・メジャー7thの和声はこういう音階を示唆してくれるんですな。
とりわけ半音(=転回すれば長七度)の響きが好きな左近治でありますが、モードとしてのダイアトニック・スケールで見ると、半音の音程が多く出現する音階というのは意外に少なく、ジプシー・スケール(=ハンガリアン・マイナー・スケール)は半音が4つも現れてくれる。すなわちダイアトニック・コードを形成すると長七度音程を持つコードが4種類も現れてくれる、と(笑)。これで楽曲を成立させてしまった代表曲は以前にも取り上げた坂本龍一作曲の「Elastic Dummy」。高橋ユキヒロのソロ・アルバム「Saravah!」に収録されている曲ですね。
半音の追究を「陽」とするならば、全音は「陰」とでも呼べるといいますか(笑)。半音の美しさと全音音程の連なりで中性的な響きの両方を兼備しているようなメロディック・マイナーは実に多様な魅力を備えているんですな。
マイナー・メジャーをうまく咀嚼できていないと、マイナー・メジャー7thコードを弾いてもトライトーンを示唆する音程関係(増5度間に内包される音列に増四度も含んでいるから)を有しているため、ボキャブラリーの少ない人だと使いこなせないワケです(笑)。和声として巧く機能させるには、少々安定感を得る為にマイナー・メジャー7thに9thや11th音を加えたりします。こうすることでマイナー・メジャーの本来持っている性格が理解しやすくなるモンなんですな。
さらにはマイナー・メジャー9thの根音の下方に3度音程を加えるとして、例えばCmM9にA♭音を加えれば、G△/A♭△というポリ・コードの出来上がり、と(笑)。マイナー・メジャー7thから音を重畳させるだけでこれだけの多様性を演出できて、VI♭音を加えればディミニッシュの応用にも繋がる、と。半音を意識しつつ全音音程の多くの連なりを有して減三和音への発想にも応用できる、と。
ひとつのモードで一挙両得どころか3倍オイシイ和声なんですな(笑)。
まあ、こういう発想で重畳させた和声の一部をomitして、もっとシンプルに響かせるコトも可能です。見慣れない分数コードになったりしますが、こういうのを追究するとウォルター・ベッカー風になります。Kクリで着うたが開始される前、私はウォルター・ベッカーの1stソロ・アルバム「11の心象」にボーナストラックとして収録の「Medical Science」という曲を当初はリリースしたくですね(笑)、出先でGaragaBand使いながら打ち込んでいた時があったんですが、あんなにシンプルな楽曲なのに、そのトンデモない和声構造をあらためて分析してみたら「コレはリリースできない(笑)」と、当時は断念した覚えがあります。見事なまでの音のomitと、その空間をモーダルに唄っているベッカーのフレーズはもはや計算されているんですね。ただ単にシンプルな音なのではないということを思い知ったワケです。他に全くアイデアを浮かばせてくれないほどだったんです(笑)。
今まで「断念」した曲というのは意外と少ない方ですが(お暗入りはまた別)、Medical Scienceは本当に鬼門です(笑)。
まあ、ハナシは長くなりましたが、そういう興味深い和声を「より汚く」聴かせてしまうコトだけは回避したいのでありまして、昔はそれがサンプリング・ピアノだったなあと痛感したワケでした。それと同時に難解な和声の響きを本当に理解するには、きちんとした発音による音ではないともはや倍音成分でジャマされる、というコトもあらためてその当時認識したワケだったんですね。
2008-01-15 13:50
ハモンドB-3を語ってみる [クロスオーバー]
普段はデジタルな話題になりがちだったので、今回はオルガン、と。半拍半フレーズの16分音符3つ分の音価に4つや5つとかの音詰め込んで不思議な連符を「勢い」で弾いたりとかですね、そういったプレイというのは他の楽器から見て非常に参考になる部分があるんですね。それを右手と左手で別のリズムをこれまた「勢い」で弾く、と。例えば左手は2拍3連のアクセントで4連(つまり1拍6連の4つフレーズ)刻みながら右手で16分音符かき鳴らし、とか。
こういうプレイを肌で覚えると、「幻想即興曲」のタイム感がようやく体得できたりとか色んなメリットがあるワケですね。
そういったプレイ的な側面とは別に、レスリースピーカーのもたらす音色変化やパーカッションスイッチを入れて少しだけアタッキーにした音を少しディストーション系で歪ませてみたりとか(笑)。
僅かに歪んでくれる(ひずみ)B-3の音ってこれまた心地良いモノがあったりするんですな。オルガンという楽器ではあるものの、音色面においては実に多様的なワケで、特に60年代の音源とかはハモンドによる「シンセサイズ」とでも形容しましょうか、そういった音を作って、まだまだ身近ではなかったシンセサイザーを充分に代用されていたワケであります。
今回は、あなくろ本舗にてGentle Giantのアルバム「Interview」収録の同名タイトル『Interview』のブリッジ部をきらびやかなシンセの音を混ぜてリリースしているのでありますが、ジェントル・ジャイアントのケリー・ミネアーは結構B-3のパーカッションスイッチのみの音色を多用するんですね。つまり、エレピっぽい音を得ているというワケであります。
ハモンドをしゃぶり尽くしているようなタイプのプレイヤーなら大概はそういう音も使うワケでありますが、あまりにハモンド漬けにシフトされてしまっているプレイヤーはそんな音の時にエレピっぽいフレーズはあまり弾かないコトが多かったりもするんですな(笑)。
ところがケリー・ミネアーやパトリック・モラツはチト違う。エレピっぽいセンスを存分に堪能できるタイプのプレイヤーなんですね。
PFM(Premiata Forneria Marconi)を聴いたって確かにパーカッションスイッチは使っても、それはやっぱり「オルガン」的なプレー。そういうタイプの音やフレーズもアリではあるんですが、プレイの多様性とヴォイシングの使い分けというのが先のお二人はさりげなく巧いんですね。
ソフト音源にて色々リリースされているB-3系の音源ですが、パーカッションスイッチオンリーの音色となると、まだまだ本物ほどの多様性に乏しいというのが左近治の印象でして、そんな中今回私がリリーした曲はLogic Pro内蔵の音源にてどうにか混ぜている、というワケであります(笑)。
パーカッションスイッチを巧みに使ってエレピっぽく弾いているという名曲はですね
Proclamation / Gentle Giant
Interview / Gentle Giant
Kabala / Patrick Moraz
辺りがオススメですね。特にパトリック・モラツの「Kabala」はプログレやロック畑にカテゴライズするには勿体無いほどのクロスオーバー・サウンドを構築しております(笑)。
とまあ、そんな一方で悟生楽横町の方では何故か「モグタン」関連のBGMをリリースしている左近治なんですが(笑)、こういう飛び道具系も久々リリースしないとなあ、と思いましてですね、これまたモンドなラインナップとなっているワケでありますね、ハイ。
左近治にとってモグタンとは結構縁深いと言いますか(笑)、当時のKクリのオーディションで私が応募したのは他でもない、「まんがはじめて物語」のオープニングテーマである「不思議な旅」のパーカッシヴなアレンジで応募したという経緯があるんで、そういう意味で縁深いというワケであります。
今回のモグタンのBGMは、いわゆる実写からアニメに切り替わる時の呪文ですね(笑)。モグタンが真ん丸になって宇宙を縦横無尽にバウンドしてる時の(笑)。たまたまムーグ系の音を作っていた時に思い付いたので作っちゃったんですけどね(笑)。正直、工数「1」です(笑)。着うたファイルコンバートの作業を除けば10分要していません。
でもですね、これだけ手を掛けなくても、原曲が素朴でありながら「効果」を的確に得ている楽曲(BGM)というのは、訴求力に衰えというものは感じないモンなんです。手間暇掛ける掛けないで語るモノではなく、それだけ元の曲がキャッチーだというコトなんです(笑)。
オルガンのパーカッションスイッチやら、シンセの素朴な音など。楽器の個性をそのまま最大限に活かして効果的な音を作りだすということは、趣きが全く異なる音楽であっても、音に対する魅力というのを実感しているからこそ具現化されているというワケで、ひとつの楽器に対して弄り倒すとでもいいましょうか、そういう追究を垣間見ることが出来るのが音楽の奥深い部分であります。
こういうプレイを肌で覚えると、「幻想即興曲」のタイム感がようやく体得できたりとか色んなメリットがあるワケですね。
そういったプレイ的な側面とは別に、レスリースピーカーのもたらす音色変化やパーカッションスイッチを入れて少しだけアタッキーにした音を少しディストーション系で歪ませてみたりとか(笑)。
僅かに歪んでくれる(ひずみ)B-3の音ってこれまた心地良いモノがあったりするんですな。オルガンという楽器ではあるものの、音色面においては実に多様的なワケで、特に60年代の音源とかはハモンドによる「シンセサイズ」とでも形容しましょうか、そういった音を作って、まだまだ身近ではなかったシンセサイザーを充分に代用されていたワケであります。
今回は、あなくろ本舗にてGentle Giantのアルバム「Interview」収録の同名タイトル『Interview』のブリッジ部をきらびやかなシンセの音を混ぜてリリースしているのでありますが、ジェントル・ジャイアントのケリー・ミネアーは結構B-3のパーカッションスイッチのみの音色を多用するんですね。つまり、エレピっぽい音を得ているというワケであります。
ハモンドをしゃぶり尽くしているようなタイプのプレイヤーなら大概はそういう音も使うワケでありますが、あまりにハモンド漬けにシフトされてしまっているプレイヤーはそんな音の時にエレピっぽいフレーズはあまり弾かないコトが多かったりもするんですな(笑)。
ところがケリー・ミネアーやパトリック・モラツはチト違う。エレピっぽいセンスを存分に堪能できるタイプのプレイヤーなんですね。
PFM(Premiata Forneria Marconi)を聴いたって確かにパーカッションスイッチは使っても、それはやっぱり「オルガン」的なプレー。そういうタイプの音やフレーズもアリではあるんですが、プレイの多様性とヴォイシングの使い分けというのが先のお二人はさりげなく巧いんですね。
ソフト音源にて色々リリースされているB-3系の音源ですが、パーカッションスイッチオンリーの音色となると、まだまだ本物ほどの多様性に乏しいというのが左近治の印象でして、そんな中今回私がリリーした曲はLogic Pro内蔵の音源にてどうにか混ぜている、というワケであります(笑)。
パーカッションスイッチを巧みに使ってエレピっぽく弾いているという名曲はですね
Proclamation / Gentle Giant
Interview / Gentle Giant
Kabala / Patrick Moraz
辺りがオススメですね。特にパトリック・モラツの「Kabala」はプログレやロック畑にカテゴライズするには勿体無いほどのクロスオーバー・サウンドを構築しております(笑)。
とまあ、そんな一方で悟生楽横町の方では何故か「モグタン」関連のBGMをリリースしている左近治なんですが(笑)、こういう飛び道具系も久々リリースしないとなあ、と思いましてですね、これまたモンドなラインナップとなっているワケでありますね、ハイ。
左近治にとってモグタンとは結構縁深いと言いますか(笑)、当時のKクリのオーディションで私が応募したのは他でもない、「まんがはじめて物語」のオープニングテーマである「不思議な旅」のパーカッシヴなアレンジで応募したという経緯があるんで、そういう意味で縁深いというワケであります。
今回のモグタンのBGMは、いわゆる実写からアニメに切り替わる時の呪文ですね(笑)。モグタンが真ん丸になって宇宙を縦横無尽にバウンドしてる時の(笑)。たまたまムーグ系の音を作っていた時に思い付いたので作っちゃったんですけどね(笑)。正直、工数「1」です(笑)。着うたファイルコンバートの作業を除けば10分要していません。
でもですね、これだけ手を掛けなくても、原曲が素朴でありながら「効果」を的確に得ている楽曲(BGM)というのは、訴求力に衰えというものは感じないモンなんです。手間暇掛ける掛けないで語るモノではなく、それだけ元の曲がキャッチーだというコトなんです(笑)。
オルガンのパーカッションスイッチやら、シンセの素朴な音など。楽器の個性をそのまま最大限に活かして効果的な音を作りだすということは、趣きが全く異なる音楽であっても、音に対する魅力というのを実感しているからこそ具現化されているというワケで、ひとつの楽器に対して弄り倒すとでもいいましょうか、そういう追究を垣間見ることが出来るのが音楽の奥深い部分であります。
2007-12-01 16:22
秋のマジ曲週間 [クロスオーバー]
さてさて、産声をあげた時からネイティヴおバカな左近治がマジ曲制作連発しているワケでございますが、明日10月12日リリースの曲はですね『Outubro』。あなくろ本舗にて。
今回リリースするのはクロスオーバー・イレブンでのエンディング曲として知られているアジムスのバージョンを模倣したものでして、アジムスのそれよりもエグいフレットレス・ベースの音をフィーチャーしております(笑)。原曲はミルトン・ナシメントの曲で、こちらもシラフじゃ聴くのが勿体ないほどのトライバル感が出ているのですが、曲を知らないけれども興味のある方は是非ともお聴きになっていただきたいと思います。原曲を(笑)。
アジムスもミルトン・ナシメントの方もどちらもiTunes Storeにて聴くことができますので。
今回制作面で力を入れたのは、やはりフレットレス・ベースの音。コレばかりは聴いていただくしかありませんな。ピノ・パラディーノやマーク・イーガン系の音になっているのではないかなあと思って作ったんですけどね。ジャコではないんです(笑)。ミック・カーンでもないんです(笑)。ミック・カーンはいずれ披露することになると思いますが(笑)。
私が好きなフレットレス・ベース奏者は沢山いますが、その中でもピッチの正確さが大好きなのがアルフォンソ・ジョンソンですね。一回しか生で見た事がありませんが。
15年くらい前に渋谷にて、トム・コスター(Kb)を中心にスティーヴ・スミス(Ds)、スコット・ヘンダーソン(Gt)、アルフォンソ・ジョンソン(Bs)という面々で、スティーヴ・スミスの当時の「フィアフィアーガ」を基本とするバンド構成でしたねえ。12プライ時代のSONORのシグネイチャーで、スティックのほぼ中心を握ってレギュラー・グリップで叩き続けるスティーヴ・スミスのダブル・ストロークって結構好きなんですよねえ。当時2nd rev.のSMF対応にした時のKORG 01W/FDのデモソングでトム・コスターの「The Perfect Date」がSMFデータで収録されていましたから当時のビッグヒットのシンセ01/Wをお持ちの方は「あの曲の人か」と思われる方もいらっしゃると思うんですが、そんな話はさておき、私はアルフォンソ・ジョンソンの音が一番好きなんだぞ、と。
その当時、アルフォンソはモデュラスのQuantumベースの5弦フレットレス(35インチ尺)使ってましたけどね。スティックの教則本にもアルフォンソは載っているんですが、アルフォンソのスティックって未だかつて耳にしたことがないんですよねー・・・。ジャコの教則ビデオではカール・トンプソンのベースをジャコに弾かせていたシーンがあったような記憶が懐かしいです(笑)。
今回目指した音はピノ・パラディーノが弾く、ビル・シャープの1stソロアルバム「Famous People」に収録の「Fools in A World of Fire」という曲を参考にしました。あっちはスティングレイなんですけどね(笑)。このEQカーブを可能な限り模倣したという次第でございます(笑)。ピノは何処どこアイスの子ぉ~♪(by 矢野顕子)というCMもありましたなあー。おそらくパンチラシーンを思い出すオジサンも相当数いらっしゃると思いますが、おバカに今日もシメることが出来て、左近治、今宵も感慨無量でございます。
今回リリースするのはクロスオーバー・イレブンでのエンディング曲として知られているアジムスのバージョンを模倣したものでして、アジムスのそれよりもエグいフレットレス・ベースの音をフィーチャーしております(笑)。原曲はミルトン・ナシメントの曲で、こちらもシラフじゃ聴くのが勿体ないほどのトライバル感が出ているのですが、曲を知らないけれども興味のある方は是非ともお聴きになっていただきたいと思います。原曲を(笑)。
アジムスもミルトン・ナシメントの方もどちらもiTunes Storeにて聴くことができますので。
今回制作面で力を入れたのは、やはりフレットレス・ベースの音。コレばかりは聴いていただくしかありませんな。ピノ・パラディーノやマーク・イーガン系の音になっているのではないかなあと思って作ったんですけどね。ジャコではないんです(笑)。ミック・カーンでもないんです(笑)。ミック・カーンはいずれ披露することになると思いますが(笑)。
私が好きなフレットレス・ベース奏者は沢山いますが、その中でもピッチの正確さが大好きなのがアルフォンソ・ジョンソンですね。一回しか生で見た事がありませんが。
15年くらい前に渋谷にて、トム・コスター(Kb)を中心にスティーヴ・スミス(Ds)、スコット・ヘンダーソン(Gt)、アルフォンソ・ジョンソン(Bs)という面々で、スティーヴ・スミスの当時の「フィアフィアーガ」を基本とするバンド構成でしたねえ。12プライ時代のSONORのシグネイチャーで、スティックのほぼ中心を握ってレギュラー・グリップで叩き続けるスティーヴ・スミスのダブル・ストロークって結構好きなんですよねえ。当時2nd rev.のSMF対応にした時のKORG 01W/FDのデモソングでトム・コスターの「The Perfect Date」がSMFデータで収録されていましたから当時のビッグヒットのシンセ01/Wをお持ちの方は「あの曲の人か」と思われる方もいらっしゃると思うんですが、そんな話はさておき、私はアルフォンソ・ジョンソンの音が一番好きなんだぞ、と。
その当時、アルフォンソはモデュラスのQuantumベースの5弦フレットレス(35インチ尺)使ってましたけどね。スティックの教則本にもアルフォンソは載っているんですが、アルフォンソのスティックって未だかつて耳にしたことがないんですよねー・・・。ジャコの教則ビデオではカール・トンプソンのベースをジャコに弾かせていたシーンがあったような記憶が懐かしいです(笑)。
今回目指した音はピノ・パラディーノが弾く、ビル・シャープの1stソロアルバム「Famous People」に収録の「Fools in A World of Fire」という曲を参考にしました。あっちはスティングレイなんですけどね(笑)。このEQカーブを可能な限り模倣したという次第でございます(笑)。ピノは何処どこアイスの子ぉ~♪(by 矢野顕子)というCMもありましたなあー。おそらくパンチラシーンを思い出すオジサンも相当数いらっしゃると思いますが、おバカに今日もシメることが出来て、左近治、今宵も感慨無量でございます。
2007-10-12 00:15
Logic8でRhodesサウンドメイキング [クロスオーバー]
まあ、のっけからブライトなRhodesの音を用いたサンプルを提示してみたワケでありますが、Logic8からChannel EQのQ幅特性がかなり変更されて色々と選択可能になったので、かなり音作りに役立てることとなったワケであります。
再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら
Logic内蔵のエレピEVP-88は物理モデルタイプのエレピ音源でありまして、フィジカル・モデリングという処理によって色んなキャラクターのエレピを発音させているのですが、従来はエグみのある中域ふくよかなセッティングが多かったものの、この手のブライトなトーンの音はEVP単体の「クセ」を熟知した上でEQのセッティングもなかなか1つでは得られなかったりした左近治でありました。
まあ、今回Logic8の地味ではあるものの、EQとコンプ類はサイドチェーン応答特性も含めてかなりオイシイ内容になっているので、ここぞとばかりにブライト系のローズサウンドを作ってみたというワケであります。
MP3で使用した他のアンサンブルはApple Loopを加工したものです。
例えばバスドラはゲートとサイドチェーンを使って少々デッドに仕上げていますが、バスドラのこの手の音の場合、左近治は、最低域にピークを作った帯域から1オクターブ+完全五度から2オクターブ上の帯域を狭いQ幅でカッとすることがキモなんですな。
例えば60Hzの2オクターブ上は240Hzというように。
こうすると太さがありながらもタイトに引き締まって前に出てくれる音になるワケで、少々中音域付近の分布が多いローズの音をうまい事馴染ませつつ、高域のブライトな音に彩りを添えようという狙いでこういう音にしてみたんですな。
ややもするとシンセのフィルタードシーケンスは不要だったかも、と思うのでありますが、まあ、オケが貧弱になるよりかはマシだろ、と思いましてですね(笑)。
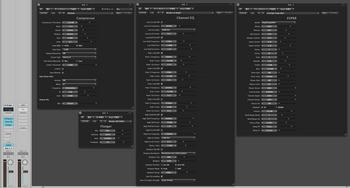
肝心のローズセッティングは上記の画像の通りですな。
コーラスではなくてフランジャーを使っているのは、フィードバックがあるかないかの辺りで、逆相で特定の周波数帯域が相殺してくれることを狙ってマイナス値のフィードバック量を与えております。こうすることでコーラスのデチューンによってブライトな成分をやたらと強調しかねない音を抑えつつ、ドライ時の音とキャラクターが大きく変貌を遂げないようにしているセッティングなのであります。
ひとつ注意なのは、96kHzサンプルレート周波数のセッティングで語っているので、44.1kHzで制作している人は同じセッティングであってもこの周波数レスポンスは得られないので注意が必要です。まあ、どことなく似るという風にはなるでしょうが、中低域辺りが相対的にブーミーな感じになると思います。
で、EVP側でベースのEQはカットしているのに、後段のEQで再び持ち上げているのは、これこそが物理モデルの「クセ」でありまして、プラマイゼロ的なEQとは全く異なるからこそ、敢えてこうしているというワケであります。
物理モデルが故に、こうした前段のクセと後段処理の妙味が活きる、というワケです。
視聴曲補足
ええと、またまた老婆心ムキ出しで視聴曲のコード進行をとりあえず載せておこうかな、と。まあ、語る必要もないかとは思うんですが念のため(笑)。
Cm9(11)→A♭M9(#11,13) on B♭→G♭M7(#11,13)→BM7(9,#11)
とまあ、こんな感じですか。2つ目のコードは2ndベースにしてるんでアッパーのコードに耳持ってかれないよう注意が必要ですよ(笑)。まあ、エンディングのアレンジとかに使える便利な、ひとつのモチーフに対してリハーモナイズさせていく、と。
最後のコードをですね、メジャー7thでサークルof 5thでパラレルモーションさせずにですね、A7(9,#11,13)としちゃうと、坂本龍一の『きみについて』系になります(笑)。つまるところ、想定される5度進行と同じ構成音をアッパーに持つ7thコードに行かせちゃうというやり方ですな。まあ、色んな遊び方ができるってェもんですな。
そうそう。坂本龍一の『きみについて』もきちんと制作中ですので(笑)。リリースされた時には記念に、イントロのPluck系サウンドをSculptureで模倣した音色データでも披露してみましょうかね、と。
再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら
Logic内蔵のエレピEVP-88は物理モデルタイプのエレピ音源でありまして、フィジカル・モデリングという処理によって色んなキャラクターのエレピを発音させているのですが、従来はエグみのある中域ふくよかなセッティングが多かったものの、この手のブライトなトーンの音はEVP単体の「クセ」を熟知した上でEQのセッティングもなかなか1つでは得られなかったりした左近治でありました。
まあ、今回Logic8の地味ではあるものの、EQとコンプ類はサイドチェーン応答特性も含めてかなりオイシイ内容になっているので、ここぞとばかりにブライト系のローズサウンドを作ってみたというワケであります。
MP3で使用した他のアンサンブルはApple Loopを加工したものです。
例えばバスドラはゲートとサイドチェーンを使って少々デッドに仕上げていますが、バスドラのこの手の音の場合、左近治は、最低域にピークを作った帯域から1オクターブ+完全五度から2オクターブ上の帯域を狭いQ幅でカッとすることがキモなんですな。
例えば60Hzの2オクターブ上は240Hzというように。
こうすると太さがありながらもタイトに引き締まって前に出てくれる音になるワケで、少々中音域付近の分布が多いローズの音をうまい事馴染ませつつ、高域のブライトな音に彩りを添えようという狙いでこういう音にしてみたんですな。
ややもするとシンセのフィルタードシーケンスは不要だったかも、と思うのでありますが、まあ、オケが貧弱になるよりかはマシだろ、と思いましてですね(笑)。
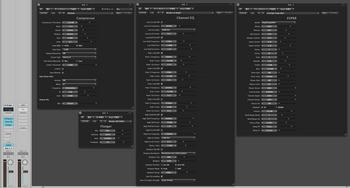
肝心のローズセッティングは上記の画像の通りですな。
コーラスではなくてフランジャーを使っているのは、フィードバックがあるかないかの辺りで、逆相で特定の周波数帯域が相殺してくれることを狙ってマイナス値のフィードバック量を与えております。こうすることでコーラスのデチューンによってブライトな成分をやたらと強調しかねない音を抑えつつ、ドライ時の音とキャラクターが大きく変貌を遂げないようにしているセッティングなのであります。
ひとつ注意なのは、96kHzサンプルレート周波数のセッティングで語っているので、44.1kHzで制作している人は同じセッティングであってもこの周波数レスポンスは得られないので注意が必要です。まあ、どことなく似るという風にはなるでしょうが、中低域辺りが相対的にブーミーな感じになると思います。
で、EVP側でベースのEQはカットしているのに、後段のEQで再び持ち上げているのは、これこそが物理モデルの「クセ」でありまして、プラマイゼロ的なEQとは全く異なるからこそ、敢えてこうしているというワケであります。
物理モデルが故に、こうした前段のクセと後段処理の妙味が活きる、というワケです。
視聴曲補足
ええと、またまた老婆心ムキ出しで視聴曲のコード進行をとりあえず載せておこうかな、と。まあ、語る必要もないかとは思うんですが念のため(笑)。
Cm9(11)→A♭M9(#11,13) on B♭→G♭M7(#11,13)→BM7(9,#11)
とまあ、こんな感じですか。2つ目のコードは2ndベースにしてるんでアッパーのコードに耳持ってかれないよう注意が必要ですよ(笑)。まあ、エンディングのアレンジとかに使える便利な、ひとつのモチーフに対してリハーモナイズさせていく、と。
最後のコードをですね、メジャー7thでサークルof 5thでパラレルモーションさせずにですね、A7(9,#11,13)としちゃうと、坂本龍一の『きみについて』系になります(笑)。つまるところ、想定される5度進行と同じ構成音をアッパーに持つ7thコードに行かせちゃうというやり方ですな。まあ、色んな遊び方ができるってェもんですな。
そうそう。坂本龍一の『きみについて』もきちんと制作中ですので(笑)。リリースされた時には記念に、イントロのPluck系サウンドをSculptureで模倣した音色データでも披露してみましょうかね、と。
2007-10-04 13:17
Azymuthに酔いしれようぜ! [クロスオーバー]
『Azymuth』ってなあに?
え~とですね、ここで語るのはブラジルのクロスオーバー系バンドの「アジムス」のコトでやんす。NHK-FMで午後11時から津嘉山正種のナレーションで、毎週平日はモンドな選曲で多彩なジャンルの音楽が流れておりましたね。往年の名ラジオ番組だったワケですね。また、選曲具合も、その辺でやたらと耳にするような雑多なタイプのものとは違う、関係者の音楽の造詣の深さやセンスの良さを思い知ることができたものであります。ある意味、左近治のKクリにおけるモンドなスタイルというのは、クロスオーバー・イレブンが参考になっております(笑)。
ま、こういうモンドで感性豊かな曲を楽しませるのは、いわゆる「渋谷系」の原点のような気がするんですなあ。まあ、NHKも渋谷にありますし。
現在、左近治がKクリにおいてアジムス関連をリリースしているのは、着メロの方での「Fly Over the Horizon」。
午後11時の時報が鳴り止むと、クロスオーバー・イレブンのイントロ音楽が始まる、と。それがこの「Fly Over the Horizon」だったワケですな。
アジムスというと、私にとってはARP2600に浸れることができるバンドのひとつだったワケでして、90年代に入ると無性にARP2600を欲しがっていたもので、Swing Out Sisterのキーボードの方が「ARP2600」を手に入れた、みたいな記事を雑誌で見かけたりすると、なにくそ!とばかりに左近治も現物探しに行ったりしたものでありました(笑)。立場が全然違うというのに、そこまで闘争心ムキ出しにして我先とばかりに探さなくても(笑)。若気の至りですなあ(笑)。
ARP2600の中域がふくよかで飽和感のある残響(笑)。これがキモですな。さらに追い討ちをかけるかのように中域エグいローズ・サウンド。これがアジムス・サウンドの真骨頂という所でしょうか。
まずは、クロスオーバー・イレブンのオープニング・テーマである『Fly Over the Horizon』

ステレオ感をこれでもか!とばかりに演出したARP2600のシルキーな高域まで伸びる倍音のシンセ・ストリングスの音に酔いしれることができる絶妙な曲。ちなみにベースはというと、音からして、リアピックアップが60年代よりブリッジ側にマウントされた70s系のスラップ音。よく聴くと、フロントビックアップのボリュームをチマチマ弄っているようで、ハーモニクス音を出しながらスラップの音も演出させたい為に色々細かく触りまくっているようです(笑)。
んで、次はクロスオーバー・イレブンのエンディング・テーマである『October』。実は左近治、この曲、着うたリリースする為に手がけています(笑)。
どうせなら、着うたでも「Fly Over the Horizon」をリリースすればイイのに、と思われる方もいらっしゃるでしょうけれど、確かに着メロ時代のMIDIファイルを流用すればすぐにリリースは可能ですが、アレは着メロだからリリースしたかった曲でして(笑)、しかも16和音時代(笑)。そういう時代に敢えてチャレンジしたいポイントは今と昔では違うんですなあ(笑)。
この「October」のように、静寂感がヒシヒシと伝わって、ローズのダイナミクスをふんだんに活かした曲はですね、着メロ時代じゃ折角の曲の雰囲気がどうしても出せません(笑)。
こういう、ヒシヒシ感というものを着うたでは個人的に追求したい部分であるので、着うたをアジムスでやるならやっぱりコレ!なんですな(笑)。和声的にも左近治はこちらの「October」の方が好みです(笑)

こんなコト書いてたら、とうとうLogic8というか、Logic Studioなる製品が発表されたようですな(笑)。Jam Pack全シリーズ買ってた私は少々力抜けしてしまいかねない、旧Expressユーザーにはとってもお得な内容と価格になっているのではないでしょうか。
左近治のG5 QuadではLogic Nodesを使用することは24ビット96kHzの環境でも殆ど無いんですが、Logic NodesでG4がサポートされなくなったのがLogic Studioの変更点でしょうか。MDDがどんどん蚊帳の外になってきましたなあ(笑)。※ブログを書いた時点ではAppleのLogic Studio製品の仕様でしか確認できずにG4が明記されていなかったのですが、マニュアルを見るとG4のシングルプロセッサでもGigabitイーサに対応していれば問題なく動作するようです。ただ、「UTPカテゴリ6じゃなきゃダメよ!」という記述は今回のバージョンでも記述が無いようです。
正直、操作性や視認性の変更を除けば、音質やエフェクト類などで目立った大きな追加点はそれほどないようですが、コンボリューションをどれくらい自分で手軽に編集できるのかは楽しみですなあ。というか、Match EQとSpace Designerで、著名な機器のプリセットをもっともっと増やしてほしいんですけどね(笑)。
ドングルも無くなって、Leopard出て半年くらいしたらすぐに8.1とかになりそうな(笑)。というより、プロ系としての隠し球があって、敢えてこの値段にしてきたとも思えますな。
Compressor(コンプじゃないっすよ)やSoundtrackを付けたのはイイんですけどね、何よりBusやAUXトラックでも分散処理できたり(※AUX、Bus上でのノードは新バージョンでも無理なようであります。チャンネルインサートで補うか、対応してくれるように夜空の流れ星にお願いしてみます)、一部のブラグイン挟んだらそれより後段のプラグインのノード処理はできなくなってしまうような点は改善されているのかどうか興味がありますな(笑)。とはいえ、G5 Quad 24bit 96kHzでNodes使わなければならないようなシーンなんて、少なくともSpace Designerは6つくらい刺して、Guitar Rigは4本使って、サンプラー系プラグインをステレオソースで40トラック以上使ったりしない限り、ノードが欲しいとは思いませんな。
個人的にはSpectra Fooのようなツールが欲しかったんですけど(笑)。※Soundtrack Pro 2でかなりのパノラマ状態やスペクトラムを確認できそうです。何よりも、Logicがバイノーラルに対応しているのが、新バージョンとっておきの飛び道具かもしれませんね(笑)。サラウンドも擬似ステレオとしてミックス&モニターできる、と。5.1chならコンボリューション関連の処理も単純計算して2chミックスの3倍アップになってしまう(笑)。こりゃあもうMac Proのクアッドcoreとっとと買え!と言われているようなモンですな。
え~とですね、ここで語るのはブラジルのクロスオーバー系バンドの「アジムス」のコトでやんす。NHK-FMで午後11時から津嘉山正種のナレーションで、毎週平日はモンドな選曲で多彩なジャンルの音楽が流れておりましたね。往年の名ラジオ番組だったワケですね。また、選曲具合も、その辺でやたらと耳にするような雑多なタイプのものとは違う、関係者の音楽の造詣の深さやセンスの良さを思い知ることができたものであります。ある意味、左近治のKクリにおけるモンドなスタイルというのは、クロスオーバー・イレブンが参考になっております(笑)。
ま、こういうモンドで感性豊かな曲を楽しませるのは、いわゆる「渋谷系」の原点のような気がするんですなあ。まあ、NHKも渋谷にありますし。
現在、左近治がKクリにおいてアジムス関連をリリースしているのは、着メロの方での「Fly Over the Horizon」。
午後11時の時報が鳴り止むと、クロスオーバー・イレブンのイントロ音楽が始まる、と。それがこの「Fly Over the Horizon」だったワケですな。
アジムスというと、私にとってはARP2600に浸れることができるバンドのひとつだったワケでして、90年代に入ると無性にARP2600を欲しがっていたもので、Swing Out Sisterのキーボードの方が「ARP2600」を手に入れた、みたいな記事を雑誌で見かけたりすると、なにくそ!とばかりに左近治も現物探しに行ったりしたものでありました(笑)。立場が全然違うというのに、そこまで闘争心ムキ出しにして我先とばかりに探さなくても(笑)。若気の至りですなあ(笑)。
ARP2600の中域がふくよかで飽和感のある残響(笑)。これがキモですな。さらに追い討ちをかけるかのように中域エグいローズ・サウンド。これがアジムス・サウンドの真骨頂という所でしょうか。
まずは、クロスオーバー・イレブンのオープニング・テーマである『Fly Over the Horizon』
ステレオ感をこれでもか!とばかりに演出したARP2600のシルキーな高域まで伸びる倍音のシンセ・ストリングスの音に酔いしれることができる絶妙な曲。ちなみにベースはというと、音からして、リアピックアップが60年代よりブリッジ側にマウントされた70s系のスラップ音。よく聴くと、フロントビックアップのボリュームをチマチマ弄っているようで、ハーモニクス音を出しながらスラップの音も演出させたい為に色々細かく触りまくっているようです(笑)。
んで、次はクロスオーバー・イレブンのエンディング・テーマである『October』。実は左近治、この曲、着うたリリースする為に手がけています(笑)。
どうせなら、着うたでも「Fly Over the Horizon」をリリースすればイイのに、と思われる方もいらっしゃるでしょうけれど、確かに着メロ時代のMIDIファイルを流用すればすぐにリリースは可能ですが、アレは着メロだからリリースしたかった曲でして(笑)、しかも16和音時代(笑)。そういう時代に敢えてチャレンジしたいポイントは今と昔では違うんですなあ(笑)。
この「October」のように、静寂感がヒシヒシと伝わって、ローズのダイナミクスをふんだんに活かした曲はですね、着メロ時代じゃ折角の曲の雰囲気がどうしても出せません(笑)。
こういう、ヒシヒシ感というものを着うたでは個人的に追求したい部分であるので、着うたをアジムスでやるならやっぱりコレ!なんですな(笑)。和声的にも左近治はこちらの「October」の方が好みです(笑)
こんなコト書いてたら、とうとうLogic8というか、Logic Studioなる製品が発表されたようですな(笑)。Jam Pack全シリーズ買ってた私は少々力抜けしてしまいかねない、旧Expressユーザーにはとってもお得な内容と価格になっているのではないでしょうか。
左近治のG5 QuadではLogic Nodesを使用することは24ビット96kHzの環境でも殆ど無いんですが、Logic NodesでG4がサポートされなくなったのがLogic Studioの変更点でしょうか。MDDがどんどん蚊帳の外になってきましたなあ(笑)。※ブログを書いた時点ではAppleのLogic Studio製品の仕様でしか確認できずにG4が明記されていなかったのですが、マニュアルを見るとG4のシングルプロセッサでもGigabitイーサに対応していれば問題なく動作するようです。ただ、「UTPカテゴリ6じゃなきゃダメよ!」という記述は今回のバージョンでも記述が無いようです。
正直、操作性や視認性の変更を除けば、音質やエフェクト類などで目立った大きな追加点はそれほどないようですが、コンボリューションをどれくらい自分で手軽に編集できるのかは楽しみですなあ。というか、Match EQとSpace Designerで、著名な機器のプリセットをもっともっと増やしてほしいんですけどね(笑)。
ドングルも無くなって、Leopard出て半年くらいしたらすぐに8.1とかになりそうな(笑)。というより、プロ系としての隠し球があって、敢えてこの値段にしてきたとも思えますな。
Compressor(コンプじゃないっすよ)やSoundtrackを付けたのはイイんですけどね、何よりBusやAUXトラックでも分散処理できたり(※AUX、Bus上でのノードは新バージョンでも無理なようであります。チャンネルインサートで補うか、対応してくれるように夜空の流れ星にお願いしてみます)、一部のブラグイン挟んだらそれより後段のプラグインのノード処理はできなくなってしまうような点は改善されているのかどうか興味がありますな(笑)。とはいえ、G5 Quad 24bit 96kHzでNodes使わなければならないようなシーンなんて、少なくともSpace Designerは6つくらい刺して、Guitar Rigは4本使って、サンプラー系プラグインをステレオソースで40トラック以上使ったりしない限り、ノードが欲しいとは思いませんな。
個人的にはSpectra Fooのようなツールが欲しかったんですけど(笑)。※Soundtrack Pro 2でかなりのパノラマ状態やスペクトラムを確認できそうです。何よりも、Logicがバイノーラルに対応しているのが、新バージョンとっておきの飛び道具かもしれませんね(笑)。サラウンドも擬似ステレオとしてミックス&モニターできる、と。5.1chならコンボリューション関連の処理も単純計算して2chミックスの3倍アップになってしまう(笑)。こりゃあもうMac Proのクアッドcoreとっとと買え!と言われているようなモンですな。
2007-09-13 00:02
マジ曲制作裏舞台 [クロスオーバー]
「マジ曲とは何!?」
え~と、コレはおバカ要素のない真面目に取り組んで制作した曲のコトを指しておりやす。
日曜日と言えばテレビコンテンツはおバカ要素タップリの曜日なワケでして、ロンQハイランド然り、さんまのスーパーからくりTVなど、おバカ心をくすぐるという裏では、マジ曲をチマチマと制作している左近治の姿がありまして、この週末のマジ曲は少々なつかし目の80年代の曲を作っていたというワケです。
レイ・バーダニとマイケル・コリーナのコンビのアルバムというと、まあ色々あるんですがこの人たちが絡むといわゆるフュージョン系でもテクひけらかしインタープレーの連続というのは少なくなり、和声の叙情性で聴かせたり、空間的なエフェクトやアンビエンスを聴かせるというアルバムになり、ややもすると音がシンセシンセになりがちという向きもあるワケですが、実にしっとりと曲全体を聴かせてくれる音のイメージになるワケですね。で、何より曲調も陰鬱な雰囲気がよく似合うというか(笑)。
レイ・バーダニの名前をサンレコで見かけたのは10年くらい遡らなければならないでしょうか。ちょっと記憶にないんですが、いつしか「久々にレイ・バーダニの名前見たなあ」というのはちょっと昔にあったような(笑)。
今回左近治が制作したマジ曲はDavid Sanbornの『Backstreet』。
リリースした時にでもこれについては詳細を述べるつもりですが、思いのほか制作がテキパキとはかどって、左近治自身ゴキゲンなワケでして。
やっぱり先日マーカス・ミラーの1stアルバム収録の『Be My Love』を制作していた影響か、ついついレイ・バーダニの方へ心奪われていってしまったのでしょうなあ。
それらとは別に、ボブ・ジェームスのアルバム「Obsession」もレイ・バーダニですが、このアルバムはDXサウンドが絶品というか、DXサウンド聴きたさにあるようなモノなんですが(笑)、このアルバムからも作りたい曲は2、3曲あるんですよねー。
アルバムタイトル曲『Obsession』のブリッジ部など、EL&Pの『Tarkus』パクった!?みたいなフレーズやら(笑)、ま、そういうのをTarkus風にアレンジしちゃおっかなー的なアイデアとか、『Gone Hollywood』のDXベースはマドンナの『Papa Don’t Preach』でも有名な、あのエグイDXベース。こういうのもう一度作ってみたいなーと思いつつ、アイデアを練っているというワケです。
『3 A.M.』と『Steady』が一番お気に入りの曲なんですけど、『Steady』のイントロはIbanezのSDR-1000使って当時はステレオ感あるエフェクトで色々弾いたモノでした。この時期はまさにSPX-90が世に出て、SonyのMU-RのOEMで発売されていたという(星野楽器から)異色のアイテム。ステレオ感が気に入って使っていたワケでした。REV-7だと重厚すぎる、というような場面でステレオ感の方が欲しい時に重宝したもんでさぁ。
とりあえず、マジ曲の方もお楽しみに。
え~と、コレはおバカ要素のない真面目に取り組んで制作した曲のコトを指しておりやす。
日曜日と言えばテレビコンテンツはおバカ要素タップリの曜日なワケでして、ロンQハイランド然り、さんまのスーパーからくりTVなど、おバカ心をくすぐるという裏では、マジ曲をチマチマと制作している左近治の姿がありまして、この週末のマジ曲は少々なつかし目の80年代の曲を作っていたというワケです。
レイ・バーダニとマイケル・コリーナのコンビのアルバムというと、まあ色々あるんですがこの人たちが絡むといわゆるフュージョン系でもテクひけらかしインタープレーの連続というのは少なくなり、和声の叙情性で聴かせたり、空間的なエフェクトやアンビエンスを聴かせるというアルバムになり、ややもすると音がシンセシンセになりがちという向きもあるワケですが、実にしっとりと曲全体を聴かせてくれる音のイメージになるワケですね。で、何より曲調も陰鬱な雰囲気がよく似合うというか(笑)。
レイ・バーダニの名前をサンレコで見かけたのは10年くらい遡らなければならないでしょうか。ちょっと記憶にないんですが、いつしか「久々にレイ・バーダニの名前見たなあ」というのはちょっと昔にあったような(笑)。
今回左近治が制作したマジ曲はDavid Sanbornの『Backstreet』。
リリースした時にでもこれについては詳細を述べるつもりですが、思いのほか制作がテキパキとはかどって、左近治自身ゴキゲンなワケでして。
やっぱり先日マーカス・ミラーの1stアルバム収録の『Be My Love』を制作していた影響か、ついついレイ・バーダニの方へ心奪われていってしまったのでしょうなあ。
それらとは別に、ボブ・ジェームスのアルバム「Obsession」もレイ・バーダニですが、このアルバムはDXサウンドが絶品というか、DXサウンド聴きたさにあるようなモノなんですが(笑)、このアルバムからも作りたい曲は2、3曲あるんですよねー。
アルバムタイトル曲『Obsession』のブリッジ部など、EL&Pの『Tarkus』パクった!?みたいなフレーズやら(笑)、ま、そういうのをTarkus風にアレンジしちゃおっかなー的なアイデアとか、『Gone Hollywood』のDXベースはマドンナの『Papa Don’t Preach』でも有名な、あのエグイDXベース。こういうのもう一度作ってみたいなーと思いつつ、アイデアを練っているというワケです。
『3 A.M.』と『Steady』が一番お気に入りの曲なんですけど、『Steady』のイントロはIbanezのSDR-1000使って当時はステレオ感あるエフェクトで色々弾いたモノでした。この時期はまさにSPX-90が世に出て、SonyのMU-RのOEMで発売されていたという(星野楽器から)異色のアイテム。ステレオ感が気に入って使っていたワケでした。REV-7だと重厚すぎる、というような場面でステレオ感の方が欲しい時に重宝したもんでさぁ。
とりあえず、マジ曲の方もお楽しみに。
2007-09-09 23:17
APOGEE DuetとRhodes聴き比べ詳細 [クロスオーバー]
APOGEEから面白そうなものがリリースされたようですね。『Duet』というバスパワー駆動のオーディオインターフェース。
スペックを見ると24ビット96kHzが最高で、72dBのゲインを確保するプリアンプ、と。Maestroが付属しているようですがUV-22HRに対応しているかどうかは明記されておりませんな。これで495ドルなら充分欲しくなってしまうアイテムですなコレは。
さてさて、先日のRhodesエレピのデモの件『Rhodesエレピ聴き比べ』について述べてみまひょ、と。
全部で5種類のエレピを使ってみたんですけどね、左近治がKクリの着うたの方で過去にリリースしてきたエレピとは正直いずれも違うんですよ(笑)。
みなさんはどういうタイプのエレピが好きだったでしょうか!?高域部の澄み渡った音を欲しがる人も多いとは思うんですが、ローズというのはどういう風にEQ施したりして相対的に高域がリッチな音にさせたとしてもですね、ミドルがふくよかに出ていないと、ただでさえ倍音が豊富ではない音なのでミドルが少ないと倍音が立たないんですな。
ハイをブーストするもよし、相対的に低域をカットするもよし、場合によってはコーラスのセッティングの位相差で生まれる高域が干渉して強調されることで得られるリッチな高域というセッティングも可能であるものの、倍音を立たせる為に必要なコトは、ミドルレンジが太くないとダメなんですな。これはローズに限らずどんな楽器にも言えると思います。狙った音が結局その帯域をカットするとしても。
ベースでもスラップでハイが強調された音というのは、元からドンシャリじゃ弄りようが無いんですね。いやらしい位にズ太いミドルを備えてくれている生の方が色々弄りやすいんです。
とゆーワケで、ローズのデモはですねある程度ミドルがしっかりしてコシのあるタイプを選んでみたつもりですけど、打鍵をとにかく強く弾いてローズ特有のブーミーな飽和感というエグい音にしてまでは弾いてません(笑)。音叉を思いっきり叩いて飽和するようなああいう感じですか。ローズ好きな人って高域の音もそうですが、この特有のエグい飽和感を好む人が圧倒的ではないかと思うんですが、私の演奏はさておき、今回デモで使用したローズはいずれもそういうブーミーな飽和感は得られます。
ではローズのデモの1フレーズ目。
これはNative InstrumentsのElektric Piano1.5のAuthenticシリーズとして新たに加わったパッチのMK-Iですね。パラメータで用意されている「ROOM」はかなり絞りましたけど箱鳴り感と特有のショート・アンビエンスは付加されています。その後Metric HaloのDSPの方のコンプとEQを足しています。
次は2フレーズ目。
これはScarbeeのC.E.P.の8ベロシティ版ですね。Kontakt内蔵のChorusを使ってMetric HaloのNative版のChannel Stripを噛ませています。
3フレーズ目。
これはRolandのS-760用のサンプルライブラリ「Keyboards of the 60’s & 70’s Vol.2」のSuitcaseのパッチをKontaktで読ませたものですね。このライブラリは10年以上前は実は結構重宝しましてですね(笑)、その後MK-80を手に入れたり、VOCEのelectric piano+を手に入れたりもした時期があったんですけど、軽量でブーミーな感じが結構好きでしたね。このデモでは低域が軽く聞こえていますけど(笑)、上記のプラグイン類とは違うモノを通しているためこうなっているという。思えばVOCEのハーフラックのアレはRhodesというよりもウーリッツァーの方が得意なキャラクターでしたけどね。ただ、このRolandのサンプルの難点は、当時私が一番愛用していたS-3200XLで32MB搭載して(最大)いたという時代。今を思えばこれだけ軽量でそれほど多くのマルチサンプルは組まれていないのでどうにかこうにかループを巧く使っているという。故にループの使い回し的な音はどうしてもディケイからサステイン部にかけてが少々PCMシンセ系になりがちで、サステインも離鍵するまでが平滑なデジピのようなエンベロープ。そういう意味では長い白玉だと不自然さが今だと顕著に感じてしまいますかねえ。個人的には結構当時はお気に入りの音だったんですけどね。
4フレーズ目。
こちらはLogic ProのEVP-88の「Stage MK-I」をアレコレ弄って、MatchEQを通している点が顕著でしょうか。MatchEQのカーブイミュレートは私がアレコレ無い知恵使って某ローズの音をエミュレートしたものを使用(笑)。
5フレーズ目。
他の音よりもトレモロが顕著ですが(笑)、これもLogic ProのEVP-88です。「Attack Piano」を使用しております。EVP-88におけるAttack Pianoは個人的には結構好きなんですが、EVP-88の弱点は、高域のベルの音がどうしても不足気味というか。ただ、中域から低域にかけては私はかなり好きな方で、ハウス系でどうしてもハイの利いた音が欲しい場合は、細めのQでオーバーシュートさせて弄ってやらないとなかなか出てくれない頑固者プラグインでもあります(笑)。
とりあえず今回はこの辺で。
スペックを見ると24ビット96kHzが最高で、72dBのゲインを確保するプリアンプ、と。Maestroが付属しているようですがUV-22HRに対応しているかどうかは明記されておりませんな。これで495ドルなら充分欲しくなってしまうアイテムですなコレは。
さてさて、先日のRhodesエレピのデモの件『Rhodesエレピ聴き比べ』について述べてみまひょ、と。
全部で5種類のエレピを使ってみたんですけどね、左近治がKクリの着うたの方で過去にリリースしてきたエレピとは正直いずれも違うんですよ(笑)。
みなさんはどういうタイプのエレピが好きだったでしょうか!?高域部の澄み渡った音を欲しがる人も多いとは思うんですが、ローズというのはどういう風にEQ施したりして相対的に高域がリッチな音にさせたとしてもですね、ミドルがふくよかに出ていないと、ただでさえ倍音が豊富ではない音なのでミドルが少ないと倍音が立たないんですな。
ハイをブーストするもよし、相対的に低域をカットするもよし、場合によってはコーラスのセッティングの位相差で生まれる高域が干渉して強調されることで得られるリッチな高域というセッティングも可能であるものの、倍音を立たせる為に必要なコトは、ミドルレンジが太くないとダメなんですな。これはローズに限らずどんな楽器にも言えると思います。狙った音が結局その帯域をカットするとしても。
ベースでもスラップでハイが強調された音というのは、元からドンシャリじゃ弄りようが無いんですね。いやらしい位にズ太いミドルを備えてくれている生の方が色々弄りやすいんです。
とゆーワケで、ローズのデモはですねある程度ミドルがしっかりしてコシのあるタイプを選んでみたつもりですけど、打鍵をとにかく強く弾いてローズ特有のブーミーな飽和感というエグい音にしてまでは弾いてません(笑)。音叉を思いっきり叩いて飽和するようなああいう感じですか。ローズ好きな人って高域の音もそうですが、この特有のエグい飽和感を好む人が圧倒的ではないかと思うんですが、私の演奏はさておき、今回デモで使用したローズはいずれもそういうブーミーな飽和感は得られます。
ではローズのデモの1フレーズ目。
これはNative InstrumentsのElektric Piano1.5のAuthenticシリーズとして新たに加わったパッチのMK-Iですね。パラメータで用意されている「ROOM」はかなり絞りましたけど箱鳴り感と特有のショート・アンビエンスは付加されています。その後Metric HaloのDSPの方のコンプとEQを足しています。
次は2フレーズ目。
これはScarbeeのC.E.P.の8ベロシティ版ですね。Kontakt内蔵のChorusを使ってMetric HaloのNative版のChannel Stripを噛ませています。
3フレーズ目。
これはRolandのS-760用のサンプルライブラリ「Keyboards of the 60’s & 70’s Vol.2」のSuitcaseのパッチをKontaktで読ませたものですね。このライブラリは10年以上前は実は結構重宝しましてですね(笑)、その後MK-80を手に入れたり、VOCEのelectric piano+を手に入れたりもした時期があったんですけど、軽量でブーミーな感じが結構好きでしたね。このデモでは低域が軽く聞こえていますけど(笑)、上記のプラグイン類とは違うモノを通しているためこうなっているという。思えばVOCEのハーフラックのアレはRhodesというよりもウーリッツァーの方が得意なキャラクターでしたけどね。ただ、このRolandのサンプルの難点は、当時私が一番愛用していたS-3200XLで32MB搭載して(最大)いたという時代。今を思えばこれだけ軽量でそれほど多くのマルチサンプルは組まれていないのでどうにかこうにかループを巧く使っているという。故にループの使い回し的な音はどうしてもディケイからサステイン部にかけてが少々PCMシンセ系になりがちで、サステインも離鍵するまでが平滑なデジピのようなエンベロープ。そういう意味では長い白玉だと不自然さが今だと顕著に感じてしまいますかねえ。個人的には結構当時はお気に入りの音だったんですけどね。
4フレーズ目。
こちらはLogic ProのEVP-88の「Stage MK-I」をアレコレ弄って、MatchEQを通している点が顕著でしょうか。MatchEQのカーブイミュレートは私がアレコレ無い知恵使って某ローズの音をエミュレートしたものを使用(笑)。
5フレーズ目。
他の音よりもトレモロが顕著ですが(笑)、これもLogic ProのEVP-88です。「Attack Piano」を使用しております。EVP-88におけるAttack Pianoは個人的には結構好きなんですが、EVP-88の弱点は、高域のベルの音がどうしても不足気味というか。ただ、中域から低域にかけては私はかなり好きな方で、ハウス系でどうしてもハイの利いた音が欲しい場合は、細めのQでオーバーシュートさせて弄ってやらないとなかなか出てくれない頑固者プラグインでもあります(笑)。
とりあえず今回はこの辺で。
2007-09-07 20:48
スティーリー・ダンをついつい想起してしまう [クロスオーバー]
ここ数日、なぜだかどうしてもスティーリー・ダンを思い浮かべてしまう出来事がありましてですね、左近治の世界観が狭いのか発想力がないのかはさておき(笑)、何故それほどまでにスティーリー・ダンを想起してしまったのか述べてみることに。
先ずは、日曜日に行われたFIFA U-17 W杯(韓国にて開催中)の日本vsハイチ戦。
ハイチと言えば、ブードゥー教かスティーリー・ダンの曲『ハイチ式離婚』か!?
ってなくらいの知識しか無いんですが(笑)、往年のポリス好きならついついスティーリー・ダンの『ハイチ式離婚』はお気に召される曲のひとつだと思うワケですが、そもそもなぜ「ハイチ式」の離婚なのか!?
この曲は、70年代中頃の米国社会における法律の抜け穴を歌っているという曲だそうでして、離婚というシステムは結婚よりも難しい複雑な法律がどの国にもあるんでしょうけど、それを簡単に回避して離婚を実現してしまう方法がある、ということを危惧する意図がある曲とのことです。フィクションではなく実際に当時はそういう法律だったとのことです。
夫か妻の片方が勝手な言い分で離婚というのは正式に通用しないワケで、代筆で離婚届出した日にゃあ公文書偽造(笑)、すったもんだで夫婦の関係を構築していくには難しい事由あると後に判断されても、それまでには調停やら裁判というステップを踏むワケですね。なんでこういうことになるかというと、財産分与や子供が居れば親権やら面接権、養育費やらそういう難しいことを線引きしないといけないからなのですね。
ハイチ式離婚だとですね、とりあえずハイチを訪れ行政窓口で「ウチはこうだからもう離婚する!」と言うと、いとも簡単にフランス語で離婚受理という書類を渡されて、それをアメリカに戻った時に提出すれば離婚成立、というこういう抜け穴があったということを嘆く曲なのだ、と。
グリーンカードの資格は年齢を超えてしまって、米国で就業するほどの英語力もない第三国人が、とりあえず目星をつけた異性にアタックして結婚、と。
片方の配偶者には異論はあれどハイチまで連れて言って口論しながら
「ほらね。わたしたち仲が悪いでしょ!? だから離婚よ!」
と言えば離婚成立なのだと(笑)。
こんなんで離婚された日にゃあ、財産目当ての偽装結婚やら目を付ける輩がいてもおかしくはありませんし、実際には慰謝料でカッパいで儲けるなんていう手段、今でもあって不思議ではないものなんでしょうが(笑)、ま、そういう曲をハイチという、サッカーでは聞きなれない国と対戦したということもあって、久々にハイチ式離婚を思い出してしまったぞ、と。
その矢先、スティーリー・ダンの名アルバムのひとつ『AJA』のジャケットにもなっている、資生堂のCMでよ~く見かけた山口小夜子さんが亡くなったというニュースが。
ビッグなアーティストのアルバムに日本人が起用されているという極めて稀な例ですな。これもまたスティーリー・ダンを思い浮かべてしまうワケですよ。
そういや来日中じゃなかったでしょうかね、スティーリー・ダンは。もう帰ったのかな?
ウォルター・ベッカーの2作目のソロ・アルバムの話もそろそろありそうですし、次のスティーリー・ダンには「Second Arrangement」をリメイクしてリリースしてもらいたいものですなあ(笑)。
先ずは、日曜日に行われたFIFA U-17 W杯(韓国にて開催中)の日本vsハイチ戦。
ハイチと言えば、ブードゥー教かスティーリー・ダンの曲『ハイチ式離婚』か!?
ってなくらいの知識しか無いんですが(笑)、往年のポリス好きならついついスティーリー・ダンの『ハイチ式離婚』はお気に召される曲のひとつだと思うワケですが、そもそもなぜ「ハイチ式」の離婚なのか!?
この曲は、70年代中頃の米国社会における法律の抜け穴を歌っているという曲だそうでして、離婚というシステムは結婚よりも難しい複雑な法律がどの国にもあるんでしょうけど、それを簡単に回避して離婚を実現してしまう方法がある、ということを危惧する意図がある曲とのことです。フィクションではなく実際に当時はそういう法律だったとのことです。
夫か妻の片方が勝手な言い分で離婚というのは正式に通用しないワケで、代筆で離婚届出した日にゃあ公文書偽造(笑)、すったもんだで夫婦の関係を構築していくには難しい事由あると後に判断されても、それまでには調停やら裁判というステップを踏むワケですね。なんでこういうことになるかというと、財産分与や子供が居れば親権やら面接権、養育費やらそういう難しいことを線引きしないといけないからなのですね。
ハイチ式離婚だとですね、とりあえずハイチを訪れ行政窓口で「ウチはこうだからもう離婚する!」と言うと、いとも簡単にフランス語で離婚受理という書類を渡されて、それをアメリカに戻った時に提出すれば離婚成立、というこういう抜け穴があったということを嘆く曲なのだ、と。
グリーンカードの資格は年齢を超えてしまって、米国で就業するほどの英語力もない第三国人が、とりあえず目星をつけた異性にアタックして結婚、と。
片方の配偶者には異論はあれどハイチまで連れて言って口論しながら
「ほらね。わたしたち仲が悪いでしょ!? だから離婚よ!」
と言えば離婚成立なのだと(笑)。
こんなんで離婚された日にゃあ、財産目当ての偽装結婚やら目を付ける輩がいてもおかしくはありませんし、実際には慰謝料でカッパいで儲けるなんていう手段、今でもあって不思議ではないものなんでしょうが(笑)、ま、そういう曲をハイチという、サッカーでは聞きなれない国と対戦したということもあって、久々にハイチ式離婚を思い出してしまったぞ、と。
その矢先、スティーリー・ダンの名アルバムのひとつ『AJA』のジャケットにもなっている、資生堂のCMでよ~く見かけた山口小夜子さんが亡くなったというニュースが。
ビッグなアーティストのアルバムに日本人が起用されているという極めて稀な例ですな。これもまたスティーリー・ダンを思い浮かべてしまうワケですよ。
そういや来日中じゃなかったでしょうかね、スティーリー・ダンは。もう帰ったのかな?
ウォルター・ベッカーの2作目のソロ・アルバムの話もそろそろありそうですし、次のスティーリー・ダンには「Second Arrangement」をリメイクしてリリースしてもらいたいものですなあ(笑)。
2007-08-21 20:38
Ride on Sequencer.... [クロスオーバー]
このタイトルでピンと来た方は80年代をご存知ですね(笑)。それでもまあ一部でしょうか。
Gazeboの1stアルバムの2曲目『Love in Your Eyes』の出だしのガゼボの声ですな。
それからモロ師岡もとい、モロに「モロダー・サウンド」たる16分音符シーケンスが始まるワケですな(笑)。
左近治が手がけていたガゼボの曲は、同じアルバムでも「Midnight Cocktail」の方ではなかったのか!?
ええ、途中で気が変わって「Love in Your Eyes」の制作の方を終えてしまいましてですね、舌は何枚でも使い分けるという、左近治の真髄を確認できたと自画自賛(笑)。もちろん、「Midnight Cocktail」の方もお蔵入りにはしませんけどね。
ジョルジオ・モロダーといえばハウスの先駆者でもあり、Queerでセクシーな方が寵愛する、独特の触感があるんですけど(笑)、その後ハウスはユーロビートに波に飲み込まれて、どちらかというと仰々しいシンセサウンドの方が持てはやされて90年代に突入する、という事になったワケですな。
それからチープでシンプルなハウスの屋台骨が見直されて、ソリーナ系サウンドでフワフワとしたストリングスのリフを織り交ぜながら、というアレンジが90年代初頭のハウスサウンドではなかったでしょうか。
例えば、レイ・ヘイデンとマッド・プロフェッサー(OPAZ)が手掛けた、クレモンティーヌの『男と女』も、アシッドサウンドでありながらハウスを取り込んでいたワケです。今現在のような8分裏打ちばかりではなく、もっとシンプルで軽妙で多様性があったワケです。
その頃左近治は、後のUKソウルとも呼ばれるモノやアシッド・ジャズ系を追っていたんですけど、自分の心に火がついたのはグランジ系の音やらKORNに代表されるインダストリアル・サウンド、つまりミクスチャーの魁系が一番フィットしていたのが90年代中盤辺り。nine inch nailsやらPortisheadにハマっていたのもこの頃で、その後KORNには触発され続け、Rob Zombieやらに傾倒していった、と(笑)。
そんな左近治が90年代終盤にさしかかった所に、ハウス心に火をつけてくれたのが『New Phunk Theory』というユニットでして、オートメーションをふんだんに使ってハウスサウンドを構築していたのは、「これこそハウス!」と感じたモノでした。
ま、この辺のジャンルというのは主観的なモノが多いんで、人それぞれの思いがあると思うんですけどね、少なくとも左近治が影響を受けた人達を列挙しているワケなんですけどね。
それからミクスチャー路線よりもハウス系に傾倒していく左近治でして、ケミカル・ブラザーズやBasement Jaxxなどにハマっていくワケでありました。
本来、一番得意なジャンルであるはずのジャズ・フュージョン系というのはですね、この頃は正直ジャズ・フュージョンは完全に死んでしまったでしょう(笑)。色んな音を取り込んでスムース・ジャズやら出現したものの、結局はハウスの領域を出ずにインプロヴァイズが無い方が受けてしまう、と(笑)。名だたるアーティストも他界していき、後世のジャズマンがなかなか育たない、と(笑)。
しばらくしてみりゃ、ボーカルもので『マイケル・ブーブレ』がヒットする程度で、「あれはジャズなのか?」と疑問符が付くと同時に、日本じゃあ、やれ美人系で売ろうとする興醒めモノの時代に今もなっております(笑)。果たして「美形」な方は居たのだろうかと(笑)。プロモーションが、その辺のポン引きレベルに成り下がっているからこそファンは逃げていってしまうのだぞ、と。
人間のグルーヴは重宝されるはずなのに、結局はスタジオ・ミュージシャンよりもシーケンサーに取り込んでしまう方が重視されてしまう。よっぽどの魅力を備えていない個人ではない限り、トコトン機械になっていきながら、機械側の編集レベルじゃ人間性を追究するという矛盾。それは、個性を失ったから機械の方に目が行くワケですね。悲しいですなあ。
Gazeboの1stアルバムの2曲目『Love in Your Eyes』の出だしのガゼボの声ですな。
それからモロ師岡もとい、モロに「モロダー・サウンド」たる16分音符シーケンスが始まるワケですな(笑)。
左近治が手がけていたガゼボの曲は、同じアルバムでも「Midnight Cocktail」の方ではなかったのか!?
ええ、途中で気が変わって「Love in Your Eyes」の制作の方を終えてしまいましてですね、舌は何枚でも使い分けるという、左近治の真髄を確認できたと自画自賛(笑)。もちろん、「Midnight Cocktail」の方もお蔵入りにはしませんけどね。
ジョルジオ・モロダーといえばハウスの先駆者でもあり、Queerでセクシーな方が寵愛する、独特の触感があるんですけど(笑)、その後ハウスはユーロビートに波に飲み込まれて、どちらかというと仰々しいシンセサウンドの方が持てはやされて90年代に突入する、という事になったワケですな。
それからチープでシンプルなハウスの屋台骨が見直されて、ソリーナ系サウンドでフワフワとしたストリングスのリフを織り交ぜながら、というアレンジが90年代初頭のハウスサウンドではなかったでしょうか。
例えば、レイ・ヘイデンとマッド・プロフェッサー(OPAZ)が手掛けた、クレモンティーヌの『男と女』も、アシッドサウンドでありながらハウスを取り込んでいたワケです。今現在のような8分裏打ちばかりではなく、もっとシンプルで軽妙で多様性があったワケです。
その頃左近治は、後のUKソウルとも呼ばれるモノやアシッド・ジャズ系を追っていたんですけど、自分の心に火がついたのはグランジ系の音やらKORNに代表されるインダストリアル・サウンド、つまりミクスチャーの魁系が一番フィットしていたのが90年代中盤辺り。nine inch nailsやらPortisheadにハマっていたのもこの頃で、その後KORNには触発され続け、Rob Zombieやらに傾倒していった、と(笑)。
そんな左近治が90年代終盤にさしかかった所に、ハウス心に火をつけてくれたのが『New Phunk Theory』というユニットでして、オートメーションをふんだんに使ってハウスサウンドを構築していたのは、「これこそハウス!」と感じたモノでした。
ま、この辺のジャンルというのは主観的なモノが多いんで、人それぞれの思いがあると思うんですけどね、少なくとも左近治が影響を受けた人達を列挙しているワケなんですけどね。
それからミクスチャー路線よりもハウス系に傾倒していく左近治でして、ケミカル・ブラザーズやBasement Jaxxなどにハマっていくワケでありました。
本来、一番得意なジャンルであるはずのジャズ・フュージョン系というのはですね、この頃は正直ジャズ・フュージョンは完全に死んでしまったでしょう(笑)。色んな音を取り込んでスムース・ジャズやら出現したものの、結局はハウスの領域を出ずにインプロヴァイズが無い方が受けてしまう、と(笑)。名だたるアーティストも他界していき、後世のジャズマンがなかなか育たない、と(笑)。
しばらくしてみりゃ、ボーカルもので『マイケル・ブーブレ』がヒットする程度で、「あれはジャズなのか?」と疑問符が付くと同時に、日本じゃあ、やれ美人系で売ろうとする興醒めモノの時代に今もなっております(笑)。果たして「美形」な方は居たのだろうかと(笑)。プロモーションが、その辺のポン引きレベルに成り下がっているからこそファンは逃げていってしまうのだぞ、と。
人間のグルーヴは重宝されるはずなのに、結局はスタジオ・ミュージシャンよりもシーケンサーに取り込んでしまう方が重視されてしまう。よっぽどの魅力を備えていない個人ではない限り、トコトン機械になっていきながら、機械側の編集レベルじゃ人間性を追究するという矛盾。それは、個性を失ったから機械の方に目が行くワケですね。悲しいですなあ。
2007-07-08 12:12
密集和音と開離和音について [クロスオーバー]
明日、6月29日はリリース日であります。まずはリリース曲の紹介から。
あなくろ本舗にて
『Virginia Sunday / Richard Tee』をリリース致します。
極上エレピサウンドの代表曲のひとつと言ってもイイでしょう。こういう分散和音を巧みに使う旋律というのはリチャード・ティーのお家芸のひとつでもあるんですが、音の埋め方としてはやたらと高度なモノではなく、音選びそのものにセンスが問われるのがこういう曲ではないかな、と左近治は思っております。
リチャード・ティーのこうしたアルペジオのフレーズの代表的なモノは他にもグローヴァー・ワシントンJr.のアルバム「Winelight」に収録されている、ビル・ウィザースの唄う『Just The Two of Us』とかもありますね。
今回左近治は、Virginia Sundayのアルペジオのほんの一部分にJust The Two of Usを思わせる音運びをしている部分があるので、原曲をご存知の方は判って頂けるのではないかとほくそ笑んでおります(笑)。
分散和音フレーズを巧く鏤めるには、やはり密集和音としての狭い音程と、開離和音にみられる広い音程のメリハリを使い分けることが重要になってくると思うんですが、リチャード・ティーも含めて、こういうフレージングが巧いのはグレッグ・フィリンゲインズも挙げられるのではないかと思います。
密集和音の定義とは、とりあえず和音を構成する各音の音程間が「長三度」以下であることが条件ですね。長三度は含むけど、それより半音広い完全四度以上となると「開離音程」となるワケです。(※長三度はたまに現れるけど、そういう音程を含むことが多いながらも開離音程が多い曲の一例であるという意味で語っておりまして、長三度は開離音程ではないので混同しないようお願いします)
この手の曲だと、のっけからクローズド・ヴォイシング(密集和音)で弾くことは少ないと思うので、鍵盤楽器のみで曲のアンサンブルを構築しようとすると概ね開離和音を弾くことが多くなると思うんですね。
例えば、クローズド・ヴォイシングを転回する際、低い音から2番目の音をオクターブ下げれば「ドロップ2」と呼ばれ、低い音から3番目の音をオクターブ下げて転回すればそれは「ドロップ3」、さらには例えば三声を超える四声の和音にて低い音から2番目と4番目の音をオクターブ下げて転回すればそれは「ドロップ2&4」と呼ばれるのはご存知だと思うワケですが、こうした予め転回されたオーブン・ヴォイシングを弾きながら、その構成音の隔たりの間に生まれるコードトーンをうまく鏤めていくと、先述のようなリチャード・ティーやらグレッグ・フィリンゲインズ風になる、というコトですね。
とはいえ、音を鏤めるにあたってその音を巧く選択できなければ唯のモードスケールなぞっただけと同じになってしまうので、フレージングにセンスが問われると書いたのはこういう理由からなんです。
ドナルド・フェイゲンのソロ・アルバム「Nightfly」に収録の『Maxine(=愛しのマキシン)』のピアノのイントロなんてぇのは最たるモノで(byグレッグ・フィリンゲインズ)、耳当たりの心地良いVirginia Sundayからさらにジャズっぽさを推し進めると、Maxineのようなヴォイシングになるというワケですな。
「ジャズをどう聴いてイイのか判らない」
こういう人達は意外と多いんです。あまりにもハードなジャズやら和声の難易度が高度なモノをいきなり聴いてしまうと、その和声すら耳が受け付けずに、他の楽器のフレージングが唯単に半音階の乱れ打ちのようにしか聴き取れないと感じる人も多いワケですね。
ただ、そういう人でもどこかしらジャズっぽさを感じる耳は持っているワケで、やさしい、ジャズの入り口を提示してくれる曲というのは、その曲を実際に耳にしてから出ないとなかなか購買意欲というのは湧かないと思うんですね。そういう意味において、人によってはジャズは当たり外れの度が高く感じてしまい、ついつい敬遠しがちになってしまいかねないという音楽ジャンルでもあるんです。
Virginia Sundayをジャズと形容するには少々誇張し過ぎかもしれませんが、充分にジャズに入り口を提示しているというのは以前のブログでも語ったコトですが、なにより、クラシック畑の人、それも幼い子たちに耳にしてもらいたいというのがこの曲だったんですね。
曲が幼いのではなく、聴く人が幼い内に早期の段階でこういう響きを耳にしてほしい、という意味ですね。
通常、ピアノのレッスンに没頭する小学生がショパンの音について語れるようになる時というのは年齢は少なくとも二桁に達していると思うんですよね。
ただ、ショパンの特徴を俗世のクラシック畑における解釈のままになってしまうと、その特徴すら理解がおぼろげになって楽理的な特徴は掴めぬまま大人になる人が多いワケです(笑)。その特徴とやらを他の曲で後押ししてもらうことで、飽くなき和声への欲求を高ぶらせて、音楽へ没頭する心が強化されれば、是、左近治は感慨無量なワケですね(笑)。
とっくにリチャード・ティーも知ってしまっている人にではなく、全く知らない人や、これからピアノ頑張るぞ!という子達にぜひ聴かせてあげたい曲というコトなのです。
「ウチの子、ナメんなよ!」というご貴兄には、私がリリースしている他の楽曲(あなくろ本舗)の和声構造でも徹底分析してもらえたらな、と思います(笑)。
でもですね、この曲は決して幼い響きじゃあないですよ(笑)。ウチの子も凄いと思いたいんですけどmihimaru GTとかオヤジも一緒になって聴いてるのが現実でして(笑)。
あなくろ本舗にて
『Virginia Sunday / Richard Tee』をリリース致します。
極上エレピサウンドの代表曲のひとつと言ってもイイでしょう。こういう分散和音を巧みに使う旋律というのはリチャード・ティーのお家芸のひとつでもあるんですが、音の埋め方としてはやたらと高度なモノではなく、音選びそのものにセンスが問われるのがこういう曲ではないかな、と左近治は思っております。
リチャード・ティーのこうしたアルペジオのフレーズの代表的なモノは他にもグローヴァー・ワシントンJr.のアルバム「Winelight」に収録されている、ビル・ウィザースの唄う『Just The Two of Us』とかもありますね。
今回左近治は、Virginia Sundayのアルペジオのほんの一部分にJust The Two of Usを思わせる音運びをしている部分があるので、原曲をご存知の方は判って頂けるのではないかとほくそ笑んでおります(笑)。
分散和音フレーズを巧く鏤めるには、やはり密集和音としての狭い音程と、開離和音にみられる広い音程のメリハリを使い分けることが重要になってくると思うんですが、リチャード・ティーも含めて、こういうフレージングが巧いのはグレッグ・フィリンゲインズも挙げられるのではないかと思います。
密集和音の定義とは、とりあえず和音を構成する各音の音程間が「長三度」以下であることが条件ですね。長三度は含むけど、それより半音広い完全四度以上となると「開離音程」となるワケです。(※長三度はたまに現れるけど、そういう音程を含むことが多いながらも開離音程が多い曲の一例であるという意味で語っておりまして、長三度は開離音程ではないので混同しないようお願いします)
この手の曲だと、のっけからクローズド・ヴォイシング(密集和音)で弾くことは少ないと思うので、鍵盤楽器のみで曲のアンサンブルを構築しようとすると概ね開離和音を弾くことが多くなると思うんですね。
例えば、クローズド・ヴォイシングを転回する際、低い音から2番目の音をオクターブ下げれば「ドロップ2」と呼ばれ、低い音から3番目の音をオクターブ下げて転回すればそれは「ドロップ3」、さらには例えば三声を超える四声の和音にて低い音から2番目と4番目の音をオクターブ下げて転回すればそれは「ドロップ2&4」と呼ばれるのはご存知だと思うワケですが、こうした予め転回されたオーブン・ヴォイシングを弾きながら、その構成音の隔たりの間に生まれるコードトーンをうまく鏤めていくと、先述のようなリチャード・ティーやらグレッグ・フィリンゲインズ風になる、というコトですね。
とはいえ、音を鏤めるにあたってその音を巧く選択できなければ唯のモードスケールなぞっただけと同じになってしまうので、フレージングにセンスが問われると書いたのはこういう理由からなんです。
ドナルド・フェイゲンのソロ・アルバム「Nightfly」に収録の『Maxine(=愛しのマキシン)』のピアノのイントロなんてぇのは最たるモノで(byグレッグ・フィリンゲインズ)、耳当たりの心地良いVirginia Sundayからさらにジャズっぽさを推し進めると、Maxineのようなヴォイシングになるというワケですな。
「ジャズをどう聴いてイイのか判らない」
こういう人達は意外と多いんです。あまりにもハードなジャズやら和声の難易度が高度なモノをいきなり聴いてしまうと、その和声すら耳が受け付けずに、他の楽器のフレージングが唯単に半音階の乱れ打ちのようにしか聴き取れないと感じる人も多いワケですね。
ただ、そういう人でもどこかしらジャズっぽさを感じる耳は持っているワケで、やさしい、ジャズの入り口を提示してくれる曲というのは、その曲を実際に耳にしてから出ないとなかなか購買意欲というのは湧かないと思うんですね。そういう意味において、人によってはジャズは当たり外れの度が高く感じてしまい、ついつい敬遠しがちになってしまいかねないという音楽ジャンルでもあるんです。
Virginia Sundayをジャズと形容するには少々誇張し過ぎかもしれませんが、充分にジャズに入り口を提示しているというのは以前のブログでも語ったコトですが、なにより、クラシック畑の人、それも幼い子たちに耳にしてもらいたいというのがこの曲だったんですね。
曲が幼いのではなく、聴く人が幼い内に早期の段階でこういう響きを耳にしてほしい、という意味ですね。
通常、ピアノのレッスンに没頭する小学生がショパンの音について語れるようになる時というのは年齢は少なくとも二桁に達していると思うんですよね。
ただ、ショパンの特徴を俗世のクラシック畑における解釈のままになってしまうと、その特徴すら理解がおぼろげになって楽理的な特徴は掴めぬまま大人になる人が多いワケです(笑)。その特徴とやらを他の曲で後押ししてもらうことで、飽くなき和声への欲求を高ぶらせて、音楽へ没頭する心が強化されれば、是、左近治は感慨無量なワケですね(笑)。
とっくにリチャード・ティーも知ってしまっている人にではなく、全く知らない人や、これからピアノ頑張るぞ!という子達にぜひ聴かせてあげたい曲というコトなのです。
「ウチの子、ナメんなよ!」というご貴兄には、私がリリースしている他の楽曲(あなくろ本舗)の和声構造でも徹底分析してもらえたらな、と思います(笑)。
でもですね、この曲は決して幼い響きじゃあないですよ(笑)。ウチの子も凄いと思いたいんですけどmihimaru GTとかオヤジも一緒になって聴いてるのが現実でして(笑)。
2007-06-28 22:48
とことん親バカぶりを発揮するッ! [クロスオーバー]
子煩悩というお行儀の良いコトバなどかなぐり捨て、トコトン親バカにさせてくれる気持ちは、我が子を持つ親の気持ちとして当然で、そんな気持ちを露にして何が悪い!と言わんばかりに親バカぶりを発揮してもらおうかな、と思いましてですね、そんな気持ちをテーマに制作した曲があるんですよ。リリースは来週ですけどね(笑)。
リチャード・ティーの名曲『Virginia Sunday』。
いわゆる、「ローズ」と呼ばれるエレクトリック・ピアノによる美しいセミ・バラード曲ですね。
左近治は調性が希薄な楽曲を嗜好するとはいえ、メジャー・キー(長調)では変ホ長調(=E♭メジャー)の調が最も好きなんです。
ベースやってると大体はEm(Eマイナー)だとか、シャープ系の調号のキーが弾きやすいため、そういう嗜好性になりがちなのが初心者(ベースの)によくある例。私の場合調号がフラット系の楽曲を嗜好することが多かったため、ベースを弾くにあたっては開放弦を殆ど使うことが無いという(笑)。
で、「Virginia Sunday」。
幼い我が子に音楽の良さを伝えたい
バイエル卒業したら、こういう和声を聴いて和声の美しさを知ってもらいたい
ウチの子、飲み込みがイイみたいで人様とはチョット違った音楽に興味を持ってもらいたい
というような、こういう親心を抱いている方にオススメできる曲がコレだと左近治は思っております。
とはいえ、ソナチネやソナタのピアノレッスンを受けている子においても満足される曲であることは間違いないでしょう。
それはですね、それらのクラシック系のピアノレッスンでは決して知ることのできない「ヴォイシング」(=和声の構造)の美しさにあるワケです。
その手のレッスンでは、どれだけ習熟しても左手のベースパートはオクターブで補うことが殆ど。
Virginia Sundayは、ジャズとまでは言えないけれども、充分にジャズの入り口を提示してくれる曲でして、ジャズの基本とは左手の7度のヴォイシングが最たるモノだと思っております。
また、左手で弾く音と右の特定の音との長七度(時には半音)の隔たりを如何にして巧くちりばめるか、それがジャズの基本だと左近治は思います。
通常、レッスンで習うような曲では現れない音、それは変化形という形で楽譜に表れ、それらの特徴的な音が、実はどこかの音と7度の関係を作っていたりするものです。
その巧みな「ヴォイシング」は、いきなり白玉でそのコード(和声)をガツン!と弾いてもですね、耳が幼いと和声の良さを捕らえきれないと思うんですね。ただ、この曲「Virginia Sunday」のように、長音ペダル(=サステインペダル)を使いながらアルペジオでなぞってくれると、音を追いやすく、和声構造の隅々まで認識することが容易になるので、この曲は低年齢の子たちにも格好の作品だと左近治はオススメするのであります。
なにせ鍵盤弾きではない左近治ですら情感豊かに弾いてこうしてリリースできるわけですから(笑)、曲そのものの難易度は低いです(笑)。ただし、和声の美しさの方を重視してもらいたいと思うのがVirginia Sundayなのですね。
この曲を覚えることによって、オーギュメントという「フラット13th」の音、すなわちオルタード・テンションという音の一部を覚えられし、左手の七度の使い方やら、長音ペダルを用いざるを得ない和声の貪欲なまでの追究、セカンダリー・ドミナントの美しさ、メジャー7thの美しさを理解できるということに役立つことでしょう。
惜しむらくは、この曲は私の知る限り楽譜が無いこと(笑)。ただ、この曲を聴音できないようでは将来は不安ですな(笑)。
少々厳しくも、幼い子供に聴き取らせてみてはどうでしょうかね。労力が必要とされますが、その労力を吹き飛ばしてまで音を探りたくなる、そういう名曲が「Virginia Sunday」なのです。
この曲の詳細については、またリリース日にでもあらためて語りましょうかね、と。
リチャード・ティーの名曲『Virginia Sunday』。
いわゆる、「ローズ」と呼ばれるエレクトリック・ピアノによる美しいセミ・バラード曲ですね。
左近治は調性が希薄な楽曲を嗜好するとはいえ、メジャー・キー(長調)では変ホ長調(=E♭メジャー)の調が最も好きなんです。
ベースやってると大体はEm(Eマイナー)だとか、シャープ系の調号のキーが弾きやすいため、そういう嗜好性になりがちなのが初心者(ベースの)によくある例。私の場合調号がフラット系の楽曲を嗜好することが多かったため、ベースを弾くにあたっては開放弦を殆ど使うことが無いという(笑)。
で、「Virginia Sunday」。
幼い我が子に音楽の良さを伝えたい
バイエル卒業したら、こういう和声を聴いて和声の美しさを知ってもらいたい
ウチの子、飲み込みがイイみたいで人様とはチョット違った音楽に興味を持ってもらいたい
というような、こういう親心を抱いている方にオススメできる曲がコレだと左近治は思っております。
とはいえ、ソナチネやソナタのピアノレッスンを受けている子においても満足される曲であることは間違いないでしょう。
それはですね、それらのクラシック系のピアノレッスンでは決して知ることのできない「ヴォイシング」(=和声の構造)の美しさにあるワケです。
その手のレッスンでは、どれだけ習熟しても左手のベースパートはオクターブで補うことが殆ど。
Virginia Sundayは、ジャズとまでは言えないけれども、充分にジャズの入り口を提示してくれる曲でして、ジャズの基本とは左手の7度のヴォイシングが最たるモノだと思っております。
また、左手で弾く音と右の特定の音との長七度(時には半音)の隔たりを如何にして巧くちりばめるか、それがジャズの基本だと左近治は思います。
通常、レッスンで習うような曲では現れない音、それは変化形という形で楽譜に表れ、それらの特徴的な音が、実はどこかの音と7度の関係を作っていたりするものです。
その巧みな「ヴォイシング」は、いきなり白玉でそのコード(和声)をガツン!と弾いてもですね、耳が幼いと和声の良さを捕らえきれないと思うんですね。ただ、この曲「Virginia Sunday」のように、長音ペダル(=サステインペダル)を使いながらアルペジオでなぞってくれると、音を追いやすく、和声構造の隅々まで認識することが容易になるので、この曲は低年齢の子たちにも格好の作品だと左近治はオススメするのであります。
なにせ鍵盤弾きではない左近治ですら情感豊かに弾いてこうしてリリースできるわけですから(笑)、曲そのものの難易度は低いです(笑)。ただし、和声の美しさの方を重視してもらいたいと思うのがVirginia Sundayなのですね。
この曲を覚えることによって、オーギュメントという「フラット13th」の音、すなわちオルタード・テンションという音の一部を覚えられし、左手の七度の使い方やら、長音ペダルを用いざるを得ない和声の貪欲なまでの追究、セカンダリー・ドミナントの美しさ、メジャー7thの美しさを理解できるということに役立つことでしょう。
惜しむらくは、この曲は私の知る限り楽譜が無いこと(笑)。ただ、この曲を聴音できないようでは将来は不安ですな(笑)。
少々厳しくも、幼い子供に聴き取らせてみてはどうでしょうかね。労力が必要とされますが、その労力を吹き飛ばしてまで音を探りたくなる、そういう名曲が「Virginia Sunday」なのです。
この曲の詳細については、またリリース日にでもあらためて語りましょうかね、と。
2007-06-21 07:43
ギターのMIDI編集 [クロスオーバー]
ギターの打ち込みとなると結構細かいMIDIイベントの編集が付き物なので、面倒くさい一方で、打ち込み魂を燃え上がらせてくれるモノであります(笑)。
正直言って一番手っ取り早いのはRolandのGR系でMIDIにしちまう、と。ギターなんてェのは押弦しただけでベンド情報は実に細かく入力されているモノなんですよ。
今回左近治があらためてギターのMIDIエディットの話題を挙げる理由はですね、今現在SHOGUNの某曲を制作しているからなのでありますが(笑)、我らが大将、芳野藤丸御大のギターをエディットするとなるとですね、手ェ抜いたらバチが当たるってェもんですよ!(笑)。
最近のギターフレーズは80年代のロックシーン(←死語)に見受けられるような派手なアーミングを耳にする機会は非常に少なくなったものですが、アーミングなんてェのも、実は各弦のベンド幅は全然違うんですよね。
プレーン弦はそれほど大きく変化しないものの、巻弦の低音弦なんてのは2オクターブ以上合っても足りないくらい落ちるんですよ(笑)。ベロンベロンにまでアームダウンさせて弦がポールピースにくっ付いちゃうような(笑)。
んで、アームの構造でこれまた変化具合が違うんですよね。
例えばフロイド・ローズ系をAカーブと例えるなら、ケーラーはBカーブ、ムスタング系ならCカーブに例えられるような変化があります。私はケーラーやムスタング系の変化量が結構好きだったりするんですが、粗悪な弦使ってるとケーラーはブリッジサドルから落ちちゃうんですよね、コレがまた(笑)。
とゆーワケで、ギターを各弦ごとにMIDIチャンネルを割り当ててMIDI編集に勤しむワケですが(笑)、最近じゃあ7弦ギターもすっかりポピュラーになったモノですが、6本から7本に増えようが、実際の所作業に大きな違いはありません。
ただ、ギターのMIDI編集で一番面白いところはですね、先述のようなベンド情報などに加えて、如何にして異弦同音をシミュレートするか、なんですよ。弦ごとに細かいベロシティ・レイヤーが組まれたサンプルなら編集そのものがやりやすくなりますが、それほど多くのベロシティ・レイヤーが組まれていない場合は、低音弦のハイポジションでの倍音の減衰度や弦振動の飽和感を演出してやらなければ面白くありません(笑)。
最近のDAW環境では、これらを緻密にオートメーションで編集して、それに追随するようにプラグイン側でもパラメータが細かくアサインしてあるものも多いため、かなり細かく編集できます。
アフタータッチやらにビビリ音のサンプルをアサインしたり、キー・オフ・ベロシティに離弦時のノイズをアサインしたりなど、弦楽器の打ち込みは奥が深いモノですが(弦楽器のみならず、楽器の演奏形態は実に置くが深い)、ハードウェア・シンセサイザーそのものにキー・オフ・ベロシティが可能なタイプとなると比較的高価なタイプになってしまうものが多く、音源上やらMIDI編集上でコントロールするものの、実際に鍵盤で弾いた感覚で実感するコトは意外と少ないという方が多いのではないかと思います。
キー・オフ・ベロシティやらポリ・アフタータッチとなると通常とは別にさらにセンサーが必要になるんで、概ねキータッチのフィールが他の鍵盤と違ったりするもので、さらには手入れをあんまりしていないと故障しやすいという側面もあります。
キー・オフ・ベロシティをよく多用するシーンは、シンバルのミュート。いわゆるチョークですね。あとはアフタータッチでスナッピーの共鳴ビビリ音とかですね(笑)。
ギターでも前述のように色々な使い道があるんですが、なんと言っても異弦同音による音の差異感を僅かながらでも演出するコトの方がよりリアル感が増します。
細かくオクターブ調整をしてもですね、やはりハイ・ポジションとなるとどんなモノでもフレット打ってある以上は、もはやドンピシャのピッチなんて有り得ないワケですよ。
現実世界においては1本の弦だけでチューナーや音叉に合わせたら後はハーモニクスだけで全部合わせてしまう痛々しい方などいらっしゃるワケですが、ハーモニクスで合わせちゃったら、最初に合わせた弦から遠ざかれば遠ざかるほどピタゴラス・コンマの世界へ行こうとしているんで、本人だけがドンピシャのつもりになっている人も多いんですが、こーゆー初歩的なミスを敢えてシミュレートする必要は無いので(笑)、ハイポジションにおける異弦同音のほんの少しのピッチのズレを演出したり、音質の差異感を演出していくだけで十分リアル感が増すというモノです。
左近治の場合はですね、13セントから35セントくらいの間までズラしちゃいます。弦の太さやポジション位置の想定する具合にもよりますが。35セントなんでクォーター・トーン八分音よりも大きいワケですが、チューニング合わせがしっかりした上でハイポジションのフレット打ちの精度の高い楽器は、オクターブ調整をした上で35セントずれても器楽的に鳴ります。
一方でチューニングすらまともでない、ハイポジションのフレット打ちも精度が粗悪、弾いている人も意識していない棒弾きタイプだと35セントは他のアンサンブルと比較して全然器楽的に鳴ってくれません。仮にチューニングの稚拙さと意図したズレが相殺されて、ピッチがほぼ合っているシーンがあったとしても、全体では器楽的にズレているモノであります。
『器楽的』に調律された弦楽器というのはですね、60セントくらいズレても器楽的に聴こえてくれるから不思議なモノです。
まあ、ELTやら中島美嘉のような歌声は器楽的とは違うフェーズのモノであることは確かですが(笑)。
ピッチ編集をする一方で、細かなピッチのズレを器楽的に演出するコト、それがサンプリングのギター音では本当に難しい所であります。
正直言って一番手っ取り早いのはRolandのGR系でMIDIにしちまう、と。ギターなんてェのは押弦しただけでベンド情報は実に細かく入力されているモノなんですよ。
今回左近治があらためてギターのMIDIエディットの話題を挙げる理由はですね、今現在SHOGUNの某曲を制作しているからなのでありますが(笑)、我らが大将、芳野藤丸御大のギターをエディットするとなるとですね、手ェ抜いたらバチが当たるってェもんですよ!(笑)。
最近のギターフレーズは80年代のロックシーン(←死語)に見受けられるような派手なアーミングを耳にする機会は非常に少なくなったものですが、アーミングなんてェのも、実は各弦のベンド幅は全然違うんですよね。
プレーン弦はそれほど大きく変化しないものの、巻弦の低音弦なんてのは2オクターブ以上合っても足りないくらい落ちるんですよ(笑)。ベロンベロンにまでアームダウンさせて弦がポールピースにくっ付いちゃうような(笑)。
んで、アームの構造でこれまた変化具合が違うんですよね。
例えばフロイド・ローズ系をAカーブと例えるなら、ケーラーはBカーブ、ムスタング系ならCカーブに例えられるような変化があります。私はケーラーやムスタング系の変化量が結構好きだったりするんですが、粗悪な弦使ってるとケーラーはブリッジサドルから落ちちゃうんですよね、コレがまた(笑)。
とゆーワケで、ギターを各弦ごとにMIDIチャンネルを割り当ててMIDI編集に勤しむワケですが(笑)、最近じゃあ7弦ギターもすっかりポピュラーになったモノですが、6本から7本に増えようが、実際の所作業に大きな違いはありません。
ただ、ギターのMIDI編集で一番面白いところはですね、先述のようなベンド情報などに加えて、如何にして異弦同音をシミュレートするか、なんですよ。弦ごとに細かいベロシティ・レイヤーが組まれたサンプルなら編集そのものがやりやすくなりますが、それほど多くのベロシティ・レイヤーが組まれていない場合は、低音弦のハイポジションでの倍音の減衰度や弦振動の飽和感を演出してやらなければ面白くありません(笑)。
最近のDAW環境では、これらを緻密にオートメーションで編集して、それに追随するようにプラグイン側でもパラメータが細かくアサインしてあるものも多いため、かなり細かく編集できます。
アフタータッチやらにビビリ音のサンプルをアサインしたり、キー・オフ・ベロシティに離弦時のノイズをアサインしたりなど、弦楽器の打ち込みは奥が深いモノですが(弦楽器のみならず、楽器の演奏形態は実に置くが深い)、ハードウェア・シンセサイザーそのものにキー・オフ・ベロシティが可能なタイプとなると比較的高価なタイプになってしまうものが多く、音源上やらMIDI編集上でコントロールするものの、実際に鍵盤で弾いた感覚で実感するコトは意外と少ないという方が多いのではないかと思います。
キー・オフ・ベロシティやらポリ・アフタータッチとなると通常とは別にさらにセンサーが必要になるんで、概ねキータッチのフィールが他の鍵盤と違ったりするもので、さらには手入れをあんまりしていないと故障しやすいという側面もあります。
キー・オフ・ベロシティをよく多用するシーンは、シンバルのミュート。いわゆるチョークですね。あとはアフタータッチでスナッピーの共鳴ビビリ音とかですね(笑)。
ギターでも前述のように色々な使い道があるんですが、なんと言っても異弦同音による音の差異感を僅かながらでも演出するコトの方がよりリアル感が増します。
細かくオクターブ調整をしてもですね、やはりハイ・ポジションとなるとどんなモノでもフレット打ってある以上は、もはやドンピシャのピッチなんて有り得ないワケですよ。
現実世界においては1本の弦だけでチューナーや音叉に合わせたら後はハーモニクスだけで全部合わせてしまう痛々しい方などいらっしゃるワケですが、ハーモニクスで合わせちゃったら、最初に合わせた弦から遠ざかれば遠ざかるほどピタゴラス・コンマの世界へ行こうとしているんで、本人だけがドンピシャのつもりになっている人も多いんですが、こーゆー初歩的なミスを敢えてシミュレートする必要は無いので(笑)、ハイポジションにおける異弦同音のほんの少しのピッチのズレを演出したり、音質の差異感を演出していくだけで十分リアル感が増すというモノです。
左近治の場合はですね、13セントから35セントくらいの間までズラしちゃいます。弦の太さやポジション位置の想定する具合にもよりますが。35セントなんで
一方でチューニングすらまともでない、ハイポジションのフレット打ちも精度が粗悪、弾いている人も意識していない棒弾きタイプだと35セントは他のアンサンブルと比較して全然器楽的に鳴ってくれません。仮にチューニングの稚拙さと意図したズレが相殺されて、ピッチがほぼ合っているシーンがあったとしても、全体では器楽的にズレているモノであります。
『器楽的』に調律された弦楽器というのはですね、60セントくらいズレても器楽的に聴こえてくれるから不思議なモノです。
まあ、ELTやら中島美嘉のような歌声は器楽的とは違うフェーズのモノであることは確かですが(笑)。
ピッチ編集をする一方で、細かなピッチのズレを器楽的に演出するコト、それがサンプリングのギター音では本当に難しい所であります。
2007-05-06 01:26
クロスオーバー・サウンドとやらを [クロスオーバー]
語ります(笑)。
左近治にとってのクロスオーバー・サウンドとは!?どこら辺がフュージョンでどこら辺がクロスオーバーなのか。境界線というのは意外に曖昧なモノですが、左近治の定義するクロスオーバーは調性が希薄。コレに尽きます(笑)。調性がキッカリとあってメロディ重視!というのは「フュージョン」と定義してます(笑)。
耳が肥えてくるであろう大学生時代(当時)、彼らの洒落た音楽(インスト物)というのがクロスオーバーやらフュージョンだったワケですよ。大学生ブランドというのが崇高な時代ですね。概ね1977~1979年辺りがいわゆる「フュージョンブーム」だったかと思います。その当時左近治は小学生ですが(笑)、早熟左近治は「キャンパス・ライフ(←死語)」というものに憧れ、いち早く成人しないものかと急いてですね、喫煙やら似合いもしない服着込んでいたりしていたモノです。
大学生がブランド化していたのは、やはり学生運動後に大学生としての地位をより強固にした上で、その基盤でゆったりとした時を満喫する、という時代に推移したからでしょうな。あらゆるメディアも日進月歩で進化しているという時代。「ふぞろいの林檎たち」辺りまでが大学生ブランドの華やかな時代だったのではないかと。
ま、そんな大学生ブランドも「おニャン子」によって駆逐され、敢え無く低年齢化して高校生が主役になっていくのでありました。
おニャン子の番組内BGMでも、パラシュート(松原正樹や今剛が在籍していたバンド)の「Hercules」とかがかかっていて、その当時でもどこか「フュージョン」は引きずっていたんですね(※番組内で故逸見政孝氏がニュースを読むコーナーでかかっていたバージョンはパラシュートのバージョンではなく「Guitar Kids Vol.1」収録のバージョン)。
暮れだか今年の正月辺りだったか、BS FUJIで「クロスオーバー・ジャパン」なるモノを放映していたんですが、私が言うのもなんですが、殆どの人、腕が落ちましたね。こう言ってはなんですが。
モニターはヒビノさんだったと記憶していますが、あのハコでモニターしづらそうな気配が感じ取れたワケですが、中音(周波数帯じゃないですよ)デカくしないようにすればイイのに、などと思ったり。それにしてもみんなバンドアンサンブルでやる時間無いのかなーなどと思ってしまいました。アレに金出して見に行った人が哀れな内容でしたね。
セールスが比較的期待できた国内のフュージョン系バンドのそれは、もはやインプロヴィゼイションなど無いに等しく、計算された世界を演出するならそれこそカンタベリー系を彷彿とさせる骨太なクロスオーバー・サウンドで繰り広げてもらいたいもんだよなぁーなどと思っていたりしていたモノでした。みなさん本当はやりたいんでしょうけどね。
アドリブだけで世界を股にかけてメシ食える人って国内じゃ本当に少ないワケで、日本人に合っているいわゆるそっち系の音はカンタベリー系などにヒントがあるのではないかと思うんですよ。
しかし、計算され尽くすほどのコード・プログレッションでアレンジすれば、ソロ取る時のモード・チェンジが大変で手グセがジャマして音外しかねない(笑)。そういうジレンマが生じるワケですが、コード・プログレッションやリフの構築をとことん追及していたのが実はカシオペアではないかと左近治は思っております。カンタベリー系でもなんでも無いですが、コード・プログレッションの飽くなき欲求という志向性はビンビン感じ取れましたね。富田恵一やスティーリー・ダンにもそういう気概を感じるワケでして。
ポピュラー音楽との融合やら歌伴やら劇伴に巧く採り入れていたのが大野雄二辺りでしょうかね。この方のコード・プログレッションのこだわりと万人が受け入れやすいようなツボを心得ている人ですよね。余談ですが、左近治は坂本龍一と大野雄二は実は似た位相に位置するものと思っております(笑)。坂本龍一から電子楽器奪えば、あまり隔たりはないんじゃないかと。
※2018年11月23日補足 先日、松原正樹の別バージョンである「Hercules」をYouTubeで見つけたので、この機会に動画リンクを貼って補足しておく事にしました。当時の『夕やけニャンニャン』番組内にて故逸見政孝氏がニュースを読むコーナーでBGMで能く流れていたのが、パラシュートでの物ではない松原正樹名義での「Hercules」でありました。
そのバージョンは懐かしSEE・SAWレーベルからリリースされていた『GUITAR KIDS.1』(品番C28R0095)に収録されていた物で、アルバムには他に鳥山雄二、横内建亨(TENSAW)、松浦由寛(TWIST)等のオムニバス・アルバムとしてリリースされていた物です。
「Hercules」のパーソネルは以下の通り。
G:松原正樹
Bs:美久月千晴
Ds:島村英二
Key:佐藤準
Perc:斎藤ノブ
余談ではありますが佐藤準は嘗て、細野晴臣がYMOの構想を立てていた頃のキーボードの候補として名が挙がっていたという逸話は有名。
左近治にとってのクロスオーバー・サウンドとは!?どこら辺がフュージョンでどこら辺がクロスオーバーなのか。境界線というのは意外に曖昧なモノですが、左近治の定義するクロスオーバーは調性が希薄。コレに尽きます(笑)。調性がキッカリとあってメロディ重視!というのは「フュージョン」と定義してます(笑)。
耳が肥えてくるであろう大学生時代(当時)、彼らの洒落た音楽(インスト物)というのがクロスオーバーやらフュージョンだったワケですよ。大学生ブランドというのが崇高な時代ですね。概ね1977~1979年辺りがいわゆる「フュージョンブーム」だったかと思います。その当時左近治は小学生ですが(笑)、早熟左近治は「キャンパス・ライフ(←死語)」というものに憧れ、いち早く成人しないものかと急いてですね、喫煙やら似合いもしない服着込んでいたりしていたモノです。
大学生がブランド化していたのは、やはり学生運動後に大学生としての地位をより強固にした上で、その基盤でゆったりとした時を満喫する、という時代に推移したからでしょうな。あらゆるメディアも日進月歩で進化しているという時代。「ふぞろいの林檎たち」辺りまでが大学生ブランドの華やかな時代だったのではないかと。
ま、そんな大学生ブランドも「おニャン子」によって駆逐され、敢え無く低年齢化して高校生が主役になっていくのでありました。
おニャン子の番組内BGMでも、パラシュート(松原正樹や今剛が在籍していたバンド)の「Hercules」とかがかかっていて、その当時でもどこか「フュージョン」は引きずっていたんですね(※番組内で故逸見政孝氏がニュースを読むコーナーでかかっていたバージョンはパラシュートのバージョンではなく「Guitar Kids Vol.1」収録のバージョン)。
暮れだか今年の正月辺りだったか、BS FUJIで「クロスオーバー・ジャパン」なるモノを放映していたんですが、私が言うのもなんですが、殆どの人、腕が落ちましたね。こう言ってはなんですが。
モニターはヒビノさんだったと記憶していますが、あのハコでモニターしづらそうな気配が感じ取れたワケですが、中音(周波数帯じゃないですよ)デカくしないようにすればイイのに、などと思ったり。それにしてもみんなバンドアンサンブルでやる時間無いのかなーなどと思ってしまいました。アレに金出して見に行った人が哀れな内容でしたね。
セールスが比較的期待できた国内のフュージョン系バンドのそれは、もはやインプロヴィゼイションなど無いに等しく、計算された世界を演出するならそれこそカンタベリー系を彷彿とさせる骨太なクロスオーバー・サウンドで繰り広げてもらいたいもんだよなぁーなどと思っていたりしていたモノでした。みなさん本当はやりたいんでしょうけどね。
アドリブだけで世界を股にかけてメシ食える人って国内じゃ本当に少ないワケで、日本人に合っているいわゆるそっち系の音はカンタベリー系などにヒントがあるのではないかと思うんですよ。
しかし、計算され尽くすほどのコード・プログレッションでアレンジすれば、ソロ取る時のモード・チェンジが大変で手グセがジャマして音外しかねない(笑)。そういうジレンマが生じるワケですが、コード・プログレッションやリフの構築をとことん追及していたのが実はカシオペアではないかと左近治は思っております。カンタベリー系でもなんでも無いですが、コード・プログレッションの飽くなき欲求という志向性はビンビン感じ取れましたね。富田恵一やスティーリー・ダンにもそういう気概を感じるワケでして。
ポピュラー音楽との融合やら歌伴やら劇伴に巧く採り入れていたのが大野雄二辺りでしょうかね。この方のコード・プログレッションのこだわりと万人が受け入れやすいようなツボを心得ている人ですよね。余談ですが、左近治は坂本龍一と大野雄二は実は似た位相に位置するものと思っております(笑)。坂本龍一から電子楽器奪えば、あまり隔たりはないんじゃないかと。
※2018年11月23日補足 先日、松原正樹の別バージョンである「Hercules」をYouTubeで見つけたので、この機会に動画リンクを貼って補足しておく事にしました。当時の『夕やけニャンニャン』番組内にて故逸見政孝氏がニュースを読むコーナーでBGMで能く流れていたのが、パラシュートでの物ではない松原正樹名義での「Hercules」でありました。
そのバージョンは懐かしSEE・SAWレーベルからリリースされていた『GUITAR KIDS.1』(品番C28R0095)に収録されていた物で、アルバムには他に鳥山雄二、横内建亨(TENSAW)、松浦由寛(TWIST)等のオムニバス・アルバムとしてリリースされていた物です。
「Hercules」のパーソネルは以下の通り。
G:松原正樹
Bs:美久月千晴
Ds:島村英二
Key:佐藤準
Perc:斎藤ノブ
余談ではありますが佐藤準は嘗て、細野晴臣がYMOの構想を立てていた頃のキーボードの候補として名が挙がっていたという逸話は有名。
2007-04-23 21:25
変拍子を考える [クロスオーバー]
今現在制作に没頭している洋楽関連曲(あなくろ本舗用)がありましてですね、それがHatfield and The Northの『Mumps』なのであります。
プログレとカテゴライズされるHatfield and The Northですが、Mumpsが収録されている2枚目のアルバム『Rotter's Club』なんてぇのは、70年代を代表するマスト・アイテムだと思われるんですな。一部の偏狭的なマニアだけには勿体無いほどの高い完成度と高度なハーモニー。
緻密に計算され尽くされたアレンジと演奏というのは正直言ってですね、その辺の人がただ単にモード・スケールなぞっただけのようなソロやらインプロヴィゼーション聴かされるより遥かに素晴らしいんですよ。楽曲的に。
例えばパット・メセニーのように瞬時にハーモニーの構造を昇華して、十二音の中で自由に巧みに操れるような人というのはかなり稀有だと思うんですよ。大概は自分の弾きたい世界へ持ち込んで解釈しているワケでありまして。
ところが稀有ではない雑多タイプの人達のソロなんてのは殆どが「やらない方がマシ」のようなソロが実に多いワケでしてですね、カンタベリー系と称される「ジャズ・ロック」の計算され尽くされた様式美というのは、クロスオーバー・サウンドとして在るべき姿だと思うんですよ。
左近治のクロスオーバー・サウンドの基準というのは実はHatfield and The Northのサウンドにあるのです。実は。
ジャズ/フュージョン畑の「クロスオーバー・サウンド」聴きたさに足運んで実につまらない演奏聴かされたコトも多々あり。高校1年の時からこちとらPIT INNに通いづめ(笑)。でもですね、ジャズ畑ではないような人達の「クロスオーバー・サウンド」というのはムダが無いし、計算されているものが多く、ソロを取ってもジャズ畑のそれよりも遥かにイイ演奏しているコトが実に多いんですよ。アンサンブル全体の「音」というのも緻密に計算しているような。
さて、『Mumps』の方を語るとしてですね、左近治はいまだにMumpsのいわゆるコアとなるテーマ部分をチマチマ作っていてリリースできるほど完成に至っておりません(笑)。20分を超える大曲ですが、左近治の作っている部分はアップロードした拍子列の小節構造部分の正味90秒のコア部分(笑)。
Mumpsの収録されているアルバム「Rotter's Club」はローズ聴いているだけでも気持ちイイものでありまして、ローズを目の前にすると左近治はついつい「Underdub」とか弾いたりするモンです。
4/4拍子一辺倒な人からすると、Mumpsを知らない人は譜例の変拍子を見て面食らうかもしれませんが、実はこの曲というのは実に「自然に」変拍子が変拍子っぽくなく聴くコトが出来る曲なのです。
4拍子のリフの中に局面だけ変拍子が入ったりするような曲の方が大半は「幾何学的」なリズムに聴こえるワケでありましてですね、コレほどスンナリ変拍子が入ってくる理由というのは恐らく、この曲のメロディやハーモニック的なリズムを与えるタイミングが、拍など気にせずに人が楽器と戯れて爪弾いているような時のフレーズに拍を当てはめたような、そういう「鼻歌要素」のあるフレージングだからだと思われます。
もちろん、作曲時点では変拍子であることを前提にアレンジしていたりするかもしれませんが、鼻歌的な要素がある変拍子というのは実に自然に溶け込むというモノです。
変拍子の扱いが巧みなバンドは他にはジェントル・ジャイアントやらレッド・ツェッペリンもありますが、鼻歌要素とはまた少し別の、リフとしてカッコイイ変拍子であってですね、やはりこのMumpsとはチト違うんですね。
フランク・ザッパは「喋り」のリズムを拍子に置換するような視点で作られたりしますが、周囲のアンサンブルはその「喋り」を楽曲的なアレンジにまで昇華できているかというと、そうでもなく、拍子の概念に支配されているプレイヤーが多いのが事実です。ザッパの曲全てがそうだとは言いませんけどね。そうは言っても左近治自身フランク・ザッパはかなり好きなんですけど(笑)。
先述の譜例で所々リズム譜を入れているのは、そこが「コア」な部分と左近治が感じ取っているだけでありまして(笑)、参考になればよいかな、と。
左近治のリズム解釈は本当はですね、譜例の拍子の分母は半分で捕えています。3/4拍子だったら左近治自身は「3/8拍子」として捕えているということですね。すなわち音符上では倍テンポ解釈なんです。打ち込みの時点でもそういう風に作っているんですけど、倍テンポ解釈だと曲全体が解釈に戸惑うような感じになると思って今回のような譜例を挙げてみたというワケであります。変拍子は奥が深いモノですが、4拍子一辺倒の人にも騙されたと思って変拍子に触れてほしいと思います(笑)。
プログレとカテゴライズされるHatfield and The Northですが、Mumpsが収録されている2枚目のアルバム『Rotter's Club』なんてぇのは、70年代を代表するマスト・アイテムだと思われるんですな。一部の偏狭的なマニアだけには勿体無いほどの高い完成度と高度なハーモニー。
緻密に計算され尽くされたアレンジと演奏というのは正直言ってですね、その辺の人がただ単にモード・スケールなぞっただけのようなソロやらインプロヴィゼーション聴かされるより遥かに素晴らしいんですよ。楽曲的に。
例えばパット・メセニーのように瞬時にハーモニーの構造を昇華して、十二音の中で自由に巧みに操れるような人というのはかなり稀有だと思うんですよ。大概は自分の弾きたい世界へ持ち込んで解釈しているワケでありまして。
ところが稀有ではない雑多タイプの人達のソロなんてのは殆どが「やらない方がマシ」のようなソロが実に多いワケでしてですね、カンタベリー系と称される「ジャズ・ロック」の計算され尽くされた様式美というのは、クロスオーバー・サウンドとして在るべき姿だと思うんですよ。
左近治のクロスオーバー・サウンドの基準というのは実はHatfield and The Northのサウンドにあるのです。実は。
ジャズ/フュージョン畑の「クロスオーバー・サウンド」聴きたさに足運んで実につまらない演奏聴かされたコトも多々あり。高校1年の時からこちとらPIT INNに通いづめ(笑)。でもですね、ジャズ畑ではないような人達の「クロスオーバー・サウンド」というのはムダが無いし、計算されているものが多く、ソロを取ってもジャズ畑のそれよりも遥かにイイ演奏しているコトが実に多いんですよ。アンサンブル全体の「音」というのも緻密に計算しているような。
さて、『Mumps』の方を語るとしてですね、左近治はいまだにMumpsのいわゆるコアとなるテーマ部分をチマチマ作っていてリリースできるほど完成に至っておりません(笑)。20分を超える大曲ですが、左近治の作っている部分はアップロードした拍子列の小節構造部分の正味90秒のコア部分(笑)。
Mumpsの収録されているアルバム「Rotter's Club」はローズ聴いているだけでも気持ちイイものでありまして、ローズを目の前にすると左近治はついつい「Underdub」とか弾いたりするモンです。
4/4拍子一辺倒な人からすると、Mumpsを知らない人は譜例の変拍子を見て面食らうかもしれませんが、実はこの曲というのは実に「自然に」変拍子が変拍子っぽくなく聴くコトが出来る曲なのです。
4拍子のリフの中に局面だけ変拍子が入ったりするような曲の方が大半は「幾何学的」なリズムに聴こえるワケでありましてですね、コレほどスンナリ変拍子が入ってくる理由というのは恐らく、この曲のメロディやハーモニック的なリズムを与えるタイミングが、拍など気にせずに人が楽器と戯れて爪弾いているような時のフレーズに拍を当てはめたような、そういう「鼻歌要素」のあるフレージングだからだと思われます。
もちろん、作曲時点では変拍子であることを前提にアレンジしていたりするかもしれませんが、鼻歌的な要素がある変拍子というのは実に自然に溶け込むというモノです。
変拍子の扱いが巧みなバンドは他にはジェントル・ジャイアントやらレッド・ツェッペリンもありますが、鼻歌要素とはまた少し別の、リフとしてカッコイイ変拍子であってですね、やはりこのMumpsとはチト違うんですね。
フランク・ザッパは「喋り」のリズムを拍子に置換するような視点で作られたりしますが、周囲のアンサンブルはその「喋り」を楽曲的なアレンジにまで昇華できているかというと、そうでもなく、拍子の概念に支配されているプレイヤーが多いのが事実です。ザッパの曲全てがそうだとは言いませんけどね。そうは言っても左近治自身フランク・ザッパはかなり好きなんですけど(笑)。
先述の譜例で所々リズム譜を入れているのは、そこが「コア」な部分と左近治が感じ取っているだけでありまして(笑)、参考になればよいかな、と。
左近治のリズム解釈は本当はですね、譜例の拍子の分母は半分で捕えています。3/4拍子だったら左近治自身は「3/8拍子」として捕えているということですね。すなわち音符上では倍テンポ解釈なんです。打ち込みの時点でもそういう風に作っているんですけど、倍テンポ解釈だと曲全体が解釈に戸惑うような感じになると思って今回のような譜例を挙げてみたというワケであります。変拍子は奥が深いモノですが、4拍子一辺倒の人にも騙されたと思って変拍子に触れてほしいと思います(笑)。
2007-03-31 21:07
最近、ハマる音がある [クロスオーバー]
制作状況が順調な左近治。すっかりゴールデンウイークに入るまでのリリース用の曲は仕上げてしまい、あとは春の特番や新番組やら新CMがあれば、それらを作ることになりそうですが、今のところは、是が非でも作らなければならないというコンテンツには遭遇しておらず、とりあえずは順調に仕上げている左近治であります。
団塊の世代のリタイアが始まるという年。今春からテレビコンテンツの方に変化があるのか無いのか!?そういう部分にも興味がありますね。
ただ、懐かし系やら以前から作ろうとしていた曲達は漏れなくリリースしていきたいと考えております。最近のテレビコンテンツというのはドラマでも2クール続くようなモノは少なく、大体が1クールで終わってしまうワケですよね。ほんの90日程度。
制作側からすれば数字が取れるかどうかも分からないのに2クールもの長期間放送しなければならないというリスクを負いたくはないだろうし、広告費収入が第一である以上は、やはり数字ありきが現実なんですよね、コレが。
そんな厳しい中で、音楽の訴求力は求められるものの、90年代にはあれほどの隆盛を誇ったCD売上も、チャートものの音楽も一部の利用者以外からはソッポを向かれ、いまや低迷状態。本当にソッポを向かれてしまっているのか!?
左近治はそうは思わないんですよね。iPodの普及もあって多くの人たちは時間を有意義に使いながら音楽を聴いているんですよ。ただ、そこに蓄積されていく音楽というのは自分の嗜好性というものをこれまでよりも増して色付けしてそれを選んで聴かれているというのが現実なんですね。
音楽離れやらテレビ離れとも言われておりますが、実際にはネットや外出している人たちの多くも情報やコンテンツの質を求めているワケでして、手放しで足運んでくれるような客層ばかりを相手にしていると本当の質を見極めるコトができなくなってしまう危険性を孕んでいるのも事実。今後の音楽界がどう推移していくのか非常に興味深いものであります。
左近治自身は、飛び道具要素の強い楽曲をこれまでよりも多くリリースを予定しているので(笑)、より楽しんでもらえるよう努力せねばならないと思っているワケですが、着うた制作にシフトして以来細心の注意を払っているのが音作り。
まあ、FM音源の着メロ時代でも音作りには一定のコダワリがあったワケですが、それ以上に音作りにこだわっているのが現在の私。シンセ類の音作りやエフェクト類での音作りも然り。
そんな中左近治が今あらためて惹きつけられる音というのがありまして、その具現化に手を焼いている音があるんですよ。
時は1985年春。左近治が生まれて初めてCDプレーヤーをゲットした時なんですが、この頃FM放送でも時々かかってその当時CDをゲットした曲があるんですが、それが鳥山雄司のソロ・アルバム『A Taste of Paradise』収録のシンディが歌う「Eyes of God」。
今、この曲にハマっているんですね。LINNのドラムマシン、フェアライト、オーバーハイムとおぼしき音がふんだんに使われているんですが、冒頭のGated ReverbがかかったLINNのドラムマシンのフィルの後のイントロの8小節目に、FM音源独特のシルキーでグラシィなとてもキメ細かいパッド音が鳴るんですね。今私はこの音に夢中なんです。どうやって作ろうかと。
「Eyes of God」を着手しているワケではなく、その音に惚れているワケですが、アレDX7だとしたら相当すごいプログラミングだなーと思っているんですよ。フェアライトなのかMatrix12なのかも予想は付かないんですが、兎にも角にも模倣するとなるとかなり難しいんですね、コレがまた。左近治はおそらくその音はフェアライトではないかと思っているんですけどね。
この音さえ作れれば着うたアレンジにおいて相当貢献してくれるキレイな音になってくれるハズなんですが(笑)、かなり難しいのが悩みの種・・・。
団塊の世代のリタイアが始まるという年。今春からテレビコンテンツの方に変化があるのか無いのか!?そういう部分にも興味がありますね。
ただ、懐かし系やら以前から作ろうとしていた曲達は漏れなくリリースしていきたいと考えております。最近のテレビコンテンツというのはドラマでも2クール続くようなモノは少なく、大体が1クールで終わってしまうワケですよね。ほんの90日程度。
制作側からすれば数字が取れるかどうかも分からないのに2クールもの長期間放送しなければならないというリスクを負いたくはないだろうし、広告費収入が第一である以上は、やはり数字ありきが現実なんですよね、コレが。
そんな厳しい中で、音楽の訴求力は求められるものの、90年代にはあれほどの隆盛を誇ったCD売上も、チャートものの音楽も一部の利用者以外からはソッポを向かれ、いまや低迷状態。本当にソッポを向かれてしまっているのか!?
左近治はそうは思わないんですよね。iPodの普及もあって多くの人たちは時間を有意義に使いながら音楽を聴いているんですよ。ただ、そこに蓄積されていく音楽というのは自分の嗜好性というものをこれまでよりも増して色付けしてそれを選んで聴かれているというのが現実なんですね。
音楽離れやらテレビ離れとも言われておりますが、実際にはネットや外出している人たちの多くも情報やコンテンツの質を求めているワケでして、手放しで足運んでくれるような客層ばかりを相手にしていると本当の質を見極めるコトができなくなってしまう危険性を孕んでいるのも事実。今後の音楽界がどう推移していくのか非常に興味深いものであります。
左近治自身は、飛び道具要素の強い楽曲をこれまでよりも多くリリースを予定しているので(笑)、より楽しんでもらえるよう努力せねばならないと思っているワケですが、着うた制作にシフトして以来細心の注意を払っているのが音作り。
まあ、FM音源の着メロ時代でも音作りには一定のコダワリがあったワケですが、それ以上に音作りにこだわっているのが現在の私。シンセ類の音作りやエフェクト類での音作りも然り。
そんな中左近治が今あらためて惹きつけられる音というのがありまして、その具現化に手を焼いている音があるんですよ。
時は1985年春。左近治が生まれて初めてCDプレーヤーをゲットした時なんですが、この頃FM放送でも時々かかってその当時CDをゲットした曲があるんですが、それが鳥山雄司のソロ・アルバム『A Taste of Paradise』収録のシンディが歌う「Eyes of God」。
今、この曲にハマっているんですね。LINNのドラムマシン、フェアライト、オーバーハイムとおぼしき音がふんだんに使われているんですが、冒頭のGated ReverbがかかったLINNのドラムマシンのフィルの後のイントロの8小節目に、FM音源独特のシルキーでグラシィなとてもキメ細かいパッド音が鳴るんですね。今私はこの音に夢中なんです。どうやって作ろうかと。
「Eyes of God」を着手しているワケではなく、その音に惚れているワケですが、アレDX7だとしたら相当すごいプログラミングだなーと思っているんですよ。フェアライトなのかMatrix12なのかも予想は付かないんですが、兎にも角にも模倣するとなるとかなり難しいんですね、コレがまた。左近治はおそらくその音はフェアライトではないかと思っているんですけどね。
この音さえ作れれば着うたアレンジにおいて相当貢献してくれるキレイな音になってくれるハズなんですが(笑)、かなり難しいのが悩みの種・・・。
2007-03-03 11:43
Throw Down / Tom Browne制作中 [クロスオーバー]
古きよきクロスオーバー・サウンドをリメイクするにあたっての好素材のこの曲。イントロ・ブリッジ部の2ndベースによるパラレル・モーションがいかにもクロスオーバーしています。王道路線ですな。
左近治はこの部分のバディ・ウィリアムスのドラム・フィルをDnB風にして、テーマ部はハウスっぽいアレンジにて制作中です。テーマ部のハットの8分裏打ちはもちろん909ハットで(笑)。我ながら超ベタなアレンジに溜め息(笑)。
原曲のベースは蚊とんぼマーカス君。いつものミドルレンジカットのスラップサウンドではなく、初期マーカス君によくあった音ですね(笑)。おそらくマーカス・ファンはこの音はあまり好きじゃないかもしれませんが、わたくし左近治は、この曲のバディ・ウィリアムスの音(ミックス)がドラムのコンプレッサーやゲートのかかり具合はバイブル的存在なのです。
アタックタイムの速い、かなり潰したコンプのスネアやタム類の音。ライドはちょっとアンビエンス切り過ぎだろーと思いつつも、スネアの音とミッドローのタムの音は秀逸!かなり勉強になる曲です。それにしてもバディ・ウィリアムスは本当にバーナード・パーディーのドラムに似ておりますな。
左近治の制作環境は99.8%ほどがMacで、DAWソフト上で使用するプラグインのほとんどはAudio Unitsプラグインです。VSTやRTASも変換していたりしますが、大体はAUです。
この曲で大活躍してくれたプラグインはdigitalfishphones.comからフリーでリリースされている「fish fillets」に含まれているゲートのプラグイン「Floor Fish」。
これが実に官能的で高機能なゲート。アンビエンスを抑えたい時、EQやコンプの前段では本当によく使います。特にドラムの音作りには欠かせない、左近治にとっては定番アイテムなのです。
コンプだけでこの手の音を作ろうとすると、掛かり過ぎて音がノッペリしてしまいがちです。どんな高音質なタイプでもかなり原音を損なうものですが、そこでコンプの前段でゲートを使うことによって、コンプの方は掛かり過ぎを回避させて音作りすることができるのですが、特にこのプラグインは重宝しています。
まあ、ベタなアレンジにしてしまうとはいえ原曲の良さがあるからこそ成立するようなものでして、この手の洗練された演奏(今となってはイナタい汗かき演奏であるものの)が現在の音楽シーンでは少々暑苦しいかもしれないんですが、本当にイナタい音と比べれば全然汗臭くないです。
今後リリース予定のクロスオーバー系のモノは
Second Degree / The Section
Mumps / Hatfield and the North
Doing the MeatballじゃなくてSecond Degreeをやるのがウチらしいかな、と。
もひとつはカンタベリー系の代名詞、Hatfield and the Northの2ndアルバムから。これもベタな選曲かなあ(笑)。クロスオーバーと呼んでいいのかどうかは別として。
左近治はこの部分のバディ・ウィリアムスのドラム・フィルをDnB風にして、テーマ部はハウスっぽいアレンジにて制作中です。テーマ部のハットの8分裏打ちはもちろん909ハットで(笑)。我ながら超ベタなアレンジに溜め息(笑)。
原曲のベースは蚊とんぼマーカス君。いつものミドルレンジカットのスラップサウンドではなく、初期マーカス君によくあった音ですね(笑)。おそらくマーカス・ファンはこの音はあまり好きじゃないかもしれませんが、わたくし左近治は、この曲のバディ・ウィリアムスの音(ミックス)がドラムのコンプレッサーやゲートのかかり具合はバイブル的存在なのです。
アタックタイムの速い、かなり潰したコンプのスネアやタム類の音。ライドはちょっとアンビエンス切り過ぎだろーと思いつつも、スネアの音とミッドローのタムの音は秀逸!かなり勉強になる曲です。それにしてもバディ・ウィリアムスは本当にバーナード・パーディーのドラムに似ておりますな。
左近治の制作環境は99.8%ほどがMacで、DAWソフト上で使用するプラグインのほとんどはAudio Unitsプラグインです。VSTやRTASも変換していたりしますが、大体はAUです。
この曲で大活躍してくれたプラグインはdigitalfishphones.comからフリーでリリースされている「fish fillets」に含まれているゲートのプラグイン「Floor Fish」。
これが実に官能的で高機能なゲート。アンビエンスを抑えたい時、EQやコンプの前段では本当によく使います。特にドラムの音作りには欠かせない、左近治にとっては定番アイテムなのです。
コンプだけでこの手の音を作ろうとすると、掛かり過ぎて音がノッペリしてしまいがちです。どんな高音質なタイプでもかなり原音を損なうものですが、そこでコンプの前段でゲートを使うことによって、コンプの方は掛かり過ぎを回避させて音作りすることができるのですが、特にこのプラグインは重宝しています。
まあ、ベタなアレンジにしてしまうとはいえ原曲の良さがあるからこそ成立するようなものでして、この手の洗練された演奏(今となってはイナタい汗かき演奏であるものの)が現在の音楽シーンでは少々暑苦しいかもしれないんですが、本当にイナタい音と比べれば全然汗臭くないです。
今後リリース予定のクロスオーバー系のモノは
Second Degree / The Section
Mumps / Hatfield and the North
Doing the MeatballじゃなくてSecond Degreeをやるのがウチらしいかな、と。
もひとつはカンタベリー系の代名詞、Hatfield and the Northの2ndアルバムから。これもベタな選曲かなあ(笑)。クロスオーバーと呼んでいいのかどうかは別として。
2006-08-28 13:29
「Groovin’ Song」Fuse One (David Matthews) 7月28日リリース [クロスオーバー]
さて、以前にもお知らせした通り、Fuse Oneの「Groovin’ Song」をあなくろ本舗の方でリリースします。
悟生楽横町の方では無料曲のみのリリースです。アトモスフィア系のパッド音を使ってきらびやかに演出してみましたので使ってみてください。悟生楽横町用のネタ曲選びが難航しているため(笑)、従来よりかは頻繁に無料曲を提供しようと思っております、ハイ。因みに、このアトモスフィア系のサウンドは15年くらい前の、PCMデジタルシンセでは初のポルタメントができるシンセの音を使っております。それは一体!?
厳密に言えばDX7もポルタメントはできます。ポリフォニックで。私の言いたいのはDX7以降のPCMシンセということです。
え~、答はRoland JD-800です。裏舞台の実際はJD-800のサンプルを使ってるんですが(笑)。まあ、別にそれだけではアレなんで一応工夫しています(笑)。
その頃のシンセだとSY99はAFM音源だけ使えばポルタメントは実現しました(モノ)が、ポリフォニック・ポルタメントとなると無理でした。まあ、JD-800/990でもモノのポルタメントが出来るくらいの記憶しかありません。SY99の良さは、鍵盤がキー・オフ・ベロシティに対応していたので、外部サンプラーとのベロシティスイッチの相性がすごく良かったのです。ちなみにJD-800もキー・オフ・ベロシティに対応しているので、こちらもサンプラーとの相性は良かったです。シンバルのミュートや弦楽器の離鍵時の音など重宝した鍵盤です。この2つのシンセは更にピッチベンドのレゾリューションが10ビット長(下位4ビット省略)という細かさも特徴でした。
MIDIイベントレベルだとピッチイベントは14ビット長ありますが、鍵盤自身が実際に14ビット長をまるまる処理することなど皆無に等しく(たぶんやったらDSPがパンクして音が止まらなくなったりすると思います)、実際には割愛して送っているんですね。
安物系だと8ビット長程度の荒いレゾリューションだったものがほとんどです。さらには鍵盤がオクターブ単位のブロックで取り付けられているため繊細なキータッチが実現できず(高価格帯の鍵盤は各鍵独立して取り外しが可能)、などとまあ色々あるわけですが、ピッチベンドの実際のレゾリューションというのは、上下に8000以上の段階が音には反映されていないのが現実なのです。あくまでもピッチベンドのコントローラーの送信情報のレゾリューションのことなので、外部のMIDIイベントでピッチベンド情報を受信するのはこの限りではないので誤解のないように。
回り道をしましたが、ポリフォニック・ポルタメントを最初に実現したのはRolandのJV-80/880ですね。PCM音源をポリフォニック・ポルタメントを可能にしたという、私の知る限りでは最初のシンセです。
いまやソフトウェア上で昔のシンセをエミュレートできる時代ですが、やはりハードウェアならではの音は捨て難いものでして、JD-800の地響きがするような低域の出力など、仮にソフトウェアでJDシリーズを実現しようにも、あの低域はソフトウェアでは敬遠されるかもしれませんね(笑)。JD出現以降は巷ではコルグの01/W一色でしたけど。あ、そうそう確かE-muのVintage Keysもポリフォニック・ポルタメント対応だったような気が・・・(もしかすると違うかも)。
一昔前のシンセ界の話などすると長くなりそうなので、またこーゆーのは別の日にでも!
悟生楽横町の方では無料曲のみのリリースです。アトモスフィア系のパッド音を使ってきらびやかに演出してみましたので使ってみてください。悟生楽横町用のネタ曲選びが難航しているため(笑)、従来よりかは頻繁に無料曲を提供しようと思っております、ハイ。因みに、このアトモスフィア系のサウンドは15年くらい前の、PCMデジタルシンセでは初のポルタメントができるシンセの音を使っております。それは一体!?
厳密に言えばDX7もポルタメントはできます。ポリフォニックで。私の言いたいのはDX7以降のPCMシンセということです。
え~、答はRoland JD-800です。裏舞台の実際はJD-800のサンプルを使ってるんですが(笑)。まあ、別にそれだけではアレなんで一応工夫しています(笑)。
その頃のシンセだとSY99はAFM音源だけ使えばポルタメントは実現しました(モノ)が、ポリフォニック・ポルタメントとなると無理でした。まあ、JD-800/990でもモノのポルタメントが出来るくらいの記憶しかありません。SY99の良さは、鍵盤がキー・オフ・ベロシティに対応していたので、外部サンプラーとのベロシティスイッチの相性がすごく良かったのです。ちなみにJD-800もキー・オフ・ベロシティに対応しているので、こちらもサンプラーとの相性は良かったです。シンバルのミュートや弦楽器の離鍵時の音など重宝した鍵盤です。この2つのシンセは更にピッチベンドのレゾリューションが10ビット長(下位4ビット省略)という細かさも特徴でした。
MIDIイベントレベルだとピッチイベントは14ビット長ありますが、鍵盤自身が実際に14ビット長をまるまる処理することなど皆無に等しく(たぶんやったらDSPがパンクして音が止まらなくなったりすると思います)、実際には割愛して送っているんですね。
安物系だと8ビット長程度の荒いレゾリューションだったものがほとんどです。さらには鍵盤がオクターブ単位のブロックで取り付けられているため繊細なキータッチが実現できず(高価格帯の鍵盤は各鍵独立して取り外しが可能)、などとまあ色々あるわけですが、ピッチベンドの実際のレゾリューションというのは、上下に8000以上の段階が音には反映されていないのが現実なのです。あくまでもピッチベンドのコントローラーの送信情報のレゾリューションのことなので、外部のMIDIイベントでピッチベンド情報を受信するのはこの限りではないので誤解のないように。
回り道をしましたが、ポリフォニック・ポルタメントを最初に実現したのはRolandのJV-80/880ですね。PCM音源をポリフォニック・ポルタメントを可能にしたという、私の知る限りでは最初のシンセです。
いまやソフトウェア上で昔のシンセをエミュレートできる時代ですが、やはりハードウェアならではの音は捨て難いものでして、JD-800の地響きがするような低域の出力など、仮にソフトウェアでJDシリーズを実現しようにも、あの低域はソフトウェアでは敬遠されるかもしれませんね(笑)。JD出現以降は巷ではコルグの01/W一色でしたけど。あ、そうそう確かE-muのVintage Keysもポリフォニック・ポルタメント対応だったような気が・・・(もしかすると違うかも)。
一昔前のシンセ界の話などすると長くなりそうなので、またこーゆーのは別の日にでも!
2006-08-05 03:02
「City Connection/エマニエル」 「Rocks/Arista All Stars」 [クロスオーバー]
さて、以前からお伝えしていたようにシティ・コネクションとアリスタ・オールスターズの「Rocks」のリリースです。
リリースまでに随分時間が経過しているのではないか!?と思われるでしょうが、リリースの3~4週間前には既に納めていますのでご容赦を(笑)。初期Kクリでは納めてから10日後くらいにはリリースできていた時期もあって時流に乗った制作もできたものですが、それがどんどん間が空くと時流を読むことすらも疲弊感に襲われてしまう・・・。もうトシですかねえ(笑)。
左近治は昨年椎間板ヘルニアの手術をしてカラダはもうボロボロ(笑)。梅雨が明けたら登山にでも行きたいものですが、今年の夏は釣りにしよーかなーなどと計画を立てております。
エマニエル坊やに関しては今後も色々と工夫を凝らしてリリースする予定ですのでお楽しみに。こういう飛び道具系の曲はやはり和みます(笑)。
そういえば最近、YMO関連が少ないので久々にYMO関連で今後制作する予定の曲はというと・・・
「Kid-Nap, the Dreamer」/高橋ユキヒロ
「今日、恋が」/高橋幸宏
「Dragoon」/坂本龍一
「Tokyo Joe」坂本龍一&渡辺香津美
「The Man in White」大村憲司
Tokyo Joeの方はまだミックスの詰めが甘いのでかなり遅れるかも(笑)。もしかしたらそのまま止めるかもしれません(笑)。ボコーダーの雰囲気を重点においてしまったという、偏った制作になってしまい現在頓挫中。進捗具合は85%と言ったところ。今年の3月中旬にはほぼ出来ていたのですがなんとなく保留中。
「Kid-Nap, the Dreamer」の方はオルタナ系やニューウェイヴリバイバル系な感じでリリースする予定です。Bare Naked Ladiesをリリースする予定なのでそれに合わせた形になるかも。
ただ、YMO関連はセニョール・ココナッツ(ウーヴェ・シュミット)のプレイズYMOにしてもいいかなあなどと思案中。あそこまでYMOを昇華できる才能には脱帽です。そうそう、最新号のサウンド&レコーディングでセニョール・ココナッツのインタビューがありましたのでとても嬉しい限りです。
リリースまでに随分時間が経過しているのではないか!?と思われるでしょうが、リリースの3~4週間前には既に納めていますのでご容赦を(笑)。初期Kクリでは納めてから10日後くらいにはリリースできていた時期もあって時流に乗った制作もできたものですが、それがどんどん間が空くと時流を読むことすらも疲弊感に襲われてしまう・・・。もうトシですかねえ(笑)。
左近治は昨年椎間板ヘルニアの手術をしてカラダはもうボロボロ(笑)。梅雨が明けたら登山にでも行きたいものですが、今年の夏は釣りにしよーかなーなどと計画を立てております。
エマニエル坊やに関しては今後も色々と工夫を凝らしてリリースする予定ですのでお楽しみに。こういう飛び道具系の曲はやはり和みます(笑)。
そういえば最近、YMO関連が少ないので久々にYMO関連で今後制作する予定の曲はというと・・・
「Kid-Nap, the Dreamer」/高橋ユキヒロ
「今日、恋が」/高橋幸宏
「Dragoon」/坂本龍一
「Tokyo Joe」坂本龍一&渡辺香津美
「The Man in White」大村憲司
Tokyo Joeの方はまだミックスの詰めが甘いのでかなり遅れるかも(笑)。もしかしたらそのまま止めるかもしれません(笑)。ボコーダーの雰囲気を重点においてしまったという、偏った制作になってしまい現在頓挫中。進捗具合は85%と言ったところ。今年の3月中旬にはほぼ出来ていたのですがなんとなく保留中。
「Kid-Nap, the Dreamer」の方はオルタナ系やニューウェイヴリバイバル系な感じでリリースする予定です。Bare Naked Ladiesをリリースする予定なのでそれに合わせた形になるかも。
ただ、YMO関連はセニョール・ココナッツ(ウーヴェ・シュミット)のプレイズYMOにしてもいいかなあなどと思案中。あそこまでYMOを昇華できる才能には脱帽です。そうそう、最新号のサウンド&レコーディングでセニョール・ココナッツのインタビューがありましたのでとても嬉しい限りです。
2006-08-05 03:02
TDKカセットテープ「AD」CMソング Double Steal / Fuse One [クロスオーバー]
YouTubeを色々徘徊して久しぶりにYMOの映像を見ようと検索してみたら、ありました(笑)。昔フジテレビで放送されたスペシャルライブ中継の映像が。直接リンクは避けたいと思いますが、タイトルは「YMO - LA satellite TV LIVE (6)」で引っ掛かります(笑)。
YouTubeにアップロードされている映像を開始して10秒ほどで、何と!昔のCMまで録画されているじゃありませんか!
そこで流れるCMが、当時のTDKカセット・テープのもの。それまでのTDKのCMと言えば、ビー・ジーズやスティーヴィー・ワンダーなど大御所ばかり。突如このCMだけそれまでと趣きが違って「おや!?」と感じたものですが、このCMの音楽は結構好きだった覚えがあります。それがFuse Oneの「Double Steal」という曲なのです。
主たるメンバーは
ウィル・リー
スタンリー・クラーク(テナー・ベースによるメロディパート)
ジェレミー・ウォール
などなど
当時はこのレコード即効ゲット!今でもCDを所有しているわけですが、このYouTubeでの映像、録画環境によるハムノイズが乗っているものの、アルバム・ミックスと音がかなり違うということに驚いたわけです。
アルバム・ミックスだとウィル・リーのプレシジョン・ベースの音がかなり中抜けになっていて引っ込んだ感じなのですが、このCMのミックスは、弦のダイナミクスがガッツンガッツン伝わってくる中低域の太さ!プレベの弦の暴れ加減が手に取るように伝わってきます。
いやあ、昔のCMは確かに規格一杯まで周波数レンジをフル活用して放送していたとはいえ、CMのミックスがこれだけ音が良かったとは・・・。このCMミックスを踏襲してアルバムをミックスして欲しかったと思うばかりです。良い曲ですしね。
とはいえ、Fuse Oneの記念すべき1stアルバムに収録されている私のイチ押しの曲は、この「Double Steal」ではなく、次の曲の「Friendship」なんですけどね。この曲のハーモニーといい、トニー・ウィリアムスとジョン・マクラフリンの演奏・・・。これだけで十分買いです。ジェフ・ベックの「Blow By Blow」が好きな(特に「Diamond Dust」とか)人にはオススメです。その次が「To Whom All You’ve Concern」はオススメです。
ともあれ、ウィル・リーのイナタい音が本来は健在であったとということを確認でき、アルバムミックスとCMミックスがこうも違うと、リマスターしてリリースしてほしいと思うばかり。山下達郎のRide on Timeでの伊藤広規によるゲージの太いジャズ・ベースの中低域をも思わせます。
YouTubeにアップロードされている映像を開始して10秒ほどで、何と!昔のCMまで録画されているじゃありませんか!
そこで流れるCMが、当時のTDKカセット・テープのもの。それまでのTDKのCMと言えば、ビー・ジーズやスティーヴィー・ワンダーなど大御所ばかり。突如このCMだけそれまでと趣きが違って「おや!?」と感じたものですが、このCMの音楽は結構好きだった覚えがあります。それがFuse Oneの「Double Steal」という曲なのです。
主たるメンバーは
ウィル・リー
スタンリー・クラーク(テナー・ベースによるメロディパート)
ジェレミー・ウォール
などなど
当時はこのレコード即効ゲット!今でもCDを所有しているわけですが、このYouTubeでの映像、録画環境によるハムノイズが乗っているものの、アルバム・ミックスと音がかなり違うということに驚いたわけです。
アルバム・ミックスだとウィル・リーのプレシジョン・ベースの音がかなり中抜けになっていて引っ込んだ感じなのですが、このCMのミックスは、弦のダイナミクスがガッツンガッツン伝わってくる中低域の太さ!プレベの弦の暴れ加減が手に取るように伝わってきます。
いやあ、昔のCMは確かに規格一杯まで周波数レンジをフル活用して放送していたとはいえ、CMのミックスがこれだけ音が良かったとは・・・。このCMミックスを踏襲してアルバムをミックスして欲しかったと思うばかりです。良い曲ですしね。
とはいえ、Fuse Oneの記念すべき1stアルバムに収録されている私のイチ押しの曲は、この「Double Steal」ではなく、次の曲の「Friendship」なんですけどね。この曲のハーモニーといい、トニー・ウィリアムスとジョン・マクラフリンの演奏・・・。これだけで十分買いです。ジェフ・ベックの「Blow By Blow」が好きな(特に「Diamond Dust」とか)人にはオススメです。その次が「To Whom All You’ve Concern」はオススメです。
ともあれ、ウィル・リーのイナタい音が本来は健在であったとということを確認でき、アルバムミックスとCMミックスがこうも違うと、リマスターしてリリースしてほしいと思うばかり。山下達郎のRide on Timeでの伊藤広規によるゲージの太いジャズ・ベースの中低域をも思わせます。
2006-08-05 02:59