アンダルシア進行およびスパイロ・ジャイラの「Foxtrot」について [楽理]
扨て、今回はアンダルシア進行について軽く触れ乍らスパイロ・ジャイラのアルバム『Carnaval』収録の「Foxtrot」でのトム・シューマンに依るキーボード・ソロ部分をYouTubeにて既に譜例動画を公開している事もあり、併せて解説して行く事に。
アンダルシア進行について詳述な説明は避けますが、基本的には「四度先」を見据えた「順次下行和音進行」というのが前提となる物です。順次下行が意味するのはスケール・ワイズ・ステップであり、過程では同度由来のステップを介在しない事も念頭に置く必要があります。つまるところ、ハ長調を基ととした時、「Ⅰ→♮Ⅶdim→♭Ⅶ△→♭Ⅵ△→Ⅴ」などという様な同度由来の和音を複数介在させない所に留意する必要があるという事です。
アンダルシア進行の場合、その「四度先」にドミナントを見る or トニックを見るという2つの種類に大別させる事ができますが、ドミナントを目指すのは調的であり、トニックを目指すのはプラガルな側面がある訳です。
そうして和音進行がスケール・ワイズに下行進行を採るのが前提であっても、愚直なまでにダイアトニックを遵守する必要はないのです。例えばハ長調を基に、
C△→B♭△→Am→G
という風に進んでも良い訳です。
同様に、今度はAマイナーを基とした時の下行スケール・ワイズ・ステップだと
Am→G△→F△→E
と進むという例もあるのです。
Aマイナー・キーを基とした時のアンダルシア進行ではない下行スケール・ワイズ・ステップで能くある類の進行としては
Am→F♯m7(♭5)→F♮△→E
という物ですが、これは短三度を介在しておりますし、同度由来の「F♯とF♮」をも介在させているのでアンダルシア進行としては括られません。
アンダルシア進行の最大の醍醐味は、サブドミナントから「四度先」であるトニックを目指す時の下行スケール・ワイズ・ステップなのであり、この際重要なのが「Ⅱ度」は「♭Ⅱ」に変じて使うのが最大の醍醐味である訳です。Cメジャーを基とした時は
F△→E♭△→D♭△→C
でも良いのであり、Cメジャーを音組織とする「F△」から端を発するも直後にノン・ダイアトニックの「E♭△」として変じつつ増二度を避けて(※Fからの後続にE♮を介在させてしまうとD♭という旨味のあるフリジアン・スーパートニックとして使用する際、過程にて [e - des] の増二度を生んでしまうという意)「D♭△」へと進行するという訳です。この時の「D♭」は、C音を基準としつつ原調の残り香をも配慮すると局所的には「Cフリジアン」に移旋する状況となります。こうした局所的乍らも「♭Ⅱ」を生じさせてフリジアンのⅡ度を仄めかすのをフリジアン・スーパートニックと呼ぶ訳です。「♭Ⅱ△7」もフリジアン・スーパートニックのコードなのです(上述のリンク先から少し進むとトム・シュネラー氏の論文のリンクもあるので併せてお読み下さい)。
同様に、Aマイナーの音組織に於てAマイナーでのサブドミナントから四度先である下行スケール・ワイズ・ステップ進行で採るとなると、
Dm(※Aドリアン想定ならばD△でも可)→C△→B♭△→Am(※ピカルディ終止と同様に長和音終止A△も可)
という風にフリギア終止の型を採るという事になります。
上述のアンダルシア進行の例はそれらが全てではありません。「四度先」を見据えての下行スケール・ワイズ・ステップとなれば多くの例が存在する事となり枚挙に遑がありません。メジャー・キーを母体としていようともトニックから「Ⅶ度」に順次下行するにしても多くの場合は「♮Ⅶ」ではなく移旋して下主音を採った「♭Ⅶ」に進む事もあり、それが更に♮Ⅵへと進むよりもⅤへの下行導音として作用する様にして「♭Ⅵ」へ進行する事の方が多い訳です。原調はメジャーであったにも拘らず。
原調からすればドミナントへ行く際に2回の移旋を経ている事となりますが、楽曲というのは原調の残り香を薫らせつつも実は多彩に移旋しているのが現状なのです。こうした適宜移旋を必要とする楽曲に対して楽曲を徹頭徹尾ひとつのモードで弾こうとするのは初学者に多いミスでありますが、「モード奏法」というのは適宜必要な移旋を伴わせて道を外れない様に対応する弾き方なのであるという事はあらためて留意して欲しい部分です。
こうしたプラガルなアンダルシア進行は、他の民族的な進行とも併せて多様な変化を見せる様になったのです。その大きな理由として、西洋音楽界隈では長らくフリギアの第7音がフィナリスに上行進行しようとする時のムシカ・フィクタを禁じておりました。つまりEフリジアンの「D♮」が「D♯」という上行導音を採る事を赦されなかったのです。Eフリジアンではフィナリスから上方五度に「H」音が存在するにも拘らず、それがドミナント感を誘引して「D♯」へのムシカ・フィクタへの欲求を誘わない様にする為に、フリギアのドミナントは第6音に置かれる訳です。つまりEフリジアンのドミナントは「C」なのです。こうして西洋音楽でのフリギアは制限されて来たのです。
つまり、フリギアの最大の特徴は [f→e] という下行導音の時に最大の威力を発揮する旋法であったので、非常に重用された訳です。下行導音で [f→e] という風に [e] に帰着した時、随伴する他声部で本来の [g] はピカルディ終止と同様に [gis] へのムシカ・フィクタは赦されたのであり、フリギアで最も頻出するムシカ・フィクタは第3音が半音上がるという物だったのです。
他方、西洋音楽以外ではギリシャ時代からフリギアはドリス旋法と呼ばれ別の発展をしていたのでありまして、アリストクセノスのハルモニア原論の様に多彩な微分音を纏い、地域によってはテトラコルドこそが全てでオクターヴを超越したりと非常に多岐に渡る発展を遂げていたのでありまして、これらがあらためて遭遇するのは18世紀にまで歴史を進める事になるのでしょうか。
そうしていつしかジプシー系統の音階(例えばハンガリアン・マイナー・スケールの第5音をフィナリスに採ったり)も入り込み、フィナリスを変えれば「♭Ⅱ」が生ずる新たなる音階が西洋音楽にも浸潤する様になったという訳です。
無論、西洋音楽界隈はそうした別個の世界観に全く気付いていなかったのではなく寧ろ「無視」していたのです。なぜなら「乞丐の雰囲気を漂わせる」として怪しからん音だとして遠ざけていたのが真相です。
今でこそハンガリアン・マイナー・スケール(※ジプシー・スケールとも)はポピュラーでありますが、フランツ・リストとバルトークの両者の取扱いではそれぞれ「フィナリス」と採る音が違うのは有名な話であります。
こうした変遷をあらためて勘案しつつ、本来ならば微分音的にも異なる様々な旋法が入り込んでくる訳でありまして、多くのそれらがアンダルシア進行の下行スケール・ワイズ・ステップから「解放」し、和音進行の発展として上行スケール・ワイズ・ステップにも多彩な変化が生じたのであります。
ですので、スパニッシュ進行を例に採れば「E△→F△」の循環進行もあれば「E△→F△→G△→F△」という上行&下行を循環進行させる様にも発展した訳でして、スパニッシュ・スケールの原型も亦、フリギア(フリジアン)にあるという訳であるのです。
同様に「フリジアン・ドミナント」と呼ばれる、嘗ては「ハーモニック・マイナー完全五度下」というスケールも、本来のハーモニック・マイナー・スケールの主音を欺き、異度となるⅤ度の音をフィナリス(モーダル・トニック)に措き、本来のトニックへとなかなか進まずに「♭ⅥとⅤ」の進行を循環させてトニックを背くそれは、スコーピオンズのウリ・ジョン・ロートやイングヴェイ・マルムスティーンのそれらしか知らない方でも斯様に例を挙げれば納得する典型例ではあるかと思います。
そうした「♭ⅥとⅤ」が実質的に「♭ⅡとⅠ」に聴こえる様にもなる為、スパニッシュのそれとも混用される例もあるという訳です。
機能和声的進行というのは通常、後続和音は先行和音の根音を自身の和音の上音へと取り込む事でカデンツという和音諸機能の起承転結を強化させる物です。例えばハ長調での「C→F」では先行のコードのルート [c] を後続の「F」の上音(※コードの第5音)に取り込んでおります。同様に「F→G7」ではサブドミナントである先行和音のルート [f] を後続のドミナント・コード「G7」が上音に取り込み、ドミナント・モーションを経てトニックの「C」へと解決する状況に於ても先行和音「G7」のルート [g] を後続の「C」が上音に取り込んでいるという事でカデンツは綺麗に体系付けられているのです。
これは対位法に伴う旋律形成と和声法が合致した妙味であります。対位法の線形づくりとして必要な事は、とりあえず線形の「極点」として一旦は「Ⅴ度」を目指して形成させる事が重要だからです。音響科学の黎明期であっても倍音を意識していたが故の事であるのは明白であります。その極点を旋律が目指すべき道標だとすると、和声の側が目指すそれは先行和音の根音を自身の極点として表す事で、「通って来た道はこう見えるのですよ」という異なる道しるべとして「補強」されているという訳です。
アンダルシア進行というのは、先行和音と後続和音の関係(音程)が近く、先行和音の上音への取り込みが遠い関係となる事で旋律に伴う和音が高次な和声感を生じやすくなり、先行和音上で鳴らされていた音が後続へそのまま繋留したとしても高次な和声感を演出する事にもなる為、和音進行としては順次スケール・ワイズ・ステップの下行形であるも、和音上での旋律形成が高次な響きに達しやすく、概して和音も複雑化させられる可能性を秘めているという事になるのです。
これらの件を勘案すれば、モーダルな方のアンダルシア進行は歴史的に見れば結構古い類になる物だと言える訳です。上行をさせずに《Ⅰと♭Ⅱとの循環した逡巡》これこそが、後述するスパイロ・ジャイラの「Foxtrot」もアンダルシア進行として括っているのは、こうした背景があるが故の含意なのです。
嘗て渡辺香津美のアルバム『TO CHI KA』収録「Unicorn」の譜例動画をYouTubeに挙げた所、それを「アンダルシア進行」と充てている事から、皮相的理解に及ぶ者からすればそれを到底「アンダルシア進行」とは認めたくはないのか、早々と「ダメね」を付けられた物でしたが、今回説明するアンダルシア進行の背景を理解こそしていれば、私のそれがアンダルシア進行からの発展形なのだという事がお判りだと思うのですが、深部を見抜いてもらえないのは実にもどかしい物でもあります。
では本題に移りましょう。スパイロ・ジャイラの「Foxtrot」であります。プログレの方のスパイロジャイラ(中黒《なかぐろ》表記なし)は 'Spirogyra' というスペルであるのですが、フュージョンの方となるとバンド名を付ける際のスペルミスが発端となって 'Spyro Gyra' となった事で、カタカナ表記の際は中黒表記ともなるのが特徴でもあります。
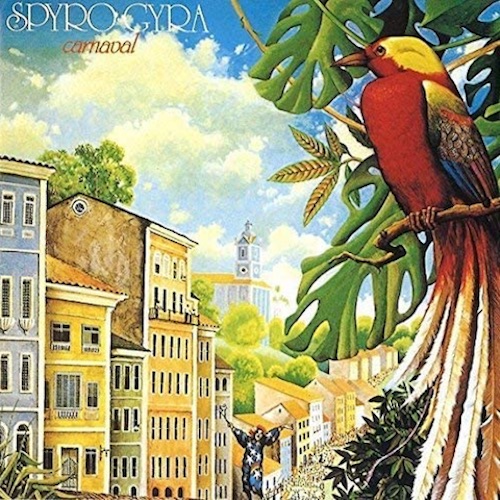
抑もフォックストロットというのは4拍子の楽曲を示す音楽用語ですが、トロットという言葉もまた馬術に由来する言葉であります。それが狐の闊歩というダブル・ミーニングを採っている可能性もありますが、音楽用語で知られるフォックストロットという意味に照らし合わせた場合本曲は若干テンポが遅めだとは思います。
まあそんな事は扨措き、本曲の拔萃部分はトム・シューマンに依るキーボード・ソロ部分となります。譜例動画にて 'Duophonic synth' と記しているのは、それがおそらくAPRオデッセイではなかろうか!? という私の個人的推察に依る物です。譜例動画に用いているソフト・シンセはKORGのARPオデッセイであります。
正直な所、ARPオデッセイらしい音を作るには少なくとも私にはKORGのそれよりも、NI Reaktor用アンサンブルの方が良い位なのですが、今回敢えてKORGの方を使ったのは押下式ピッチ・ベンド用ボタンに依る微妙な音高変化幅を想起するに当たって実機を正確に表している方が使いやすかろうという単純な目論見に依る物です。
ご存知の様にARPオデッセイのRev.2以降のモデルでは押下型のピッチ・ベンド・ボタンの他に狭い37鍵盤をフルに使える様にオクターヴ切り替えのトランスポーズ・スイッチが装備されております。それを用いると瞬時に同一鍵盤箇所を2オクターヴ増減させる事が可能となる訳です。
これは例えば、ソロを採っている最中に物理的な鍵盤位置にある最低音として「C3」を弾いていたとしましょう。それよりも低い音を奏でたい場合、オクターヴ切り替えを低くさせれば瞬時に「C3」は「C1」となる訳です。即ち運指からすれば「B2」を発音させたい場合は、1オクターヴ+長七度上の音を弾く様になるという訳です。
譜例動画抜粋部のキーボード・ソロの途中に於て32分音符&32分5連符という速いパッセージに於て同度進行(同じ音高が連続する)が頻発するプレイの私の推測は、APRオデッセイのオクターヴ切り替えで運指を2オクターヴ違いで同度進行を実現させているのではなく、左手をサポートさせて弾いているのであろうという物であります。これについて後ほど縷述します。
尚、譜例動画に振ってある小節番号は楽曲冒頭からの正確な小節数ではなく、キーボード・ソロに入るアウフタクト部とした不完全小節(※この不完全小節は物理的に原曲では生じていない便宜的な措置)を除いた後続の小節からカウントした物ですのでご注意下さい。
アウフタクト部でのシンセの [c] に 'Mod wheel' と記しておりますが、以降は 'M.W.' と略記されるのでご注意下さい。加えて、先ず注目してもらいたいのは調号なのでありますが、変種記号4つの調号であるので一応はヘ短調を基準に措いております。とはいえ、本曲では徹頭徹尾ヘ短調で表される物ではなく、終盤や終止和音では変ロ長調(=B♭)へ転調するという解釈が適切であります。
また、キーボード・ソロ部分はヘ短調の調号で表さざるを得ないだけに過ぎず、当該部分はヘ短調の音組織に於ける「♭Ⅵ△→Ⅴ7」の循環であるものの決してフリジアン・ドミナントのそれとは異なります。
そもそもフリジアン・ドミナントという呼称はハーモニック・マイナー・スケールのⅤ度をフィナリスに採ったモードの事を指し示すという狭い状況であるため、本曲の「♭Ⅵ△→Ⅴ7」をフリジアン・ドミナントとは呼びません。
仮にもそうした呼び方が本曲に適用できたとしても(言葉の上で)、多くの人々は却って混乱を招きかねない物となる事でありましょう。フリジアン・ドミナントという呼称はポピュラー音楽界隈でしか通用しない事であり、名称そのものはフリジアンがⅤ度に現れる状況でⅤ度を根音とする和音の第3音が半音高く変ずるという理解にあるとしても、先述の通りフリギア旋法の歴史は長らく上行導音を形成するムシカ・フィクタを許されなかったのであり、フリギアのⅥ度がドミナントとして置かれる事で上行導音を制限されていたのですから、フリジアンのⅤ度上の和音の第3音が上行導音を採る為にムシカ・フィクタとして半音高く変じているという状況は長い歴史にも背いた表現であるのです。
本来であればフリジアン・ドミナントという語句そのものが関係各所に配慮の行き届いていない語句として注意して取り扱われる呼称である筈ですが、「五度下にハーモニック・マイナー・スケールがありますよ」と言いたい言葉が「ハーモニック・マイナー完全五度下」という風に、英語をそのまま訳してしまった事で本意が伝わりにくい状況は、英語のそのままでの呼び方でも本国の人は「変な表現だなあ」と思い乍ら市民権を獲得できなかったが故の「フリジアン・ドミナント」という呼称であろうとは十分に推察し得る物ではあります。
という訳で話を戻しますが、本曲は決してFハーモニック・マイナーの音組織を利用している状況ではない「♭Ⅵ△→Ⅴ7」ので注意していただきたい点であります。そもそも、Fハーモニック・マイナーを前提としたとしても、「D♭△9」の九度音=「E♭」が生ずる以上はハーモニック・マイナーにならない事はすぐに気付く事でありましょう。
D♭△9およびソロ後半で四和音化する時のD♭△7でのモードはD♭リディアンであり、C9および後半の四和音化するC7では長属九を明示するのでFメジャーでのFミクソリディアンを想起してインプロヴァイズを執り行うというのが本曲のソロの流れです。
ではトム・シューマンのソロ2小節目3拍目に注目してもらう事にしましょう。器楽的素養が浅い方の場合、茲を平滑な16分音符に依る4音 [e - d - c - c] と知覚してしまいがちですが、実際には譜例通り32分音符が拍頭に来る逆付点の音形であるのです。こうした音形はバロック以降の西洋音楽界隈の短前打音としての装飾音の技法を高いレベルで身に付けている表れとなる独特の音形です。
ジャズをはじめポピュラー音楽の殆どのプレイヤーの前打音は、担当楽器のそれは無関係に西洋音楽界隈での前打音の採り方が明らかに違います。拍頭や拍の強勢に前打音が示される場合のジャズおよびポピュラー音楽界隈の殆どは、拍頭(強勢)より前のめりに前打音が現れ後続の実音が拍頭に来るのが殆どです。
他方西洋音楽の前打音の採り方というのは、前打音である装飾音が拍頭(強勢)にあり、実音が強勢を背いて遅れて奏されるのです。
西洋音楽界隈からポピュラー音楽界隈の装飾音のそれを比較して照らし合わせた場合、実際には「後打音」と称した方が良いかもしれませんが、西洋音楽界隈での「後打音」という呼び方も実に狭い範囲での決まり事であり、大抵の楽典や理論書でも省かれる事が多いです。しかも後打音は、上拍&弱勢に現れるのが適切な表現としての後打音なのです。ですので、ポピュラー音楽界隈の多くの装飾音のケースを後打音と総称する事は出来ず「前のめり」と称した方が配慮された言葉になるのです。
斯様な装飾音の実際がお判りいただけたかと思いますが、先の32分音符から始まる逆付点の型をポピュラー音楽での譜例で遭遇する事は相当レアなケースでありましょうし、採譜者(出版社)の側は西洋音楽的解釈での装飾音として記譜していたとしても、ポピュラー音楽界隈で瀰漫する装飾音の採り方を奏者が優先してしまえば、前のめりの演奏として聴かれてしまうという訳です。
そうした「両義的」な解釈が生じてしまう以上、装飾音を付記するのではなくプレイの実際に則った記譜をした方が注意喚起も含めての配慮された記譜になるだろうと思ったので私は今回逆付点の型を書いたのであります。
4小節目2拍目弱勢で生ずる5連符は [3:2] パルス構造のものであり、少々ずんぐりとしたリズムになる物です。
5小節目4拍目では8分の強勢と弱勢との連行の分割前後で同度進行が見られます。まあ普通の運指でこれを親指→人差し指→中指でのサイクルで出来る人は相当高度なテクニックを有しているであろうと思いますが、このテンポなら出来なくもないという人もまた居られるかと思います。唯、私の見解としては先述の通りこれはARPオデッセイのトランスポーズ・スイッチに依る切り替えが齎す物ではなく左手サポートに依る同度進行であろうかと思います。
37鍵あるARPオデッセイですが、この同度進行 [C3] が奏されている物理的な鍵盤位置をAPRオデッセイの左から数えて2番目のC鍵(最低音から数えて1オクターヴ上のC鍵)だと仮定します。同小節4拍目8分裏から奏される5連符の拍頭 [c] からの [c - g - c - g] の4音は左手サポートに依るプレイだと思われます。
そのまま左手のサポートは6小節目1拍目拍頭の [c] まで継続し、5連符の残りの4音 [c - g - c - e] が右手に移るフレージングだと私は解釈しております。この同度進行が生ずる「C4」の演奏レンジは、直後の8分裏拍頭でトランスポーズ・スイッチを上げた場合、弾いていたC鍵は直後に「C6」となります。8分裏拍頭で生ずる「G5」は実際の物理的な運指は「C3」が「C5」へとオクターヴ切り替えで上げた後に、四度下に下がって演奏しているという訳です。
そうして運指の実際は1オクターヴ下の鍵盤であるAPRオデッセイの物理的に一番左端にあるC鍵を「左手」を添えて弾く事で達成する事が出来ます。
加えて、同小節1拍目8分裏からの先行音 [e] から10度音程跳躍での4音 [g - c - c - g] は右手で弾くも、8分裏拍頭の [g=G5] の所でオクターヴ切り替えを「上げ」て2オクターヴ上げます。運指は物理的には下がって「G5」を弾く訳ですが、直後に現れる [c] の同度進行の部分は左手サポートに頼らずに右手で弾ききっている物と思われます。その理由は、この同度進行で左手サポートを使ってしまうと同小節2拍目で生ずるピッチ・ベンドの為の圧力検知型のボタンを押下する必要が生ずる為、ここでの運指に左手サポートをしてしまうとピッチ・ベンド・ボタンの操作が不可能となるからです。
そうして6小節目2拍目で生じている微分音はC音より75セント高い7単位八分音となるに等しいピッチ・ベンドのボタンを押下している事によって生じた微分音でありますが、これは偶然生じた微分音ではなく、きちんと制御されて出された微分音であろうと思います。
この6小節目でのベース・パートでのウィル・リーのフレージングは特に際立って素晴らしいインタープレイを繰り広げております。「C9」上で13th [a] と9th音 [d] を強調させたフレージングとしており、4拍目でルート [c] に復帰しつつ循環の [des] へと上行導音を採るという、直前までは9th音 [d] を強調していたにも拘らずにこのクロマティシズム溢れたフレージングには畏れ入るばかりです。
8小節目2拍目から3拍目拍頭に生じているスラーで表されるピッチ・ベンドでの [f - ges] ですが、この「C9」上の [ges] は決してオルタード・テンションの「♯11th」と同一視してはいけない音です。なぜなら、直前の [f] はアヴォイド・ノートであるにせよ直後の [ges] への上行導音を態々採っており、[ges] は「C9」上でのブルー五度として振る舞う音であるからです。そういう背景から「C9」上では四度由来のオルタード・テンションなのではなく五度由来とする音として解釈しなくてはならないのです。
加えて、8小節目3拍目・4拍目では [dis - e] というスラーで括られたピッチ・ベンドが2箇所現れます。[dis] は「♯9th」相当のオルタード・テンションではあるも、バックのコードは長属九として「♮9th」を和声的に使っている状況である為、同度由来の音が和声的に並存する事は避けられるべき(※複調はその誹りを受けない)シーンです。ですが、短い音価のフレーズとして聴かせており且つそれが [e] への上行導音という振る舞いであるからこそ許容される「美しい」和音外音の使い方となる訳です。
尚、8小節目でのウィル・リーの弾く連続する16分音符のパッセージはメゾスタッカートで奏される必要のある音です。16分音符という抑も短い音価でメゾスタッカートとは一体!? と疑問を抱かれる方も居られるかもしれませんが、ウィル・リーは左手のミュートを使ってこうした表現を頻繁に行うプレーヤーなのであります。
例えば、一連のパッセージに於て左手の人差し指の押弦だけでポジションを上げ下げさせていると考えてみましょう。[c・b・h・c] は総じて左手人差し指でG弦を押弦するという事になります。その際、左手の空いた指──特に中指・薬指──の腹で軽く弦を触れてミュートさせるというテクニックです。おそらく指が太目の方ではないと押弦した位置の近傍をミュートさせるにも弦負けしそうな程なので、そこそこの圧と面積を以てしてミュートしないとなかなか実現しづらく、人差し指の押弦とミュート加減が釣られてしまいそうになり力の配分加減はかなり難しいテクニックです。しかし、それをスンナリとやるのがウィル・リーの素晴らしさであり、同小節3〜4拍目にかけてのA弦 [c] の16分音符の同様のミュートに依るメゾスタッカートであります。
9小節目からのコード進行は四和音と変化するのも注意が必要です。また、茲からウィル・リーはG&E弦(1・4弦)を用いたダブル・ストップをプレイしますが、ダブル・ストップ前の [d] はA弦であり、ダブル・ストップ時の [d] はE弦であるという所も注意が必要です。
10小節目2拍目でのシンセの微分音を示す箇所は、[e] より25セントつまり1単位八分音低く採るピッチ・ベンドの操作が必要となる箇所です。
11小節目2拍目のシンセ・ソロの5連符は [2:3] のパルス比の物で、半拍5連である所も注意が必要な箇所となるダブル・クロマティック下行フレーズです。加えて、同小節4拍目最後の [fis] は後続拍頭の [g] に対する経過音ではある物の、コード上では「♮Ⅳ→♯Ⅳ」という風に、D♭リディアンならばそのまま [f - g] と進めば良いものを、[g] への上行導音として [fis] を挟み込むのは優れたフレージングであろうかと思います。[g] への上行導音である事から [g] 由来の [ges] ではなく異度由来となるので [fis] なのであります。
12小節目3拍目のシンセ・ソロ部で生ずる六分音は [b] より33セント高い(※正位位置である [h] からは67セント低い)事を示す微分音で、こちらも単なるイントネーション的揺さぶりとは異なる微小音程を狙った音である事は明白です。
14小節目4拍目での2ndギター・パートの1オクターヴ高い [c] は、後打音としての装飾音符で表しても良かったのですが、明示的に実音としました。ツッコミ気味にボトルネックに依るスライドを利かせているという訳です。
私がこれまで譜例動画で明示的に後打音を使ったのは、U・Kの「Nevermore」イントロ部のホールズワースに依るプレイの時位でしょうか。高速パッセージに入る時の音が前のめりで突っ込んで入って来るので、それを短前打音とは表記するのは許せなかったのです。そうした前のめりが此処でも表れているという訳です。「Nevermore」の譜例動画に関しては次の埋め込み当該箇所で確認出来ます(※譜例動画冒頭より4小節目4拍目の最後に置かれる [a -f] 2音の複後打音)。
そうして15〜16小節目でのシンセ・ソロは32分音符のパッセージが再度現れ、16小節目1拍目では同度進行があります。茲は左手サポートではなく右手の運指に依る物であろうと思われます。
16小節目3拍目でのベース・パートにはフォルテピアノが付されているのがお判りかと思いますが、この直後の音を弱めて欲しいのであり、その後はアクセントを付けてトゥッティという訳です。トランペット(in B♭)とアルトサックス(in E♭)は共に移調譜ですのでご注意下さい。
私は本曲のギターのパーソネルをかねてよりジョン・トロペイとハイラム・ブロックの2人だと今猶信じて已みません。色んなパーソネルを見る限りではジョン・トロペイばかりで重ね録りなのかと思わんばかりなのですが。まあボヤキとして留めておいて下さい(笑)。
アンダルシア進行について詳述な説明は避けますが、基本的には「四度先」を見据えた「順次下行和音進行」というのが前提となる物です。順次下行が意味するのはスケール・ワイズ・ステップであり、過程では同度由来のステップを介在しない事も念頭に置く必要があります。つまるところ、ハ長調を基ととした時、「Ⅰ→♮Ⅶdim→♭Ⅶ△→♭Ⅵ△→Ⅴ」などという様な同度由来の和音を複数介在させない所に留意する必要があるという事です。
アンダルシア進行の場合、その「四度先」にドミナントを見る or トニックを見るという2つの種類に大別させる事ができますが、ドミナントを目指すのは調的であり、トニックを目指すのはプラガルな側面がある訳です。
そうして和音進行がスケール・ワイズに下行進行を採るのが前提であっても、愚直なまでにダイアトニックを遵守する必要はないのです。例えばハ長調を基に、
C△→B♭△→Am→G
という風に進んでも良い訳です。
同様に、今度はAマイナーを基とした時の下行スケール・ワイズ・ステップだと
Am→G△→F△→E
と進むという例もあるのです。
Aマイナー・キーを基とした時のアンダルシア進行ではない下行スケール・ワイズ・ステップで能くある類の進行としては
Am→F♯m7(♭5)→F♮△→E
という物ですが、これは短三度を介在しておりますし、同度由来の「F♯とF♮」をも介在させているのでアンダルシア進行としては括られません。
アンダルシア進行の最大の醍醐味は、サブドミナントから「四度先」であるトニックを目指す時の下行スケール・ワイズ・ステップなのであり、この際重要なのが「Ⅱ度」は「♭Ⅱ」に変じて使うのが最大の醍醐味である訳です。Cメジャーを基とした時は
F△→E♭△→D♭△→C
でも良いのであり、Cメジャーを音組織とする「F△」から端を発するも直後にノン・ダイアトニックの「E♭△」として変じつつ増二度を避けて(※Fからの後続にE♮を介在させてしまうとD♭という旨味のあるフリジアン・スーパートニックとして使用する際、過程にて [e - des] の増二度を生んでしまうという意)「D♭△」へと進行するという訳です。この時の「D♭」は、C音を基準としつつ原調の残り香をも配慮すると局所的には「Cフリジアン」に移旋する状況となります。こうした局所的乍らも「♭Ⅱ」を生じさせてフリジアンのⅡ度を仄めかすのをフリジアン・スーパートニックと呼ぶ訳です。「♭Ⅱ△7」もフリジアン・スーパートニックのコードなのです(上述のリンク先から少し進むとトム・シュネラー氏の論文のリンクもあるので併せてお読み下さい)。
同様に、Aマイナーの音組織に於てAマイナーでのサブドミナントから四度先である下行スケール・ワイズ・ステップ進行で採るとなると、
Dm(※Aドリアン想定ならばD△でも可)→C△→B♭△→Am(※ピカルディ終止と同様に長和音終止A△も可)
という風にフリギア終止の型を採るという事になります。
上述のアンダルシア進行の例はそれらが全てではありません。「四度先」を見据えての下行スケール・ワイズ・ステップとなれば多くの例が存在する事となり枚挙に遑がありません。メジャー・キーを母体としていようともトニックから「Ⅶ度」に順次下行するにしても多くの場合は「♮Ⅶ」ではなく移旋して下主音を採った「♭Ⅶ」に進む事もあり、それが更に♮Ⅵへと進むよりもⅤへの下行導音として作用する様にして「♭Ⅵ」へ進行する事の方が多い訳です。原調はメジャーであったにも拘らず。
原調からすればドミナントへ行く際に2回の移旋を経ている事となりますが、楽曲というのは原調の残り香を薫らせつつも実は多彩に移旋しているのが現状なのです。こうした適宜移旋を必要とする楽曲に対して楽曲を徹頭徹尾ひとつのモードで弾こうとするのは初学者に多いミスでありますが、「モード奏法」というのは適宜必要な移旋を伴わせて道を外れない様に対応する弾き方なのであるという事はあらためて留意して欲しい部分です。
こうしたプラガルなアンダルシア進行は、他の民族的な進行とも併せて多様な変化を見せる様になったのです。その大きな理由として、西洋音楽界隈では長らくフリギアの第7音がフィナリスに上行進行しようとする時のムシカ・フィクタを禁じておりました。つまりEフリジアンの「D♮」が「D♯」という上行導音を採る事を赦されなかったのです。Eフリジアンではフィナリスから上方五度に「H」音が存在するにも拘らず、それがドミナント感を誘引して「D♯」へのムシカ・フィクタへの欲求を誘わない様にする為に、フリギアのドミナントは第6音に置かれる訳です。つまりEフリジアンのドミナントは「C」なのです。こうして西洋音楽でのフリギアは制限されて来たのです。
つまり、フリギアの最大の特徴は [f→e] という下行導音の時に最大の威力を発揮する旋法であったので、非常に重用された訳です。下行導音で [f→e] という風に [e] に帰着した時、随伴する他声部で本来の [g] はピカルディ終止と同様に [gis] へのムシカ・フィクタは赦されたのであり、フリギアで最も頻出するムシカ・フィクタは第3音が半音上がるという物だったのです。
他方、西洋音楽以外ではギリシャ時代からフリギアはドリス旋法と呼ばれ別の発展をしていたのでありまして、アリストクセノスのハルモニア原論の様に多彩な微分音を纏い、地域によってはテトラコルドこそが全てでオクターヴを超越したりと非常に多岐に渡る発展を遂げていたのでありまして、これらがあらためて遭遇するのは18世紀にまで歴史を進める事になるのでしょうか。
そうしていつしかジプシー系統の音階(例えばハンガリアン・マイナー・スケールの第5音をフィナリスに採ったり)も入り込み、フィナリスを変えれば「♭Ⅱ」が生ずる新たなる音階が西洋音楽にも浸潤する様になったという訳です。
無論、西洋音楽界隈はそうした別個の世界観に全く気付いていなかったのではなく寧ろ「無視」していたのです。なぜなら「乞丐の雰囲気を漂わせる」として怪しからん音だとして遠ざけていたのが真相です。
今でこそハンガリアン・マイナー・スケール(※ジプシー・スケールとも)はポピュラーでありますが、フランツ・リストとバルトークの両者の取扱いではそれぞれ「フィナリス」と採る音が違うのは有名な話であります。
こうした変遷をあらためて勘案しつつ、本来ならば微分音的にも異なる様々な旋法が入り込んでくる訳でありまして、多くのそれらがアンダルシア進行の下行スケール・ワイズ・ステップから「解放」し、和音進行の発展として上行スケール・ワイズ・ステップにも多彩な変化が生じたのであります。
ですので、スパニッシュ進行を例に採れば「E△→F△」の循環進行もあれば「E△→F△→G△→F△」という上行&下行を循環進行させる様にも発展した訳でして、スパニッシュ・スケールの原型も亦、フリギア(フリジアン)にあるという訳であるのです。
同様に「フリジアン・ドミナント」と呼ばれる、嘗ては「ハーモニック・マイナー完全五度下」というスケールも、本来のハーモニック・マイナー・スケールの主音を欺き、異度となるⅤ度の音をフィナリス(モーダル・トニック)に措き、本来のトニックへとなかなか進まずに「♭ⅥとⅤ」の進行を循環させてトニックを背くそれは、スコーピオンズのウリ・ジョン・ロートやイングヴェイ・マルムスティーンのそれらしか知らない方でも斯様に例を挙げれば納得する典型例ではあるかと思います。
そうした「♭ⅥとⅤ」が実質的に「♭ⅡとⅠ」に聴こえる様にもなる為、スパニッシュのそれとも混用される例もあるという訳です。
機能和声的進行というのは通常、後続和音は先行和音の根音を自身の和音の上音へと取り込む事でカデンツという和音諸機能の起承転結を強化させる物です。例えばハ長調での「C→F」では先行のコードのルート [c] を後続の「F」の上音(※コードの第5音)に取り込んでおります。同様に「F→G7」ではサブドミナントである先行和音のルート [f] を後続のドミナント・コード「G7」が上音に取り込み、ドミナント・モーションを経てトニックの「C」へと解決する状況に於ても先行和音「G7」のルート [g] を後続の「C」が上音に取り込んでいるという事でカデンツは綺麗に体系付けられているのです。
これは対位法に伴う旋律形成と和声法が合致した妙味であります。対位法の線形づくりとして必要な事は、とりあえず線形の「極点」として一旦は「Ⅴ度」を目指して形成させる事が重要だからです。音響科学の黎明期であっても倍音を意識していたが故の事であるのは明白であります。その極点を旋律が目指すべき道標だとすると、和声の側が目指すそれは先行和音の根音を自身の極点として表す事で、「通って来た道はこう見えるのですよ」という異なる道しるべとして「補強」されているという訳です。
アンダルシア進行というのは、先行和音と後続和音の関係(音程)が近く、先行和音の上音への取り込みが遠い関係となる事で旋律に伴う和音が高次な和声感を生じやすくなり、先行和音上で鳴らされていた音が後続へそのまま繋留したとしても高次な和声感を演出する事にもなる為、和音進行としては順次スケール・ワイズ・ステップの下行形であるも、和音上での旋律形成が高次な響きに達しやすく、概して和音も複雑化させられる可能性を秘めているという事になるのです。
これらの件を勘案すれば、モーダルな方のアンダルシア進行は歴史的に見れば結構古い類になる物だと言える訳です。上行をさせずに《Ⅰと♭Ⅱとの循環した逡巡》これこそが、後述するスパイロ・ジャイラの「Foxtrot」もアンダルシア進行として括っているのは、こうした背景があるが故の含意なのです。
嘗て渡辺香津美のアルバム『TO CHI KA』収録「Unicorn」の譜例動画をYouTubeに挙げた所、それを「アンダルシア進行」と充てている事から、皮相的理解に及ぶ者からすればそれを到底「アンダルシア進行」とは認めたくはないのか、早々と「ダメね」を付けられた物でしたが、今回説明するアンダルシア進行の背景を理解こそしていれば、私のそれがアンダルシア進行からの発展形なのだという事がお判りだと思うのですが、深部を見抜いてもらえないのは実にもどかしい物でもあります。
では本題に移りましょう。スパイロ・ジャイラの「Foxtrot」であります。プログレの方のスパイロジャイラ(中黒《なかぐろ》表記なし)は 'Spirogyra' というスペルであるのですが、フュージョンの方となるとバンド名を付ける際のスペルミスが発端となって 'Spyro Gyra' となった事で、カタカナ表記の際は中黒表記ともなるのが特徴でもあります。
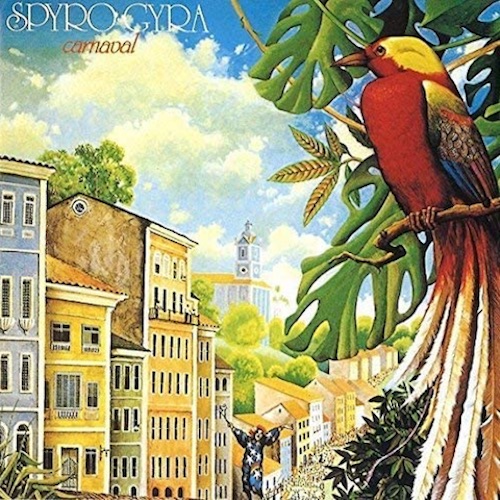
抑もフォックストロットというのは4拍子の楽曲を示す音楽用語ですが、トロットという言葉もまた馬術に由来する言葉であります。それが狐の闊歩というダブル・ミーニングを採っている可能性もありますが、音楽用語で知られるフォックストロットという意味に照らし合わせた場合本曲は若干テンポが遅めだとは思います。
まあそんな事は扨措き、本曲の拔萃部分はトム・シューマンに依るキーボード・ソロ部分となります。譜例動画にて 'Duophonic synth' と記しているのは、それがおそらくAPRオデッセイではなかろうか!? という私の個人的推察に依る物です。譜例動画に用いているソフト・シンセはKORGのARPオデッセイであります。
正直な所、ARPオデッセイらしい音を作るには少なくとも私にはKORGのそれよりも、NI Reaktor用アンサンブルの方が良い位なのですが、今回敢えてKORGの方を使ったのは押下式ピッチ・ベンド用ボタンに依る微妙な音高変化幅を想起するに当たって実機を正確に表している方が使いやすかろうという単純な目論見に依る物です。
ご存知の様にARPオデッセイのRev.2以降のモデルでは押下型のピッチ・ベンド・ボタンの他に狭い37鍵盤をフルに使える様にオクターヴ切り替えのトランスポーズ・スイッチが装備されております。それを用いると瞬時に同一鍵盤箇所を2オクターヴ増減させる事が可能となる訳です。
これは例えば、ソロを採っている最中に物理的な鍵盤位置にある最低音として「C3」を弾いていたとしましょう。それよりも低い音を奏でたい場合、オクターヴ切り替えを低くさせれば瞬時に「C3」は「C1」となる訳です。即ち運指からすれば「B2」を発音させたい場合は、1オクターヴ+長七度上の音を弾く様になるという訳です。
譜例動画抜粋部のキーボード・ソロの途中に於て32分音符&32分5連符という速いパッセージに於て同度進行(同じ音高が連続する)が頻発するプレイの私の推測は、APRオデッセイのオクターヴ切り替えで運指を2オクターヴ違いで同度進行を実現させているのではなく、左手をサポートさせて弾いているのであろうという物であります。これについて後ほど縷述します。
尚、譜例動画に振ってある小節番号は楽曲冒頭からの正確な小節数ではなく、キーボード・ソロに入るアウフタクト部とした不完全小節(※この不完全小節は物理的に原曲では生じていない便宜的な措置)を除いた後続の小節からカウントした物ですのでご注意下さい。
アウフタクト部でのシンセの [c] に 'Mod wheel' と記しておりますが、以降は 'M.W.' と略記されるのでご注意下さい。加えて、先ず注目してもらいたいのは調号なのでありますが、変種記号4つの調号であるので一応はヘ短調を基準に措いております。とはいえ、本曲では徹頭徹尾ヘ短調で表される物ではなく、終盤や終止和音では変ロ長調(=B♭)へ転調するという解釈が適切であります。
また、キーボード・ソロ部分はヘ短調の調号で表さざるを得ないだけに過ぎず、当該部分はヘ短調の音組織に於ける「♭Ⅵ△→Ⅴ7」の循環であるものの決してフリジアン・ドミナントのそれとは異なります。
そもそもフリジアン・ドミナントという呼称はハーモニック・マイナー・スケールのⅤ度をフィナリスに採ったモードの事を指し示すという狭い状況であるため、本曲の「♭Ⅵ△→Ⅴ7」をフリジアン・ドミナントとは呼びません。
仮にもそうした呼び方が本曲に適用できたとしても(言葉の上で)、多くの人々は却って混乱を招きかねない物となる事でありましょう。フリジアン・ドミナントという呼称はポピュラー音楽界隈でしか通用しない事であり、名称そのものはフリジアンがⅤ度に現れる状況でⅤ度を根音とする和音の第3音が半音高く変ずるという理解にあるとしても、先述の通りフリギア旋法の歴史は長らく上行導音を形成するムシカ・フィクタを許されなかったのであり、フリギアのⅥ度がドミナントとして置かれる事で上行導音を制限されていたのですから、フリジアンのⅤ度上の和音の第3音が上行導音を採る為にムシカ・フィクタとして半音高く変じているという状況は長い歴史にも背いた表現であるのです。
本来であればフリジアン・ドミナントという語句そのものが関係各所に配慮の行き届いていない語句として注意して取り扱われる呼称である筈ですが、「五度下にハーモニック・マイナー・スケールがありますよ」と言いたい言葉が「ハーモニック・マイナー完全五度下」という風に、英語をそのまま訳してしまった事で本意が伝わりにくい状況は、英語のそのままでの呼び方でも本国の人は「変な表現だなあ」と思い乍ら市民権を獲得できなかったが故の「フリジアン・ドミナント」という呼称であろうとは十分に推察し得る物ではあります。
という訳で話を戻しますが、本曲は決してFハーモニック・マイナーの音組織を利用している状況ではない「♭Ⅵ△→Ⅴ7」ので注意していただきたい点であります。そもそも、Fハーモニック・マイナーを前提としたとしても、「D♭△9」の九度音=「E♭」が生ずる以上はハーモニック・マイナーにならない事はすぐに気付く事でありましょう。
D♭△9およびソロ後半で四和音化する時のD♭△7でのモードはD♭リディアンであり、C9および後半の四和音化するC7では長属九を明示するのでFメジャーでのFミクソリディアンを想起してインプロヴァイズを執り行うというのが本曲のソロの流れです。
ではトム・シューマンのソロ2小節目3拍目に注目してもらう事にしましょう。器楽的素養が浅い方の場合、茲を平滑な16分音符に依る4音 [e - d - c - c] と知覚してしまいがちですが、実際には譜例通り32分音符が拍頭に来る逆付点の音形であるのです。こうした音形はバロック以降の西洋音楽界隈の短前打音としての装飾音の技法を高いレベルで身に付けている表れとなる独特の音形です。
ジャズをはじめポピュラー音楽の殆どのプレイヤーの前打音は、担当楽器のそれは無関係に西洋音楽界隈での前打音の採り方が明らかに違います。拍頭や拍の強勢に前打音が示される場合のジャズおよびポピュラー音楽界隈の殆どは、拍頭(強勢)より前のめりに前打音が現れ後続の実音が拍頭に来るのが殆どです。
他方西洋音楽の前打音の採り方というのは、前打音である装飾音が拍頭(強勢)にあり、実音が強勢を背いて遅れて奏されるのです。
西洋音楽界隈からポピュラー音楽界隈の装飾音のそれを比較して照らし合わせた場合、実際には「後打音」と称した方が良いかもしれませんが、西洋音楽界隈での「後打音」という呼び方も実に狭い範囲での決まり事であり、大抵の楽典や理論書でも省かれる事が多いです。しかも後打音は、上拍&弱勢に現れるのが適切な表現としての後打音なのです。ですので、ポピュラー音楽界隈の多くの装飾音のケースを後打音と総称する事は出来ず「前のめり」と称した方が配慮された言葉になるのです。
斯様な装飾音の実際がお判りいただけたかと思いますが、先の32分音符から始まる逆付点の型をポピュラー音楽での譜例で遭遇する事は相当レアなケースでありましょうし、採譜者(出版社)の側は西洋音楽的解釈での装飾音として記譜していたとしても、ポピュラー音楽界隈で瀰漫する装飾音の採り方を奏者が優先してしまえば、前のめりの演奏として聴かれてしまうという訳です。
そうした「両義的」な解釈が生じてしまう以上、装飾音を付記するのではなくプレイの実際に則った記譜をした方が注意喚起も含めての配慮された記譜になるだろうと思ったので私は今回逆付点の型を書いたのであります。
4小節目2拍目弱勢で生ずる5連符は [3:2] パルス構造のものであり、少々ずんぐりとしたリズムになる物です。
5小節目4拍目では8分の強勢と弱勢との連行の分割前後で同度進行が見られます。まあ普通の運指でこれを親指→人差し指→中指でのサイクルで出来る人は相当高度なテクニックを有しているであろうと思いますが、このテンポなら出来なくもないという人もまた居られるかと思います。唯、私の見解としては先述の通りこれはARPオデッセイのトランスポーズ・スイッチに依る切り替えが齎す物ではなく左手サポートに依る同度進行であろうかと思います。
37鍵あるARPオデッセイですが、この同度進行 [C3] が奏されている物理的な鍵盤位置をAPRオデッセイの左から数えて2番目のC鍵(最低音から数えて1オクターヴ上のC鍵)だと仮定します。同小節4拍目8分裏から奏される5連符の拍頭 [c] からの [c - g - c - g] の4音は左手サポートに依るプレイだと思われます。
そのまま左手のサポートは6小節目1拍目拍頭の [c] まで継続し、5連符の残りの4音 [c - g - c - e] が右手に移るフレージングだと私は解釈しております。この同度進行が生ずる「C4」の演奏レンジは、直後の8分裏拍頭でトランスポーズ・スイッチを上げた場合、弾いていたC鍵は直後に「C6」となります。8分裏拍頭で生ずる「G5」は実際の物理的な運指は「C3」が「C5」へとオクターヴ切り替えで上げた後に、四度下に下がって演奏しているという訳です。
そうして運指の実際は1オクターヴ下の鍵盤であるAPRオデッセイの物理的に一番左端にあるC鍵を「左手」を添えて弾く事で達成する事が出来ます。
加えて、同小節1拍目8分裏からの先行音 [e] から10度音程跳躍での4音 [g - c - c - g] は右手で弾くも、8分裏拍頭の [g=G5] の所でオクターヴ切り替えを「上げ」て2オクターヴ上げます。運指は物理的には下がって「G5」を弾く訳ですが、直後に現れる [c] の同度進行の部分は左手サポートに頼らずに右手で弾ききっている物と思われます。その理由は、この同度進行で左手サポートを使ってしまうと同小節2拍目で生ずるピッチ・ベンドの為の圧力検知型のボタンを押下する必要が生ずる為、ここでの運指に左手サポートをしてしまうとピッチ・ベンド・ボタンの操作が不可能となるからです。
そうして6小節目2拍目で生じている微分音はC音より75セント高い7単位八分音となるに等しいピッチ・ベンドのボタンを押下している事によって生じた微分音でありますが、これは偶然生じた微分音ではなく、きちんと制御されて出された微分音であろうと思います。
この6小節目でのベース・パートでのウィル・リーのフレージングは特に際立って素晴らしいインタープレイを繰り広げております。「C9」上で13th [a] と9th音 [d] を強調させたフレージングとしており、4拍目でルート [c] に復帰しつつ循環の [des] へと上行導音を採るという、直前までは9th音 [d] を強調していたにも拘らずにこのクロマティシズム溢れたフレージングには畏れ入るばかりです。
8小節目2拍目から3拍目拍頭に生じているスラーで表されるピッチ・ベンドでの [f - ges] ですが、この「C9」上の [ges] は決してオルタード・テンションの「♯11th」と同一視してはいけない音です。なぜなら、直前の [f] はアヴォイド・ノートであるにせよ直後の [ges] への上行導音を態々採っており、[ges] は「C9」上でのブルー五度として振る舞う音であるからです。そういう背景から「C9」上では四度由来のオルタード・テンションなのではなく五度由来とする音として解釈しなくてはならないのです。
加えて、8小節目3拍目・4拍目では [dis - e] というスラーで括られたピッチ・ベンドが2箇所現れます。[dis] は「♯9th」相当のオルタード・テンションではあるも、バックのコードは長属九として「♮9th」を和声的に使っている状況である為、同度由来の音が和声的に並存する事は避けられるべき(※複調はその誹りを受けない)シーンです。ですが、短い音価のフレーズとして聴かせており且つそれが [e] への上行導音という振る舞いであるからこそ許容される「美しい」和音外音の使い方となる訳です。
尚、8小節目でのウィル・リーの弾く連続する16分音符のパッセージはメゾスタッカートで奏される必要のある音です。16分音符という抑も短い音価でメゾスタッカートとは一体!? と疑問を抱かれる方も居られるかもしれませんが、ウィル・リーは左手のミュートを使ってこうした表現を頻繁に行うプレーヤーなのであります。
例えば、一連のパッセージに於て左手の人差し指の押弦だけでポジションを上げ下げさせていると考えてみましょう。[c・b・h・c] は総じて左手人差し指でG弦を押弦するという事になります。その際、左手の空いた指──特に中指・薬指──の腹で軽く弦を触れてミュートさせるというテクニックです。おそらく指が太目の方ではないと押弦した位置の近傍をミュートさせるにも弦負けしそうな程なので、そこそこの圧と面積を以てしてミュートしないとなかなか実現しづらく、人差し指の押弦とミュート加減が釣られてしまいそうになり力の配分加減はかなり難しいテクニックです。しかし、それをスンナリとやるのがウィル・リーの素晴らしさであり、同小節3〜4拍目にかけてのA弦 [c] の16分音符の同様のミュートに依るメゾスタッカートであります。
9小節目からのコード進行は四和音と変化するのも注意が必要です。また、茲からウィル・リーはG&E弦(1・4弦)を用いたダブル・ストップをプレイしますが、ダブル・ストップ前の [d] はA弦であり、ダブル・ストップ時の [d] はE弦であるという所も注意が必要です。
10小節目2拍目でのシンセの微分音を示す箇所は、[e] より25セントつまり1単位八分音低く採るピッチ・ベンドの操作が必要となる箇所です。
11小節目2拍目のシンセ・ソロの5連符は [2:3] のパルス比の物で、半拍5連である所も注意が必要な箇所となるダブル・クロマティック下行フレーズです。加えて、同小節4拍目最後の [fis] は後続拍頭の [g] に対する経過音ではある物の、コード上では「♮Ⅳ→♯Ⅳ」という風に、D♭リディアンならばそのまま [f - g] と進めば良いものを、[g] への上行導音として [fis] を挟み込むのは優れたフレージングであろうかと思います。[g] への上行導音である事から [g] 由来の [ges] ではなく異度由来となるので [fis] なのであります。
12小節目3拍目のシンセ・ソロ部で生ずる六分音は [b] より33セント高い(※正位位置である [h] からは67セント低い)事を示す微分音で、こちらも単なるイントネーション的揺さぶりとは異なる微小音程を狙った音である事は明白です。
14小節目4拍目での2ndギター・パートの1オクターヴ高い [c] は、後打音としての装飾音符で表しても良かったのですが、明示的に実音としました。ツッコミ気味にボトルネックに依るスライドを利かせているという訳です。
私がこれまで譜例動画で明示的に後打音を使ったのは、U・Kの「Nevermore」イントロ部のホールズワースに依るプレイの時位でしょうか。高速パッセージに入る時の音が前のめりで突っ込んで入って来るので、それを短前打音とは表記するのは許せなかったのです。そうした前のめりが此処でも表れているという訳です。「Nevermore」の譜例動画に関しては次の埋め込み当該箇所で確認出来ます(※譜例動画冒頭より4小節目4拍目の最後に置かれる [a -f] 2音の複後打音)。
そうして15〜16小節目でのシンセ・ソロは32分音符のパッセージが再度現れ、16小節目1拍目では同度進行があります。茲は左手サポートではなく右手の運指に依る物であろうと思われます。
16小節目3拍目でのベース・パートにはフォルテピアノが付されているのがお判りかと思いますが、この直後の音を弱めて欲しいのであり、その後はアクセントを付けてトゥッティという訳です。トランペット(in B♭)とアルトサックス(in E♭)は共に移調譜ですのでご注意下さい。
私は本曲のギターのパーソネルをかねてよりジョン・トロペイとハイラム・ブロックの2人だと今猶信じて已みません。色んなパーソネルを見る限りではジョン・トロペイばかりで重ね録りなのかと思わんばかりなのですが。まあボヤキとして留めておいて下さい(笑)。



