Polish Radio Experimental Studio (PRES) [書評]
先日、ドイツでの音楽関連著作物を物色していると Kehrer verlag から2019年に刊行された『Ultra Sounds The Sonic Art of Polish Radio Experimental Studio (by David Crowly)』が目に留まり、瞬時に興奮を抑えきれない私が居たものでありました。
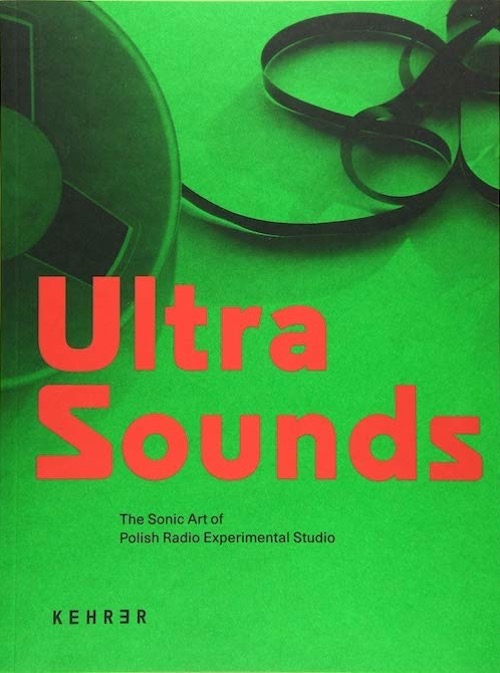
ドイツの刊行物であるも英訳というのは私としては聊か嬉しいもので、なにより普段触れる外国語は比較的英語の方が多い事もあり独語よりかは読みやすい。私が子供の頃の医師と言えばカルテを独語の手書きで書くというのが平常の光景でありましたが独語に触れる機会というのは私にとっては音楽関連の文献に当たる事以外では少ない物です。とはいえ私の英語スキルなど褒められる物では到底ないのでありますが、いくらか他の言語よりかは比較的理解しやすい方であるので浅学菲才な私からすれば非常に有難いものです。
遅ればせ乍ら発刊から1年ほど経過している物の購入を急ぎとりあえず日本国内のアマゾンで確認してみると、定価€39.90である筈がなんと日本円で税込700円を切っているではありませんか(※現在は1300円台の値を付けている様ですが、それでも安い)!!
Ultra Sounds
https://vimeo.com/332170973
https://twitter.com/theQuietus/status/1154020911701483527?s=20
ポーランド国営ラジオ放送実験スタジオ(以下PRES)の情報を審らかにしている顕著なサイトのひとつに、意外な所ではありますがDAWソフトでもおなじみの ableton のサイトで確認する事ができます。
現代音楽が最先端の科学や知識を援用して作り上げるのは今猶当然の事であるとして、更に重要な事は旧来の体系の異化(dissimilation)という所も非常に重要な側面でもあります。そういう意味からも PRES を知るというのは第二次大戦後の現代音楽シーンには切っても切り離すことの出来ない重要な存在である訳ですが、こうした重要な機関は他に代表的な物としてドイツに於けるケルン派の研究・活動を知るのは必須項目でもある程です。
超が付く程の名著であるプリーベルク著『電気技術時代の音楽』は、日本語訳者である入野義朗に依る著者をも超越する詳悉な脚注に圧倒される物でもありますが、例えばシュトックハウゼンが音程比 [1:5] という純正長二十四度(単音程への転回・還元とすれば純正長三度)の25等分律を用いて『習作Ⅱ』を作ったのも、そこには聴覚として捉える臨界帯域(聴覚フィルター)と結合差音および可聴帯域に由来する物でもあり、この背景には音響心理学からの援用があっての事で、それがケルン派の大きな役割だったのであります。
臨界帯域に伴う聴覚の特性としては、一般的に人間が知覚しやすい数百ヘルツ〜1kHz近傍での「協和音程」を低域にシフトしても「協和」感が喪失していってしまうという物です。例えば「完全五度」音程などは低域でそれを弾いた所で、音のエネルギーとしての飽和量が増加するだけで協和感は上方の帯域で聴く完全五度よりも明澄度は弱まり濁って聴こえるという訳です。倍音を含まないサイン波での完全五度を通常の帯域ではなく低域で弾けば、協和感としての明澄度が低域では混濁している感じは直ぐに掴める事でしょう。
こうした原因は、有毛細胞が可聴帯域に伴ってエキスポネンシャルに分布しているのではなく、どの帯域を知覚する部分であろうと細胞の分布がある程度の束となって一様に同じ整列となっている事(聴覚フィルターと呼ぶ)で、低域では僅かな物理的振動数の差を持った音程であろうとも、その振動数の差=1Hzという周波数の差は低域側と高域側では全く違い、低域側では大きな音程差となります(※1000Hzと1001Hzの音程比は僅か1.7セントでその差はスキスマよりも狭いにも拘らず、40Hzと41Hzでは42.7セントにも拡大してしまう大きな差となる)。
聴覚フィルターのひとつの束は音程を捉える事よりも振動数に呼応している為、低域になればなるほど複合音および和音で生じている音程を明確に捉えていた筈の音程感とは異なった印象として捉える事となり、何某かの音程の姿としての音程の「近傍」を聴き乍ら知覚しようとしているからです。
そうした状況をどうにか上手く喩える事ができないものかと私自身忸怩たる思いを抱いてしまいますが、人間が知覚しやすい帯域での音程の状況を「目が良く見える」状況だとするならば、低域側にシフト(移高)させただけの音程であるにも拘らず、その音程は《どんなに目をこすってもぼやけてしまう》という風に音程を捉えてしまう状況と喩える事が出来るかと思います。
こうした状況は低域側にシフトした途端に突然変わるのではなく、人間が知覚しやすい帯域でも微妙にその音程を捉える聴覚フィルターの捉え方というのは変化しており、知覚に作用しているのです。
例えばある曲を単純にヴォイシングもそのままに半音上あるいは下に移高(トランスポーズ)させたら元と丸っ切り情感が違って聴こえる(=単に移高させただけとは異なる印象)を抱いてしまうのも聴覚フィルタの影響のせいでもあるのです。ですので、ヴォイシングもそのままに、移高させた状況を元の状況と全く同一と捉えてしまうのは、知覚に無理強いしているか or 全く無頓着で居られるかのどちらかでしかないのです。
ですので、複合音および和音となれば協和感を逸してしまうという訳です。協和感は複数の聴覚フィルター同士から作られる組み合わせを脳が覚えるという事になります。
そうした背景から完全五度と同じ様に完全八度の協和感も変わりますし、協和音程よりも次点の協和となる「不完全協和音程」(※長・短の三度/六度など)や「不協和音程」が低域にシフトされればどういう風に響くかと言えば、更に不協和感が増大するのは推して知るべしであります。

下限可聴周波数を20Hzとした時、20Hzと100Hzの振動比は1:5であります。100Hzと500Hzも同様に1:5となります。100Hzと500Hzの周波数をフィルターバンクとして捉えて25等分すると、その帯域幅は20Hzとなります。20Hzから100Hzの帯域を25等分すればフィルターバンクは3.2Hz毎に存在する事になります。無論、これらのフィルターバンクは周波数毎にみれば違う帯域幅ではあるものの、音律の世界から見れば5^(1/25)という事になり、純正長二十四度25等分平均律となる訳です。
オクターヴという概念を捨て去らない限り、100Hzに対して80Hzという振動数を類推しかねませんが、仮にそこで80Hzが生じても差音は20Hzに思弁的に生ずる筈でありますが、実際の5^(1/25)という単位微分音は80Hzではなくその近傍を採るので、差音が従前の協和感を避けつつ「別の協和感」を形成するという意味合いが、ケルン派の研究の背景にある訳です。そうした所にも『習作Ⅱ』は端を発しており、その後の音響図案化と「行為譜」と呼ばれる図形楽譜の構想化に拍車をかける物となり、PRESでの実験もケルン派の実証が影響を与え、後年の電子的な実験を重ねていく事となる訳です。
関連ブログ記事
https://tawauwagotsakonosamu.blog.ss-blog.jp/2014-04-18
第一次世界大戦前から音楽界はゲーテの『色彩論』ミレニアム期に豊かな学識が一般社会にも敷衍される様になり、『色彩論』の新たなる社会通念の勃興に前後して音律の醸成(=等分平均律化)が強固な牽引力となると共に、ヘルムホルツの音響心理学の側面など他の分野や科学の影響を多大に受ける事となり、強固な機能和声社会はもはや無調の世界へ邁進する事を止める事は難しかったであろうと思いますが、歴史的にも名を遺す数学界の偉人が音楽理論にも論文を著して来たものの数学界の悪癖なのかエゴなのか。音楽理論の解を一義的にまとめようとするきらいがあった事はいうまでもありません。
現今社会にも残るその悪しき解釈のひとつが、上方倍音列には完全音程たる下属音が存在しないという大前提には触れずに調性を一義的に取り扱う為にプレドミナントとしてドミナントとしての位置付けを甘受させる様にしつつ、古代ギリシャでは2種類の属音(上属音と下属音)で2つの相貌で音楽を形成したにも関わらずオクターヴの同一性と単音程への転回還元という組織的な効率化を伴わせ、いつしか上方倍音列の世界で一義的な方向を向いてしまった不文律を数学者たちは何の疑念もなく土台としてしまったのは反省すべき点でありましょう。
然し乍らその厳然たる一義的な姿勢もまた、機能和声社会に於ける調性への厳格な姿勢を貫いて音楽感を形成したのも事実。こうした貢献の後に調性が崩壊するのは至極当然の成り行きだった事でしょう。
リップス/マイヤーの法則でも知られるマックス・フリードリヒ・マイヤーの場合はもはや上方倍音列という相貌は、近傍の音が知覚を丸め込めるという風に解釈したのか(※機能和声社会でのプレドミナントは勿論その後のサブドミナントいう「和音機能」は軽んじられていたという背景に伴う)第21次倍音を下属音とみなす(※勿論、第21次倍音は完全音程ではない)のは非常に興味深い所であります。
斯様な音響心理学方面からの新たなる援用が、次なる音楽の為の新たな材料となるのも是亦至極当然な流れなのでありますが、いかんせん一般的な音楽の捉え方(知覚としての)というのは保守的なもので、保守的な聴き方をする人々からすればシュトックハウゼンの『習作Ⅱ』など500年先ほど進んだ音楽に相当する位に突き抜けた物かもしれません。とはいえ19世紀までは古典的でいびつな不等分音律の世界観が残っていたのですから、現今社会の十二等分平均律に均された(≒慣らされた)人々は、あらためて不等分音律やら他の音律に注力せねばならぬほどに現今の音楽はあらためて多様な変化が求められる歴史の変遷期であるのかもしれません。
音響心理学など多くの実験的な研究はケルン派のみならず世界の其処彼処で進んだ訳ですが、西洋音楽界に於て社会主義時代のポーランドに於けるPRESの存在も社会思想を超えて音楽界に貢献して来たという訳です。
『Ultra Sounds』で特徴的なのは、和書に例えればB5変版サイズでの336ページという物なので、『コード理論大全』に極めて近いサイズと思っていただければ良いでしょう。この大きさであるので内容もかなり充実した物となっておりまして、4色カラーの図版も非常に多く、図形楽譜の多さも驚くばかり。
嘗てはこうした図形楽譜を学ぶには、エルハルト・カルコシュカ著 入野義朗訳『現代音楽の記譜』やヴァルター・ギーゼラー著 佐野光司訳『20世紀の作曲』を当たるしか無かったもので、これら2冊の図書はいずれも高価であり、特に4色カラーで触れる事が可能な『20世紀音楽』でのリゲティの図形楽譜などは今猶その譜面に興奮してしまう物ですが、これらの2冊にも掲載されていないレアな図形楽譜が数多く載せられて1300円台で入手できるというのは驚きを禁じ得ません。和訳すれば間違いなく1万円に近い値を付けて発売される事でしょう。
余談ではありますが、YMOが解散(※彼等は散開と呼んだ)時のコンサートおよび解散記念に発表した映画『PROPAGANDA』公開にて販売されていた刊行物『Chaos』のハードカバー装丁は、先のカルコシュカ著『現代音楽の記譜』(全音楽譜出版社刊)のそれを模したサイズとデザインであるのは明白な物です。こうしたアイデアはおそらく坂本龍一に依るものではないかと推察されます。
日本の場合は敗戦国であるため戦時加算が適用される事で、比較的新しい所の楽譜は図形楽譜と雖も著作権が有効となる事で値を釣り上げてしまう理由のひとつとなる訳ですが、それにしても安い。無論、楽理的な論述は少ないのですが、それでも矢張り、実験スタジオの詳細な記録として読むだけでも充分な価値を具備しているので興味のある方は是非とも手にとってお読みいただきたいと思います。
オイゲニウス・ルードニクの写真に当たれるのもあらためて驚かされるばかりで、象徴的な写真をあらためて載せておきたい所です。

他にもルッフ・ムジチュニ(Ruch Muzyczny)、ユゼフ・パトコフスキらをはじめ、『広島の犠牲者に捧げる哀歌』でも知られ、その丰貌(ふうぼう)は仲代達矢にも似るペンデレツキ、クシシュトフ・スリフィルスキ、ボグスワフ・シェッフェルなど枚挙に遑(いとま)がありません。
特に、ペンデレツキの『広島の犠牲者に捧げる哀歌』の告知ポスターをカラー図版で確認できるのはあらためて驚いたもので、私自身今回初めて知る事が出来ました。四分音クラスターが音楽的な蛍光色の様な印象すら抱くそれが、化学的な象徴として放射線を表しているのは歴然ですが、音楽的な蛍光色な印象とは裏腹に、赤を基調としたそのポスターには多くの示唆を感じた物です。
扨て図形譜の譜面(ふづら)は、一般的な五線譜と比しても記譜法として共通する体系化とまでは至っていないので多くの方策があるものの、一定以上の音楽的素養があれば譜面が示す「何某か」の訴えは読み手の音楽的素養をより一層喚起させる物であり、そこには多くの楽譜が示す定量的な拍節よりも、万人が抱く時間のイメージの図示と、それに随伴する行動の量的な変化を直観的に示される事が重視されているのはは言うまでもありません。
そうした図形楽譜が一般的な記譜法の方法論を超越しているとは雖も多くの場合は舞踊楽譜をヒントにした現代への異化なのでもあり、舞踊楽譜となると是亦途端に目に触れにくい分野でもありますが、一般的な記譜法で示されない「パラメータ」が示されている事自体が音楽的素養を擽って呉れる物でもあり、音楽演奏の為に必要且つ一般的な記譜法で明示されない「要素」即ちパラメータとしての音楽表現への欲求の高まりが図形楽譜を導いたりするのであります。
言葉を文字に表すにしても、それは「整列」させる事が不文律となっている物でありますが、「行間表記法」という手法(※この表記法は言語学から援用され音声学にて用いる手法で音楽的な関わりは比較的浅くなります)を用いて特定の言葉の僅かなイントネーションの差異(音高の変化)を表現する為に、文字の揃えを上下にずらしたり、発話する音の音量の増減を文字の大きさで以て変化させたりするだけでも、一般的な文字揃えの体系とは異なる「パラメータ」により、アクセントやイントネーションの変化が理解できる物になるでしょう。
図形楽譜というのもこうした所を援用し乍ら時には音響という側面から時間と音高を方眼紙の様に見立てて音声信号をスペクトログラフ化させたりする物です。
舞踊楽譜そのものはバロック時代から既に存在しており、言語のイントネーションの正確さ表現するにあたって音楽を援用して言語の記譜法として発表したのがジョシュア・スティールの表記法で、これがベートーヴェン誕生9年後の1779年という訳ですから、20世紀音楽が形成して来た当時の現代音楽が総じて今猶新しいという物では全く無く、単に一般的に広く知られていない事をあらためて掘り下げて古き体系を知る必要があろうかと思う事頻りです。
斯様なパラメータで音楽を「読む」事は、演奏の具象化が従前の記譜法にはどういうパラメータが不要で、どういうパラメータが直観的に作用する事が得策であるのか!? という多くの試みを、多くのカラーの図版だけでも十分に伝えて呉れる物であり、第二次大戦後の音楽がいかにして科学的にも直結しながらメディアという資本力によって科学の力で新たな牽引力を得ていたのかが能く判ります。
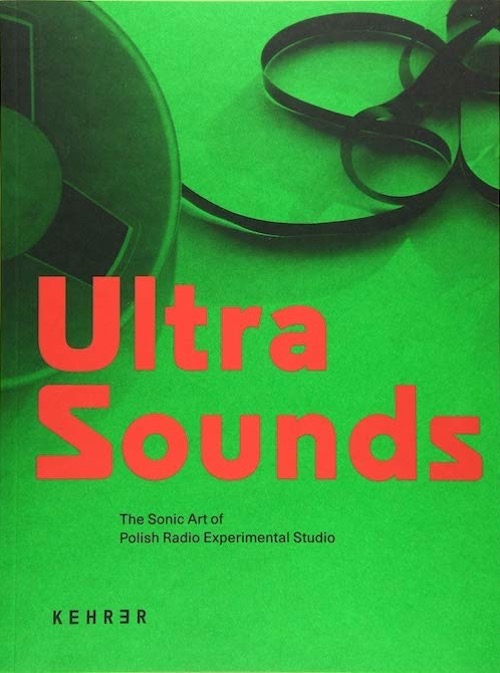
ドイツの刊行物であるも英訳というのは私としては聊か嬉しいもので、なにより普段触れる外国語は比較的英語の方が多い事もあり独語よりかは読みやすい。私が子供の頃の医師と言えばカルテを独語の手書きで書くというのが平常の光景でありましたが独語に触れる機会というのは私にとっては音楽関連の文献に当たる事以外では少ない物です。とはいえ私の英語スキルなど褒められる物では到底ないのでありますが、いくらか他の言語よりかは比較的理解しやすい方であるので浅学菲才な私からすれば非常に有難いものです。
遅ればせ乍ら発刊から1年ほど経過している物の購入を急ぎとりあえず日本国内のアマゾンで確認してみると、定価€39.90である筈がなんと日本円で税込700円を切っているではありませんか(※現在は1300円台の値を付けている様ですが、それでも安い)!!
Ultra Sounds
https://vimeo.com/332170973
https://t.co/YJMU3oqtaE pic.twitter.com/wOEusawVvK
— The Quietus (@theQuietus) July 21, 2019
https://twitter.com/theQuietus/status/1154020911701483527?s=20
'ULTRA SOUNDS:
— Culture.pl (@culture_pl) August 21, 2019
https://t.co/eOEuJceFTr@zkmkarlsruhe @calvertjournal @BBC6Music @SFTEWpodcast pic.twitter.com/DkyzExeiIM
ポーランド国営ラジオ放送実験スタジオ(以下PRES)の情報を審らかにしている顕著なサイトのひとつに、意外な所ではありますがDAWソフトでもおなじみの ableton のサイトで確認する事ができます。
現代音楽が最先端の科学や知識を援用して作り上げるのは今猶当然の事であるとして、更に重要な事は旧来の体系の異化(dissimilation)という所も非常に重要な側面でもあります。そういう意味からも PRES を知るというのは第二次大戦後の現代音楽シーンには切っても切り離すことの出来ない重要な存在である訳ですが、こうした重要な機関は他に代表的な物としてドイツに於けるケルン派の研究・活動を知るのは必須項目でもある程です。
超が付く程の名著であるプリーベルク著『電気技術時代の音楽』は、日本語訳者である入野義朗に依る著者をも超越する詳悉な脚注に圧倒される物でもありますが、例えばシュトックハウゼンが音程比 [1:5] という純正長二十四度(単音程への転回・還元とすれば純正長三度)の25等分律を用いて『習作Ⅱ』を作ったのも、そこには聴覚として捉える臨界帯域(聴覚フィルター)と結合差音および可聴帯域に由来する物でもあり、この背景には音響心理学からの援用があっての事で、それがケルン派の大きな役割だったのであります。
臨界帯域に伴う聴覚の特性としては、一般的に人間が知覚しやすい数百ヘルツ〜1kHz近傍での「協和音程」を低域にシフトしても「協和」感が喪失していってしまうという物です。例えば「完全五度」音程などは低域でそれを弾いた所で、音のエネルギーとしての飽和量が増加するだけで協和感は上方の帯域で聴く完全五度よりも明澄度は弱まり濁って聴こえるという訳です。倍音を含まないサイン波での完全五度を通常の帯域ではなく低域で弾けば、協和感としての明澄度が低域では混濁している感じは直ぐに掴める事でしょう。
こうした原因は、有毛細胞が可聴帯域に伴ってエキスポネンシャルに分布しているのではなく、どの帯域を知覚する部分であろうと細胞の分布がある程度の束となって一様に同じ整列となっている事(聴覚フィルターと呼ぶ)で、低域では僅かな物理的振動数の差を持った音程であろうとも、その振動数の差=1Hzという周波数の差は低域側と高域側では全く違い、低域側では大きな音程差となります(※1000Hzと1001Hzの音程比は僅か1.7セントでその差はスキスマよりも狭いにも拘らず、40Hzと41Hzでは42.7セントにも拡大してしまう大きな差となる)。
聴覚フィルターのひとつの束は音程を捉える事よりも振動数に呼応している為、低域になればなるほど複合音および和音で生じている音程を明確に捉えていた筈の音程感とは異なった印象として捉える事となり、何某かの音程の姿としての音程の「近傍」を聴き乍ら知覚しようとしているからです。
そうした状況をどうにか上手く喩える事ができないものかと私自身忸怩たる思いを抱いてしまいますが、人間が知覚しやすい帯域での音程の状況を「目が良く見える」状況だとするならば、低域側にシフト(移高)させただけの音程であるにも拘らず、その音程は《どんなに目をこすってもぼやけてしまう》という風に音程を捉えてしまう状況と喩える事が出来るかと思います。
こうした状況は低域側にシフトした途端に突然変わるのではなく、人間が知覚しやすい帯域でも微妙にその音程を捉える聴覚フィルターの捉え方というのは変化しており、知覚に作用しているのです。
例えばある曲を単純にヴォイシングもそのままに半音上あるいは下に移高(トランスポーズ)させたら元と丸っ切り情感が違って聴こえる(=単に移高させただけとは異なる印象)を抱いてしまうのも聴覚フィルタの影響のせいでもあるのです。ですので、ヴォイシングもそのままに、移高させた状況を元の状況と全く同一と捉えてしまうのは、知覚に無理強いしているか or 全く無頓着で居られるかのどちらかでしかないのです。
ですので、複合音および和音となれば協和感を逸してしまうという訳です。協和感は複数の聴覚フィルター同士から作られる組み合わせを脳が覚えるという事になります。
そうした背景から完全五度と同じ様に完全八度の協和感も変わりますし、協和音程よりも次点の協和となる「不完全協和音程」(※長・短の三度/六度など)や「不協和音程」が低域にシフトされればどういう風に響くかと言えば、更に不協和感が増大するのは推して知るべしであります。

下限可聴周波数を20Hzとした時、20Hzと100Hzの振動比は1:5であります。100Hzと500Hzも同様に1:5となります。100Hzと500Hzの周波数をフィルターバンクとして捉えて25等分すると、その帯域幅は20Hzとなります。20Hzから100Hzの帯域を25等分すればフィルターバンクは3.2Hz毎に存在する事になります。無論、これらのフィルターバンクは周波数毎にみれば違う帯域幅ではあるものの、音律の世界から見れば5^(1/25)という事になり、純正長二十四度25等分平均律となる訳です。
オクターヴという概念を捨て去らない限り、100Hzに対して80Hzという振動数を類推しかねませんが、仮にそこで80Hzが生じても差音は20Hzに思弁的に生ずる筈でありますが、実際の5^(1/25)という単位微分音は80Hzではなくその近傍を採るので、差音が従前の協和感を避けつつ「別の協和感」を形成するという意味合いが、ケルン派の研究の背景にある訳です。そうした所にも『習作Ⅱ』は端を発しており、その後の音響図案化と「行為譜」と呼ばれる図形楽譜の構想化に拍車をかける物となり、PRESでの実験もケルン派の実証が影響を与え、後年の電子的な実験を重ねていく事となる訳です。
関連ブログ記事
https://tawauwagotsakonosamu.blog.ss-blog.jp/2014-04-18
第一次世界大戦前から音楽界はゲーテの『色彩論』ミレニアム期に豊かな学識が一般社会にも敷衍される様になり、『色彩論』の新たなる社会通念の勃興に前後して音律の醸成(=等分平均律化)が強固な牽引力となると共に、ヘルムホルツの音響心理学の側面など他の分野や科学の影響を多大に受ける事となり、強固な機能和声社会はもはや無調の世界へ邁進する事を止める事は難しかったであろうと思いますが、歴史的にも名を遺す数学界の偉人が音楽理論にも論文を著して来たものの数学界の悪癖なのかエゴなのか。音楽理論の解を一義的にまとめようとするきらいがあった事はいうまでもありません。
現今社会にも残るその悪しき解釈のひとつが、上方倍音列には完全音程たる下属音が存在しないという大前提には触れずに調性を一義的に取り扱う為にプレドミナントとしてドミナントとしての位置付けを甘受させる様にしつつ、古代ギリシャでは2種類の属音(上属音と下属音)で2つの相貌で音楽を形成したにも関わらずオクターヴの同一性と単音程への転回還元という組織的な効率化を伴わせ、いつしか上方倍音列の世界で一義的な方向を向いてしまった不文律を数学者たちは何の疑念もなく土台としてしまったのは反省すべき点でありましょう。
然し乍らその厳然たる一義的な姿勢もまた、機能和声社会に於ける調性への厳格な姿勢を貫いて音楽感を形成したのも事実。こうした貢献の後に調性が崩壊するのは至極当然の成り行きだった事でしょう。
リップス/マイヤーの法則でも知られるマックス・フリードリヒ・マイヤーの場合はもはや上方倍音列という相貌は、近傍の音が知覚を丸め込めるという風に解釈したのか(※機能和声社会でのプレドミナントは勿論その後のサブドミナントいう「和音機能」は軽んじられていたという背景に伴う)第21次倍音を下属音とみなす(※勿論、第21次倍音は完全音程ではない)のは非常に興味深い所であります。
斯様な音響心理学方面からの新たなる援用が、次なる音楽の為の新たな材料となるのも是亦至極当然な流れなのでありますが、いかんせん一般的な音楽の捉え方(知覚としての)というのは保守的なもので、保守的な聴き方をする人々からすればシュトックハウゼンの『習作Ⅱ』など500年先ほど進んだ音楽に相当する位に突き抜けた物かもしれません。とはいえ19世紀までは古典的でいびつな不等分音律の世界観が残っていたのですから、現今社会の十二等分平均律に均された(≒慣らされた)人々は、あらためて不等分音律やら他の音律に注力せねばならぬほどに現今の音楽はあらためて多様な変化が求められる歴史の変遷期であるのかもしれません。
音響心理学など多くの実験的な研究はケルン派のみならず世界の其処彼処で進んだ訳ですが、西洋音楽界に於て社会主義時代のポーランドに於けるPRESの存在も社会思想を超えて音楽界に貢献して来たという訳です。
『Ultra Sounds』で特徴的なのは、和書に例えればB5変版サイズでの336ページという物なので、『コード理論大全』に極めて近いサイズと思っていただければ良いでしょう。この大きさであるので内容もかなり充実した物となっておりまして、4色カラーの図版も非常に多く、図形楽譜の多さも驚くばかり。
嘗てはこうした図形楽譜を学ぶには、エルハルト・カルコシュカ著 入野義朗訳『現代音楽の記譜』やヴァルター・ギーゼラー著 佐野光司訳『20世紀の作曲』を当たるしか無かったもので、これら2冊の図書はいずれも高価であり、特に4色カラーで触れる事が可能な『20世紀音楽』でのリゲティの図形楽譜などは今猶その譜面に興奮してしまう物ですが、これらの2冊にも掲載されていないレアな図形楽譜が数多く載せられて1300円台で入手できるというのは驚きを禁じ得ません。和訳すれば間違いなく1万円に近い値を付けて発売される事でしょう。
余談ではありますが、YMOが解散(※彼等は散開と呼んだ)時のコンサートおよび解散記念に発表した映画『PROPAGANDA』公開にて販売されていた刊行物『Chaos』のハードカバー装丁は、先のカルコシュカ著『現代音楽の記譜』(全音楽譜出版社刊)のそれを模したサイズとデザインであるのは明白な物です。こうしたアイデアはおそらく坂本龍一に依るものではないかと推察されます。
日本の場合は敗戦国であるため戦時加算が適用される事で、比較的新しい所の楽譜は図形楽譜と雖も著作権が有効となる事で値を釣り上げてしまう理由のひとつとなる訳ですが、それにしても安い。無論、楽理的な論述は少ないのですが、それでも矢張り、実験スタジオの詳細な記録として読むだけでも充分な価値を具備しているので興味のある方は是非とも手にとってお読みいただきたいと思います。
オイゲニウス・ルードニクの写真に当たれるのもあらためて驚かされるばかりで、象徴的な写真をあらためて載せておきたい所です。

他にもルッフ・ムジチュニ(Ruch Muzyczny)、ユゼフ・パトコフスキらをはじめ、『広島の犠牲者に捧げる哀歌』でも知られ、その丰貌(ふうぼう)は仲代達矢にも似るペンデレツキ、クシシュトフ・スリフィルスキ、ボグスワフ・シェッフェルなど枚挙に遑(いとま)がありません。
特に、ペンデレツキの『広島の犠牲者に捧げる哀歌』の告知ポスターをカラー図版で確認できるのはあらためて驚いたもので、私自身今回初めて知る事が出来ました。四分音クラスターが音楽的な蛍光色の様な印象すら抱くそれが、化学的な象徴として放射線を表しているのは歴然ですが、音楽的な蛍光色な印象とは裏腹に、赤を基調としたそのポスターには多くの示唆を感じた物です。
扨て図形譜の譜面(ふづら)は、一般的な五線譜と比しても記譜法として共通する体系化とまでは至っていないので多くの方策があるものの、一定以上の音楽的素養があれば譜面が示す「何某か」の訴えは読み手の音楽的素養をより一層喚起させる物であり、そこには多くの楽譜が示す定量的な拍節よりも、万人が抱く時間のイメージの図示と、それに随伴する行動の量的な変化を直観的に示される事が重視されているのはは言うまでもありません。
そうした図形楽譜が一般的な記譜法の方法論を超越しているとは雖も多くの場合は舞踊楽譜をヒントにした現代への異化なのでもあり、舞踊楽譜となると是亦途端に目に触れにくい分野でもありますが、一般的な記譜法で示されない「パラメータ」が示されている事自体が音楽的素養を擽って呉れる物でもあり、音楽演奏の為に必要且つ一般的な記譜法で明示されない「要素」即ちパラメータとしての音楽表現への欲求の高まりが図形楽譜を導いたりするのであります。
言葉を文字に表すにしても、それは「整列」させる事が不文律となっている物でありますが、「行間表記法」という手法(※この表記法は言語学から援用され音声学にて用いる手法で音楽的な関わりは比較的浅くなります)を用いて特定の言葉の僅かなイントネーションの差異(音高の変化)を表現する為に、文字の揃えを上下にずらしたり、発話する音の音量の増減を文字の大きさで以て変化させたりするだけでも、一般的な文字揃えの体系とは異なる「パラメータ」により、アクセントやイントネーションの変化が理解できる物になるでしょう。
図形楽譜というのもこうした所を援用し乍ら時には音響という側面から時間と音高を方眼紙の様に見立てて音声信号をスペクトログラフ化させたりする物です。
舞踊楽譜そのものはバロック時代から既に存在しており、言語のイントネーションの正確さ表現するにあたって音楽を援用して言語の記譜法として発表したのがジョシュア・スティールの表記法で、これがベートーヴェン誕生9年後の1779年という訳ですから、20世紀音楽が形成して来た当時の現代音楽が総じて今猶新しいという物では全く無く、単に一般的に広く知られていない事をあらためて掘り下げて古き体系を知る必要があろうかと思う事頻りです。
斯様なパラメータで音楽を「読む」事は、演奏の具象化が従前の記譜法にはどういうパラメータが不要で、どういうパラメータが直観的に作用する事が得策であるのか!? という多くの試みを、多くのカラーの図版だけでも十分に伝えて呉れる物であり、第二次大戦後の音楽がいかにして科学的にも直結しながらメディアという資本力によって科学の力で新たな牽引力を得ていたのかが能く判ります。



