ちくま学芸文庫『バルトーク音楽論選』を読んで [書評]
2018年6月初旬、ちくま学芸文庫にて『バルトーク音楽論選』が刊行されたのでありましたが、刊行前にふと私の脳裡を過った事は、文庫化する前の単行本の存在が筑摩書房に有ったであろうか!? という事でありました。
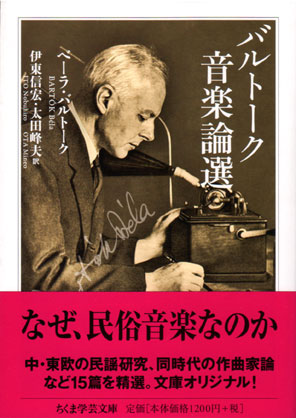
文庫化するという事は概してその本を底本とする単行本が過去に流通していた事を想起させる訳であり、単行本が絶版となったり或いは装幀のコストや作者への権料を見直して新たに流通させるという事もあって文庫化は為される物であると信じて已まぬ私は、ついつい余計な事を考えてしまった物です。齢五十を過ぎ、迷妄の度も著しい私が皮相浅薄な出版界の諸事情を探ろうとも大して利する事もないのでありますが、何しろ音楽関連書籍のビブロフィリアもといブックホーダーである私が、これまで筑摩書房にて『バルトーク音楽論選』なるタイトルの単行本が刊行されたという記憶は無かったので、これは他社での刊行物を文庫化した物なのではないか!? という推察に及んだ訳であります。
結論から言えば『バルトーク音楽論選』は、過去に刊行された岩城肇編訳『バルトークの世界』(講談社)『バルトーク音楽論集』(御茶の水書房)であるのは事実です。但し、今回あらためて文庫化されるに当って新たに〈ハーヴァード大学での講義〉が《Ⅳ 講義と自伝》として追加されているのは喜ばしい事であり本書の1/3ほどを占める文書量でもあり、文庫という安価な価格で新たにこの内容に触れる事が出来るのは感謝したくなる物で、詳密な内容を新たに知る事の出来る喜びを多くの人に知ってもらいたいという気持ちにさせてくれる物です。他にも初出となる物は跋文でも纏められているので、あらためて伊東信宏・太田峰夫両氏に感謝します。
両氏はバルトーク関連に於ても能く名前を見掛ける方々でありますし、なにより太田峰夫の近著は2017年に『バルトーク 音楽のプリミティヴィズム』(慶応義塾大学出版会)から刊行されていた事もあり記憶に新しく、楽式論的視点で詳らかに分析されている原譜の図版なども併せて充実した内容となっている物です。それから1年も俟たずにあらためて新たなる情報にアクセスできるのは重ねて喜ばしい限りであります。

舊來の岩城肇訳編の文を改めた理由も跋文にて述べられておりますが、本書を初めて手に取る方は殊の外譜例の充実ぶりに驚かれるかもしれません。五線譜の第4間のみに変種記号が充てられる特殊調号など、短調の第6・7音のムシカ・フィクタを前提とした書き方で示されるアロイス・ハーバの『Harmonielehre』をあらためて思い返してしまう程でありますが、充実した譜例には気付かされる事が多いのではないかと思う事頻りです。
譜例に用いられる音部記号のフォルムは『バルトーク音楽論集』の頃だと、少々クセのある、現在の楽譜浄書ソフトにあるフォントとは趣きの異なる物で謂わばPetrucciとGoutenbergの中間の様な物でしたが、『バルトーク音楽論選』ではMaestroフォントに統一されているようで読み易くなっております。単行本が袖珍本へと縮小されると、単行本時での譜例という物も総じて縮小してしまう為、線数が低めの印刷品質ですと五線譜の細さを細く取れずに他の玉や変化記号ばかりが潰れて行ってしまうので概ね読みづらくなってしまう物ですが、楽譜浄書ソフト由来であれば楽譜データそのものがPostScriptまたはEPSデータとして出力できるので、製本サイズが小さくとも線数がある程度維持出来ていれば潰れずに読み易くなるので、原譜を扱って縮小印刷されてしまうよりもこうしてデジタル・データを巧く利用した方が読みやすくなっているのはとても熟慮されていると思われ、文庫化と雖も決して手を抜く事のない作業にあらためて拍手を送りたいと思います。
東欧の民族音楽は疑いなくロマ族(所謂ジプシー民族)の影響があるでしょうが、ロマ族というのは人種として明確に区別される物でもなく、貧困を招いた各地の人々が放浪を繰り返すインド出自の民族と交雑化するという複雑な事情も孕んでいる物の、彼等が器楽演奏を生業とする事で近年になって名声を贏ち得た側面もありますが多くは差別されてきた物でもあります。音律が熟成され不協和の度を強め、旋法性の多様な解釈もあって民族的な音の活用が受け入れられる様になった訳でもあり、ビゼーによる『カルメン』の描写などまさにジプシー出自の者と恋に落ちるのは、映り行く世相の変化を反映している物であるとも言えるでしょう。
東欧や中東、特にトルコ音楽などは多様な音階な勿論、リズムの細分化や拍節構造の複雑化など多岐に亘る物でありまして、ジャズ/ポピュラー音楽界隈しか判らない人であってもフランク・ザッパの「Black Page」に見られる複雑怪奇なリズム構造を例に挙げればその複雑さは何となく理解に及ぶかもしれませんが、トルコ音楽というのは「Black Page」よりも遥かに複雑な音楽が常に日常的に瀰漫している物でありまして、そうした事情を踏まえ乍ら東欧地域などの民俗性を鑑みると、より深く理解できるかもしれません。特殊調号として表わさざるを得ない音楽的な状況や複雑な混合拍子の拍節構造など、それらは本書でも明らかにされており、章末毎に記される詳密な訳注は決して読み飛ばさずに理解してほしい所です。勿論、原注と訳注も別けて書かれているので、こうした点は読み飛ばさぬ様注意をされたし。こうした内容で税抜き1200円で読む事が出来るのですから、豊富な内容と比してこの価格の安さはあらためて驚くばかりです。
加えて、本書の最も特徴的な物となるハーヴァード大学での講義の部分だけでも大変興味深く読む事ができるのでありますが、詳細は読者の方が実際に手に取って読んでもらう必要性がありますが、少しでも手に取る事の欲求を高める上で、私が次に語る事をヒントにして昂らせていただければと思います。例えばアロイス・ハーバ、ヴィシネツグラツキー、ヨーゼフ・マティアス・ハウアーへの言及など。また、シェーンベルクとストラヴィンスキーを対照させて語っていた事は大変興味深いと思います。
ストラヴィンスキーも十二音技法に手を出した事はありましたが、国内では船山隆著『ストラヴィンスキー 二十世紀の鏡像』にて確認する事も出来ますし、シェーンベルクとストラヴィンスキーは夫々全く趣の異なる概念からクロマティシズムを実現していたという事がバルトークの口から語られる点は実に興味深いでありましょう。本書のこうした部分に興味を抱いた方は是非とも『ストラヴィンスキー 二十世紀の鏡像』も手に取ってもらいたいと思う事頻りです。
また、長・短三度が併存する響きの解説についても、中心軸システムの解説とは異なる本人の語り口で述べられる事に遭遇出来るのは非常に興味深い物でもあります。こうした点に興味を抱いた方は、四の五の言わずに安価な本書を手に取るべきだと思います。
尚、本書ではヴィシネグラツキーを長音記号無しで《ヴィシネグラツキ》と明記しておりますが、この表記についてはいただけない点と思われます。主要新聞用語でも統一される表記ですが、ヴィシネグラツキーから最後の長音記号を割愛してしまうと、それはポーランド人名の表記と混同する事になってしまう為、ヴィシネグラツキーは長音記号が充てられて然るべきなのです。つまり「ツキ」という長音無しの表記はポーランド人特有の「-cki」の為の物である為、ペンデレツキなどはまさにこの表記に当て嵌まる為逆に長音記号は不要となる訳でありますが、現今社会ですとコンピュータ、プリンタ、メモリなど、末尾の長音記号を省く手法が横行してしまってそれが方々で悪しき影響を与えるシーンがあります。
直接の外部サイトへのリンクは避けますが、その外部サイトは、ポーランド語が現地語として実際の発音として読まれている [-cki] は長音化して耳に届くにも拘らず日本でのポーランド人名表記の矛盾およびソ連の影響下にあった時代などの著名な作曲家の例などを引き合いに出して批判されている物であり、「ポーランド」人名などとやれば当該サイトを顕著にグーグル検索では拾って来るものであるもので、私が述べる事は、そのサイトでは触れられない重要な部分を附言するものであります。
ポーランド語としての表記と発音の実際とが異なっていようともポーランド人の人名にて [-cki] などを長音化せずにカタカナ表記をするのは単に日本のみの慣例であるのではなく、ポーランド語という言語がラテン語を元に今猶旧い発音を残しているという事を拝戴しての事なのです。スラブ系の言語の中でも旧いラテン語の発音が残っているという部分がキモなのでありますが、ラテン語に於ける「古典ラテン語」というのは特に、母音の長音の有無に明示的な違いなどありません。このような先蹤を拝戴した上で我々の様な凡庸な日本人が、発音の実際だけを論って「長音無し」表記を無闇に批判する事こそが野暮という物なのであります。
ですので、ポーランド人音楽家が、その出生時代に於てソビエトとの関連があろうとなかろうと、それは野暮な事なのであり、よもやポーランド人名の表記のそれを自説の強化の為に断章取義としてしまったり、或いは編集の手が及ばなかったという事をお座なりにしてしまってはならないと思うばかりであります。言語学界隈はおろか音楽界に於て「拉典」の世界をも軽んじてしまう事はあってはならないと思う訳でありまして、曲がりなりにもポーランド人名の長音化という事を選択してしまう様では配慮が足らない点であったろうと私は思うのであります。訳が良いだけに殘念頻りな点であります。
特に民間での業務経験のない象牙の塔で育ってしまって、文書データおよび字数の削減の為に割愛してしまう様な物は行政に於ける白書などでも能く見受けられる物で、褒められるべき慣習ではないと感じます。これらの様な悪しき側面を鑑みても、ヴィシネグラツキーをついつい長音記号を省略してしまうのは避けるべきであると考えます。こうした事が横行してしまうと、ヴィシネグラツキーの出身国などを誤解してしまう人間を生んでしまう事になりかねず、況してや新聞用語でも細心の注意を払われている人名表記なのですから訂正すべき表記であると言えるでしょう。
加えて、ヨーゼフ・マティアス・ハウアーという名を本書では「J・ハウアー Josef Matthias Hauer」と、原語併記となっているものの、これまでのハウアーの呼び方は他の多くの著書や論文に於て、ヨーゼフ・マティアス・ハウアーやJ・M・ハウアーという表記で知られていたのでありまして、ここで新たに「J・ハウアー」という表記が加わってしまうのは読者に不親切な表記であると個人的には感じました。昨年逝去された故田代櫂著『アルバン・ベルク 地獄のアリア』(春秋社)の157頁でもフルネームにてカタカナ表記されていた事が記憶に新しく、瑣末事ではありますがこれらの2人(ヴィシネグラツキー、ヨーゼフ・マティアス・ハウアー)の表記については気になった点であります。
誤謬が広く瀰漫している状況であった場合、それを払拭する為には正しい表記が為されて然るべきでありますが、新奇性の高い専門用語の外来語を示す訳でもなく、界隈ではある程度知られている人名表記については細心の注意を払う必要があったのではなかろうかと思います。
話題を戻しますが、リディアンを基にするペンタコルドと、それと基音を同じく採るフリジアンを基とするペンタコルドの併存によって半音階は得られるという内容など、パーシケッティ著『20世紀の和声法』を補強して呉れる内容に触れられる訳ですし、それに加えて長・短三度音程の併存までも詳らかに語られているとなれば、多くのヒントがちりばめられている訳で、お読みになられていない方は是非とも本書に触れてほしいと思います。
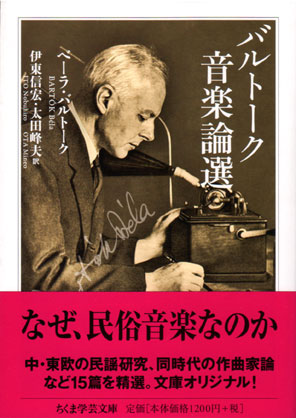
文庫化するという事は概してその本を底本とする単行本が過去に流通していた事を想起させる訳であり、単行本が絶版となったり或いは装幀のコストや作者への権料を見直して新たに流通させるという事もあって文庫化は為される物であると信じて已まぬ私は、ついつい余計な事を考えてしまった物です。齢五十を過ぎ、迷妄の度も著しい私が皮相浅薄な出版界の諸事情を探ろうとも大して利する事もないのでありますが、何しろ音楽関連書籍のビブロフィリアもといブックホーダーである私が、これまで筑摩書房にて『バルトーク音楽論選』なるタイトルの単行本が刊行されたという記憶は無かったので、これは他社での刊行物を文庫化した物なのではないか!? という推察に及んだ訳であります。
結論から言えば『バルトーク音楽論選』は、過去に刊行された岩城肇編訳『バルトークの世界』(講談社)『バルトーク音楽論集』(御茶の水書房)であるのは事実です。但し、今回あらためて文庫化されるに当って新たに〈ハーヴァード大学での講義〉が《Ⅳ 講義と自伝》として追加されているのは喜ばしい事であり本書の1/3ほどを占める文書量でもあり、文庫という安価な価格で新たにこの内容に触れる事が出来るのは感謝したくなる物で、詳密な内容を新たに知る事の出来る喜びを多くの人に知ってもらいたいという気持ちにさせてくれる物です。他にも初出となる物は跋文でも纏められているので、あらためて伊東信宏・太田峰夫両氏に感謝します。
両氏はバルトーク関連に於ても能く名前を見掛ける方々でありますし、なにより太田峰夫の近著は2017年に『バルトーク 音楽のプリミティヴィズム』(慶応義塾大学出版会)から刊行されていた事もあり記憶に新しく、楽式論的視点で詳らかに分析されている原譜の図版なども併せて充実した内容となっている物です。それから1年も俟たずにあらためて新たなる情報にアクセスできるのは重ねて喜ばしい限りであります。

舊來の岩城肇訳編の文を改めた理由も跋文にて述べられておりますが、本書を初めて手に取る方は殊の外譜例の充実ぶりに驚かれるかもしれません。五線譜の第4間のみに変種記号が充てられる特殊調号など、短調の第6・7音のムシカ・フィクタを前提とした書き方で示されるアロイス・ハーバの『Harmonielehre』をあらためて思い返してしまう程でありますが、充実した譜例には気付かされる事が多いのではないかと思う事頻りです。
譜例に用いられる音部記号のフォルムは『バルトーク音楽論集』の頃だと、少々クセのある、現在の楽譜浄書ソフトにあるフォントとは趣きの異なる物で謂わばPetrucciとGoutenbergの中間の様な物でしたが、『バルトーク音楽論選』ではMaestroフォントに統一されているようで読み易くなっております。単行本が袖珍本へと縮小されると、単行本時での譜例という物も総じて縮小してしまう為、線数が低めの印刷品質ですと五線譜の細さを細く取れずに他の玉や変化記号ばかりが潰れて行ってしまうので概ね読みづらくなってしまう物ですが、楽譜浄書ソフト由来であれば楽譜データそのものがPostScriptまたはEPSデータとして出力できるので、製本サイズが小さくとも線数がある程度維持出来ていれば潰れずに読み易くなるので、原譜を扱って縮小印刷されてしまうよりもこうしてデジタル・データを巧く利用した方が読みやすくなっているのはとても熟慮されていると思われ、文庫化と雖も決して手を抜く事のない作業にあらためて拍手を送りたいと思います。
東欧の民族音楽は疑いなくロマ族(所謂ジプシー民族)の影響があるでしょうが、ロマ族というのは人種として明確に区別される物でもなく、貧困を招いた各地の人々が放浪を繰り返すインド出自の民族と交雑化するという複雑な事情も孕んでいる物の、彼等が器楽演奏を生業とする事で近年になって名声を贏ち得た側面もありますが多くは差別されてきた物でもあります。音律が熟成され不協和の度を強め、旋法性の多様な解釈もあって民族的な音の活用が受け入れられる様になった訳でもあり、ビゼーによる『カルメン』の描写などまさにジプシー出自の者と恋に落ちるのは、映り行く世相の変化を反映している物であるとも言えるでしょう。
東欧や中東、特にトルコ音楽などは多様な音階な勿論、リズムの細分化や拍節構造の複雑化など多岐に亘る物でありまして、ジャズ/ポピュラー音楽界隈しか判らない人であってもフランク・ザッパの「Black Page」に見られる複雑怪奇なリズム構造を例に挙げればその複雑さは何となく理解に及ぶかもしれませんが、トルコ音楽というのは「Black Page」よりも遥かに複雑な音楽が常に日常的に瀰漫している物でありまして、そうした事情を踏まえ乍ら東欧地域などの民俗性を鑑みると、より深く理解できるかもしれません。特殊調号として表わさざるを得ない音楽的な状況や複雑な混合拍子の拍節構造など、それらは本書でも明らかにされており、章末毎に記される詳密な訳注は決して読み飛ばさずに理解してほしい所です。勿論、原注と訳注も別けて書かれているので、こうした点は読み飛ばさぬ様注意をされたし。こうした内容で税抜き1200円で読む事が出来るのですから、豊富な内容と比してこの価格の安さはあらためて驚くばかりです。
加えて、本書の最も特徴的な物となるハーヴァード大学での講義の部分だけでも大変興味深く読む事ができるのでありますが、詳細は読者の方が実際に手に取って読んでもらう必要性がありますが、少しでも手に取る事の欲求を高める上で、私が次に語る事をヒントにして昂らせていただければと思います。例えばアロイス・ハーバ、ヴィシネツグラツキー、ヨーゼフ・マティアス・ハウアーへの言及など。また、シェーンベルクとストラヴィンスキーを対照させて語っていた事は大変興味深いと思います。
ストラヴィンスキーも十二音技法に手を出した事はありましたが、国内では船山隆著『ストラヴィンスキー 二十世紀の鏡像』にて確認する事も出来ますし、シェーンベルクとストラヴィンスキーは夫々全く趣の異なる概念からクロマティシズムを実現していたという事がバルトークの口から語られる点は実に興味深いでありましょう。本書のこうした部分に興味を抱いた方は是非とも『ストラヴィンスキー 二十世紀の鏡像』も手に取ってもらいたいと思う事頻りです。
また、長・短三度が併存する響きの解説についても、中心軸システムの解説とは異なる本人の語り口で述べられる事に遭遇出来るのは非常に興味深い物でもあります。こうした点に興味を抱いた方は、四の五の言わずに安価な本書を手に取るべきだと思います。
尚、本書ではヴィシネグラツキーを長音記号無しで《ヴィシネグラツキ》と明記しておりますが、この表記についてはいただけない点と思われます。主要新聞用語でも統一される表記ですが、ヴィシネグラツキーから最後の長音記号を割愛してしまうと、それはポーランド人名の表記と混同する事になってしまう為、ヴィシネグラツキーは長音記号が充てられて然るべきなのです。つまり「ツキ」という長音無しの表記はポーランド人特有の「-cki」の為の物である為、ペンデレツキなどはまさにこの表記に当て嵌まる為逆に長音記号は不要となる訳でありますが、現今社会ですとコンピュータ、プリンタ、メモリなど、末尾の長音記号を省く手法が横行してしまってそれが方々で悪しき影響を与えるシーンがあります。
直接の外部サイトへのリンクは避けますが、その外部サイトは、ポーランド語が現地語として実際の発音として読まれている [-cki] は長音化して耳に届くにも拘らず日本でのポーランド人名表記の矛盾およびソ連の影響下にあった時代などの著名な作曲家の例などを引き合いに出して批判されている物であり、「ポーランド」人名などとやれば当該サイトを顕著にグーグル検索では拾って来るものであるもので、私が述べる事は、そのサイトでは触れられない重要な部分を附言するものであります。
ポーランド語としての表記と発音の実際とが異なっていようともポーランド人の人名にて [-cki] などを長音化せずにカタカナ表記をするのは単に日本のみの慣例であるのではなく、ポーランド語という言語がラテン語を元に今猶旧い発音を残しているという事を拝戴しての事なのです。スラブ系の言語の中でも旧いラテン語の発音が残っているという部分がキモなのでありますが、ラテン語に於ける「古典ラテン語」というのは特に、母音の長音の有無に明示的な違いなどありません。このような先蹤を拝戴した上で我々の様な凡庸な日本人が、発音の実際だけを論って「長音無し」表記を無闇に批判する事こそが野暮という物なのであります。
ですので、ポーランド人音楽家が、その出生時代に於てソビエトとの関連があろうとなかろうと、それは野暮な事なのであり、よもやポーランド人名の表記のそれを自説の強化の為に断章取義としてしまったり、或いは編集の手が及ばなかったという事をお座なりにしてしまってはならないと思うばかりであります。言語学界隈はおろか音楽界に於て「拉典」の世界をも軽んじてしまう事はあってはならないと思う訳でありまして、曲がりなりにもポーランド人名の長音化という事を選択してしまう様では配慮が足らない点であったろうと私は思うのであります。訳が良いだけに殘念頻りな点であります。
特に民間での業務経験のない象牙の塔で育ってしまって、文書データおよび字数の削減の為に割愛してしまう様な物は行政に於ける白書などでも能く見受けられる物で、褒められるべき慣習ではないと感じます。これらの様な悪しき側面を鑑みても、ヴィシネグラツキーをついつい長音記号を省略してしまうのは避けるべきであると考えます。こうした事が横行してしまうと、ヴィシネグラツキーの出身国などを誤解してしまう人間を生んでしまう事になりかねず、況してや新聞用語でも細心の注意を払われている人名表記なのですから訂正すべき表記であると言えるでしょう。
加えて、ヨーゼフ・マティアス・ハウアーという名を本書では「J・ハウアー Josef Matthias Hauer」と、原語併記となっているものの、これまでのハウアーの呼び方は他の多くの著書や論文に於て、ヨーゼフ・マティアス・ハウアーやJ・M・ハウアーという表記で知られていたのでありまして、ここで新たに「J・ハウアー」という表記が加わってしまうのは読者に不親切な表記であると個人的には感じました。昨年逝去された故田代櫂著『アルバン・ベルク 地獄のアリア』(春秋社)の157頁でもフルネームにてカタカナ表記されていた事が記憶に新しく、瑣末事ではありますがこれらの2人(ヴィシネグラツキー、ヨーゼフ・マティアス・ハウアー)の表記については気になった点であります。
誤謬が広く瀰漫している状況であった場合、それを払拭する為には正しい表記が為されて然るべきでありますが、新奇性の高い専門用語の外来語を示す訳でもなく、界隈ではある程度知られている人名表記については細心の注意を払う必要があったのではなかろうかと思います。
話題を戻しますが、リディアンを基にするペンタコルドと、それと基音を同じく採るフリジアンを基とするペンタコルドの併存によって半音階は得られるという内容など、パーシケッティ著『20世紀の和声法』を補強して呉れる内容に触れられる訳ですし、それに加えて長・短三度音程の併存までも詳らかに語られているとなれば、多くのヒントがちりばめられている訳で、お読みになられていない方は是非とも本書に触れてほしいと思います。
2018-06-17 22:00



